勝負の分かれ目として「天王山」という言葉は日本人の常識語になっています。これは光秀と秀吉の山崎の合戦の勝敗が天王山の争奪によって決まったという「史実」から生まれた言葉です。
しかし、これは史実でもなんでもなく、小瀬甫庵(おぜ・ほあん)という人が本能寺の変から43年後の1625年に出版した『太閤記』(『太閤記』という名前の本はいろいろあるので『甫庵太閤記』と呼ばれる)に書いた話に過ぎません。それまで、天王山の争奪戦について書いた史料は一切ありません。秀吉自身が書かせた『惟任退治記』にも記載はありません。
この『甫庵太閤記』は歴史の記録として書かれたものではありません。軍記物と呼ばれた物語です。甫庵という人は創作力豊かな人といえるでしょう。彼が創作した話は天王山争奪戦だけではなく、小栗栖の竹薮で光秀が槍に刺され溝尾勝兵衛が介錯して首を落とした話も創作しています。甫庵の前作『甫庵信長記』では信長の桶狭間の戦いが奇襲攻撃だったという話や長篠の戦で鉄砲の「三段撃ち」を行った話も創作しています。
★ Wikipedia「小瀬甫庵」記事
この甫庵は節操のない人で、『甫庵信長記』は太田牛一の書いた『信長公記』の盗作、『甫庵太閤記』は大村由己の『惟任退治記』などの盗作です。盗作した上で好き勝手に創作して改竄したのです。光秀の謀反の動機も『甫庵信長記』では信長の信賞必罰の厳しい姿勢を恐れたためとし、『甫庵太閤記』ではそのような話には一切触れずに、家康饗応役を解任されて怨んだためとしています。
こうしてみてきても、『甫庵信長記』や『甫庵太閤記』に初めて出てくる話は史実ではない、歴史捜査の証拠として採用できないと断定できます。よって、山崎の合戦にかかわる天王山や小栗栖の話は嘘だ、ということになります。天王山の話は甫庵が仕えていた堀尾吉晴(秀吉の家臣)の活躍する場面を創ったに過ぎないのです。Wikipediaの「堀尾吉晴」の記事には見事に天王山での活躍が書かれていますので甫庵の創作は現代に生きているわけです。残念ながら桶狭間の奇襲攻撃や長篠の「三段撃ち」も現代の歴史の常識になってしまっていますね。
★ Wikipedia「堀尾吉晴」記事
以上のように天王山の争奪戦はなかった、と結論は簡単に出てしまったわけですが、これで本稿を終わってしまうと「歴史捜査」としては身も蓋もないとお叱りを受けそうです。そこで、少し傍証を固めたいと思います。
『兼見卿記』の記事で確認してみましょう。これを書いた吉田兼見(かねみ)は朝廷にあって信長や光秀との対応役だった公家であり、吉田神社の神官でもありました。細川藤孝の従兄弟でしたので、本能寺の変にからむキーマン達とは緊密な関係がありました。
十日 光秀、摂津を攻める。
十一日 光秀、下鳥羽に退き淀城を固める。
十二日 勝竜寺の西において足軽の鉄砲戦あり。近辺が放火された。
十三日 雨降、申刻に至り山崎において鉄砲の音、数刻鳴り止まず、一戦に及ぶ。
光秀は十日に摂津まで侵出し、その後山崎近辺まで退却してきています。したがって、天王山に布陣するつもりであれば十一日でも十二日でも兵を置くことができました。したがって、光秀は天王山に兵を置くつもりがなかった、ということになります。
それは何故でしょうか?
山崎の合戦の地図を思い起こしてください。
★ 歴史捜査「山崎の合戦」その1:捜査開始宣言
光秀軍は大山崎の東黒門の出口の先で秀吉軍を待ち受ける形となっていました。大山崎は堺と並んで自治都市の代表とされるような集落で、応仁の乱の際には東軍に味方して、天王山に陣取った西軍を追い落とすのに協力しています。山崎の合戦に先立って、大山崎は光秀、秀吉の両軍から禁制を得ています。禁制とは軍勢通行や戦乱にあたっての一般に告知された禁止事項の文書です。これにより、両軍とも大山崎の集落内での濫妨・狼藉、陣取・放火が禁止されました。
(この段落は『歴史群像シリーズ 俊英明智光秀』所収の『山崎合戦の新視点』福島克彦著を参考にして書きました)
つまり、どちらの軍勢も大山崎においては西国街道を粛々と通過するだけしかできないことになりました。これこそ光秀が東黒門の出口の先を決戦場に選んだ理由でしょう。多勢に無勢の光秀にはこの作戦しかなかったはずです。秀吉軍の中央は横に広がることのできない態勢です。これがどれだけ軍隊の移動の制約になるかは、火災訓練で非常階段をたくさんの人が降りていく場面を想像すれば容易にわかります。
実は同じことが天王山にも当てはまるのではないでしょうか。急峻で細い山道を大量の軍勢が一気に駆け下ることは難しいでしょう。しかも、『兼見卿記』によれば当日は雨降。山道の行軍には最悪の条件だったでしょう。
天王山に光秀軍が布陣していても同様の条件でした。兵力の少ない光秀軍の一部を天王山に分割配置するメリットはなかったのでしょう。それよりも兵力を東黒門出口に集中することに光秀は賭けた、そしてそれは妥当な作戦だったと考えられます。

(注)この地図は『別冊歴史読本11 明智光秀 野望!本能寺の変』新人物往来社発行(1989年)と『歴史群像シリーズ・戦国セレクション 俊英 明智光秀』学習研究社発行(2002年)に書かれていた地図・俯瞰図を参考にして作成しています。
>>> 歴史捜査「山崎の合戦」その3:秀吉の証言
>>> 歴史捜査「山崎の合戦」その4:フロイスの証言
-------------------------
名門・土岐明智氏の行く末に危機感を抱いていた光秀。信長の四国征伐がさらに彼を追いこんでゆく。ところが、絶望する光秀の前に、天才・信長自身が張りめぐらした策謀が、千載一遇のチャンスを与えた! なぜ光秀は信長を討ったのか。背後に隠された驚くべき状況と、すべてを操る男の存在とは!? 新事実をもとに日本史最大のクーデターの真実に迫る、壮大な歴史捜査ドキュメント!
>>> 「本能寺の変 431年目の真実」読者書評
>>> 「本能寺の変の真実」決定版出版のお知らせ
--------------------------
明智憲三郎著の第4作『「本能寺の変」は変だ! 明智光秀の子孫による歴史捜査授業』文芸社
「秀吉がねつ造し、軍記物に汚染された戦国史を、今一度洗濯いたし申し候」。40万部突破の『本能寺の変 431年目の真実』の著者、明智憲三郎がさらなる歴史捜査を通じて、より解り易く「本能寺の変」の真実を解説した歴史ドキュメント! 「ハゲだから謀反って変だ! 」「歴史の流れ無視って変だ! 」「信長の油断って変だ! 」等々、まだある驚愕の真実に迫る!
本能寺の変研究の欠陥を暴き、「本当の歴史」を知る面白さを説く!
「若い方々や歴史に興味のない方々に歴史を好きになってもらいたいと思って書きました」 明智憲三郎
>>> サンテレビ「カツヤマサヒコSHOW」対談YouTube動画はこちら
【明智憲三郎著作一覧】
2016年5月発売予定
『「本能寺の変」は変だ! 明智光秀の子孫による歴史捜査授業』文芸社
>>> 文芸社のページ
2015年7月発売
『織田信長 四三三年目の真実 信長脳を歴史捜査せよ!』幻冬舎
>>> 幻冬舎のページ
2013年12月発売
『本能寺の変 431年目の真実』文芸社文庫
>>> 文芸社のページ
2009年3月発売
『本能寺の変 四二七年目の真実』プレジデント社
しかし、これは史実でもなんでもなく、小瀬甫庵(おぜ・ほあん)という人が本能寺の変から43年後の1625年に出版した『太閤記』(『太閤記』という名前の本はいろいろあるので『甫庵太閤記』と呼ばれる)に書いた話に過ぎません。それまで、天王山の争奪戦について書いた史料は一切ありません。秀吉自身が書かせた『惟任退治記』にも記載はありません。
この『甫庵太閤記』は歴史の記録として書かれたものではありません。軍記物と呼ばれた物語です。甫庵という人は創作力豊かな人といえるでしょう。彼が創作した話は天王山争奪戦だけではなく、小栗栖の竹薮で光秀が槍に刺され溝尾勝兵衛が介錯して首を落とした話も創作しています。甫庵の前作『甫庵信長記』では信長の桶狭間の戦いが奇襲攻撃だったという話や長篠の戦で鉄砲の「三段撃ち」を行った話も創作しています。
★ Wikipedia「小瀬甫庵」記事
この甫庵は節操のない人で、『甫庵信長記』は太田牛一の書いた『信長公記』の盗作、『甫庵太閤記』は大村由己の『惟任退治記』などの盗作です。盗作した上で好き勝手に創作して改竄したのです。光秀の謀反の動機も『甫庵信長記』では信長の信賞必罰の厳しい姿勢を恐れたためとし、『甫庵太閤記』ではそのような話には一切触れずに、家康饗応役を解任されて怨んだためとしています。
こうしてみてきても、『甫庵信長記』や『甫庵太閤記』に初めて出てくる話は史実ではない、歴史捜査の証拠として採用できないと断定できます。よって、山崎の合戦にかかわる天王山や小栗栖の話は嘘だ、ということになります。天王山の話は甫庵が仕えていた堀尾吉晴(秀吉の家臣)の活躍する場面を創ったに過ぎないのです。Wikipediaの「堀尾吉晴」の記事には見事に天王山での活躍が書かれていますので甫庵の創作は現代に生きているわけです。残念ながら桶狭間の奇襲攻撃や長篠の「三段撃ち」も現代の歴史の常識になってしまっていますね。
★ Wikipedia「堀尾吉晴」記事
以上のように天王山の争奪戦はなかった、と結論は簡単に出てしまったわけですが、これで本稿を終わってしまうと「歴史捜査」としては身も蓋もないとお叱りを受けそうです。そこで、少し傍証を固めたいと思います。
『兼見卿記』の記事で確認してみましょう。これを書いた吉田兼見(かねみ)は朝廷にあって信長や光秀との対応役だった公家であり、吉田神社の神官でもありました。細川藤孝の従兄弟でしたので、本能寺の変にからむキーマン達とは緊密な関係がありました。
十日 光秀、摂津を攻める。
十一日 光秀、下鳥羽に退き淀城を固める。
十二日 勝竜寺の西において足軽の鉄砲戦あり。近辺が放火された。
十三日 雨降、申刻に至り山崎において鉄砲の音、数刻鳴り止まず、一戦に及ぶ。
光秀は十日に摂津まで侵出し、その後山崎近辺まで退却してきています。したがって、天王山に布陣するつもりであれば十一日でも十二日でも兵を置くことができました。したがって、光秀は天王山に兵を置くつもりがなかった、ということになります。
それは何故でしょうか?
山崎の合戦の地図を思い起こしてください。
★ 歴史捜査「山崎の合戦」その1:捜査開始宣言
光秀軍は大山崎の東黒門の出口の先で秀吉軍を待ち受ける形となっていました。大山崎は堺と並んで自治都市の代表とされるような集落で、応仁の乱の際には東軍に味方して、天王山に陣取った西軍を追い落とすのに協力しています。山崎の合戦に先立って、大山崎は光秀、秀吉の両軍から禁制を得ています。禁制とは軍勢通行や戦乱にあたっての一般に告知された禁止事項の文書です。これにより、両軍とも大山崎の集落内での濫妨・狼藉、陣取・放火が禁止されました。
(この段落は『歴史群像シリーズ 俊英明智光秀』所収の『山崎合戦の新視点』福島克彦著を参考にして書きました)
つまり、どちらの軍勢も大山崎においては西国街道を粛々と通過するだけしかできないことになりました。これこそ光秀が東黒門の出口の先を決戦場に選んだ理由でしょう。多勢に無勢の光秀にはこの作戦しかなかったはずです。秀吉軍の中央は横に広がることのできない態勢です。これがどれだけ軍隊の移動の制約になるかは、火災訓練で非常階段をたくさんの人が降りていく場面を想像すれば容易にわかります。
実は同じことが天王山にも当てはまるのではないでしょうか。急峻で細い山道を大量の軍勢が一気に駆け下ることは難しいでしょう。しかも、『兼見卿記』によれば当日は雨降。山道の行軍には最悪の条件だったでしょう。
天王山に光秀軍が布陣していても同様の条件でした。兵力の少ない光秀軍の一部を天王山に分割配置するメリットはなかったのでしょう。それよりも兵力を東黒門出口に集中することに光秀は賭けた、そしてそれは妥当な作戦だったと考えられます。

(注)この地図は『別冊歴史読本11 明智光秀 野望!本能寺の変』新人物往来社発行(1989年)と『歴史群像シリーズ・戦国セレクション 俊英 明智光秀』学習研究社発行(2002年)に書かれていた地図・俯瞰図を参考にして作成しています。
>>> 歴史捜査「山崎の合戦」その3:秀吉の証言
>>> 歴史捜査「山崎の合戦」その4:フロイスの証言
-------------------------
名門・土岐明智氏の行く末に危機感を抱いていた光秀。信長の四国征伐がさらに彼を追いこんでゆく。ところが、絶望する光秀の前に、天才・信長自身が張りめぐらした策謀が、千載一遇のチャンスを与えた! なぜ光秀は信長を討ったのか。背後に隠された驚くべき状況と、すべてを操る男の存在とは!? 新事実をもとに日本史最大のクーデターの真実に迫る、壮大な歴史捜査ドキュメント!
 | 【文庫】 本能寺の変 431年目の真実 |
| 明智 憲三郎 | |
| 文芸社 |
>>> 「本能寺の変 431年目の真実」読者書評
>>> 「本能寺の変の真実」決定版出版のお知らせ
--------------------------
明智憲三郎著の第4作『「本能寺の変」は変だ! 明智光秀の子孫による歴史捜査授業』文芸社
「秀吉がねつ造し、軍記物に汚染された戦国史を、今一度洗濯いたし申し候」。40万部突破の『本能寺の変 431年目の真実』の著者、明智憲三郎がさらなる歴史捜査を通じて、より解り易く「本能寺の変」の真実を解説した歴史ドキュメント! 「ハゲだから謀反って変だ! 」「歴史の流れ無視って変だ! 」「信長の油断って変だ! 」等々、まだある驚愕の真実に迫る!
本能寺の変研究の欠陥を暴き、「本当の歴史」を知る面白さを説く!
「若い方々や歴史に興味のない方々に歴史を好きになってもらいたいと思って書きました」 明智憲三郎
>>> サンテレビ「カツヤマサヒコSHOW」対談YouTube動画はこちら
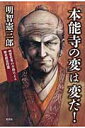 「本能寺の変」は変だ!著者:明智憲三郎価格:1,080円(税込、送料込)楽天ブックスで詳細を見る |
 | 「本能寺の変」は変だ! 明智光秀の子孫による歴史捜査授業 |
| amazonで詳細を見る | |
| 文芸社 |
【明智憲三郎著作一覧】
2016年5月発売予定
『「本能寺の変」は変だ! 明智光秀の子孫による歴史捜査授業』文芸社
>>> 文芸社のページ
2015年7月発売
『織田信長 四三三年目の真実 信長脳を歴史捜査せよ!』幻冬舎
>>> 幻冬舎のページ
2013年12月発売
『本能寺の変 431年目の真実』文芸社文庫
>>> 文芸社のページ
2009年3月発売
『本能寺の変 四二七年目の真実』プレジデント社




















さらに不可解なのは、12日から対峙、合戦は13日の午後遅く、というタイミングです。 つまり秀吉軍がボトルネックを出た直後に大規模戦闘はおこらなかった、としか考えられません。 何故、敵が一番脆弱なタイミングで攻撃が仕掛けられなかったのか、あるいは仕掛けたが撃退されたのでしょうか? このあたり、光秀の意図が理解できません。
不知火さんが示唆されていた援軍を待っていた可能性、とても魅力的な仮説と思います。 これで、挟撃をしなかったこと、不可解な時間の引き延ばし、淀城、勝龍寺城の重要性(援軍でも突然戦場に飛び込むと思わぬ混乱を引き起こすでしょう。 城などの明確な拠点に集合し、その後に連携して行動を起こすことが好ましいと思われます。)などがきれいに説明できると思います。 そうすると、次の疑問は「光秀は、誰が、どのルートで山崎に駆けつけると想定していたか?」、あるいはそのあたりに光秀の敗走と死に関する謎の答えがあるかもしれませんね。
それにしても、うすうす感じてはいましたが、「天王山の戦い」が無かったとは…。 今回の通説斬りも実にお見事です。 日本人はありもしなかった戦闘を、ワーテルローやゲティスバーグのように称えていたんですね。 軍記物恐るべし、と言ったところでしょうか。
ただ、この東黒門に光秀が軍を布陣したのであれば、これがまさに「西国街道隘路説」ではないでしょうか?
禁制により門から門までを戦場にしなかったとしても、光秀が東黒門出口に布陣し、秀吉軍を誘導する作戦を取ったとしたら、今まで多く語られた、狭い隘路で迎え撃つ作戦そのままになります。
そして、この説だと天王山支配権の重要性が増し、定説のまま「天王山支配が勝敗を分けた」説も成り立ってしまいます。
この地図通り、まさに天王山の秀吉軍が光秀軍の側面から討つ事が出来るためです。
(禁制のため)布陣が隘路の中央でなく、隘路出口であったとしても、「西国街道を通らなくても光秀軍に到達出来るルートがある」ことは秀吉にとっては大きなメリットかと思われます。
雨だったから天王山からの攻撃の有効性は低かったというのは当日の天気の結果論であり、「前夜」の段階まで、この作戦を遂行するに当たっては天王山の重要性は高いと思われます。
定説では「前夜の天王山争奪戦に光秀が負けた」→「横からの攻撃を受けるため隘路での作戦は出来ない」→「円明寺川に対峙するところまで陣を引いて決戦」ということだと思いますが、明智先生の説では、当日の天気の判断で、敢えてやはり光秀は隘路出口に布陣して決戦したということでしょうか?
もしくは、円明寺川で対峙してる状態から隘路出口まで布陣しなおすことは不可能ですので、この説では円明寺川で双方が対峙したことすらなかったと考えて宜しいのでしょうか?
こちらが、現在天王山展望台で紹介されている山崎合戦の布陣図です。
下記にアップしましたので、宜しければご覧下さい。
http://www.geocities.jp/yaminooni2000/yamazakikassenn.jpg
この形が一応現在の定説の「円明寺川対峙説」の形かと思いますが、近年の研究では、「隘路出口決戦説」が有力ということになるのでしょうか?
もしそうだとしたら、この事実は大山崎町に確認する必要があるように思いました。
しかしながら、「隘路出口」が決戦の場だったとしたら、円明寺川で対峙する説よりも、「天王山の重要性は遥かに増す」ように思いますので、「天王山争奪戦」が無かったとしても、後に「天王山を支配したことが勝敗を決した」と宣伝するのはあながち間違いでは無いように思います。
「甫庵太閤記」に関しては、やはり、なるほど。と感じました。
作家の井沢元彦先生も「元祖「太閤記」が史実を曲げた」と指摘されていますね。
しかしながら、私は小瀬甫庵の問題以上に、その間違いをわかっていながら定説を修正しようとする動きが少ない現代の方が問題のように思います。
大河ドラマなどでは、歴史の正確性よりも、エンターテイメント性の方が重要視され、史実にないエピソードがどんどん加えられて歴史人物が意図的に作られ続けています。
国営放送がそういうスタンスですので、それを受け取る一般視聴者側が誤った情報を受け続けているように思います。
あと1点、面白いと感じたのが「光秀は十日に摂津まで侵出し、その後山崎近辺まで退却してきています。」という点です。
これは記録としてちゃんと残っていないことなのですが、実は私の地元尼崎(私は尼崎出身、現在伊丹在住です)で、秀吉が備中から尼崎に入ろうと武庫川を渡る時に、秀吉軍と明智軍の交戦があったとの言い伝えがあります。
この辺りも、私にとりましては調べて行きたい部分でもあります。
こうして疑問点を明確にして、その疑問を晴らすように捜査を続けて蓋然性(確からしさの度合)を上げていくことが現代の犯罪捜査にも私の歴史捜査にも共通する基本事項です。
よい材料をいろいろいただきましたので、『歴史捜査「山崎の合戦」その3:合戦の経緯』でその辺りの解明をしてみたいと思います。軍記物が作った通説を排除するとどのような真実が見えてくるか?私も楽しみです。
「西国街道隘路説」も「円明寺川対峙説」も知りませんが、逆に全く白紙で捜査するメリットも高いと思います。虚心坦懐で判決を下す裁判官の姿勢と同じ立場に立てます。どのような説にも思い入れがないのです。
私が本能寺の変の蓋然性の高い真実を見出しえた理由は今思えばここにあったと思います。何も先入観を持たない。ただ、史実を見極めて、そこから推理する。
結論が「西国街道隘路説」になるのか「円明寺川対峙説」になるのか全くわかりません。また、そのどちらかに答を求めるつもりもありません。信憑性ある史料が何を語っているか、そしてそこから何を(どこまで)言えるのか。これが歴史捜査の姿勢です。
こうして私の出す答をご期待いただきたいですし、それに対する反論も期待しています。そのキャッチボールが蓋然性を高めていくステップとなります。
ですので山の手にも川の手にも対面する形で、明智軍も兵を置いていたと思われます。
つまり、円明寺川を挟んでの両軍対峙の形ですね。
明智軍も兵を分散させていたのであれば、高山軍に負けたこともあり得たのではないでしょうか。
しかし、地形的に言えることは、中央の明智軍は完全な平場に対して、高山軍は東黒門が城門の役割を果たせていた可能性があると思います。
フロイス2さんがご指摘されている通り、防御壁があれば火力は絶大です。黒門の規模はわかりませんが、当時の山崎の町の能力を考えると堺に匹敵するかそれ以上に守りの強い門と壁を備えていた可能性があり、雨をしのげた形で一斉放火出来たとも考えられます。
実は、私が感じる謎に通じるのですが、秀吉軍は天王山と山崎の隘路を押さえており、圧倒的に有利な地形条件を持っていたという点です。
明智軍にあるのは、勝龍寺城のみであとは何の守りもありません。
ですので、兵数だけでなく、地理的条件で既に羽柴軍の勝利が確定しています。
例え明智軍が獅子奮迅の働きで羽柴軍を押し、奇跡的に兵数をカバー出来たとしても、狭い隘路と天王山を備えた羽柴本陣に明智軍が到達することは不可能です。しかし、光秀側は対面した兵のどこかが敗れるとすぐ決壊し、本陣を突かれるという非常に脆い配置になっています。つまり全てにおいてこれは負け戦が決まっていた合戦であると言えます。
そこで感じるのは、「何故光秀はこの場所で合戦したのか」という点です。坂本や安土は遠い選択肢だったとしても、京に秀吉を入れないためであったとしたら、下鳥羽から山崎の間で、この勝龍寺城が最善の策だった、という点にはなはだ疑問を持ちます。
山崎の町は禁制があるから、戦場を数百メートルずらしました。などという判断はあり得ないと思います。
ですので、光秀が本陣を構えた場所が「勝龍寺城近辺である」という点に深い意味を感じてしまいます。
ここに光秀が本陣を置き、勝利の可能性を上げる唯一の理由として考えられるのはもはや「勝龍寺城に援軍が来る」ことのみです。
残された証言等を見ても、山崎合戦は確かに一見大きな謎など無いように感じます。
しかし、要所で「疲労し」や「暗闇」等と不自然な表現が、不整合を緩和する潤滑油の役割をもたらしているような気がしてなりません。
あと、私が地元民だからかもしれないですが、
兼見卿記の「十日 光秀、摂津を攻める。」この一文も非常に気になります。
光秀は摂津のどこまで来ていたのか。西国街道の山崎を越えるとそこは摂津。そしてまず現れる主要な町は高山右近の高槻城になります。この時に右近と交戦したのか、それともこの時点では右近は明智軍の進軍をスルーさせたのか。
そして、私の地元尼崎に「明智軍と羽柴軍の交戦があった」との伝説があります。
これは軍記物の創作なのかもしれませんが、光秀が尼崎で「待つ討ちの陣」を敷いていたとされ、その場所が松内町という町名で残っていたりします。
(私のブログでその点触れていますので宜しければ見てみてください。http://ameblo.jp/tokinoasiato/entry-10549273533.html)
もしも10日に攻めた摂津が尼崎だったとしたら、山崎合戦の先陣、高山右近(高槻城)、中川清秀(茨木城)、池田恒興親子(伊丹城・尼崎城)は10日の明智軍の侵攻に対してスルーしていたことになります。
この、摂津衆と明智軍の間の、山崎合戦に至るまでの関係性がどのようなものだったのかも私にとっては大きな謎です。
そして、光秀が最期に選択した勝龍寺城は元々は盟友とされた細川藤孝の城。
残された史料が少ない中では真実の解明はとても難しいのかもしれませんが、この山崎合戦には様々な調略や攻防、裏切りがうごめいているように感じます。