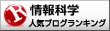2回に分けて光秀前半生の歴史捜査について書きましたが、本格的な捜査はまだこれからです。
光秀前半生の歴史捜査:鍵は朽木谷!
光秀前半生の歴史捜査:鍵は連歌!
これまでの捜査でわかったことは「信長上洛以降の戦国後期に比して戦国前期の研究が極めて少ない」ということです。これは小説やテレビ・映画の取り扱いとも共通しています。我々日本人の知識量は戦国前期と後期とでは異常なアンバランスな状 . . . 本文を読む
前回は光秀が将軍足利義晴・義輝父子に従って近江朽木谷にいた可能性を示しました。
★ 光秀前半生の歴史捜査:鍵は朽木谷!
もう少し前のこともわからないかと捜査を進めています。まだ確たることがわかってはいませんが、見えてきたことをご報告いたします。
『尊卑分脈』明智系図に注目!
系図はどれも出鱈目というのが通説です。というのも、ある時点である人が自分の都合のよいように系図を作るというこ . . . 本文を読む
「戦国時代って織田信長、豊臣秀吉、徳川家康なの?」という疑問を持ちませんか?歴史小説やテレビ・映画では信長が足利義昭と共に上洛した永禄十一年(1568年)からを戦国時代として扱っているように見えてしまいます。従来の「本能寺の変」の研究も視野に入れているのは、だいたいその辺りからではないでしょうか。
でも、そんなことはないはず!と私は思っています。信長にしろ光秀にしろ、もっと以前からの人生や父祖 . . . 本文を読む
前回は『甲陽軍鑑』の話から『元親記』や『当代記』の話へ展開しました。焦点となったのが武田攻めからの信長一行の帰路となった家康領通過です。そこで光秀方・家康方双方の家臣による同盟交渉が行われた可能性が浮かび上がりました。
今回は家康領通過が「家康領の軍事視察」であったという拙著『本能寺の変 四二七年目の真実』での主張を裏付けるエピソードが『甲陽軍鑑』に書かれているお話をしましょう。
巻二十の三 . . . 本文を読む
前回は『甲陽軍鑑』の信憑性についてと、光秀が武田勝頼に謀反を起こすので味方になれと伝えてきていた記事があることを書きました。
★ 『甲陽軍鑑』の歴史捜査(その1)
それが天正十年二月であることが信長の二月九日に発した命令と符合している点を指摘しました。もうひとつ符合しているのが長宗我部元親の家臣の書いた『元親記』の記事です。これは拙著『本能寺の変 四二七年目の真実』にも書きましたが、この年 . . . 本文を読む
『甲陽軍鑑』という武田信玄・勝頼の事跡を書いた書物があります。甲州流の軍学書ともいわれ、NHK大河ドラマ「風林火山」で有名になった山本勘助の活躍も書かれています。ところが、この書は歴史研究界では偽書として山本勘助の実在と共に抹殺されてきました。そのように位置づけられた書物だったので拙著『本能寺の変 四二七年目の真実』にも一切参考にしませんでした。
でも、それって本当かな?!
歴史研究界の研究 . . . 本文を読む
慶應義塾大学卒業生の同窓会イベント(連合三田会)の理工学部同窓会講演会で講演したご縁で理工学部のホームページの卒業生コラム「塾員往来」への寄稿を依頼されました。
★ 連合三田会大会での講演
情報システム学会からのご依頼とほぼ同時期に依頼をいただいたので、締め切りに間に合うか若干心配しつつもお引き受けしました。締切日の早かった情報システム学会の寄稿を先に終わらせて、塾員往来の寄稿はようやく数 . . . 本文を読む
戦国時代末期を生きた江村専斎(えむら・せんさい)という老人が語った話を聞き書きした『老人雑話』というものがあるのは「本能寺の変」研究者にはよく知られた話です。そこには通説とは少しずれた話が書かれており、研究者が引用する場合にも極めて遠慮した使い方がされています。本能寺の変の当時に十八歳だったという老人からの聞き書きを私も信憑性がないとこれまで全く無視していました。
とはいえ、最近少し気になって . . . 本文を読む
【2010年12月4日追記】
2010年5月16日にTBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」に生出演させていただきました。今思えば、私と拙著『本能寺の変 四二七年目の真実』にとってはエポックメイキングなイベントでした。何故ならば、amazonでの拙著の売上順位が急騰し、しかも1ヶ月以上に渡ってその順位が持続したからです。つまり、この放送によって私が世の中に広めたかったことへの理解者が格段に増えたとい . . . 本文を読む