「戦国時代って織田信長、豊臣秀吉、徳川家康なの?」という疑問を持ちませんか?歴史小説やテレビ・映画では信長が足利義昭と共に上洛した永禄十一年(1568年)からを戦国時代として扱っているように見えてしまいます。従来の「本能寺の変」の研究も視野に入れているのは、だいたいその辺りからではないでしょうか。
でも、そんなことはないはず!と私は思っています。信長にしろ光秀にしろ、もっと以前からの人生や父祖の人生での経験などからも様々な影響を受けていたはずです。そういった背景をよく理解しないで、限定されたわずかな幅で切り出された時空間での出来事から歴史を判断してはいけないだろうと感じています。
そこで光秀の前半生や出自についても調べて、従来の通説とは全く異なる姿を拙著『本能寺の変 四二七年目の真実』に書きました(第2章 通説とは異なる光秀の前半生)。拙著の中で、光秀は足利将軍の親衛隊である奉公衆の家柄であることや義輝将軍時代には細川藤孝に仕えていて、義輝が暗殺されて義昭が近江に逃れてから義昭の奉公衆に採用されたことをかなり高い蓋然性で明らかにしました。ただ、それだけではまだ十分に解明できたとはいえません。家系図もはっきりしませんし、出生地やどこでどう過ごしてきたのかも明らかにはなっていません。
そこで、今年の夏頃からそこを知りたいと思って歴史捜査を再開しました。現時点では次のような仮説にたどりついています。
「足利義輝の父の義晴将軍の時代から将軍周辺にいた!」
その根拠をご説明します。
福知山に光秀を祀った御霊神社がありますが、光秀の霊を勧招したのは1669年に福知山の藩主となった朽木稙昌(くつき・たねまさ)です。1582年の本能寺の変から80年以上もたって、何故謀反人の霊をわざわざ勧招したのか不思議に思いませんか?

そう思って調べてみると、この人物の三代前の晴綱・藤綱・成綱・輝孝の四兄弟はいずれも幕府に仕えていたことがわかりました。藤綱・成綱・輝孝は光秀が足軽衆として書かれている幕府の役人名簿である『永禄六年諸役人附』に名前が書かれています。つまり光秀の同僚!
朽木一族と光秀とは深い縁があって、その縁で稙昌が光秀の霊を勧招したという仮説が立ちます。
さらに調べると、この朽木一族は将軍義晴・義輝父子とは極めて縁が深いことがわかりました。この時代、足利将軍の力は弱まり、細川氏や三好氏との抗争でしばしば京都から逃げ出す事態に追い込まれていました。義晴・義輝父子が逃げてかくまわれた先が近江の朽木谷、つまり朽木氏でした。長いときは5年も朽木谷に留まっていました。
★ Wikipedia「朽木氏」
★ Wikipedia「足利義晴」
その関係の深さを示すのが朽木一族の名前です。晴綱の晴は将軍義晴、藤綱の藤は将軍義輝(初め義藤と名乗った)、輝孝の輝は将軍義輝からもらっています。
義輝の側近だった細川藤孝(義晴の落胤という説もある)に仕えていた光秀は当然のこととして藤孝が仕える義晴・義輝に同行して朽木谷へ行ったでしょう。藤孝・光秀、そして朽木一族は都落ちした将軍を支えて苦楽を共にしたわけです。
★ Wikipedia「細川藤孝」
以上のように推理しましたが、いかがでしょうか。
将軍は朽木谷に逃れる前には近江の坂本に逃れています。後に光秀が信長から領地として与えられた地です。ひょっとすると、光秀はもともと坂本にいて、逃れてきた将軍と一緒に朽木谷へ行ったのかもしれません。信長は光秀にゆかりのある地だったので光秀に坂本を与えたとも考えられるからです。
まだまだ、捜査は始まったばかりです。何か関連する情報がありましたら教えてください。
<<続く>>
>>>ブログのご案内
>>>本能寺の変 四二七年目の真実
でも、そんなことはないはず!と私は思っています。信長にしろ光秀にしろ、もっと以前からの人生や父祖の人生での経験などからも様々な影響を受けていたはずです。そういった背景をよく理解しないで、限定されたわずかな幅で切り出された時空間での出来事から歴史を判断してはいけないだろうと感じています。
そこで光秀の前半生や出自についても調べて、従来の通説とは全く異なる姿を拙著『本能寺の変 四二七年目の真実』に書きました(第2章 通説とは異なる光秀の前半生)。拙著の中で、光秀は足利将軍の親衛隊である奉公衆の家柄であることや義輝将軍時代には細川藤孝に仕えていて、義輝が暗殺されて義昭が近江に逃れてから義昭の奉公衆に採用されたことをかなり高い蓋然性で明らかにしました。ただ、それだけではまだ十分に解明できたとはいえません。家系図もはっきりしませんし、出生地やどこでどう過ごしてきたのかも明らかにはなっていません。
そこで、今年の夏頃からそこを知りたいと思って歴史捜査を再開しました。現時点では次のような仮説にたどりついています。
「足利義輝の父の義晴将軍の時代から将軍周辺にいた!」
その根拠をご説明します。
福知山に光秀を祀った御霊神社がありますが、光秀の霊を勧招したのは1669年に福知山の藩主となった朽木稙昌(くつき・たねまさ)です。1582年の本能寺の変から80年以上もたって、何故謀反人の霊をわざわざ勧招したのか不思議に思いませんか?

そう思って調べてみると、この人物の三代前の晴綱・藤綱・成綱・輝孝の四兄弟はいずれも幕府に仕えていたことがわかりました。藤綱・成綱・輝孝は光秀が足軽衆として書かれている幕府の役人名簿である『永禄六年諸役人附』に名前が書かれています。つまり光秀の同僚!
朽木一族と光秀とは深い縁があって、その縁で稙昌が光秀の霊を勧招したという仮説が立ちます。
さらに調べると、この朽木一族は将軍義晴・義輝父子とは極めて縁が深いことがわかりました。この時代、足利将軍の力は弱まり、細川氏や三好氏との抗争でしばしば京都から逃げ出す事態に追い込まれていました。義晴・義輝父子が逃げてかくまわれた先が近江の朽木谷、つまり朽木氏でした。長いときは5年も朽木谷に留まっていました。
★ Wikipedia「朽木氏」
★ Wikipedia「足利義晴」
その関係の深さを示すのが朽木一族の名前です。晴綱の晴は将軍義晴、藤綱の藤は将軍義輝(初め義藤と名乗った)、輝孝の輝は将軍義輝からもらっています。
義輝の側近だった細川藤孝(義晴の落胤という説もある)に仕えていた光秀は当然のこととして藤孝が仕える義晴・義輝に同行して朽木谷へ行ったでしょう。藤孝・光秀、そして朽木一族は都落ちした将軍を支えて苦楽を共にしたわけです。
★ Wikipedia「細川藤孝」
以上のように推理しましたが、いかがでしょうか。
将軍は朽木谷に逃れる前には近江の坂本に逃れています。後に光秀が信長から領地として与えられた地です。ひょっとすると、光秀はもともと坂本にいて、逃れてきた将軍と一緒に朽木谷へ行ったのかもしれません。信長は光秀にゆかりのある地だったので光秀に坂本を与えたとも考えられるからです。
まだまだ、捜査は始まったばかりです。何か関連する情報がありましたら教えてください。
<<続く>>
>>>ブログのご案内
>>>本能寺の変 四二七年目の真実
 | 本能寺の変 四二七年目の真実明智 憲三郎プレジデント社このアイテムの詳細を見る |










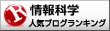















昨年は大変お世話になりました。
今年も宜しくご指導ください。
朽木氏と明智氏の繋がりについて、ちょっと気になることを
思い出しました。
御存知のように、朽木街道や鯖街道と呼ばれる道を通ると、
近江の国から比叡山を越えて京都側に入ってすぐ
上高野・大原・八瀬に至るエリアに着きます。
この上高野・大原・八瀬に至る分岐点にあたる地点に、
三宅八幡宮という、地元ではよく知られた神社があります。
(実はわたしもまだ訪れたことがないので土地鑑はないのですが・汗)
この三宅八幡宮というのは、光秀公の娘・倫と結婚した
明智秀満(三宅左馬助)の先祖といわれる児島高徳ゆかりの神社なので、
三宅八幡宮と呼ばれるようになったそうです。
本能寺の変の直後、左馬助は当時二歳だった息子・三宅藤兵衛を
いくらかの金とともに姥に預け落ちのびさせたという伝承を
島原図書館で見つけました。
伝承には二種類あり、一つは藤兵衛を抱えた姥は八瀬の里に
辿りつき、八瀬の里人(八瀬童子という鬼の子孫として有名ですね!)
は喜んで藤兵衛を匿ったという話。
もう一つは、長じた藤兵衛の家臣だった人が語り遺した話です。
藤兵衛を抱えた姥は京の町まで辿りつき、
左馬助の友人だった大文字屋という人に預けられ、
そこで十代まで育ったという話です。
元服後細川家を尋ね、藤兵衛の生存を喜んだ
ガラシャ夫人が面倒をみるようになったと伝わります。
この大文字屋という人についてちょっと調べてみたところ、
光秀公と親しく、茶会でも顔を合わせている大文字屋宗観という、
京の大商人で大富豪の人が確かに存在していたのです。
藤兵衛を保護したのはこの大文字屋宗観なのでしょうか…。
わたしの考えでは、藤兵衛が保護された二つの話、
八瀬説、大文字屋説の二説は、両方とも真実を伝えているような気がします。
本能寺後、近江から近い八瀬へひとまず落ち着き、
その後京へと辿りついたのではないでしょうか。
朽木氏ゆかりの場所に、明智氏のみならず三宅氏との関わりも
見えてくるような気がするのですが、わたしの考え過ぎでしょうか。
朽木氏の話からかなり脱線してしまったみたいです。失礼いたしました(汗)