
秀吉がねつ造し、軍記物に汚染された戦国史を今一度洗濯いたし申候
新作『織田信長 四三三年目の真実』幻冬舎では「なぜ桶狭間の戦いで信長が勝てたか」という謎も解明いたしました。『信長公記』首巻に書かれた桶狭間の戦いの記述を基にして正面攻撃説が唱えられて20年。多勢に無勢の信長が正面攻撃で勝てた理由は「偶然・幸運」とされていましたが、極めて妥当な作戦が立てられていたことが初めて立証されました。
>>> 「桶狭間の戦い」信長必勝の作戦が解けた!!
本としての全体バランスの関係からカットした文を以下に掲載します。『信長公記』の信憑性をどのように評価するかというのが主題ですが、「本能寺の変」研究で見られる奇妙な論理の一例のご紹介ともなっています。
【『信長公記』首巻の信憑性】
『信長公記』は織田信長側近の太田牛一が信長の死後に編纂した史料である。信長の側近が書いた史料ということで「第一級の史料」と評価されるが、「二次史料(後世の編纂物)」であるとして軍記物と同列視する研究者もいる。しかし、後世の小説家(軍記物作家)が書いたものと現場に立ち会った本人が後に書いたものとでは決定的に信憑性が異なることは明らかだ。紋切り型の「二次史料だから信憑性がない」という評価は科学的ではない。
『信長公記』は信長の少年期から上洛に至るまでの前半生をまとめて書いた首巻と上洛後の後半生の一年を一巻にして書かれた十五巻とから構成される。後半生の十五巻は牛一自身が「日記の如くに書き溜めたものをのちに編纂した」と書き残しており、記憶違いもなく、信憑性が高いことは確かだ。ただし、最後の第十五巻に書かれている光秀の愛宕山での連歌興行の話と徳川家康の伊賀越えの話は牛一が情報を直接入手する立場にない。誰かからの伝聞情報であり、明らかに信憑性が落ちる。
問題は首巻である。牛一はそもそも『信長公記』という本を書いたわけではなく、首巻と十五巻が別々に書かれていたものを後世の人が一冊にまとめて『信長公記』と称されるようになったものである。十五巻から成る『信長記』を編纂し終えた牛一が信長を偲(しの)んで別に書いたものが首巻と呼ばれているのだ。したがって、詳細の記憶は薄れている可能性があるが、重要な要点は覚えていて書かれているとみてよいであろう。牛一の記憶に深く刻まれたことが書かれたのだ。特に自分が参陣した合戦の記憶は忘れがたいものがあったはずだ。
『信長公記』は印刷出版されず、牛一の自筆の原本から写し書きした写本が作られ、さらに写本から写し書きして写本が作られるといった形で広まった。このため、現存する『信長公記』の記述は一冊ごとに異なっている。ここに『信長公記』の信憑性評価の難しさがある。書き写した際に誤記もあれば、省略・追記も生じる。無意識に起きる場合もあるし、意図的な省略・追記もあり得る。したがって、自筆本の伝存していない首巻については個々に写本間の記述の差異を評価して信憑性を評価するしかない。
具体例として桶狭間の戦いの記述についてご紹介しよう。町田本や陽明文庫本と呼ばれる写本と天理大学附属図書館所蔵本(天理本)では異なる記述がなされている。この天理本には桶狭間の戦いの前夜に軍議が行われ、信長の決戦の意思に対して家老衆が反対して籠城を主張したことなどの記述がある。町田本や陽明文庫本には「軍議は行われなかった」ことが書かれている。
歴史作家の桐野作人氏は天理本の記述が『甫庵信長記』と類似していることを指摘した上で、天理本の記述が正しいものとして、これまで信憑性に問題ありとされてきた『甫庵信長記』の再評価をすべきと主張している(『歴史読本』二〇〇一年十二月号)。
しかし、これは奇妙な論理であり、話が全く逆である。天理本が書き写された際に『甫庵信長記』を参照して加筆修正が行われたとみるべきだ。『甫庵信長記』は慶長十七年(1612)に印刷出版されてベストセラーとなり広まった。桐野氏は天理本が書き写された時期が「寛永年間頃」としており、1624~1645年頃に書き写されたと認識しておられる。既に『甫庵信長記』が世の中に流布している状況での写本である。
『甫庵信長記』の作者が十年以上も後に成立した天理本を参照して書くことはタイムマシンでもないと不可能だ。そうではないとすると、天理本と同じ記述をした牛一の自筆本なり別の写本が『甫庵信長記』の書かれた慶長十七年以前に存在したと仮定しないと成立しない論理だ。しかし、このような本は発見されていない。
一方、天理本を写し書きした人物はその際に『甫庵信長記』を参照可能であり、これを参照して書いた蓋然性の方が明らかに高い。
この例のように、江戸時代に書かれてベストセラーとなった『甫庵信長記』(1612年成立)や『明智軍記』(1702年以前成立)の記述に類似した記述がある書物については、まずこれら軍記物から「汚染」されたことを疑って、成立した年を確認すべきである。
桐野氏がやはり信憑性ありとみなしている『稲葉家譜』に書かれている「斎藤利三を元の主君へ返せと信長が怒って光秀の頭を叩いたら、かつらが外れて光秀が恥をかいた」という話は正に『明智軍記』からの汚染と考えるべきだ。
桐野氏がなぜこのような奇妙な論理を展開しているのかも「本能寺の変」研究におけるひとつの謎であろう。
>>> 桐野作人氏の奇妙な論理:『稲葉家譜』の信憑性
【他にもある、奇妙な論理】
>>> 兼見卿記:金子拓准教授の強引な論理
もっと「奇妙な論理」の実例を知りたい方におすすめの本『「本能寺の変」は変だ!』
簿記検定史受験対策講座を開設している公認会計士柴山政行氏の「おすすめ本」動画です。『「本能寺の変」は変だ』明智憲三郎著。ご覧ください。5分間で大変わかりやすく解説されています。 >>> YouTube動画へ
>>> 公認会計士柴山政行氏のブログのページへ
>>> 『「本能寺の変」は変だ!』読者書評
>>> 歴史学は未来学(『「本能寺の変」は変だ!』はじめに)
>>> 本能寺の変、その「うんちく」間違ってます!
>>> 『「本能寺の変」は変だ!』目次
【明智憲三郎著作一覧】
2016年5月発売
『「本能寺の変」は変だ! 明智光秀の子孫による歴史捜査授業』文芸社
>>> 文芸社のページ
2015年7月発売
『織田信長 四三三年目の真実 信長脳を歴史捜査せよ!』幻冬舎
>>> 幻冬舎のページ
2013年12月発売
『本能寺の変 431年目の真実』文芸社文庫
>>> 文芸社のページ
2009年3月発売
『本能寺の変 四二七年目の真実』プレジデント社

(この記事は2015年7月19日投稿の記事に加筆修正したものです)
新作『織田信長 四三三年目の真実』幻冬舎では「なぜ桶狭間の戦いで信長が勝てたか」という謎も解明いたしました。『信長公記』首巻に書かれた桶狭間の戦いの記述を基にして正面攻撃説が唱えられて20年。多勢に無勢の信長が正面攻撃で勝てた理由は「偶然・幸運」とされていましたが、極めて妥当な作戦が立てられていたことが初めて立証されました。
>>> 「桶狭間の戦い」信長必勝の作戦が解けた!!
本としての全体バランスの関係からカットした文を以下に掲載します。『信長公記』の信憑性をどのように評価するかというのが主題ですが、「本能寺の変」研究で見られる奇妙な論理の一例のご紹介ともなっています。
【『信長公記』首巻の信憑性】
『信長公記』は織田信長側近の太田牛一が信長の死後に編纂した史料である。信長の側近が書いた史料ということで「第一級の史料」と評価されるが、「二次史料(後世の編纂物)」であるとして軍記物と同列視する研究者もいる。しかし、後世の小説家(軍記物作家)が書いたものと現場に立ち会った本人が後に書いたものとでは決定的に信憑性が異なることは明らかだ。紋切り型の「二次史料だから信憑性がない」という評価は科学的ではない。
『信長公記』は信長の少年期から上洛に至るまでの前半生をまとめて書いた首巻と上洛後の後半生の一年を一巻にして書かれた十五巻とから構成される。後半生の十五巻は牛一自身が「日記の如くに書き溜めたものをのちに編纂した」と書き残しており、記憶違いもなく、信憑性が高いことは確かだ。ただし、最後の第十五巻に書かれている光秀の愛宕山での連歌興行の話と徳川家康の伊賀越えの話は牛一が情報を直接入手する立場にない。誰かからの伝聞情報であり、明らかに信憑性が落ちる。
問題は首巻である。牛一はそもそも『信長公記』という本を書いたわけではなく、首巻と十五巻が別々に書かれていたものを後世の人が一冊にまとめて『信長公記』と称されるようになったものである。十五巻から成る『信長記』を編纂し終えた牛一が信長を偲(しの)んで別に書いたものが首巻と呼ばれているのだ。したがって、詳細の記憶は薄れている可能性があるが、重要な要点は覚えていて書かれているとみてよいであろう。牛一の記憶に深く刻まれたことが書かれたのだ。特に自分が参陣した合戦の記憶は忘れがたいものがあったはずだ。
『信長公記』は印刷出版されず、牛一の自筆の原本から写し書きした写本が作られ、さらに写本から写し書きして写本が作られるといった形で広まった。このため、現存する『信長公記』の記述は一冊ごとに異なっている。ここに『信長公記』の信憑性評価の難しさがある。書き写した際に誤記もあれば、省略・追記も生じる。無意識に起きる場合もあるし、意図的な省略・追記もあり得る。したがって、自筆本の伝存していない首巻については個々に写本間の記述の差異を評価して信憑性を評価するしかない。
具体例として桶狭間の戦いの記述についてご紹介しよう。町田本や陽明文庫本と呼ばれる写本と天理大学附属図書館所蔵本(天理本)では異なる記述がなされている。この天理本には桶狭間の戦いの前夜に軍議が行われ、信長の決戦の意思に対して家老衆が反対して籠城を主張したことなどの記述がある。町田本や陽明文庫本には「軍議は行われなかった」ことが書かれている。
歴史作家の桐野作人氏は天理本の記述が『甫庵信長記』と類似していることを指摘した上で、天理本の記述が正しいものとして、これまで信憑性に問題ありとされてきた『甫庵信長記』の再評価をすべきと主張している(『歴史読本』二〇〇一年十二月号)。
しかし、これは奇妙な論理であり、話が全く逆である。天理本が書き写された際に『甫庵信長記』を参照して加筆修正が行われたとみるべきだ。『甫庵信長記』は慶長十七年(1612)に印刷出版されてベストセラーとなり広まった。桐野氏は天理本が書き写された時期が「寛永年間頃」としており、1624~1645年頃に書き写されたと認識しておられる。既に『甫庵信長記』が世の中に流布している状況での写本である。
『甫庵信長記』の作者が十年以上も後に成立した天理本を参照して書くことはタイムマシンでもないと不可能だ。そうではないとすると、天理本と同じ記述をした牛一の自筆本なり別の写本が『甫庵信長記』の書かれた慶長十七年以前に存在したと仮定しないと成立しない論理だ。しかし、このような本は発見されていない。
一方、天理本を写し書きした人物はその際に『甫庵信長記』を参照可能であり、これを参照して書いた蓋然性の方が明らかに高い。
この例のように、江戸時代に書かれてベストセラーとなった『甫庵信長記』(1612年成立)や『明智軍記』(1702年以前成立)の記述に類似した記述がある書物については、まずこれら軍記物から「汚染」されたことを疑って、成立した年を確認すべきである。
桐野氏がやはり信憑性ありとみなしている『稲葉家譜』に書かれている「斎藤利三を元の主君へ返せと信長が怒って光秀の頭を叩いたら、かつらが外れて光秀が恥をかいた」という話は正に『明智軍記』からの汚染と考えるべきだ。
桐野氏がなぜこのような奇妙な論理を展開しているのかも「本能寺の変」研究におけるひとつの謎であろう。
>>> 桐野作人氏の奇妙な論理:『稲葉家譜』の信憑性
【他にもある、奇妙な論理】
>>> 兼見卿記:金子拓准教授の強引な論理
もっと「奇妙な論理」の実例を知りたい方におすすめの本『「本能寺の変」は変だ!』
簿記検定史受験対策講座を開設している公認会計士柴山政行氏の「おすすめ本」動画です。『「本能寺の変」は変だ』明智憲三郎著。ご覧ください。5分間で大変わかりやすく解説されています。 >>> YouTube動画へ
>>> 公認会計士柴山政行氏のブログのページへ
>>> 『「本能寺の変」は変だ!』読者書評
>>> 歴史学は未来学(『「本能寺の変」は変だ!』はじめに)
>>> 本能寺の変、その「うんちく」間違ってます!
>>> 『「本能寺の変」は変だ!』目次
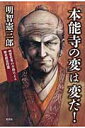 「本能寺の変」は変だ!著者:明智憲三郎価格:1,080円(税込、送料込)楽天ブックスで詳細を見る |
 | 「本能寺の変」は変だ! 明智光秀の子孫による歴史捜査授業 |
| amazonで詳細を見る | |
| 文芸社 |
【明智憲三郎著作一覧】
2016年5月発売
『「本能寺の変」は変だ! 明智光秀の子孫による歴史捜査授業』文芸社
>>> 文芸社のページ
2015年7月発売
『織田信長 四三三年目の真実 信長脳を歴史捜査せよ!』幻冬舎
>>> 幻冬舎のページ
2013年12月発売
『本能寺の変 431年目の真実』文芸社文庫
>>> 文芸社のページ
2009年3月発売
『本能寺の変 四二七年目の真実』プレジデント社

(この記事は2015年7月19日投稿の記事に加筆修正したものです)










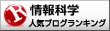















「既に『甫庵信長記』が世の中に流布している状況での写本である。」
わかりやすい解説!。見事な推理です。文章としてもわかりやすい。逆転の発送になっているし、矛盾の解読になっている。
また「汚染」という言葉がいいですね。この単語もわかりやすいです。
「かつらが外れて光秀が恥をかいた」という話は正に『明智軍記』からの汚染とのことで、『織田信長 四三三年目の真実』では『明智軍記』で頭を叩いたという話があったと思うので、まさに稲葉家譜の「汚染」箇所ですね