
このブログでは世の中の通説・俗説・虚説をいろいろ斬ってきました。
★ 通説・俗説・虚説を斬る!シリーズの目次
今回まな板に載せるのは明智滝朗著『光秀行状記』です。中部経済新聞社から1966年6月に出版されています。既に絶版となって久しく、中古本市場では5000円程度の値がついています。
著者は苗字からわかるように光秀の子孫で太平洋戦争後、占領軍より追放処分を受け、その無念と無聊を埋めるために光秀研究に没頭したようです。
著者は『明智軍記』のストーリーの基本線を採用しつつも、細部のエピソードについては企業人らしい常識で否定もしており、また、数多くの軍記物の記述を紹介しつつも同様の視点でとらえています。
著者は光秀伝承の地をくまなく訪ねて現地取材を行っています。軍記物の記述とは異なる真実を発掘したかったものと思われます。掲載されている写真は本人が現地取材した際に撮影したもので、写真に付けられたタイトルを列挙すると光秀伝承の地とされるものがほぼ漏れなく並んでいます。
恵那郡明智町千畳敷、明智町萬ケ洞、光秀初湯之井、人丸神社、白鷹城跡、明智城跡、若宮八幡、福井市弥念寺、光秀寺小屋跡、福井県東大味明智屋敷跡、雄島神社、一乗谷朝倉義景居館跡、福井県武生市竜門寺、朝倉義景之墓、京都府亀岡市亀山城跡、八上城跡、福知山城跡、福知山御霊神社、山梨県塩山市恵林寺山門、京都府南桑田郡篠八幡宮、同郡老坂、本能寺織田信長墓、京都二条城、安土城跡織田信長廟、八幡町洞ヶ峠、安土城跡、大手門跡、左馬助光春の鞍と鎧(坂本西教寺)、坂本城跡、明智藪、光秀胴塚、光秀社(光秀首塚)、高野山光秀墓、西教寺光秀墓、岐阜県山県郡中洞光秀墓、福井県東大味光秀墓、比叡山光秀寄進石灯籠、周山城跡、京都府周山町慈眼寺光秀木像並びに位牌
この努力の結果、各地に残る光秀伝承を網羅して紹介する本として価値あるものとなったようで、今でもインターネットで書き込まれている光秀伝承の記事のかなりのものが、それと知ってか知らずかは別にして、この本の記述を引用したものになっています。
そしてこの本が有名にした光秀伝説が「天海僧正光秀説」です。
著者は本の最終章「後日譚」で光秀が山崎の合戦の後も生き残ったという各地の伝承を記しています。これは子孫としての先祖へのロマンの現れといえるでしょう。この章の後半で天海僧正について様々な史料の記事をもとに詳しく書いており、両者の筆跡の写真も載せて、同一人物であった可能性に言及しています。ただし、同一人物と決めつけたわけではなく、「果たして慈眼大師天海大僧正が光秀の後身であるのか、永遠の謎でもあろう」としています。
とはいえ、子孫としての「そうあって欲しい」という思いは強く感じられる文章であり、どうやらこれが発火点となって現代の「天海僧正光秀伝説」を生むことになったようです。Wikipediaの「天海」記事には「この説は明治時代になって唱えられた(須藤光暉『大僧正天海』冨山房、大正五年)もので、明智光秀の子孫と称する明智滝朗が流布したことから広く知られるようになった」と書かれています。
なお、現代の「天海僧正光秀伝説」信奉者が唱える「日光東照宮に桔梗紋がある」という話を私は現地調査して否定しました。著者の名誉にかけて申し上げますが、著者・明智滝朗氏はこのような話を一切書いておりません。
★ 日光東照宮桔梗紋説を斬る!
さて、今回、私はこの『光秀行状記』を斬れませんでした。それは、著者の思いや研究姿勢に私と共通のものを感じるからです。そして加えて、何よりも、著者が私の祖父だからです!
>>>トップページ
>>>ブログのご案内
>>>本能寺の変 四二七年目の真実
【定説の根拠を斬る!シリーズ】
通説を作った羽柴秀吉『惟任退治記』
軍神豊臣秀吉が歪めた本能寺の変研究
定説の根拠を斬る!「中国大返し」
定説の根拠を斬る!「安土城放火犯」
定説の根拠を斬る!「神君伊賀越え」
定説の根拠を斬る!「神君伊賀越え」(続き)
定説の根拠を斬る!「神君伊賀越え」(最終回)
定説の根拠を斬る!「朝倉義景仕官」
定説の根拠を斬る!「光秀の敗走とその死」
定説の根拠を斬る!「光秀の敗走とその死」その2
定説の根拠を斬る!「光秀の敗走とその死」その3
定説の根拠を斬る!「光秀の敗走とその死」その4
【信長は謀略で殺されたのだ 偶発説を嗤うシリーズ】
信長は謀略で殺されたのだ:本能寺の変・偶発説を嗤う
信長は謀略で殺されたのだ:本能寺の変・偶発説を嗤う(続き)
信長は謀略で殺されたのだ:本能寺の変・偶発説を嗤う(完結編)
信長は謀略で殺されたのだ:本能寺の変・偶発説を嗤う(駄目押し編)
★ 通説・俗説・虚説を斬る!シリーズの目次
今回まな板に載せるのは明智滝朗著『光秀行状記』です。中部経済新聞社から1966年6月に出版されています。既に絶版となって久しく、中古本市場では5000円程度の値がついています。
著者は苗字からわかるように光秀の子孫で太平洋戦争後、占領軍より追放処分を受け、その無念と無聊を埋めるために光秀研究に没頭したようです。
著者は『明智軍記』のストーリーの基本線を採用しつつも、細部のエピソードについては企業人らしい常識で否定もしており、また、数多くの軍記物の記述を紹介しつつも同様の視点でとらえています。
著者は光秀伝承の地をくまなく訪ねて現地取材を行っています。軍記物の記述とは異なる真実を発掘したかったものと思われます。掲載されている写真は本人が現地取材した際に撮影したもので、写真に付けられたタイトルを列挙すると光秀伝承の地とされるものがほぼ漏れなく並んでいます。
恵那郡明智町千畳敷、明智町萬ケ洞、光秀初湯之井、人丸神社、白鷹城跡、明智城跡、若宮八幡、福井市弥念寺、光秀寺小屋跡、福井県東大味明智屋敷跡、雄島神社、一乗谷朝倉義景居館跡、福井県武生市竜門寺、朝倉義景之墓、京都府亀岡市亀山城跡、八上城跡、福知山城跡、福知山御霊神社、山梨県塩山市恵林寺山門、京都府南桑田郡篠八幡宮、同郡老坂、本能寺織田信長墓、京都二条城、安土城跡織田信長廟、八幡町洞ヶ峠、安土城跡、大手門跡、左馬助光春の鞍と鎧(坂本西教寺)、坂本城跡、明智藪、光秀胴塚、光秀社(光秀首塚)、高野山光秀墓、西教寺光秀墓、岐阜県山県郡中洞光秀墓、福井県東大味光秀墓、比叡山光秀寄進石灯籠、周山城跡、京都府周山町慈眼寺光秀木像並びに位牌
この努力の結果、各地に残る光秀伝承を網羅して紹介する本として価値あるものとなったようで、今でもインターネットで書き込まれている光秀伝承の記事のかなりのものが、それと知ってか知らずかは別にして、この本の記述を引用したものになっています。
そしてこの本が有名にした光秀伝説が「天海僧正光秀説」です。
著者は本の最終章「後日譚」で光秀が山崎の合戦の後も生き残ったという各地の伝承を記しています。これは子孫としての先祖へのロマンの現れといえるでしょう。この章の後半で天海僧正について様々な史料の記事をもとに詳しく書いており、両者の筆跡の写真も載せて、同一人物であった可能性に言及しています。ただし、同一人物と決めつけたわけではなく、「果たして慈眼大師天海大僧正が光秀の後身であるのか、永遠の謎でもあろう」としています。
とはいえ、子孫としての「そうあって欲しい」という思いは強く感じられる文章であり、どうやらこれが発火点となって現代の「天海僧正光秀伝説」を生むことになったようです。Wikipediaの「天海」記事には「この説は明治時代になって唱えられた(須藤光暉『大僧正天海』冨山房、大正五年)もので、明智光秀の子孫と称する明智滝朗が流布したことから広く知られるようになった」と書かれています。
なお、現代の「天海僧正光秀伝説」信奉者が唱える「日光東照宮に桔梗紋がある」という話を私は現地調査して否定しました。著者の名誉にかけて申し上げますが、著者・明智滝朗氏はこのような話を一切書いておりません。
★ 日光東照宮桔梗紋説を斬る!
さて、今回、私はこの『光秀行状記』を斬れませんでした。それは、著者の思いや研究姿勢に私と共通のものを感じるからです。そして加えて、何よりも、著者が私の祖父だからです!
>>>トップページ
>>>ブログのご案内
>>>本能寺の変 四二七年目の真実
 | 本能寺の変 四二七年目の真実明智 憲三郎プレジデント社このアイテムの詳細を見る |
【定説の根拠を斬る!シリーズ】
通説を作った羽柴秀吉『惟任退治記』
軍神豊臣秀吉が歪めた本能寺の変研究
定説の根拠を斬る!「中国大返し」
定説の根拠を斬る!「安土城放火犯」
定説の根拠を斬る!「神君伊賀越え」
定説の根拠を斬る!「神君伊賀越え」(続き)
定説の根拠を斬る!「神君伊賀越え」(最終回)
定説の根拠を斬る!「朝倉義景仕官」
定説の根拠を斬る!「光秀の敗走とその死」
定説の根拠を斬る!「光秀の敗走とその死」その2
定説の根拠を斬る!「光秀の敗走とその死」その3
定説の根拠を斬る!「光秀の敗走とその死」その4
【信長は謀略で殺されたのだ 偶発説を嗤うシリーズ】
信長は謀略で殺されたのだ:本能寺の変・偶発説を嗤う
信長は謀略で殺されたのだ:本能寺の変・偶発説を嗤う(続き)
信長は謀略で殺されたのだ:本能寺の変・偶発説を嗤う(完結編)
信長は謀略で殺されたのだ:本能寺の変・偶発説を嗤う(駄目押し編)










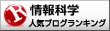















天海僧正光秀説とは無縁の講座と思いますが興味ある方は下記のホームページの春季特別講座ページをご覧ください。誰でも申し込めるようです。
http://open.gakushuin.ac.jp/
(本件は、ブログの読者からメールで情報をいただいたものです。なお、私は神戸に行っており受講できません)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%BE%E6%8C%87
http://www.youtube.com/watch?v=Xno_NQdLrnQ
なるほど難しいですね。やってみたら全く音が出ませんでした。
先日、身内の法事に行って来ました。
家は曹洞宗なんですが、初めて天台宗を体験して来ました。
そこで、和尚さんから天台宗と他宗との違いを簡単に説明を頂いたのですが、この経験上!
天海=光秀は!ないのでは?
もしくは、光秀は元・天台宗派の修行僧でない限り、簡単に出来ないと感じたからです。
と言うのも、そこの和尚さんの話の中で「弾指を高く鳴らすのに5年は掛りました・・・。」と冗談の様な話しからで、家に帰って真似ましたが上手く鳴らないものです。
逆に!天台宗の高僧が弾指が出来なかったら問題ではないでしょ~か?
平にお許しを!
とうとうバレてしまいましたか(滝汗)
いつ気付かれたのでしょうか…。
これからも呆れずお付き合いくだされば幸いです。
またまた 貴重なエピソードを教えて頂き、大変ありがとうございます。秀満公が光秀公の小姓だった
というのも大変興味深いです。仰せの通り藤兵衛殿の年齢を考えても、『享年26歳』の方が信憑性があると思います。それにしてもそのようなエピソードからも秀満公は大変魅力的な人物なのが伝わって
きます。変の時は先鋒を務めたり、安土に抑えとして残り、最期は唯一坂本城にて・・・ 光秀公の余程の信頼を得ていた事は周知の事実ですが・・・ また私にとって謎に満ちているところが余計に魅力を掻き立てます・・・
こちらこそ失礼いたしました。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
先の私の書き込みで少し文字の打ち間違いが
ありましたので訂正いたします。
三宅藤兵衛が備前唐津藩士と書いた部分は、
もちろん肥前唐津藩士の誤りです。
寺沢家が改札易処分となり…の部分は
改易処分の誤りです。
失礼いたしました。
まっつん様のご指摘、ウィキには確かに
「明智秀満が僧衣に着替えた…」
との記述があります。
これは元を辿ると近江の盛安寺に伝わっている
伝承のようです。
残念ながら私は不勉強で、なぜこのような
伝承があるのかその答えを知りません。
今後の課題とさせていただけますか?
どなたかご存知であれば教えていただきたいと
思います。
秀満の享年ですが、この人も光秀公と同じく
謎の多い…というより史料がほとんど
遺されていない、あるいは表に出ていない為、
わからないことだらけです。
うちの家系の伝承として、享年26と伝わって
いるとだけしかお答えできません。
お許しください。
ただ、その他に伝わっている話として、
秀満は光秀公の小姓として仕え、
そこから出世したという話があります。
「ある時、坂本城を細川忠興公が訪れて、
光秀公と対話していました。その時廊下の外を
誰かが通りかかり、その人は障子が閉まっている
廊下の側からその場に正座し、中の二人に
むかってお辞儀をし、再び立ち上がって静かに
立ち去りました。
忠興公は、とても礼儀正しい家臣がいるものだと
感心し、光秀公にあれはどなたか?と
尋ねたところ、光秀公は、あれはきっと
三宅弥平次でしょう…と答えた。」
…というエピソードが伝わっています。
なにか物語りのように良く出来過ぎの
気がしなくもないのですが(汗)
小姓説が事実だとすると、光秀公の年齢や、
ある程度生活に余裕が出来て小姓を
使う身分になった年月などを考えて、
明智秀満の享年は40代というよりも
20代という方が納得できる気がします。
三宅藤兵衛が本能寺の変の時点で
2才だったことも、40代よりは20代の
父親がいたと考える方が自然ではないでしょうか。
以上、またまた長文失礼いたしました。
のなのでしょうか・・・?
私の先祖、備前唐津藩筆頭家老(天草富岡城城代。唐津藩の飛び地が天草にありました。)三宅藤兵衛が島原の乱で討死した後、その息子たちは、藤兵衛と仲の良かった唐津藩士原田伊予の励ましで、富岡城籠城戦を戦いました。原田伊予の活躍により、落城することなく危機を脱しました。
その後唐津藩主寺沢家はは改札易処分となり、藩士たちは浪人することとなりました。
三宅藤兵衛の息子たちは、親戚の熊本藩主細川家に呼び戻され細川藩士となりました。
また、原田伊予は、天海僧正の紹介で会津に行き、会津藩士となりました。現在も会津にご子孫が続いています。
天海は当然、天草島原の乱と三宅藤兵衛について原田伊予から聞き及んでいます。天海が明智秀満ならば、自分の孫である三宅藤兵衛の息子たちに対して何らかの接触があったのではないでしょうか?
また、天草島原の乱収束後、細川藩主は静養と関係者の慰労の為に、細川藩江戸屋敷で茶会を開きました。その席に天海も招かれました。
もし天海が明智秀満ならば、細川家の近い親戚であり、三宅藤兵衛の父である明智秀満だとわかっているはずです。
しかしその席には藤兵衛の息子らは出席していません。
本当に天海=明智秀満なら、細川藩主はなぜ祖父と孫たちを対面させなかったのか、はなはだ疑問です。
私の家系には、明智秀満は坂本城で亡くなっており、享年26歳と伝わっています。
私がどうしても光秀天海説に納得できないのは、斎藤利三の子・福は春日局として救済されたのに、光秀の子供は誰一人として救済されていないことと顔の知られた光秀が別人として通用しないだろうということにあります。
その点では、秀満の可能性は確かに残ります。福の一族が取り立てられたということでは斉藤利三の可能性も残ります。利三は処刑されていますが、弟がいたようなので弟が身代わりになった可能性もないとはいえません。
ただし、いずれも証拠不十分であり、秀満、利三の筆跡鑑定など新たな捜査の進展を期待します。
実は私も明智様の著書を拝見し、また法丸様のブログにて「光秀は天海僧正ではない」と斬られるまで
戦国最大の歴史ロマンとして、「ありえるのでは・・・」とわくわくしておりました・・・ しかしやはりネットの至る所でも、「年齢に無理がある」「テレビ番組で筆跡鑑定を行ったところ 同一人物ではないと判定された」とあり 多くの人は違うと認識しているのではないでしょうか・・・ しかし現在 唯一の歴史ロマンとして『秀満―天海僧正説』は まだありえるのではないかと私としては捨て切れません・・・(真実のみを追究し歴史捜査されている明智様にとって甚だ論外でお怒りかもしれませんが・・・) ただ私は明智様の歴史捜査により解明された「安土城放火は家康の命による伊賀者によるもの」という真実から、秀満が安土を去る際 秀満と家康の命を帯びた伊賀者が接触した可能性は充分にありえると考えます・・・WIKIPEDIAの『明智秀満』にも「坂本城で自害したのは疑問もある」とも載っています 他の明智一族や斎藤利三の一族と同じく生き延びた可能性はないでしょうか? 一方で天海僧正の前半生が載っているとされる『東叡山開山慈眼大師縁起』等が 信憑性のあるものなのか 『歴史捜査』する価値があるのでは・・・と思っております 以上長々とスミマセン・・・