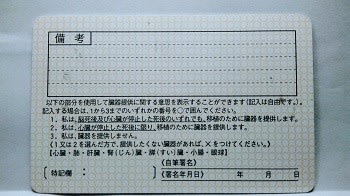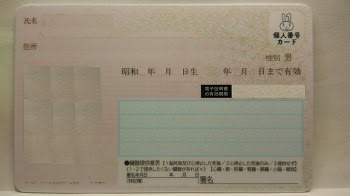テレビや新聞報道によると、
日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」)の大洗研究開発センターで作業員5人が内部被ばくした事故で、原子力規制委員会(以下、「規制委員会」)は25日、原子力機構が9月に提出した事故の報告書について、「組織的な原因の分析が不十分」として再提出を求めた。
原子力機構は事故を想定せず、汚染は起きないと最初から思っていたのではないかと問題視。組織的な原因の分析や線量評価、再発防止に向けたマニュアルの改善が不十分だと判断して再提出を求めることにしたとのこと。
除染用シャワーの水の出方が悪く長時間使えなかったことや、除染が不十分のまま作業員を退出させたことなど5件を保安規定違反にあたると認定した。
これについて、報告書の概要は次のとおりだ。
保安違反と判断される5点(詳細は規制委員会のホームページに掲載の報告書を参照)。
1. 作業計画立案(規定や要綱に基づく「非定常作業計画書」を作成しなかった)
2. 核燃料物質の貯蔵について(規定の「放射線分解によるガス圧の上昇に十分注意する。」があるにもかかわらず、現在に至るまでこれが考慮されていなかった。)
3.線量限度を超える被ばく(線量限度50mSv/年を超えないように管理すると規定されているが、作業員1名が線量限度を超える被ばくをした)
4. 除染用シャワーの不備(除染用シャワーの点検では、一定時間使用できるかどうかの確認が行われていなかったこと、水の出方が悪いことに気づいたものの、原因である減圧弁を交換せず、除染用シャワーが長時間利用できなかったことから、適切な管理が行われていなかった)
5. 身体汚染検査の管理不備(退出するときは、手、足、衣服等に汚染のないことを確認すると規定されているが、除染が不十分のまま作業員を管理区域から退出させたために、放医研における身体汚染検査において汚染が検出された)
また、保安規定違反ではないが改善が必要な事項(詳細は報告書を参照)
1. 技術情報等の過去の知見が活かされなかったことについて
2. 身体汚染等を想定した教育訓練の不備
また、規制委員会は、原子力機構が作業員の被曝線量を「プライバシーにあたる」として詳細に報告していないことも問題だという。規制委員会幹部は「被曝線量は事故評価に必要な情報で、報告しないのはおかしい」と話している。
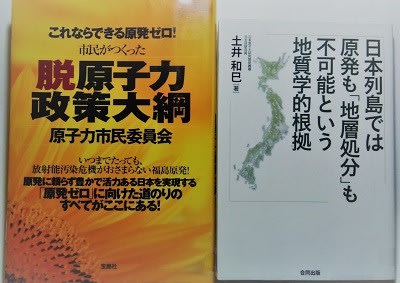
市民活動レベルの「脱原子力政策大綱」と日本列島は地質学的に原発が不可能という主旨の本。
原発ゼロを目指すのなら本来は規制委員会の存在そのものも疑問視される。しかし、今回の、原子力機構に対して違反に該当する等の指摘をしたことは評価できる。規制委員会の存在の可否はともかく、報告された内容には驚かされる。日産や神戸製鋼の不正以上にひどい。作業員の被ばくという事故が起きてしまったのだ。原子力を扱う要領が規定されているにもかかわらず、違反項目に該当するのが5件もあった。それも人の健康・生命にかかる事項なのに、実施されていなかった。リスク管理の甘さだ。モノづくりの技術は優秀でも、リスクや組織の管理の甘さを露呈している。
何故、このような事態に陥っているのだろうか。その根の一つは、わが国の行政・政治のあり方に課題があるように思う。一般のサラリーマンや年金生活者からは、所得税や健康保険・介護保険税は、待ったなしに給与・年金から天引きされる。おまけに生活に必要な品物を買えば消費税がかかる。国民の一人ひとりからは細部に至るまで厳格に管理されている。しかし、日産・神戸製鋼の不正や原子力機構の事故が起こる。不正は10年単位でだいぶ前から行われていた。原子力機構では、安全に対する基準や規定があるにもかかわらず、履行されていなかった。規定はしっかり運用しなければ、まったく意味がない。組織に対しては甘い。
いずれの問題も、基準や規定を作成した時点で、「良し。終了」として気が緩んでしまったのではないか。わが国特有の「甘えの構造」にあるように思える。上層部は、「ちゃんとした安全基準があるので、作業員はそれに従ってやっているだろう」と思う。しかし、現場では中間層(中間管理職)からの指示で作業するが、実際は現場での経験が主体となる。中間層は現場からの報告を他の中間層へまたは上層部へ、報告する。このときも、歪められることもあろう。こうして、現場から中間層へ、中間層から別の中間層へ、中間層から上層部へと流れるいくつかのレベルで、いわゆる忖度も働き、つじつま合わせだけの報告、または報告書の作成が行われている場合があると思える。報告が流れているうちに、真実とは異なった内容で、書類で事務処理される。そして、どこかで書類の破棄、さらなる書き換えなども起こりうる。
このように組織として、上層部は現場の実情は分からない仕組みになっているところに問題があるのだろう。真実とは異なっていても書類に書かれていることが、事実として認知される可能性がある。こうした流れや、事務処理は国の行政や国会でも見られる気がしてならない。否、私の記憶違いでなければ、つい最近の国会審議でも展開されていたと思う。
特別国会が来月1日に召集されるようだ。しかし、今のところ総理の所信表明演説は行われないし、臨時国会は開催されそうもない。森友・加計問題などはやがて忘れ去られていくのを待っているのだろうか? またまた、謙虚、真摯、丁寧さは実行の伴わない、空しい言葉になってしまうのだろうか?
日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」)の大洗研究開発センターで作業員5人が内部被ばくした事故で、原子力規制委員会(以下、「規制委員会」)は25日、原子力機構が9月に提出した事故の報告書について、「組織的な原因の分析が不十分」として再提出を求めた。
原子力機構は事故を想定せず、汚染は起きないと最初から思っていたのではないかと問題視。組織的な原因の分析や線量評価、再発防止に向けたマニュアルの改善が不十分だと判断して再提出を求めることにしたとのこと。
除染用シャワーの水の出方が悪く長時間使えなかったことや、除染が不十分のまま作業員を退出させたことなど5件を保安規定違反にあたると認定した。
これについて、報告書の概要は次のとおりだ。
保安違反と判断される5点(詳細は規制委員会のホームページに掲載の報告書を参照)。
1. 作業計画立案(規定や要綱に基づく「非定常作業計画書」を作成しなかった)
2. 核燃料物質の貯蔵について(規定の「放射線分解によるガス圧の上昇に十分注意する。」があるにもかかわらず、現在に至るまでこれが考慮されていなかった。)
3.線量限度を超える被ばく(線量限度50mSv/年を超えないように管理すると規定されているが、作業員1名が線量限度を超える被ばくをした)
4. 除染用シャワーの不備(除染用シャワーの点検では、一定時間使用できるかどうかの確認が行われていなかったこと、水の出方が悪いことに気づいたものの、原因である減圧弁を交換せず、除染用シャワーが長時間利用できなかったことから、適切な管理が行われていなかった)
5. 身体汚染検査の管理不備(退出するときは、手、足、衣服等に汚染のないことを確認すると規定されているが、除染が不十分のまま作業員を管理区域から退出させたために、放医研における身体汚染検査において汚染が検出された)
また、保安規定違反ではないが改善が必要な事項(詳細は報告書を参照)
1. 技術情報等の過去の知見が活かされなかったことについて
2. 身体汚染等を想定した教育訓練の不備
また、規制委員会は、原子力機構が作業員の被曝線量を「プライバシーにあたる」として詳細に報告していないことも問題だという。規制委員会幹部は「被曝線量は事故評価に必要な情報で、報告しないのはおかしい」と話している。
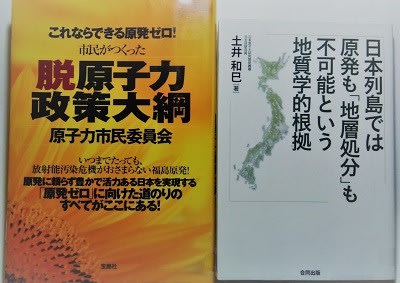
市民活動レベルの「脱原子力政策大綱」と日本列島は地質学的に原発が不可能という主旨の本。
原発ゼロを目指すのなら本来は規制委員会の存在そのものも疑問視される。しかし、今回の、原子力機構に対して違反に該当する等の指摘をしたことは評価できる。規制委員会の存在の可否はともかく、報告された内容には驚かされる。日産や神戸製鋼の不正以上にひどい。作業員の被ばくという事故が起きてしまったのだ。原子力を扱う要領が規定されているにもかかわらず、違反項目に該当するのが5件もあった。それも人の健康・生命にかかる事項なのに、実施されていなかった。リスク管理の甘さだ。モノづくりの技術は優秀でも、リスクや組織の管理の甘さを露呈している。
何故、このような事態に陥っているのだろうか。その根の一つは、わが国の行政・政治のあり方に課題があるように思う。一般のサラリーマンや年金生活者からは、所得税や健康保険・介護保険税は、待ったなしに給与・年金から天引きされる。おまけに生活に必要な品物を買えば消費税がかかる。国民の一人ひとりからは細部に至るまで厳格に管理されている。しかし、日産・神戸製鋼の不正や原子力機構の事故が起こる。不正は10年単位でだいぶ前から行われていた。原子力機構では、安全に対する基準や規定があるにもかかわらず、履行されていなかった。規定はしっかり運用しなければ、まったく意味がない。組織に対しては甘い。
いずれの問題も、基準や規定を作成した時点で、「良し。終了」として気が緩んでしまったのではないか。わが国特有の「甘えの構造」にあるように思える。上層部は、「ちゃんとした安全基準があるので、作業員はそれに従ってやっているだろう」と思う。しかし、現場では中間層(中間管理職)からの指示で作業するが、実際は現場での経験が主体となる。中間層は現場からの報告を他の中間層へまたは上層部へ、報告する。このときも、歪められることもあろう。こうして、現場から中間層へ、中間層から別の中間層へ、中間層から上層部へと流れるいくつかのレベルで、いわゆる忖度も働き、つじつま合わせだけの報告、または報告書の作成が行われている場合があると思える。報告が流れているうちに、真実とは異なった内容で、書類で事務処理される。そして、どこかで書類の破棄、さらなる書き換えなども起こりうる。
このように組織として、上層部は現場の実情は分からない仕組みになっているところに問題があるのだろう。真実とは異なっていても書類に書かれていることが、事実として認知される可能性がある。こうした流れや、事務処理は国の行政や国会でも見られる気がしてならない。否、私の記憶違いでなければ、つい最近の国会審議でも展開されていたと思う。
特別国会が来月1日に召集されるようだ。しかし、今のところ総理の所信表明演説は行われないし、臨時国会は開催されそうもない。森友・加計問題などはやがて忘れ去られていくのを待っているのだろうか? またまた、謙虚、真摯、丁寧さは実行の伴わない、空しい言葉になってしまうのだろうか?