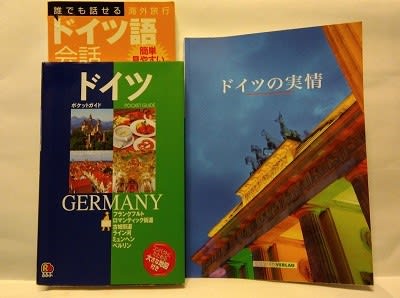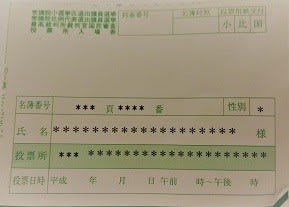今日は夕方は忙しくなるので、早めのアップです。
今年の秋は天候が不順だ。雨が多い。砂利を敷いた駐車場に、黒、茶や緑の混ざった海藻のようなものが、出てきたなと思っていた。それも日に日に多くなる。今朝、小雨で濡れている庭を見たら、なんと駐車場の真ん中あたり一面にはこびっていた。

砂利の上にはびこるイシクラゲ。まるで海辺のようだ。
前々から次男がこれ食べられるみたいと言っていたが、見た目が単にワカメのように見えるので冗談かと思っていた。しかし、調べてみると、なんとコケの一種で「イシクラゲ」というとのこと。昔は食用としていたらしい。

ワカメより透明感があっておいしそうに見えるが?
しかし、食べるのには大分勇気がいる。靴について車内も汚れる。コンクリートなどの上に生えると滑る。他のブログやホームページ等には、駆除方法も載っている。イシクラゲはアルカリ性の土壌を好むとのこと。苔専用の駆除剤もあるようだが、簡単にできそうなのは酢を散布するのもよさそうだ。
そして、更にイシクラゲより転倒リスクの高い苔やカビが生えている。家の周囲は、檜、杉やその他の実や葉が落ち、掃除に手間がかかる。従って、周囲はレンガやブロックを敷いて掃きやすくしている。ところが、それらが雨でぬれると滑りやすくなる。あまり歩かないところは、緑色の苔が育つとそれなりに趣があるのだが・・・。

庭石とレンガに生えた緑の苔。

庭にあるレンガ作りの小道。この辺はあまり歩かない所だ。
これらの緑の苔は残しておきたい。愛でるのは、人間の独りよがりかもしれない。苔もカビもひたすら自らの生命を営んでいるだけなのに・・・とチラリと思いがよぎる。

薄いベージュ色の30cm四方のブロックの周囲に生えてきた黒っぽい苔というかカビかな? かろうじて中心部分は生えていないが、やがて一面が黒っぽくなる。すると滑りやすくなる。

右下のレンガは一面に黒くなり、艶がある。軽く触れただけでも滑る。上方のレンガは次第に浸食されつつある。
特に玄関へのアプローチは、少々登り坂になっているので、滑りやすい。妻や私をはじめ遊びに来る孫たちも滑った。
イシクラゲの駆除と共に、黒いカビのようなものがついたレンガやブロックを磨いて汚れを除去しなければならない。デッキブラシかタワシでこすり取ろうと思っている。
イシクラゲは乾燥すると休眠状態になるので、駆除は雨上がり直後など、水分があるうちが効果的とのこと。
来週、台風が通り過ぎたら酢を散布してみよう。
今年の秋は天候が不順だ。雨が多い。砂利を敷いた駐車場に、黒、茶や緑の混ざった海藻のようなものが、出てきたなと思っていた。それも日に日に多くなる。今朝、小雨で濡れている庭を見たら、なんと駐車場の真ん中あたり一面にはこびっていた。

砂利の上にはびこるイシクラゲ。まるで海辺のようだ。
前々から次男がこれ食べられるみたいと言っていたが、見た目が単にワカメのように見えるので冗談かと思っていた。しかし、調べてみると、なんとコケの一種で「イシクラゲ」というとのこと。昔は食用としていたらしい。

ワカメより透明感があっておいしそうに見えるが?
しかし、食べるのには大分勇気がいる。靴について車内も汚れる。コンクリートなどの上に生えると滑る。他のブログやホームページ等には、駆除方法も載っている。イシクラゲはアルカリ性の土壌を好むとのこと。苔専用の駆除剤もあるようだが、簡単にできそうなのは酢を散布するのもよさそうだ。
そして、更にイシクラゲより転倒リスクの高い苔やカビが生えている。家の周囲は、檜、杉やその他の実や葉が落ち、掃除に手間がかかる。従って、周囲はレンガやブロックを敷いて掃きやすくしている。ところが、それらが雨でぬれると滑りやすくなる。あまり歩かないところは、緑色の苔が育つとそれなりに趣があるのだが・・・。

庭石とレンガに生えた緑の苔。

庭にあるレンガ作りの小道。この辺はあまり歩かない所だ。
これらの緑の苔は残しておきたい。愛でるのは、人間の独りよがりかもしれない。苔もカビもひたすら自らの生命を営んでいるだけなのに・・・とチラリと思いがよぎる。

薄いベージュ色の30cm四方のブロックの周囲に生えてきた黒っぽい苔というかカビかな? かろうじて中心部分は生えていないが、やがて一面が黒っぽくなる。すると滑りやすくなる。

右下のレンガは一面に黒くなり、艶がある。軽く触れただけでも滑る。上方のレンガは次第に浸食されつつある。
特に玄関へのアプローチは、少々登り坂になっているので、滑りやすい。妻や私をはじめ遊びに来る孫たちも滑った。
イシクラゲの駆除と共に、黒いカビのようなものがついたレンガやブロックを磨いて汚れを除去しなければならない。デッキブラシかタワシでこすり取ろうと思っている。
イシクラゲは乾燥すると休眠状態になるので、駆除は雨上がり直後など、水分があるうちが効果的とのこと。
来週、台風が通り過ぎたら酢を散布してみよう。