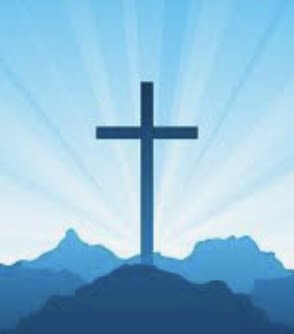先日のブログ、かぐや姫から川崎の月讀神社に行くことを思いつき、そこの狛犬の台座に書かれた文字、輝山から、「カグヤマ」が気になりました。
じつは、カグヤマは何度か気になり調べてました。1度目は初めて妹と熊さんの巡礼の旅に参加させてもらった時です。
その参拝は、最初から最後まで素晴らしかったです。説明すると長くなりますので、またの機会があれば。全ての参拝を終え、帰り私を最寄り駅まで送ってくれるというので辺りは暗くなっていましたが、熊さんの運転で後部座席でまったりしていました。
すると、星にしてはかなり大きくて、月にしては小さいそれは輝く光(星?)が三角形に夜空に見えたのです。他の星は見えないのにそれだけ見えました。妹も驚いてあれは何??と。熊さんも、信号で止まった時にみました。
あれは、いったい何だったのか。今でも解りません。前の光はなんなのか。これもわかりません。肉眼で見た時はこんな光は無かったですが、動く車からだから、電灯が前にあった?のか、星だけだった気がしますけれど。

妹撮影
後ろの星は夜空に輝く冬の大三角形?かもしれませんが、スマホのカメラでも撮れるくらいの大きさで、肉眼ではかなり大きく見えました。不思議だね、凄いね、感動だねと話しました。
不思議は続きます。帰ってから熊さんの携帯に、不思議な文字がどっからか入りました。妹にこれ何わかる?と熊さんがラインで尋ねたたようで、妹もわからず、妹経由で私にも尋ねられました。しかし、熊さんも、妹も、私も何のメッセージか解りません。かなり調べましたが、お手上げ。謎のままです。
それがこれです。

しかし、ずっとその後も私は気になっていました。額田王について漫画を読み返して、香具山だ!と思いました。香語山は籠山ともとれるし、しかも難しい漢字で聲网山と書かれています。
聲は、声、響き、音、誉れのこと、声を難しくした漢字。読みは「セイ、ショウ、コエ、コワ」。网は読みは、「モウ、ボウ、アミ」で、魚や動物をとるあみ。物にかぶせるあみのこと。
声を網で被せた山が、天香語山?ってこと?
籠山という山は、奈良の天川村の近くにもあるようですし、また、その時の参拝ルートに、京都の籠神社、眞名井神社も含まれていましたから、籠神社のカゴ、に関係あるのかなぁとかも話してましたが、でも解らずそのままです。
ところで、大和三山のひとつに天香久山があります。藤原京を囲むように、耳梨山と畝傍山と三角形の位置に並んでいます。
あの星は大和三山に関係あったのか?夜だし車窓からみた方角が奈良の方だったのかは、全く方向感覚のない私は解りませんが、ざっくり関西から三重に向かって車で走っていました。
先日、額田王について書きましたが、中大兄皇子は、
「香具山は 畝傍ををしと 耳梨と 相争ひき 神代より かくにあるらし 古(いにしへ)も 然(しか)にあれこそ うつせみも 妻をあらそふらしき」
(訳:香久山は畝傍山が愛しいといって、耳成山と争った。神代の時代からこんなふうであるらしい。昔もそうだからこそ、今の世でも妻を争うらしい。)
という和歌を詠み、畝傍山を額田王とみたてて、香具山と耳成山を自分達兄弟として三角関係を詠んでいます。
万葉集にも沢山詠まれた香具山ですが、古代から「天」という尊称が付くほど大和三山のうち最も神聖視された山だそうです。
『伊予国風土記』逸文には天から山が2つに分かれて落ち、1つが伊予国(愛媛県)「天山(あめやま)」となり1つが大和国「天加具山」になったと記されています。
また『阿波国風土記』逸文では「アマノモト(またはアマノリト)山」という大きな山が阿波国(徳島県)に落ち、それが砕けて大和に降りつき天香具山と呼ばれたとも記されています。
大和三山でひとつだけ、天がつく。天の香りが具わる山。天の香りの言霊の山。天の香りの久しい山。天の香具山、香語山、香久山の漢字からそんなふうに空想しました。
言霊が宿るといえば、万葉集ではカグヤマの音は、香山、香来山、高山、芳来山、芳山の表記もあるようです。
高い所にあり、芳しい香りの山、また、芳来山(カグヤマ)を音読みすればホウライ、蓬莱や、不死鳥の鳳凰が来る⇨鳳来さえその漢字からイメージできます。
香具山の山頂からは、畝傍山(うねびやま)を望めるみたいです。畝傍は、火がうねる火山だから名付けられたといわれています。畝傍山の麓にある橿原神宮は、明治時代に神武天皇の「御霊」を移したとされる場所のようですね。
大和三山は、サムハラの地にあり太古の神話が生きる場所です。
香具山の山頂には國常立命を祭神とする國常立神社があって、2つの小さな祠のうちの1つには高龗神様が祀られているようです。
高龗も、タカオカミとも音読みではコウライとも読めます。コウライは、香来とも表記でき、すると、またカグとも読める!言葉が面白くループとなります!!!と、ひとり楽しむ私。笑
眷属神の龍神様が、神世7代の初めの尊い神様、国常立命と共にいらっしゃるのでしょうか。
かぐや姫から、月讀宮の狛犬の台座、輝山へ。そして、カグヤだけで、ずっと気になっていた天香語山へ。カグヤの響きだけで繋げた、全くなんのこっちゃの話ですカグヤマニアと笑って許して下さい。
ただ、熊さんの携帯に入った文字も謎解きたいし、なんだか、天香具山は凄いかも!!ということで参拝したくなりました。