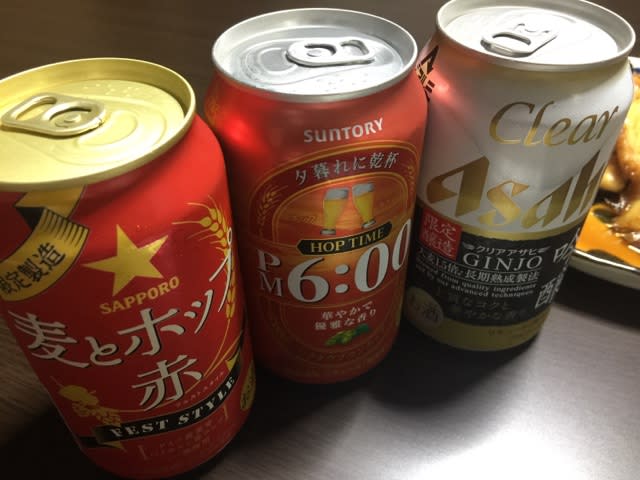「若者の貧困」に大人はあまりに無理解すぎる 仕事や家族に頼れる時代は、終わりを迎えた
要するに、"若者への支援は本当に必要なのか?"という疑念だ。これは若者たちの置かれている現状の厳しさが、いまだに多くの人々の間で共有されていないことを端的に表している。今回の連載を通して、「若者なんだから、努力すれば報われる」という主張など、ナンセンスであることを明らかにしていきたい。
もはや通用しない労働万能説
若者は働けば自立できる、働きさえすればまともな生活ができるという神話(労働万能説)が根強く存在している。働けばそれに見合った賃金を得られ、その賃金によってまっとうな生活を営めるというものだ。
賃金を得るために、若者はどのような職場に入るか、どのようなキャリアを積むかで悩まなくてはならない。また、安定した仕事に就くように要請する社会的な圧力にも悩まされる。そのため、就職活動で人気があるのは、やはり一部上場企業であり、公務員志望の学生も増えている。
しかし当然ながら、上場企業へ入社できたり、公務員になれる人数はもともと決まっている。すべての人がまともな賃金を得られる職業を確保することも、現実では不可能である。
事実、働いてもまともな賃金が得られる保証がない職種も増えている。そして、その仕事はたいてい非正規雇用で、終身雇用ではないため、不安定な就労形態をとっている。賞与や福利厚生がない職場も多く、働いたからといって、生活が豊かにならないことが現在の労働市場で起こっているのだ。いわゆる「ワーキングプア問題」が注目されるようになってきた。働いても貧困が温存されてしまうのである。
これは何も本人が低学歴であったり、コミュニケーション能力が低いということに由来しているわけではない。大学を卒業しても、普通に働いて生計を維持することが急速に困難になっているのだ。
労働社会学者の木下武男氏は、これらの若者の雇用について、「経済界・企業は、多くの若者を日本型システムから排除すること、つまり、若者を犠牲にしながら、日本型システムを温存しようとしたのです」(『若者の逆襲 ワーキングプアからユニオンへ』旬報社)と述べている。つまり、経済界や企業は、意図的に若者の雇用を崩壊させてきた経緯があることを的確に指摘しているのだ。若者たちが働いても「しんどい」状況は、労働社会学者が指摘するように、大人たちによって"つくられた"のである。
ブラック企業の台頭も若者の困難に拍車をかける。普通に働きたいが、普通に働くことも許してもらえず、短期間で使い捨てにされてしまう。それによって、うつ病や精神疾患を発症してしまい、働けない状態に追いやられることも珍しくない。だから、「働けば何とかなる」という「労働万能説」はもはや通用しない。
たとえ行き着く先がブラック企業でも…
またこの労働万能説を論じる人々は、労働していない若者や、労働を望まない若者を怠惰だと見なす傾向がある。そのため、できるだけ早く労働するように、なかば「仕事は選ばなければ何でもある」と、労働に若者を駆り立てる。たとえ、駆り立てられた若者が行き着く先がブラック企業であったとしても─―。
若者の一部は、望まない非正規雇用やブラック企業に長年、身を投じた揚げ句、「結局は報われない労働だった」とすでに体感していたり、今後もそうなりたくないと思っている場合が多い。だからこそ、働く先を選びたいのである。これはぜいたくでも何でもない当たり前の要求だろう。安心して働くことができない雇用が増え続けている中で、労働に対するインセンティブが湧いてこない若者たちが出てくるのも当然である。そして、彼らに強調しておかなければならないことだが、何でもいいからすぐに仕事に飛びつくことは、極力しないでほしい。
劣悪な労働環境でも人が集まってくることがわかれば、その労働者の処遇はいつまでも良くならない。安心して失業し続けられる社会には、劣悪な労働環境がここまで拡散することはない。そもそも社会保障が充実している他の先進国では、賃金に依存しなくても、ある程度暮らしていけるため、過酷な労働にはそれなりの対価が支払われるし、ひどい企業も淘汰されていく。社会保障や社会福祉が遅れているからこそ、失業したときに困るし、早急に労働や労働市場へ駆り立てられることになる。
たとえば、ブラック企業を辞めたが、すぐに仕事をしないと生活に困ってしまうので、急いで再就職をした別の企業も、またブラック企業であったという話はいくらでもある。じっくりと仕事を選び、準備をして余裕を持って就職をしてほしいし、その環境こそ整備していきたいものである。
そして、労働市場の劣化は、若者の労働意欲を奪っていく。どのように働いていくべきかを悩み、資格をいくつも取る人々、自己啓発に関する書籍を読みあさる人々などをよく見かける。本質的には、この労働市場の構造を変えずに、彼らの苦悩は消えないのにもかかわらず、である。
また、たとえ働かなくとも、若者たちには父母や祖父母がいるので、多少おカネに困ったとしても、家族が手を差し伸べてくれるのではないかという神話(家族扶養説)がある。
しかし、もうかつてのように、家族は若者を救えない。家族の世帯員が縮小し、相互扶助機能は前例がないレベルまで弱まっているからだ。世帯年収も減少傾向にあり、若者の親世代や祖父母世代は、自分たちの生活だけで精一杯であろう。
家族への依存も、もはや困難に
わたしは生活に困窮してしまった若者たちの相談を受けて、年間何十件も生活保護申請に同行する。NPO法人全体としては、なんと年間300件超(!)である。申請に行くと、福祉事務所職員は必ず、「頼れる家族はいませんか?」と聞く。
しかし、家族が扶養できた事例には、残念ながら一件も出会っていない。若者が生活に困窮していたとしても、家族は頼れないのだ。そもそも家族を頼れる関係にあるのなら、NPOや役所には相談しないのではないか。
奨学金を借りて大学に進学する学生の多くも、家族による学費負担や仕送りが十分に期待できない状況にある。家族相互に扶助が可能な世帯は、いったいこの日本にどれくらい残っているのだろうかと嘆息せざるを得ない。雇用の不安定化や賃金、年金の減少、物価の高騰などで自分自身の生計を維持することがやっとだという世帯が一般的であるように思う。
また、悲しいことだが、家族自体が自らの子どもを、搾取の対象とする事例もある。
長年、児童虐待を受けてきたり、十分な養育や教育を家族から受けることができなかった若者の存在だ。家族の存在自体が温かいものではなく、若者本人に対して、害悪を与える存在として機能する場合もあるということだ。社会的には"毒親"などと評する論調もあるくらいである。
家族がいても期待される機能が発揮できない。あるいは家族関係自体にストレスを生じやすく、同居や支援を求めることによって、問題が悪化することもある。たとえば、精神疾患を有する若者が実家で生活している場合、疾患に対する理解が不十分な両親が、就労をしきりに促すことによって、過大なストレスを生じるといった相談事例は後を絶たない。
彼らには、「家族の支援をきっと受けられるから大丈夫だよ」などとは口が裂けても言えない。このような家族と別居して暮らしたいが、生計を維持できないから、自由な暮らしを阻害されている。これに対してどうしたらよいかと相談を受ける。すなわち、「実家から出られない若者」の悩みである。
いずれにしても、若者たちを取り巻く環境を見る際には、家族への依存は困難になっていると想定しておく必要があるだろう。さらに20歳を超えた成人に対して、家族がどこまで面倒を見るべきなのか、についても議論を進める必要がある。諸外国では当然であるが、成人した場合、血のつながりのある者同士でも、日本ほど扶養をすることはない。主に夫婦間や未成年の子どもに対する扶養義務くらいで、成人後は生活や就労を政府や社会システムが保障していく。「困ったら家族を頼る」ということが当たり前の社会でなくなることを示していきたいとも思う。
つまり、困ったら家族が助けてやればいいという論調は、ややもすると社会福祉や社会保障の機能を家族に丸抱えさせることにつながってしまう。これでは家族が共倒れの状況を招きかねず、さらに社会福祉や社会保障の発展も妨げる。そういう点において、家族扶養説は危険な前近代の思想であると言えるだろう。
簡単に馘首されるからねぇ…って、オレだけか!?