
青森市中世の館。青森市浪岡大字浪岡字岡田。
2022年9月28日(水)。
中世の館は、15世紀後半から16世紀の津軽で勢力のあった北畠氏が住んでいた青森県を代表する中世城館「国史跡・浪岡城跡」から発掘された出土品を中心に展示している資料館である。
また、浪岡地区の縄文時代の土器や平安時代の「国史跡・高屋敷館遺跡」の遺物などを展示し、町の歴史を紹介している。
また構内に、旧坪田家住宅を野外展示している。








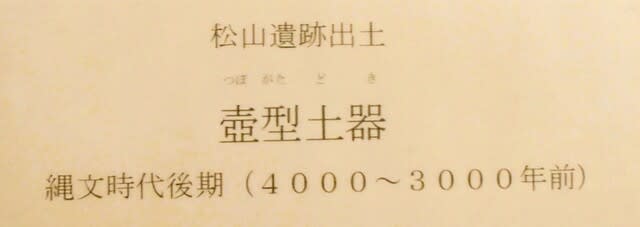






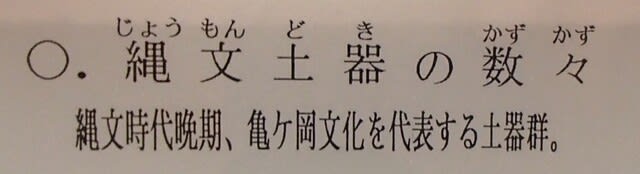






旧坪田家住宅。県重宝。
旧坪田家住宅は、寄せ棟茅葺き屋根、木造軸組構法で江戸時代末期文久年間(1861~63年)頃に建てられたと推定されている。建築面積は、179.78㎡。「じょい」と呼ばれる居間の奥に整形四間取(同じ形・大きさの四部屋をもつ)を持つ上層農家特有の住居形態と「ちょうば」を持つ商家の名残りを併せ持つ点が特徴である。中二階部分に、雪深い地方の農家住宅で特徴的な「切り上げ窓」を持っている。
坪田家の先祖は、江戸時代初め頃、近江から津軽の玉余魚沢(かれいざわ)に移り住んだ商人で、初めは旧大豆坂(まめさか)街道の「峠の茶屋」を営んでいたが、のちに農業と茶屋を兼業し始め、幕末には玉余魚沢随一の豪農になった。
このあと、近くにある国史跡・浪岡城跡を見学したのち津軽半島北部へ向かい、JR木造駅へ立ち寄った。



















