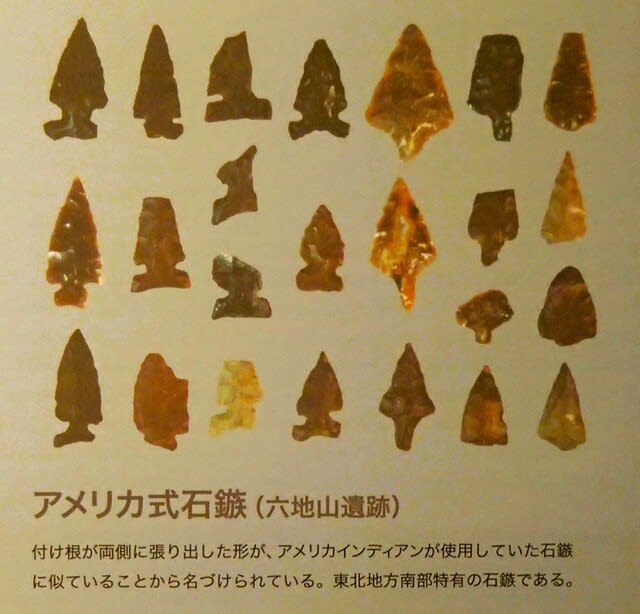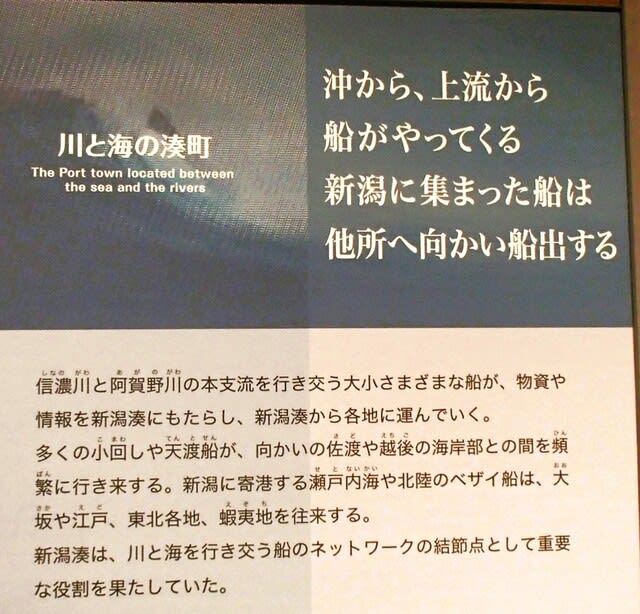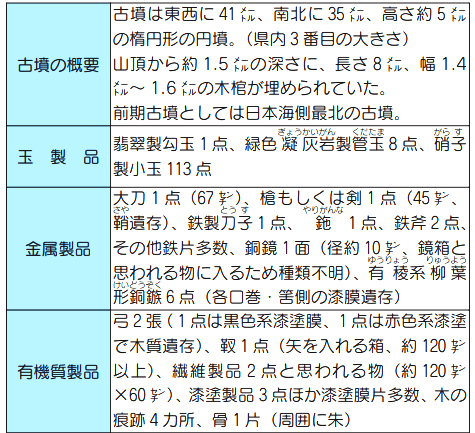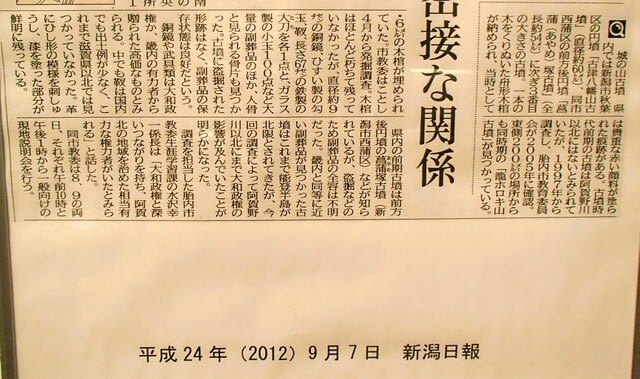旧第四銀行住吉町支店。登録有形文化財。新潟市中央区柳島町。
2023年9月30日(土)。
新潟市歴史博物館の見学を終え、海側にある旧第四銀行住吉町支店と交差点側にある旧新潟税関庁舎を見学した。3館を併せて一帯は「みなとぴあ」とよばれている。

旧第四(し)銀行住吉町支店は、昭和前期1927年の竣工、2003年移築。鉄筋コンクリート造2階一部3階建、建築面積537㎡。
重厚な古典主義様式の銀行建築。2階建で,躯体は鉄筋コンクリート造,外壁に花崗岩を張って石造風とし,コーニスを廻す。正面入口にはイオニア式列柱4本を並べ,柱間の壁上部アーチ型窓とする。当初の外装材,内部の造作をよく保存している。ロビー部の大理石製のカウンターなどが建設当初の姿に復原された。
新古典主義といわれるが、1920年代に流行していたアールデコの影響も受けていると思われる。内部2階まで見学した。


国史跡・重文・旧新潟税関庁舎。新潟市中央区緑町。
開港五港の中で唯一現存する、開港当時の運上所(税関)の遺構である国史跡「旧新潟税関」の敷地内に建つ。運上所の庁舎は、地元・新潟の大工たちが、一足先に開港した横浜や江戸に建てられ始めた洋風建築を参考にして造ったもので、明治2(1869)年8月21日に上棟、10月に完成した。
いわゆる擬洋風建築の一例で、赤瓦葺きの屋根とナマコ壁の外観にアーチ状の玄関口と塔屋などの洋風の意匠を取り入れている。


幕末の安政5(1858)年、徳川幕府はアメリカ・オランダ・イギリス・ロシア・フランスの五か国と修好通商条約を結び、新潟・横浜・函館・長崎・神戸の五港を開港することにした。新潟港は日本海側最大の港町であること、幕府領であることなどが理由で開港地に選ばれた。しかし、開港が実現しないまま幕府は倒れ、明治新政府が新潟港を開港したのは明治元年11月19日(西暦1869年1月1日)のことであった。


外国との貿易に際して、開港場には輸出入貨物の監督や税金の徴収といった運上業務や、外交事務を取り扱う「運上所」が設けられた。新潟港は川港であったため、開港後、信濃川の河口近くのヨシが生い茂る川岸を出島のように埋め立てて、運上所が建設された。
この「新潟運上所」は、明治6(1873)年に「新潟税関」と改称されて以後、昭和41(1966)年までの約100年間、税関業務に使用された。

内部に入ったが、パネル展示がある程度であった。塔屋へ登る階段がある。
万代そば。新潟市中央区万代。万代シテイバスセンタービル 1階。
旅行雑誌で予習していると、新潟市民のソウルフード「バスセンターのカレー」というのが目に入った。シンプルながらも一度食べたらやみつきになるその味は、県内外から注目を集めて、観光客も立ち寄るという。
自動車旅行で立ち寄るとなると駐車料金が高いのはコスパが悪い。検索していくと、朱鷺(とき)メッセ万代島駐車場Aが最適と気付いた。入場から最初の60分間は無料で、万代シテイバスセンターに近い。混雑時でなければ、60分以内で食事して帰って来られる距離であると予測できた。
「みなとぴあ」を出て、16時過ぎに万代島駐車場Aに着いた。満車に近かったが、駐車はできた。そこから15分弱歩いてバスセンターに着いた。中に入って店の場所を探す時間がかかると困ると思いながら一番近い入口に近づくと、カレーの臭いがした。入口のすぐ左という最適な場所にあったのは幸いであった。夕食の代わりにしたいことと、蕎麦屋なのでカレーだけでなく蕎麦も食べることにして、カレーはミニカレーにした。合計で680円だった。

「万代そば」は、「安い、早い、うまい」をモットーに1973年から続く老舗立喰そば屋という。

黄色いルーには、トンコツスープをベースに、玉ねぎ、にんじん、新潟県産の豚肉を使用。その下にはカレー用にブレンドされた県産米が隠れている。
無事、50分余りで万代島駐車場Aに帰り着き、駐車料金は無料だった。本日の行程を終えたので、道の駅「新潟ふるさと村」へ向かった。