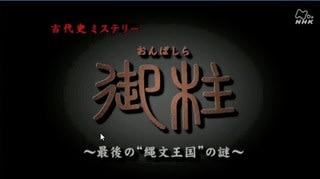 今年は7年に1度の御柱の年だった。蓼科に別荘があった20年間には3度、その壮大なお祭りを見物した。今年は御柱の時期に別荘解体を予定していた関係で、夏前まで蓼科には全く出掛けなかった。
今年は7年に1度の御柱の年だった。蓼科に別荘があった20年間には3度、その壮大なお祭りを見物した。今年は御柱の時期に別荘解体を予定していた関係で、夏前まで蓼科には全く出掛けなかった。
春に放映されたNHKスペシャル“御柱”を観て、御柱や縄文文化について新たに幾つかの事を知った。中ッ原遺跡の存在を知り、夏にはそこへ出掛けた。番組は何度も観たいと思える出来栄えだったが、録画していなかった。後の祭りだった。そこで窮余の一策、NHKオンデマンドの継続会員となってしまった。月の払いが972円は痛いが・・・。疑問点もあり“御柱”を何度か観た。
 番組は縦糸の過去形と横糸の現在進行形で構成されていた。二つの糸を交互に登場させる巧みな進行だった。
番組は縦糸の過去形と横糸の現在進行形で構成されていた。二つの糸を交互に登場させる巧みな進行だった。
過去の糸では、これほどの巨木祭が何故、諏訪地方にだけ受け継がれて来たのか。御柱とは何なのか。その謎解き。
遥か1万年前、森の中で育まれた縄文人の祈り。やがて日本列島にコメ作りの技術が伝わると時代は激しく動き出す。狩猟に長けた縄文の神と農耕を司る弥生の神。御柱には二つの神の争いと和解の物語が秘められていたとして、聖なる年の熱狂の中に潜む古代史のミステリーに迫る。
現在進行形の糸では、今年の祭りで氏子たちの先頭に立ち御柱を守り抜く御幣持ちの大役に選ばれた北澤聖顕(まさあき)さんの奮闘記。 曳く綱の長さは200メートル。3000人を超える人が力を合わせ一本の巨木を曳いていく。かつて諏訪の人達は御柱の年には結婚も葬式も家を作ることもしなかったそうな。長さ18メートル、重さ10トンもある、御柱のなかで最も太い上社本宮の一の柱。その柱の上での、一生に一度限りの重い務めを無事果たした北澤さんの物語が語られた。
曳く綱の長さは200メートル。3000人を超える人が力を合わせ一本の巨木を曳いていく。かつて諏訪の人達は御柱の年には結婚も葬式も家を作ることもしなかったそうな。長さ18メートル、重さ10トンもある、御柱のなかで最も太い上社本宮の一の柱。その柱の上での、一生に一度限りの重い務めを無事果たした北澤さんの物語が語られた。 今日のブログは北澤さんの奮闘記から。
今日のブログは北澤さんの奮闘記から。
祭を8日後に控えた3月25日、御柱が祭の出発地点に運ばれて来た。御柱のなかで最も太い上社本宮の一の柱。御幣持ちに選ばれた北澤さんは、神の宿る巨木と始めて対面した。彼はそう簡単に巨木に触らない。「何故触らないのですか」と問われ、「まだ触らないほうがいいかなと思っただ。怖いとかはないですね。湧き上がる熱いものしかないですね」と。
数日後、本番に備えての練習会で練習用の御幣を手にした。御幣には神が宿り御柱を守ると言われ、祭りの間中彼は御柱の上に立ち続けなければならない。御柱祭を通して一人前として認められていく諏訪の男たち。思い共有する仲間に励まされていた。 4月3日、祭りが始まった。彼は、諏訪大社から授かった御幣を握りしめ初めて御柱の上に立った。この日は8キロ先の木落場を目指す。巨木が動き出し、縄文時代に起源を持つと考えられる巨木の祭りの幕が切って落とされた。
4月3日、祭りが始まった。彼は、諏訪大社から授かった御幣を握りしめ初めて御柱の上に立った。この日は8キロ先の木落場を目指す。巨木が動き出し、縄文時代に起源を持つと考えられる巨木の祭りの幕が切って落とされた。
 直角に曲がる難所大曲では、御幣持ち北澤さんの力の籠った声が氏子たちを元気づけた。“ここは難所だぜ~~”木遣の合図とともに力を合わせる氏子たちが一斉に綱を引く。一気に大曲を抜けた。この場面が大きな見どころだった。
直角に曲がる難所大曲では、御幣持ち北澤さんの力の籠った声が氏子たちを元気づけた。“ここは難所だぜ~~”木遣の合図とともに力を合わせる氏子たちが一斉に綱を引く。一気に大曲を抜けた。この場面が大きな見どころだった。
出発して5時間、目的地について漸く一息。しかし御幣持ちの北澤さんは柱の上に立ち続けなければならない。トイレに行くことも出来ないため、食べ物も水分も最低限に抑える。日も暮れかかる午後5時、御柱を引き始めてから10時間が過ぎ、たどり着いのは木落場。だが北澤さんは御柱から降りようとしない。山の神と一つになったかのように立ち続けた。
それから更に2時間が過ぎ、仲間から促されて漸く御柱から降りた。彼曰く「体力と精神力があれば明日までたち続けていたい。一瞬一瞬を記憶に残したいです」 翌日の木落場。御柱祭最大の難所。重さ10トンの巨木が高さ19メートルの急な坂を一気に下る。柱の上には御幣を掲げた北澤さん。柱に立ったままでこの坂に挑んだ。御幣が大きく揺らいだが、彼は振り落とされなかった。北澤さんは無事大役を果たし終えた。神宿る木と過ごした一月。安堵の姿がそこにはあった。(写真:落ち始めても御幣を立てる北澤さん)
翌日の木落場。御柱祭最大の難所。重さ10トンの巨木が高さ19メートルの急な坂を一気に下る。柱の上には御幣を掲げた北澤さん。柱に立ったままでこの坂に挑んだ。御幣が大きく揺らいだが、彼は振り落とされなかった。北澤さんは無事大役を果たし終えた。神宿る木と過ごした一月。安堵の姿がそこにはあった。(写真:落ち始めても御幣を立てる北澤さん)

(御幣を返還する)

(漸く見せた笑顔)
今日の一葉(昨日は冬至で、月は下弦)










