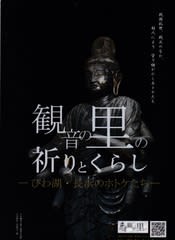 観ていると心が和んでくるホトケさまたちだった。「ようこそいらっしゃいました」と出迎えてくれているような10数体もの、一同に会した観音さまたち。それに導かれるように、ここ東京芸大美術館を訪れた実に多くのヒトたち。
観ていると心が和んでくるホトケさまたちだった。「ようこそいらっしゃいました」と出迎えてくれているような10数体もの、一同に会した観音さまたち。それに導かれるように、ここ東京芸大美術館を訪れた実に多くのヒトたち。
このところ上野へはよく出かける。その時眼にした本展示ポスターの副題ー琵琶湖・長浜のホトケたちーを見て、何かが匂った。長浜にはついては、戦国の世に、羽柴秀吉居城の城下町だったこと程度の知識しか持ち合わせていないが、その観音の里におわしますホトケたちが誘ってくれたと思いたい。4月9日(水)のことである。

10数年前、大津でレンタカーを借りて琵琶湖を北上し、湖北地方の十一面観音さまを蔵する2・3の寺を訪れたことがあった。どのお寺も小さく、ひそやかに存在していた。京都のお寺とは大きく違う。本展示は、その謎解きもしてくれた。
『この地方は幾多の戦乱や災害に見舞われましたが、地域住民の手によって観音さまは難を逃れ、今日まで大切に守り継がれてきました。大きな寺社に守られることなく、地域の暮らしに根付き、そこに住む人々の信仰や生活、人生、地域の風土などと深く結び付きながら、今なおひそやかに守り継がれています』とある。
又『これらを生み出した大規模な寺院の多くは中世の頃には廃絶したものと見られ、その後は「惣村」と呼ばれる自治組織を基礎に、高い自治能力をそなえた住民たちによって観音が守り伝えられてきました』ともある。
多くの観音がつくられた背景として、己高山(こだかみやま)を中心とした山岳信仰についても語られていた。 慈愛にみちた観音さまをじっくりと拝観した。なかでも善隆寺蔵の、少年の雰囲気ある十一面観音立像がひときわ美しく思える。馬頭観音・千手観音・聖観音など18体の仏たちに囲まれての拝観。ふと、報道陣が多いことに気が付いた。その中心に滋賀県知事嘉田由紀子氏がいた。前回の衆議院総選挙以来あまり姿を見なくなったが、熱心に説明に耳を傾け、質問をする姿があった。2階レストランで食事を摂るときにも知事は私の真後ろでの食事という偶然。今後を期待したい政治家のひとり。(写真:重要文化財の善隆寺蔵の十一面観音)
慈愛にみちた観音さまをじっくりと拝観した。なかでも善隆寺蔵の、少年の雰囲気ある十一面観音立像がひときわ美しく思える。馬頭観音・千手観音・聖観音など18体の仏たちに囲まれての拝観。ふと、報道陣が多いことに気が付いた。その中心に滋賀県知事嘉田由紀子氏がいた。前回の衆議院総選挙以来あまり姿を見なくなったが、熱心に説明に耳を傾け、質問をする姿があった。2階レストランで食事を摂るときにも知事は私の真後ろでの食事という偶然。今後を期待したい政治家のひとり。(写真:重要文化財の善隆寺蔵の十一面観音)



















