 8月17日(土)、「江戸上水基礎講座その3 玉川上水」を受講してきた。会場の「東京都水道歴史館」へは開講1時間前の13時に到着。前回、開講直前に到着した為、席が最後列という失敗から学んだ積りで、今回は最前列で見易く聴きやすかった。今回の参加者は150名近かったと思う。1つの机に3名が並ぶ席が出るほどの盛況。このテーマへの関心の高さが分かる。
8月17日(土)、「江戸上水基礎講座その3 玉川上水」を受講してきた。会場の「東京都水道歴史館」へは開講1時間前の13時に到着。前回、開講直前に到着した為、席が最後列という失敗から学んだ積りで、今回は最前列で見易く聴きやすかった。今回の参加者は150名近かったと思う。1つの机に3名が並ぶ席が出るほどの盛況。このテーマへの関心の高さが分かる。
「玉川上水」についてはある程度のことは知っている積りで、このブログにも書いたと思うが、今回受講した事柄を改めてまとめておきたい。
〇玉川上水とは
玉川上水は、江戸時代前期の承応3年(1654)に完成し、明治34年(1901)まで機能した、江戸二大上水のひとつ。創設にあたっては、町人玉川庄右衛門・清右衛門がその実務に当たった。その経路は、多摩川羽村堰から取水して開渠で武蔵野台地上を走り、四谷大木戸に達する。そこからは暗渠となった。
〇玉川上水の誕生
成立年代のはっきりしない神田上水に対して、玉川上水はその造られた年代については、『公儀日記』に記されているように、完成は承応3年(1654)の6月。この時点で江戸城東側と丸の内方面への取り入れ口である虎ノ門まで水路が完成したものと考えられる。開渠の、羽村から四谷大木戸部分(43Km)については8ヶ月という短期間で完成した。
〇玉川上水の給水範囲
少なくとも寛永期(1630~40年代)に完成した神田上水が江戸の北東部に給水したのに対して、玉川上水は江戸の南西部に給水された。
〇玉川上水誕生に関する逸話
『公儀日記』には、玉川兄弟に対して7,500両が渡されたとあるに対して、資料「玉川庄右衛門・清右衛門書上」には6,000両と記され、齟齬が見られる。
他の資料には取水口の変更や「水喰土」(みずくらいど)についての記述も見られる。
「水喰土」については『玉川兄弟』(著:杉本苑子)で大変面白く読んだ記憶がある。上水道が完成したと思い、水を流したところ、ある地点まで来た水がそこで消えてしまった(=吸い取られるように地下へ潜ってしまつた)。工事のやり直しである。これらの記述は内容を吟味する必要があるとも、学芸員の金子氏は語っていた。が、水道歴史館内では、水喰土の話は実際にあったかのような映像が流れている。
学芸員金子氏の話はテンポが良く、声も大きく、分かり易い。
今日の一葉。富士神社付近に咲く白い蓮の花











 今回の長岡行に際し、ネットで長岡の名物料理を調べたら“洋風カツ丼”があげられ、それがB級グルメ的名物になっていることを知った。私の40数年前の、微かな記憶とオバーラップし、長岡は肉料理と一人悟り、事前に「レストランナカタ」と決めていた。
今回の長岡行に際し、ネットで長岡の名物料理を調べたら“洋風カツ丼”があげられ、それがB級グルメ的名物になっていることを知った。私の40数年前の、微かな記憶とオバーラップし、長岡は肉料理と一人悟り、事前に「レストランナカタ」と決めていた。 お店は2階にあり、2階へと通じる狭い階段には長い列が出来ていた。室外の温度は30度をはるかに超えていたと思う。しかし待つほかない。40分は待っただろう。漸く入店して店内を見渡すと、東京では「洋食屋」といった風情のお店で居心地感が良い。メニューを見て、“洋風”の意味するところを知った。普通丼物はどんぶりに入れられて出て来るが、洋風カツ丼では皿にご飯が盛られ、その上にトンカツが乗せられているのだ。私は「ハーフ&ハーフ」のコース(1360円)を注文した。
お店は2階にあり、2階へと通じる狭い階段には長い列が出来ていた。室外の温度は30度をはるかに超えていたと思う。しかし待つほかない。40分は待っただろう。漸く入店して店内を見渡すと、東京では「洋食屋」といった風情のお店で居心地感が良い。メニューを見て、“洋風”の意味するところを知った。普通丼物はどんぶりに入れられて出て来るが、洋風カツ丼では皿にご飯が盛られ、その上にトンカツが乗せられているのだ。私は「ハーフ&ハーフ」のコース(1360円)を注文した。 まずはスープ。続いて上の写真のように2種類のソース(デミグラスとケチャップ)が掛けられ洋風カツ丼。最後にコーヒー。ソースは濃厚で、揚げたてのカツがさくさくしていて実に美味しかった。ご飯もしっかり食べて腹ごしらえ終了。15時過ぎ、一路花火会場を目指したのだった。
まずはスープ。続いて上の写真のように2種類のソース(デミグラスとケチャップ)が掛けられ洋風カツ丼。最後にコーヒー。ソースは濃厚で、揚げたてのカツがさくさくしていて実に美味しかった。ご飯もしっかり食べて腹ごしらえ終了。15時過ぎ、一路花火会場を目指したのだった。 知らない土地を訪れたとき、まずは観光案内所に行き、地図など頂く。今回もそうだった。「馬高縄文館」方面行のバスは出たばかりで、「新潟県立博物館
知らない土地を訪れたとき、まずは観光案内所に行き、地図など頂く。今回もそうだった。「馬高縄文館」方面行のバスは出たばかりで、「新潟県立博物館 入館すると直ぐ目にするのが
入館すると直ぐ目にするのが その火焔型土器と王冠型土器が多数展示され、じっくり見学した。私達の祖先の縄文人が5,000年ほど前に、
その火焔型土器と王冠型土器が多数展示され、じっくり見学した。私達の祖先の縄文人が5,000年ほど前に、 縄文館には目玉がもうひとつあった。重文指定の“ミス馬高”と名付けられた土偶。この館は撮影が自由なのでバッチリ撮影させてもらったが、ミス馬高は実に小さい。ミニチャーかと思い係員に聞くと「本物です」。微笑んでいるに見える、可愛らしい土偶だった。(写真:ミス馬高)
縄文館には目玉がもうひとつあった。重文指定の“ミス馬高”と名付けられた土偶。この館は撮影が自由なのでバッチリ撮影させてもらったが、ミス馬高は実に小さい。ミニチャーかと思い係員に聞くと「本物です」。微笑んでいるに見える、可愛らしい土偶だった。(写真:ミス馬高)

 さかた海鮮市場2Fにあるお店は「海鮮どんやとびしま」という名前だった。11時開店なのだが、11時少し過ぎた時間帯には既に長い待ち行列が出来ていた。並んで待つ間に遠目にも見えるメニューから、4人とも「舟盛膳」(1000円。下の写真)にしようと決めていた。
さかた海鮮市場2Fにあるお店は「海鮮どんやとびしま」という名前だった。11時開店なのだが、11時少し過ぎた時間帯には既に長い待ち行列が出来ていた。並んで待つ間に遠目にも見えるメニューから、4人とも「舟盛膳」(1000円。下の写真)にしようと決めていた。
 しかし、私達が注文する前に品切れとなり、作戦変更で、1000円の「刺身定食」3名と「とびしま膳」1名に。更に岩ガキを加えるもの2名。東京ならば2000円はすると思われる定食に舌鼓をうった。新鮮な刺身10点盛り。実に実に美味しかった。ここ酒田港から飛島へのは定期船「とびしま」が運航されている。(写真:刺身定食のうちの刺身)
しかし、私達が注文する前に品切れとなり、作戦変更で、1000円の「刺身定食」3名と「とびしま膳」1名に。更に岩ガキを加えるもの2名。東京ならば2000円はすると思われる定食に舌鼓をうった。新鮮な刺身10点盛り。実に実に美味しかった。ここ酒田港から飛島へのは定期船「とびしま」が運航されている。(写真:刺身定食のうちの刺身) 酒田から鶴岡に向い、鶴岡公園内の「藤沢周平記念館」へ。私は2度目の入館だが、掲示されているものを初めてのように熟読した。周平の心に生き続けたで間にあろう鶴岡・庄内の原風景の写真がいい。藤沢作品の全てが展示されている。大泉学園での書斎も展示されていた。藤沢ファンは多い。若菜さんはここを訪れたかったと言っていた。菅原さんは周平作品の全てを単行本で持っていて、しかもそれが全部が初版本とのことだった。(写真:記念館入口)
酒田から鶴岡に向い、鶴岡公園内の「藤沢周平記念館」へ。私は2度目の入館だが、掲示されているものを初めてのように熟読した。周平の心に生き続けたで間にあろう鶴岡・庄内の原風景の写真がいい。藤沢作品の全てが展示されている。大泉学園での書斎も展示されていた。藤沢ファンは多い。若菜さんはここを訪れたかったと言っていた。菅原さんは周平作品の全てを単行本で持っていて、しかもそれが全部が初版本とのことだった。(写真:記念館入口)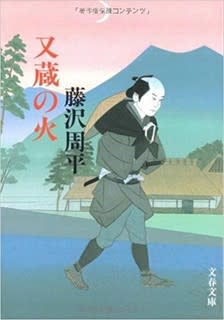 特別展示は『又蔵の火』。これは、故郷・鶴岡の史実「土屋丑蔵・虎松の仇討」を作品化した仇討ものだそうで、本人は直木賞を受賞作品『暗殺の年輪』よりもこちらの作品のほうを評価していたそうな。ともあれ藤沢作品のうちでも初期のもの。(写真:文春文庫)
特別展示は『又蔵の火』。これは、故郷・鶴岡の史実「土屋丑蔵・虎松の仇討」を作品化した仇討ものだそうで、本人は直木賞を受賞作品『暗殺の年輪』よりもこちらの作品のほうを評価していたそうな。ともあれ藤沢作品のうちでも初期のもの。(写真:文春文庫) この日の宿泊先は「東急ハーヴェストクラブ 裏磐梯グランデコ」。夕食は部屋食と決めていたから、鶴岡で食料等を調達しておきたかった。記念館のスタッフに聞くと、「主婦の店 イーネ」を紹介された。食料や御酒などを購入し、一路裏磐梯へ。
この日の宿泊先は「東急ハーヴェストクラブ 裏磐梯グランデコ」。夕食は部屋食と決めていたから、鶴岡で食料等を調達しておきたかった。記念館のスタッフに聞くと、「主婦の店 イーネ」を紹介された。食料や御酒などを購入し、一路裏磐梯へ。 昼食は酒田市内観音寺にある「花の家食堂」でとった。私の記憶にはないが、昼食に相応しいお店を妻と二人でネット検索した結果だったらしい。観音寺という町の住宅街にぽっんと一軒だけある食堂で、注文したものが出てくるまで不安だったが、現れた定食を見て一安心。690円にしては上出来の定食。刺身や焼き魚が新鮮で、山仲間の評価も◎。(写真:概観は平凡な食堂)
昼食は酒田市内観音寺にある「花の家食堂」でとった。私の記憶にはないが、昼食に相応しいお店を妻と二人でネット検索した結果だったらしい。観音寺という町の住宅街にぽっんと一軒だけある食堂で、注文したものが出てくるまで不安だったが、現れた定食を見て一安心。690円にしては上出来の定食。刺身や焼き魚が新鮮で、山仲間の評価も◎。(写真:概観は平凡な食堂) 駐車場から25分で「滝ノ小屋」に到着。ここは山形県
駐車場から25分で「滝ノ小屋」に到着。ここは山形県 八丁坂3合目で待っていた山仲間に、私は「山頂までは無理かも知れない」と話した。途中で腹を強打した仲間がもう一人いて、「二人は降りるから二人だけで登って来て」とも言った。丁度その時だった。強風に加え激しい雨が降ってきた。全員撤去しようの声が上がった。誰も反対しなかった。下山途中、
八丁坂3合目で待っていた山仲間に、私は「山頂までは無理かも知れない」と話した。途中で腹を強打した仲間がもう一人いて、「二人は降りるから二人だけで登って来て」とも言った。丁度その時だった。強風に加え激しい雨が降ってきた。全員撤去しようの声が上がった。誰も反対しなかった。下山途中、