
自画像をたくさん描いた画家といえばレンブラントとゴッホだろう。僕は絵について詳しく知っているわけではないから、ことによるともっともっといるのかも知れないけれど。
ゴッホはレンブラントについてたくさん語っている。弟宛の手紙のなかで。
画風の違いは2人の自画像に決定的な相違をもたらす。そもそも自画像を描くという行為を想像してみるのが難しい。画家に、できれば自画像を描いたことのある画家に訊ねてみたいものである。いったいどのような気持ちで自分自身を描くのだろうか。自分を一個の物体と観じるまで見つめるというのだろうか。
近代の心理学(もどき)の深層心理だの無意識だのはここでは無縁である。といって画家の心境とやらが安易に出たものはやはり駄目である。
レンブラントの自画像は背後の褐色の中に溶け込もうとするようにも、暗い背景から浮かび上がったようにも見える。僕たちはその像に対し、ためらいながら語りかける。
対して、ゴッホの自画像は画面一杯に光を浴び、身を隠すことなくすべてをさらけ出している。そして僕たちに向かって語りかけるかのようだ。教えてくれ、ここにいる男はいったい何者なのか、と。
それでいながら、画家の目は自身を一個の物体として捉えている。キャンバスを前にした像、亡くなる少し前の、薄い緑で渦巻くような背景の像、どれもが実に沈着に描かれている。どこにもゴッホという不幸な男を訴えるようなものは見当たらない。そしてそれ故に僕たちは否応なしに異様なまでの緊張の許にさらされ、目の前にいるのが紛れもなく不幸な男であると感じる。僕らはかろうじて訊ねる。いったいこのゴッホと呼ばれる男とは何者であったのか。
耳を切った時ゴッホは錯乱状態にあった。平静を取り戻したゴッホは頭を包帯で巻かれた自画像を描く。この絵のカーンと静まりかえった世界は無類である。手紙で弟に訴えている不安も、病気に対する疑念も、一切が無い。あるのは一人のパイプをくわえた男の姿ばかりだ。
美術史家の高階秀爾さんは、ゴッホの自殺が、弟の気を惹きたいがための狂言であり、不幸にも本当に命をおとしたことを「証明」したそうである。そのことは僕は洲之内徹さんの本で知ったのだが。
洲之内さんは、高階さんのような専門家に自分のような素人は太刀打ちできるはずがない、と言いながら高階さんの説を覆して行く。その絡み方がじつにうまい。それこそ僕のような素人にできる芸当ではない。
最後に彼は言う。「耳を切った自画像」と自殺の1ヶ月前の最後の自画像を載せておく、それをよく見て欲しい、これが弟の気を惹くために狂言をうつ男の顔に見えるだろうか、と。
僕が付け加える必要はあるまい。洲之内徹「さらば、きまぐれ美術館」を読んで下さればそれですむ。
ゴッホはレンブラントについてたくさん語っている。弟宛の手紙のなかで。
画風の違いは2人の自画像に決定的な相違をもたらす。そもそも自画像を描くという行為を想像してみるのが難しい。画家に、できれば自画像を描いたことのある画家に訊ねてみたいものである。いったいどのような気持ちで自分自身を描くのだろうか。自分を一個の物体と観じるまで見つめるというのだろうか。
近代の心理学(もどき)の深層心理だの無意識だのはここでは無縁である。といって画家の心境とやらが安易に出たものはやはり駄目である。
レンブラントの自画像は背後の褐色の中に溶け込もうとするようにも、暗い背景から浮かび上がったようにも見える。僕たちはその像に対し、ためらいながら語りかける。
対して、ゴッホの自画像は画面一杯に光を浴び、身を隠すことなくすべてをさらけ出している。そして僕たちに向かって語りかけるかのようだ。教えてくれ、ここにいる男はいったい何者なのか、と。
それでいながら、画家の目は自身を一個の物体として捉えている。キャンバスを前にした像、亡くなる少し前の、薄い緑で渦巻くような背景の像、どれもが実に沈着に描かれている。どこにもゴッホという不幸な男を訴えるようなものは見当たらない。そしてそれ故に僕たちは否応なしに異様なまでの緊張の許にさらされ、目の前にいるのが紛れもなく不幸な男であると感じる。僕らはかろうじて訊ねる。いったいこのゴッホと呼ばれる男とは何者であったのか。
耳を切った時ゴッホは錯乱状態にあった。平静を取り戻したゴッホは頭を包帯で巻かれた自画像を描く。この絵のカーンと静まりかえった世界は無類である。手紙で弟に訴えている不安も、病気に対する疑念も、一切が無い。あるのは一人のパイプをくわえた男の姿ばかりだ。
美術史家の高階秀爾さんは、ゴッホの自殺が、弟の気を惹きたいがための狂言であり、不幸にも本当に命をおとしたことを「証明」したそうである。そのことは僕は洲之内徹さんの本で知ったのだが。
洲之内さんは、高階さんのような専門家に自分のような素人は太刀打ちできるはずがない、と言いながら高階さんの説を覆して行く。その絡み方がじつにうまい。それこそ僕のような素人にできる芸当ではない。
最後に彼は言う。「耳を切った自画像」と自殺の1ヶ月前の最後の自画像を載せておく、それをよく見て欲しい、これが弟の気を惹くために狂言をうつ男の顔に見えるだろうか、と。
僕が付け加える必要はあるまい。洲之内徹「さらば、きまぐれ美術館」を読んで下さればそれですむ。












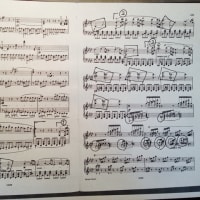







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます