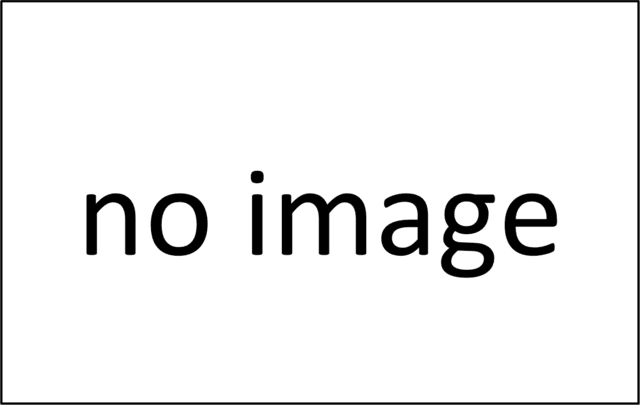
6月8日〜10日岡山で開催された第54回日本リハビリテーション医学会学術集会に参加してきました。
近年の特徴として、関連職種の発表も可能となったために演題数は多くなっています。
教育講演やシンポジウムなどの企画も充実しています。
それに伴ってQuantity(量)は増えてきているもののQuality(質)については個人的には「?」のつく、違和感を感じるような演題も・・・
違和感のその一は、発表の際に、考察が結果のまとめや結果の繰り返しで終わっていて、どうしてそうなるのか、考察がされていないものです。
この結果からは、こういうことが考察・推測される、的な部分がないので、何とも中途半端な印象です。
二つめは、こういう介入をしたら結果が良くなった、的な発表です。
このような研究の場合は、介入しない場合との比較が必要ですが、その部分が欠けているものがありました。
これだと、介入方法が良かったのか、ただ評価方法が良くなかったのか、人が関わるだけで良かったのか、本当に意味のあったことが何なのかはっきりしません。
両方が重なると、理由はよくわからないけど、常識とされてきたことでは説明ができない理由で病気が良くなった、的な突拍子もない結果が出てくることもあります。
三つめは、発表方法についてです。
発表の内容は十分であっても、発表には決められた方式・時間があります。
その中にまとめてこそ実力があると思うのですが、そこから逸脱する発表があり残念な感じがしました。
研究をして発表(学会での発表や論文としての発表いずれでも)するには、研究デザインを考えるところから、発表方法についてまで、試行錯誤を繰り返して推敲を重ねていく、というところがもう少し欲しいような印象を受けました。
そういうところが十分でないと、「風が吹けば桶屋が儲かる」ではないですが、例えば「こういう介入をすると麻痺が治るんです!」という発表があったとしても、その結果だけが一人歩きして、その前提条件やプロセスは無視されて、思うような結果が再現できず、リハビリテーション医学の前進につながらないような気がしました。
当科でも臨床研究をいくつも行っていますが、こうした経験を「他山の石」として、より良いものにしていきたいと思います。
東埼玉病院リハ科ホームページはこちらをクリック
近年の特徴として、関連職種の発表も可能となったために演題数は多くなっています。
教育講演やシンポジウムなどの企画も充実しています。
それに伴ってQuantity(量)は増えてきているもののQuality(質)については個人的には「?」のつく、違和感を感じるような演題も・・・
違和感のその一は、発表の際に、考察が結果のまとめや結果の繰り返しで終わっていて、どうしてそうなるのか、考察がされていないものです。
この結果からは、こういうことが考察・推測される、的な部分がないので、何とも中途半端な印象です。
二つめは、こういう介入をしたら結果が良くなった、的な発表です。
このような研究の場合は、介入しない場合との比較が必要ですが、その部分が欠けているものがありました。
これだと、介入方法が良かったのか、ただ評価方法が良くなかったのか、人が関わるだけで良かったのか、本当に意味のあったことが何なのかはっきりしません。
両方が重なると、理由はよくわからないけど、常識とされてきたことでは説明ができない理由で病気が良くなった、的な突拍子もない結果が出てくることもあります。
三つめは、発表方法についてです。
発表の内容は十分であっても、発表には決められた方式・時間があります。
その中にまとめてこそ実力があると思うのですが、そこから逸脱する発表があり残念な感じがしました。
研究をして発表(学会での発表や論文としての発表いずれでも)するには、研究デザインを考えるところから、発表方法についてまで、試行錯誤を繰り返して推敲を重ねていく、というところがもう少し欲しいような印象を受けました。
そういうところが十分でないと、「風が吹けば桶屋が儲かる」ではないですが、例えば「こういう介入をすると麻痺が治るんです!」という発表があったとしても、その結果だけが一人歩きして、その前提条件やプロセスは無視されて、思うような結果が再現できず、リハビリテーション医学の前進につながらないような気がしました。
当科でも臨床研究をいくつも行っていますが、こうした経験を「他山の石」として、より良いものにしていきたいと思います。
S1(MD)
東埼玉病院リハ科ホームページはこちらをクリック









