前回、氏本農園さんの豚と牛のことを少し書いたが、その後のことを続ける。

氏本さんところの豚ちゃんを眺めていると、突然山からパーンという猟銃の音がした。えっ?この小さな山で猟をしてるの?と耳を疑ったのだが、しばらくするとまたパーンという音が聞こえる。
側で子供達に豚を見せていたNPOの休日学校の先生に聞いてみたが、その音の正体は知らないようだった。
近くに島の人も見当たらず、この山で一体「何」が捕れるんだろうか・・・と思いながら、再び自転車を漕ぎ始めた。
真っ青な空の下で響く銃声は、その「何」かがなんだかよくわからないのもあって、少し不安な気分になった。
誰もいない道に立っていると、島には、私と猟銃を構えた姿の見えない猟師の二人しかいないような気分になった・・・。
なーんて、文学みたいというか、ちょっと感傷的な気分に浸っていたのだが、東京で「ミツバチの羽音と地球の回転」の上映会で氏本農園の氏本長一さんに話を聞いてその謎が解けた。
あの銃声、ひどく合理的なものだった。
実はあの銃声は録音したものを流しているのだ。
山に植えてある「びわの実」をカラスから守るために定期的に鳴らしているらしい。

こうした銃声でカラスを追うやり方は、全国どこのびわ農家でもやっているというものではないらしい。
祝島のびわはほぼ無農薬なので、カラスに突かれやすいのだ。
映画「ミツバチの~」の中でも、びわの収穫の場面が出てくるが、もともと山の斜面に海からの照り返しがあり、かつて柑橘類を作っていた祝島の段々畑で、その上無農薬で、祝島のびわは作られている。まずいわけがない。
カラスはそれを一番よく知っているというわけだ。
あの銃声は、不安どころか、祝島のびわの品質を保証する音だったのである。
そして、祝島といえば、やはり漁業と海産物である。
しかし、今回は土曜日だったからか、海藻取りやその加工作業などに出会う事はなかった。また、桟橋の船の周りにもほとんど人がいなかった(たまたま私が通った時間にいなかっただけかもしれないが)。
そんな中で、唯一、船底を洗っているおじいちゃんたちに出会った。

ホースからものすごい強い水圧の水が出て、船の底にくっついたフジツボなどを剥がすのだそうだ。
写真ではよく見えないけど、特別な洗浄機がここに置いてある。
この洗浄機は、島の漁協(たしか漁協と言ってたと思うのだが間違ってたらすいません。とにかく船持ちの人たちが共同で)で買ったのだと言う。そして、この洗浄機を1回使用するごとに1万5000円払うと言っていた。こういう船の掃除も外の業者に出したりせず、全部自分たちでやっているのだ。昔はみんなそうだったわけだから当然と言えば当然だが、いまだに全て自分たちの手でメンテナンスまでやっているのは離島ならではかもしれない。
アウトソーシングするとよそに出て行ってしまうお金が、これで島の中で廻る。高度成長以降いろんな仕事を大都市圏の会社や工場にアウトソーシングするようになってから、地方の富は中央に吸い取られるようになってしまった。
こうしたおじいちゃんたちの姿勢は、今後再び地方が再生するためのヒントとなりうると思った。
氏本農園の生ゴミと豚の餌の関係といい、祝島には「循環する」ものが多い。多分これは「離島」だからなのだが、「循環」とか「サスティナブル(持続可能な)」ということが時代のキーワードとなっている今、「離島」はほかにも私たちの暮らしのヒントとなるものをたくさん持っているに違いない。
氏本さんのブログによれば、祝島も一時期は便利な農業を求めて、耕耘機や化学肥料を外部から取り入れ、そのことが離島農業の持続性や循環性や有機性を衰えさせ、逆に高コスト化をもたらして市場性を失う結果となったという。
祝島だってそうした反省から再び今があるのである。
と、今回はここまでにします。「祝島へ行った」はまだ続きます。

氏本さんところの豚ちゃんを眺めていると、突然山からパーンという猟銃の音がした。えっ?この小さな山で猟をしてるの?と耳を疑ったのだが、しばらくするとまたパーンという音が聞こえる。
側で子供達に豚を見せていたNPOの休日学校の先生に聞いてみたが、その音の正体は知らないようだった。
近くに島の人も見当たらず、この山で一体「何」が捕れるんだろうか・・・と思いながら、再び自転車を漕ぎ始めた。
真っ青な空の下で響く銃声は、その「何」かがなんだかよくわからないのもあって、少し不安な気分になった。
誰もいない道に立っていると、島には、私と猟銃を構えた姿の見えない猟師の二人しかいないような気分になった・・・。
なーんて、文学みたいというか、ちょっと感傷的な気分に浸っていたのだが、東京で「ミツバチの羽音と地球の回転」の上映会で氏本農園の氏本長一さんに話を聞いてその謎が解けた。
あの銃声、ひどく合理的なものだった。
実はあの銃声は録音したものを流しているのだ。
山に植えてある「びわの実」をカラスから守るために定期的に鳴らしているらしい。

こうした銃声でカラスを追うやり方は、全国どこのびわ農家でもやっているというものではないらしい。
祝島のびわはほぼ無農薬なので、カラスに突かれやすいのだ。
映画「ミツバチの~」の中でも、びわの収穫の場面が出てくるが、もともと山の斜面に海からの照り返しがあり、かつて柑橘類を作っていた祝島の段々畑で、その上無農薬で、祝島のびわは作られている。まずいわけがない。
カラスはそれを一番よく知っているというわけだ。
あの銃声は、不安どころか、祝島のびわの品質を保証する音だったのである。
そして、祝島といえば、やはり漁業と海産物である。
しかし、今回は土曜日だったからか、海藻取りやその加工作業などに出会う事はなかった。また、桟橋の船の周りにもほとんど人がいなかった(たまたま私が通った時間にいなかっただけかもしれないが)。
そんな中で、唯一、船底を洗っているおじいちゃんたちに出会った。

ホースからものすごい強い水圧の水が出て、船の底にくっついたフジツボなどを剥がすのだそうだ。
写真ではよく見えないけど、特別な洗浄機がここに置いてある。
この洗浄機は、島の漁協(たしか漁協と言ってたと思うのだが間違ってたらすいません。とにかく船持ちの人たちが共同で)で買ったのだと言う。そして、この洗浄機を1回使用するごとに1万5000円払うと言っていた。こういう船の掃除も外の業者に出したりせず、全部自分たちでやっているのだ。昔はみんなそうだったわけだから当然と言えば当然だが、いまだに全て自分たちの手でメンテナンスまでやっているのは離島ならではかもしれない。
アウトソーシングするとよそに出て行ってしまうお金が、これで島の中で廻る。高度成長以降いろんな仕事を大都市圏の会社や工場にアウトソーシングするようになってから、地方の富は中央に吸い取られるようになってしまった。
こうしたおじいちゃんたちの姿勢は、今後再び地方が再生するためのヒントとなりうると思った。
氏本農園の生ゴミと豚の餌の関係といい、祝島には「循環する」ものが多い。多分これは「離島」だからなのだが、「循環」とか「サスティナブル(持続可能な)」ということが時代のキーワードとなっている今、「離島」はほかにも私たちの暮らしのヒントとなるものをたくさん持っているに違いない。
氏本さんのブログによれば、祝島も一時期は便利な農業を求めて、耕耘機や化学肥料を外部から取り入れ、そのことが離島農業の持続性や循環性や有機性を衰えさせ、逆に高コスト化をもたらして市場性を失う結果となったという。
祝島だってそうした反省から再び今があるのである。
と、今回はここまでにします。「祝島へ行った」はまだ続きます。












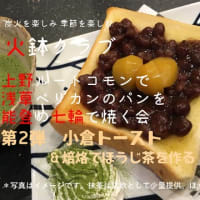



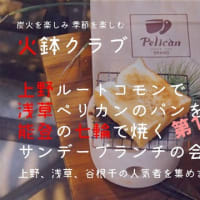



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます