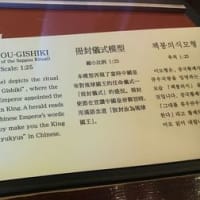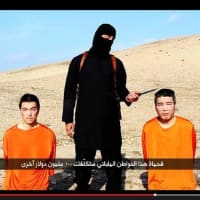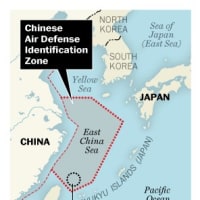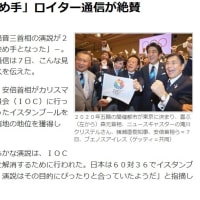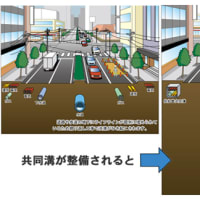うん?自由民主党の議員立法により2002年6月7日に成立、同月14日公布、施行された現行の「エネルギー政策基本法」の何がいけなかったのですか?
この法律の条文を読む限り、現在の「脱原発」論がいかにヒステリックな論議を仕掛けているかがわかりますよ!では詳しく解説します!
まず、第2条の条文(安定供給の確保)をピックアップします。
************
エネルギーの安定的な供給については、世界のエネルギーに関する国際情勢が不安定な要素を有していること等にかんがみ、石油等の一次エネルギーの輸入における特定の地域への過度な依存を低減するとともに、我が国にとって重要なエネルギー資源の開発、エネルギー輸送体制の整備、エネルギーの備蓄及びエネルギーの利用の効率化を推進すること並びにエネルギーに関し適切な危機管理を行うこと等により、エネルギーの供給源の多様化、エネルギー自給率の向上及びエネルギーの分野における安全保障を図ることを基本として施策が講じられなければならない。
************
つまり、この観点を抜きにした政策論争などあり得ないのですよ。と言うかエネルギー政策とは言えないのです。では、民主・共産・社民・未来の各政党が、この条文に答えるように「脱原発」の優位性を唱えていますか?唱えていないでしょう?
特に、「石油等の一次エネルギーの輸入における特定の地域への過度な依存を低減する」どころか、現状では原発を止めたら液化天然ガスを大量に必要とする火力発電の依存度がますます上がるんですよ!と言うことは、その前述にある「世界のエネルギーに関する国際情勢が不安定な要素を有している」影響をますます受けるんですよ!
この事への対処も民主・共産・社民・未来の各政党の「脱原発派」は言わないでしょ?
とにかく「まともな日本のエネルギー政策をまったく考えていない」のが「脱原発派」の皆さんと言えるでしょう!
福島県民へ感情論で訴えて、不安を煽る選挙戦術は、責任ある政治家として民主・共産・社民・未来の各政党の皆様はやめたらいかがですか?
慎んでご忠告申し上げます。
では(その2)に続けます。
【関連資料】
●エネルギー政策基本法(ウィキペディア)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95
エネルギー政策の大きな方向性を示すことを目的として制定された[1]。自由民主党の議員立法により2002年6月7日に成立、同月14日公布、施行された。
「安定供給の確保」、「環境への適合」、「市場原理の活用」などの基本理念が掲げられている。
また国の責務、地方公共団体の責務、事業者の責務、国民の努力、相互協力などが規定されている。
また国は「エネルギー基本計画」を定めなければならないこと、国際協力の推進、知識の普及についても規定されている。
●エネルギー政策基本法
(平成十四年六月十四日法律第七十一号)
(目的)
第一条 この法律は、エネルギーが国民生活の安定向上並びに国民経済の維持及び発展に欠くことのできないものであるとともに、その利用が地域及び地球の環境に大きな影響を及ぼすことにかんがみ、エネルギーの需給に関する施策に関し、基本方針を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、エネルギーの需給に関する施策の基本となる事項を定めることにより、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進し、もって地域及び地球の環境の保全に寄与するとともに我が国及び世界の経済社会の持続的な発展に貢献することを目的とする。
(安定供給の確保)
第二条 エネルギーの安定的な供給については、世界のエネルギーに関する国際情勢が不安定な要素を有していること等にかんがみ、石油等の一次エネルギーの輸入における特定の地域への過度な依存を低減するとともに、我が国にとって重要なエネルギー資源の開発、エネルギー輸送体制の整備、エネルギーの備蓄及びエネルギーの利用の効率化を推進すること並びにエネルギーに関し適切な危機管理を行うこと等により、エネルギーの供給源の多様化、エネルギー自給率の向上及びエネルギーの分野における安全保障を図ることを基本として施策が講じられなければならない。
2 他のエネルギーによる代替又は貯蔵が著しく困難であるエネルギーの供給については、特にその信頼性及び安定性が確保されるよう施策が講じられなければならない。
(環境への適合)
第三条 エネルギーの需給については、エネルギーの消費の効率化を図ること、太陽光、風力等の化石燃料以外のエネルギーの利用への転換及び化石燃料の効率的な利用を推進すること等により、地球温暖化の防止及び地域環境の保全が図られたエネルギーの需給を実現し、併せて循環型社会の形成に資するための施策が推進されなければならない。
(市場原理の活用)
第四条 エネルギー市場の自由化等のエネルギーの需給に関する経済構造改革については、前二条の政策目的を十分考慮しつつ、事業者の自主性及び創造性が十分に発揮され、エネルギー需要者の利益が十分に確保されることを旨として、規制緩和等の施策が推進されなければならない。
(国の責務)
第五条 国は、第二条から前条までに定めるエネルギーの需給に関する施策についての基本方針(以下「基本方針」という。)にのっとり、エネルギーの需給に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国は、エネルギーの使用に当たっては、エネルギーの使用による環境への負荷の低減に資する物品を使用すること等により、環境への負荷の低減に努めなければならない。
(地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、基本方針にのっとり、エネルギーの需給に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、その区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 地方公共団体は、エネルギーの使用に当たっては、エネルギーの使用による環境への負荷の低減に資する物品を使用すること等により、環境への負荷の低減に努めなければならない。
(事業者の責務)
第七条 事業者は、その事業活動に際しては、自主性及び創造性を発揮し、エネルギーの効率的な利用、エネルギーの安定的な供給並びに地域及び地球の環境の保全に配慮したエネルギーの利用に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するエネルギーの需給に関する施策に協力する責務を有する。
(国民の努力)
第八条 国民は、エネルギーの使用に当たっては、その使用の合理化に努めるとともに新エネルギーの活用に努めるものとする。
(相互協力)
第九条 国及び地方公共団体並びに事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体は、エネルギーの需給に関し、相互に、その果たす役割を理解し、協力するものとする。
(法制上の措置等)
第十条 政府は、エネルギーの需給に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。
(国会に対する報告)
第十一条 政府は、毎年、国会に、エネルギーの需給に関して講じた施策の概況に関する報告を提出しなければならない。
(エネルギー基本計画)
第十二条 政府は、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画(以下「エネルギー基本計画」という。)を定めなければならない。
2 エネルギー基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 エネルギーの需給に関する施策についての基本的な方針
二 エネルギーの需給に関し、長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策
三 エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するために重点的に研究開発のための施策を講ずべきエネルギーに関する技術及びその施策
四 前三号に掲げるもののほか、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 経済産業大臣は、関係行政機関の長の意見を聴くとともに、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、エネルギー基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 経済産業大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、エネルギー基本計画を、速やかに、国会に報告するとともに、公表しなければならない。
5 政府は、エネルギーをめぐる情勢の変化を勘案し、及びエネルギーに関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも三年ごとに、エネルギー基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、エネルギー基本計画の変更について準用する。
7 政府は、エネルギー基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国際協力の推進)
第十三条 国は、世界のエネルギーの需給の安定及びエネルギーの利用に伴う地球温暖化の防止等の地球環境の保全に資するため、国際的なエネルギー機関及び環境保全機関への協力、研究者等の国際的交流、国際的な研究開発活動への参加、国際的共同行動の提案、二国間及び多国間におけるエネルギー開発協力その他の国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(エネルギーに関する知識の普及等)
第十四条 国は、広く国民があらゆる機会を通じてエネルギーに対する理解と関心を深めることができるよう、エネルギーに関する情報の積極的な公開に努めるとともに、営利を目的としない団体の活用に配慮しつつ、エネルギーの適切な利用に関する啓発及びエネルギーに関する知識の普及に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
この法律の条文を読む限り、現在の「脱原発」論がいかにヒステリックな論議を仕掛けているかがわかりますよ!では詳しく解説します!
まず、第2条の条文(安定供給の確保)をピックアップします。
************
エネルギーの安定的な供給については、世界のエネルギーに関する国際情勢が不安定な要素を有していること等にかんがみ、石油等の一次エネルギーの輸入における特定の地域への過度な依存を低減するとともに、我が国にとって重要なエネルギー資源の開発、エネルギー輸送体制の整備、エネルギーの備蓄及びエネルギーの利用の効率化を推進すること並びにエネルギーに関し適切な危機管理を行うこと等により、エネルギーの供給源の多様化、エネルギー自給率の向上及びエネルギーの分野における安全保障を図ることを基本として施策が講じられなければならない。
************
つまり、この観点を抜きにした政策論争などあり得ないのですよ。と言うかエネルギー政策とは言えないのです。では、民主・共産・社民・未来の各政党が、この条文に答えるように「脱原発」の優位性を唱えていますか?唱えていないでしょう?
特に、「石油等の一次エネルギーの輸入における特定の地域への過度な依存を低減する」どころか、現状では原発を止めたら液化天然ガスを大量に必要とする火力発電の依存度がますます上がるんですよ!と言うことは、その前述にある「世界のエネルギーに関する国際情勢が不安定な要素を有している」影響をますます受けるんですよ!
この事への対処も民主・共産・社民・未来の各政党の「脱原発派」は言わないでしょ?
とにかく「まともな日本のエネルギー政策をまったく考えていない」のが「脱原発派」の皆さんと言えるでしょう!
福島県民へ感情論で訴えて、不安を煽る選挙戦術は、責任ある政治家として民主・共産・社民・未来の各政党の皆様はやめたらいかがですか?
慎んでご忠告申し上げます。
では(その2)に続けます。
【関連資料】
●エネルギー政策基本法(ウィキペディア)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95
エネルギー政策の大きな方向性を示すことを目的として制定された[1]。自由民主党の議員立法により2002年6月7日に成立、同月14日公布、施行された。
「安定供給の確保」、「環境への適合」、「市場原理の活用」などの基本理念が掲げられている。
また国の責務、地方公共団体の責務、事業者の責務、国民の努力、相互協力などが規定されている。
また国は「エネルギー基本計画」を定めなければならないこと、国際協力の推進、知識の普及についても規定されている。
●エネルギー政策基本法
(平成十四年六月十四日法律第七十一号)
(目的)
第一条 この法律は、エネルギーが国民生活の安定向上並びに国民経済の維持及び発展に欠くことのできないものであるとともに、その利用が地域及び地球の環境に大きな影響を及ぼすことにかんがみ、エネルギーの需給に関する施策に関し、基本方針を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、エネルギーの需給に関する施策の基本となる事項を定めることにより、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進し、もって地域及び地球の環境の保全に寄与するとともに我が国及び世界の経済社会の持続的な発展に貢献することを目的とする。
(安定供給の確保)
第二条 エネルギーの安定的な供給については、世界のエネルギーに関する国際情勢が不安定な要素を有していること等にかんがみ、石油等の一次エネルギーの輸入における特定の地域への過度な依存を低減するとともに、我が国にとって重要なエネルギー資源の開発、エネルギー輸送体制の整備、エネルギーの備蓄及びエネルギーの利用の効率化を推進すること並びにエネルギーに関し適切な危機管理を行うこと等により、エネルギーの供給源の多様化、エネルギー自給率の向上及びエネルギーの分野における安全保障を図ることを基本として施策が講じられなければならない。
2 他のエネルギーによる代替又は貯蔵が著しく困難であるエネルギーの供給については、特にその信頼性及び安定性が確保されるよう施策が講じられなければならない。
(環境への適合)
第三条 エネルギーの需給については、エネルギーの消費の効率化を図ること、太陽光、風力等の化石燃料以外のエネルギーの利用への転換及び化石燃料の効率的な利用を推進すること等により、地球温暖化の防止及び地域環境の保全が図られたエネルギーの需給を実現し、併せて循環型社会の形成に資するための施策が推進されなければならない。
(市場原理の活用)
第四条 エネルギー市場の自由化等のエネルギーの需給に関する経済構造改革については、前二条の政策目的を十分考慮しつつ、事業者の自主性及び創造性が十分に発揮され、エネルギー需要者の利益が十分に確保されることを旨として、規制緩和等の施策が推進されなければならない。
(国の責務)
第五条 国は、第二条から前条までに定めるエネルギーの需給に関する施策についての基本方針(以下「基本方針」という。)にのっとり、エネルギーの需給に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国は、エネルギーの使用に当たっては、エネルギーの使用による環境への負荷の低減に資する物品を使用すること等により、環境への負荷の低減に努めなければならない。
(地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、基本方針にのっとり、エネルギーの需給に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、その区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 地方公共団体は、エネルギーの使用に当たっては、エネルギーの使用による環境への負荷の低減に資する物品を使用すること等により、環境への負荷の低減に努めなければならない。
(事業者の責務)
第七条 事業者は、その事業活動に際しては、自主性及び創造性を発揮し、エネルギーの効率的な利用、エネルギーの安定的な供給並びに地域及び地球の環境の保全に配慮したエネルギーの利用に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するエネルギーの需給に関する施策に協力する責務を有する。
(国民の努力)
第八条 国民は、エネルギーの使用に当たっては、その使用の合理化に努めるとともに新エネルギーの活用に努めるものとする。
(相互協力)
第九条 国及び地方公共団体並びに事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体は、エネルギーの需給に関し、相互に、その果たす役割を理解し、協力するものとする。
(法制上の措置等)
第十条 政府は、エネルギーの需給に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。
(国会に対する報告)
第十一条 政府は、毎年、国会に、エネルギーの需給に関して講じた施策の概況に関する報告を提出しなければならない。
(エネルギー基本計画)
第十二条 政府は、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画(以下「エネルギー基本計画」という。)を定めなければならない。
2 エネルギー基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 エネルギーの需給に関する施策についての基本的な方針
二 エネルギーの需給に関し、長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策
三 エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するために重点的に研究開発のための施策を講ずべきエネルギーに関する技術及びその施策
四 前三号に掲げるもののほか、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 経済産業大臣は、関係行政機関の長の意見を聴くとともに、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、エネルギー基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 経済産業大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、エネルギー基本計画を、速やかに、国会に報告するとともに、公表しなければならない。
5 政府は、エネルギーをめぐる情勢の変化を勘案し、及びエネルギーに関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも三年ごとに、エネルギー基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、エネルギー基本計画の変更について準用する。
7 政府は、エネルギー基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国際協力の推進)
第十三条 国は、世界のエネルギーの需給の安定及びエネルギーの利用に伴う地球温暖化の防止等の地球環境の保全に資するため、国際的なエネルギー機関及び環境保全機関への協力、研究者等の国際的交流、国際的な研究開発活動への参加、国際的共同行動の提案、二国間及び多国間におけるエネルギー開発協力その他の国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(エネルギーに関する知識の普及等)
第十四条 国は、広く国民があらゆる機会を通じてエネルギーに対する理解と関心を深めることができるよう、エネルギーに関する情報の積極的な公開に努めるとともに、営利を目的としない団体の活用に配慮しつつ、エネルギーの適切な利用に関する啓発及びエネルギーに関する知識の普及に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。