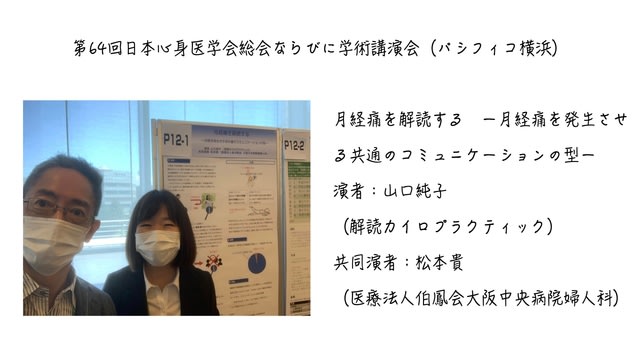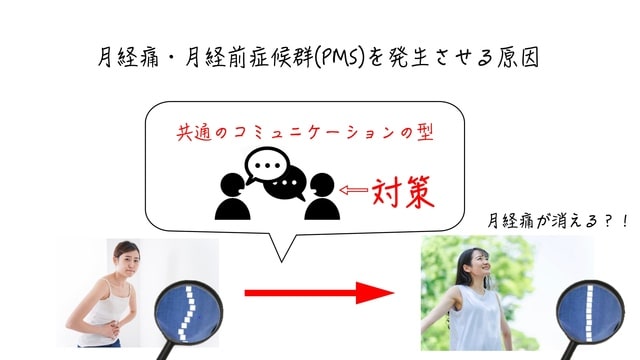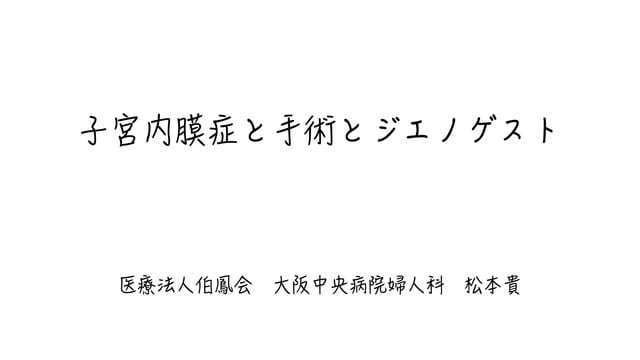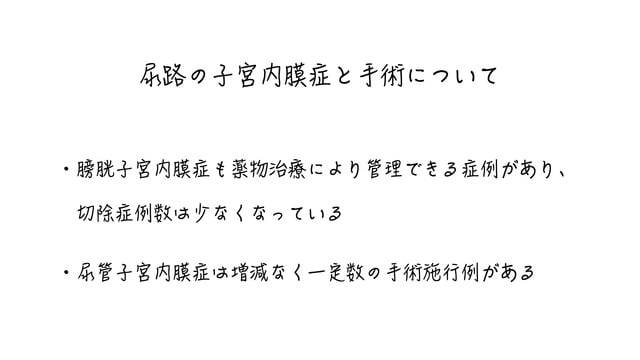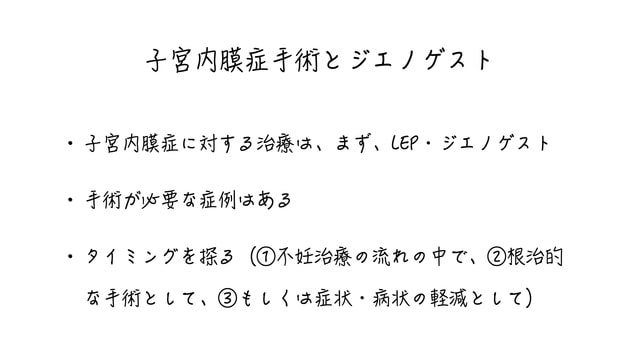手術時間については、いろいろと考えさせられることがあります。
私の手術は、比較的早い方だと思います。ですが、世の中には私よりもはるかに早い手術をする人がたくさんいます。「手術が早い=良い手術」というわけではありませんが、やはり手術時間は短い方が、患者さんの体への負担も少なく、医療費の削減・病院の経費節減にもつながります。
では、どうすれば手術時間を短縮できるのでしょうか?
もちろん、闇雲にスピードを上げるだけではいけません。一つ一つの手術操作を丁寧に行いながらも、無駄を省き、効率的に手術を進めることが重要です。
私は、たとえ一手間かかっても、より安全で確実な方法を選択するようにしています。例えば、止血する際でも気になるところは糸針で縫合するようにしています。これは、一見すると時間がかかるように思えるかもしれません。しかし、この一手間をかけることで止血操作をスムーズに終えることで実際には時間が短縮しますし、術後の出血リスクを大幅に減らすことができます。
また、私は手術中の無駄な動きを極力減らすように心がけています。要領の悪い無駄な手術操作は、時間の無駄につながるだけでなく、手術室のランニングコストを増大させてしまいます。
私は、手術室のランニングコストは1分間で2000~3000円程度と算出しています。無駄な時間を10分間削減できれば、2万~3万円のコスト削減になるわけです。これは、決して無視できる金額ではありません。技術認定医であっても無駄を省いていける人は少ないように思います。
手術時間に対する私の考え方をまとめると、以下のようになります。
- 手術は、早ければ良いというわけではない。
- 患者さんの安全を第一に考え、丁寧な手術を心がける。
- 無駄な手術操作を避け、効率的に手術を進める。
- 手術時間短縮は病院の経済的負担を減らし良質な医療の提供に寄与しています。
手術が早ければ、その分早く家に帰れるし超過勤務手当も削減できて病院経営にも好影響です。(もちろん安全第一ですよ😊 )