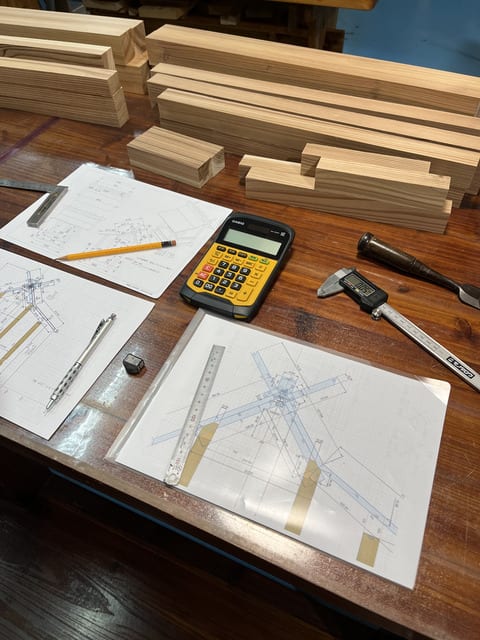漆塗り
漆の塗り厚が水研ぎできるレベルまで達したので、平面出しの作業に入る。
写真右手前は水研ぎした後。

↑ この屋根板への漆塗りは、厚めに塗った上に、湿度が高く、乾燥が早く進んで縮みができてしまった。
なので、縮みの凹凸が目立たなくなるまで 砥石(♯1200)で念入りに水研ぎをする。
屋根の漆塗りは、少しでも厚塗りにしたいので、拭き漆を繰り返した後、ヘラ押さえでの仕上げを繰り返す。
ヘラで仕上げると、多少のムラやスジがでるが、透明感のある美しい仕上がりとなる。
自己流の漆塗りなのです。
千木の漆塗り。

マスキングテープを使い、2回に分けての塗装。
こちらは鰹木。

円柱状のため、ヘラで押さえることができないので拭き漆での仕上げ。
木組の確認作業
こちらは、仮組み前の作業。

各部材の取り合いが複雑なので何度も確認。
このお社製作、予定よりも随分と時間がかかってしまっている。
関連記事
福島木工家具店
オーダー・造作家具 木製品設計製作
〒891-4404 鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間752
mail : fukumoku1@gmail.com
T/F : 0997-47-2695
木育ブログはこちら → 家具職人の木育ブログ