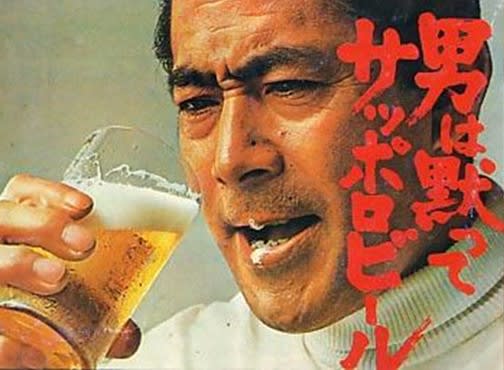「素敵なご臨終」に立ち会った緩和ケア医が教える、いい最期を迎えるために、医師に聞くこと話すことをためらってはいけない訳
11/16(土) 6:01配信
ダイヤモンド・オンライン
「素敵なご臨終」に立ち会った緩和ケア医が教える、いい最期を迎えるために、医師に聞くこと話すことをためらってはいけない訳
写真:ダイヤモンド・オンライン
人は自分の死を自覚した時、あるいは死ぬ時に何を思うのか。そして家族は、それにどう対処するのが最善なのか。
16年にわたり医療現場で1000人以上の患者とその家族に関わってきた看護師によって綴られた『後悔しない死の迎え方』は、看護師として患者のさまざまな命の終わりを見つめる中で学んだ、家族など身近な人の死や自分自身の死を意識した時に、それから死の瞬間までを後悔せずに生きるために知っておいてほしいことを伝える一冊です。
「死」は誰にでも訪れるものなのに、日ごろ語られることはあまりありません。そのせいか、いざ死と向き合わざるを得ない時となって、どうすればいいかわからず、うろたえてしまう人が多いのでしょう。
今回は、『後悔しない死の迎え方』の著者で看護師の後閑愛実(ごかんめぐみ)さんが、『素敵なご臨終』の著者で緩和ケア医の廣橋猛(ひろはしたけし)先生に「大切な人の素敵なご臨終に向けて」というテーマでお話をうかがいました。
【この記事の画像を見る】
● 病院か在宅かの二者択一ではなく
後閑愛実さん(以下、後閑):今日は緩和ケア医の廣橋先生に、がんを抱えた大切な人を支えるご家族のためになるお話をうかがえればと思っています。
まずは簡単に自己紹介していただいてもよろしいですか?
廣橋猛先生(以下、廣橋):私は病院に勤務しながら必要な時に患者さんの家に診にいくという、病院と在宅医療の両方に携わる二刀流の緩和ケア医です。
今は永寿総合病院と、近くのクリニックの両方に勤務する形をとっています。
それぞれの勤務時間は決めていますが、どちらも主治医という形で何か急なことがあった時には対応できるようにしています。24時間365日、両方の患者さんを診ています。
後閑:在宅で診ていた患者さんを具合が悪いので入院させたいという場合には、永寿総合病院に入院してもらって入院中も診ていただくということができますか?
廣橋:はい。ですから入院している患者さんからすると、「先生が診にきてくれるのなら、がんばって帰ろう」ということになります。また、家で具合が悪くなって入院が必要になった時には迅速に入院できるようにしています。
ソーシャルワーカーや病院の先生は、「これから病院で過ごしたいですか? おうちで過ごしたいですか?」という二者択一で聞くことが多いのですが、希望する場はその時々で変わっていくものなので、臨機応変に変えていくお手伝いが必要です。二刀流はそのために続けています。
後閑:「病院か、在宅か」という二者択一でなく必要に応じて、具合が悪い時は入院して、ちょっと良くなったら家で過ごす、それを本人が選べるというのがいいですね。
廣橋:治療もケアも切れ目ないほうが、人生で大切にしているものを継続していけます。患者さんや家族も安心だし、医療者もやりがいを感じられると思います。
● 本人の意思決定が家族の迷いをやわらげる
後閑:廣橋先生が見送られた患者さんで、これは「素敵なご臨終」と思った事例はありますか?
廣橋:長いおつきあいで、自分にとっても感慨深く、思い出深い方がいます。
60代前半の男性で、奥さんと2人暮らし、子どもは結婚して家を出られている方でした。
患者さんは奥さんのほうです。奥さんは抗がん剤を拒否し、怪しい治療を受けようとしていました。そうしたら具合が悪くなり、苦しくなって入院してきたのです。治療で苦しさは取れ、とても楽になったので、「やっぱり真面目に治療しないといけない」と口にしたのです。
僕は緩和ケア医ですが、患者さんに長く頑張りたいという気持ちがあり、チャンスがあるなら治療をおすすめするのが当然の役割だろうと思っています。ですから、ちゃんとした医師に適切ながん治療を相談したほうがいいと伝えました。
廣橋:そもそもその患者さんが怪しい治療に行ってしまったのは、もともとの主治医の先生と相性が悪く、コミュニケーションがうまくとれていなかったからでした。私が信頼している腫瘍内科の先生を紹介したら、とても安心され、信頼して治療もその後だいぶ長く頑張られました。
ただ、そうは言っても、この患者さんの場合、抗がん剤は延命のための治療であり、どこかで効かなくなってしまうので、そのために将来に向けての準備という意味で緩和ケアのかかわりは必要です。その患者さんとは数か月に1回という感じで定期的に面談しました。体調管理のことや、将来具合が悪くなった時にどうする、どうしたいという話し合いをしたり、何を大切に今を生きているのかという話もしました。
ご本人は緩和ケアの意味を理解していましたし、いずれは死を迎える状況であることをわかっていたので、終活に燃え始めていました。
フラダンスがご趣味で、教室に通ってフラダンスの発表会に出ることが生きがいでした。治療している医師もそれをよくわかってくださっていて、治療のスケジュールもフラダンスに影響が出ないように工夫してくれて、治療だけでなく人生を支えてくださったんです。
患者さんはご自分で遺影なども準備し始めました。それに対してご主人は「本人はいいんでしょうが、僕は少しショックです」と言うこともありました。でも、そういう奥さんを精一杯支えていました。
そんな時期が2年くらい続きました。
その後、具合が悪くなってきてしまい、いよいよ治療が効かなくなってきてしまいました。抗がん剤の治療も終了としました。
以前から亡くなる時はこうしたいというのを決めていて、自分で動けなくなったら緩和ケア病棟に入院したい、最後が苦しくなるようだったら、いわゆる鎮静、眠るようにして苦しみをとり、穏やかに最期を迎えたい、ということをはっきりと言われていました。
事前に人生の締めくくり方を医師と話し合っていて、そういった話をご主人ももちろん横でいつも一緒に聴いてメモしていました。時には子どもさんもいらして、最期をどう過ごすのか、特に、入院するかどうか、鎮静するかどうかという話をしました。
いざそうなった時に選択肢を初めて出されると、皆さんすごく迷います。バタバタと物事も進むし、落ち着いて考えられないんですよ。
いざその場に直面した時は心がすごく動揺しているので、本来の決め方ができない方が多いんです。その時にはご本人の意識が確認できなくなっていることもあります。
この患者さんの場合は、はっきりとご自分の意思を明示されていたので、ご主人が「こういう状況になったので入院させてやりたい、妻も自分でそう決めてずっと言っていたから、僕もそれがいいと思う」ということで緩和ケア病棟に入院しました。
入院した時はご本人も、「ようやくここまできました。最後先生のところで穏やかに終わることができると思っているから安心です」と言われて、その後穏やかに過ごされていました。
遺影まで病室に持ってきて、準備万端です、といった感じでした。ご主人は微妙な感じでしたが。でも、「ご本人の思うようにやってやりたい、それが一番いいだろう」と。
最終的には呼吸が苦しくなってこられたんです。モルヒネなどで苦しさをとる治療は続けていましたが、ご本人もそろそろ起きて話しているのがつらいというので、以前からお話ししていた眠ることも考えましょうかという話をすると、「そうしたい」と。ご主人も「前々からそう話をしていたから、これで鎮静でも僕は後悔しません」と。
そして、眠ってもらうような治療に切り替え、数日後に亡くなられました。
最後はフラダンスの衣装に着替えてお帰りになりました。
大事なのは、治療を支えるのも緩和ケアでしたし、治療しながらでも人生で大事なことであるフラダンスを踊ることができていましたし、亡くなる時に悔いのない準備もできていました。最後を過ごす場の意思決定や鎮静をどうするかという意思決定も事前にちゃんとご本人にできていたので、ご家族も迷うことがありませんでした。
ご主人もお子さんもいい終わり方ができてよかったと言ってくださいました。その後もこちらで定期的に開いている遺族会というものにも参加してくれて、そういったお話を聞かせてくださったり、お手紙をくださったりして、よかったなと思いました。私の中ではとても印象深い患者さんです。
● 医師は聞かれないと言ってはくれない
後閑:廣橋先生がすごく適切なタイミングで説明していたんでしょうね。
たとえば、最後苦しさが取れなくなってきたら眠らせて苦しみをとることもできるということを一般の人は知りませんよね。そういうことを事前に適切にお話しされていたのだろうと思います。すべての先生が廣橋先生のようにうまく説明できているわけではないでしょうし、言ってくれない医師のほうが多いように思います。
廣橋:そうですね。聞かれないので言わないということは多々あります。
医師も悪い話を自分からは言いにくいものなので、医師が話しやすいきっかけ作りを患者さんにもしていただけるといいかと思います。
ですがその内容が医師だけでは説明しきれないもので、十分な情報提供や時間が取れないようならば、特にがん患者さんなら、がん相談に乗ってくれる相談員、ソーシャルワーカー、看護師といったサポートする体制が日本には複数できているので、次につなげることも可能です。ですから、そういったことを気にしているというサインを患者さんがまず出していくことが大事です。
後閑:そうしないと、症状が出てから対応する、困りごとが出てから対応する、という後手後手になって、結局痛みが取れなかったり、苦しんで困ったまま最後を迎えるということになってしまいますよね。
廣橋:そうなんです。がんの場合は基本的に先が読めます。だいたい経過というのはわかります。なのに、後手後手になってしまうのはすごくもったいないことです。
先回りして準備できていたら、必ずもっとラクな過ごし方ができます。そういったことを知っておいてほしかったので『素敵なご臨終』という本を書いたんです。
後閑:緩和ケアの定義にも、「苦しみを緩和するだけでなく苦しみを予防する」ということがありますよね。
緩和ケアは痛くなってから行くところではなく、痛くなる前、困る前からかかることで、あらかじめ困る芽を摘んでおくということもできますから。
廣橋:緩和ケア病棟だと、そろそろ死が近いとなった時に医師は今の症状と今後の見通しについて話をするのですが、担当の看護師に同席してもらって、実際に亡くなる時にどういう付き添いをしたいのか、亡くなった後のご葬儀の話、私たちが「お清めの服」と呼んでいる、亡くなってお帰りになる時の服装をどうしたいのかを確認したりします。そして病棟の倉庫にお清め服を用意しておきます。
先ほどの患者さんはフラダンスの衣装でしたが、この辺りは下町で祭りも多いから祭りの法被で帰りたい人もいれば、背広の人も着物の人もいます。こういった話をすることで、その人が元気だった頃のイメージをみんなで話し合えるので、それをきっかけにいいコミュニケーションがとれるようです。
後閑:その人の今だけでなく、過ごしてきた人生の物語を知ることにもつながりますよね。
最後に着せたい服なんて、いちばん好きで気に入っていたか、思い出があったものでしょうし、そういうことをご家族と話すこともグリーフケアにつながったりもするかなと思います。
脳腫瘍で亡くなられた40代の女性はご主人に看取られたのですが、「ミニーちゃんのパジャマを着せてほしいです」と言われたんです。
後閑:入院中、その奥さんはずっとディズニーのパジャマを着ていたので、「ディズニーがお好きだったんですか?」と聞いたら、「ディズニーが好きというか、ディズニーランドに子どもたちと行くのがすごく好きだったから、少しでもその時の気分を味わえたらと思って」と言われました。意思疎通ができなくなっても、常に周りはディズニーのグッズであふれていました。
好きだったことや物にも思い出が宿って、本人にとっては宝物ですし、ご家族にとっても何かしてあげられた気持ちになるものと思っています。
廣橋:看取りは、長い物語の終着駅であり総まとめです。物語を締めくくる大事な場面ですので、どんな人生だったかという物語の話をするのはいいと思いますし、大事なことだと思います。
最後に着る服は、その象徴かもしれませんね。
後閑:そうですね。
私たち医療者は、病気で入院してきた後の、具合が悪い状態という、切り取られた人生の一部分しか見ることができません。ですから、どういう人生を歩んできたかということがわからないまま、何となく症状に対する治療を始めてしまいますが、どう過ごしてきて、どういう物語を続けてきて、最後までどういう物語を続けたいと思っているのか、それを支えるための医療が提供できたらいいと思うので、「こんなことを先生に言ってもいいのかな」と思わずに、ご家族にはご本人の物語を医療者に話してほしいです。
がんを抱えた大切な人を支える家族に知っておいて欲しいこと
●治療を支えるために最初から緩和ケアを受けること
●治療しながら最期まで、本人が人生で大切にしているものを重視すること
●最期に過ごす場や鎮静をどうするかという意思決定を事前に本人がしておくこと、それを家族が知っておくこと、その準備をしておくこと、このために医師に聞くこと話すことをためらわないこと。
後閑愛実

病気ではなく老化現象? 健康寿命“75歳の壁”の正体〈週刊朝日〉
11/16(土) 11:30配信
AERA dot.
病気ではなく老化現象? 健康寿命“75歳の壁”の正体〈週刊朝日〉
がん年齢別罹患者数 (週刊朝日2019年11月22日号より)
約7人に1人が「後期高齢者」にあたる75歳以上という日本。体や心の機能が10~20年前に比べて5~10歳若返っており、社会で活躍する後期高齢者も少なくない。だが、やはり“寄る年波には勝てない”ことを実感するのも、このころからではないだろうか。実態をつかむことが対策の第一歩。75歳の壁の正体を知り、うまく乗り越えよう。
【イラストで見る】75歳以上に多い病気
今年1月に75歳の誕生日を迎えた主婦のヨシコさん(仮名)は、「いろんな問題が顔を出した一年だった」と振り返る。
春には白内障と診断され手術。これまで安定していた生活習慣病関連の数値が急に悪くなり、めまいや足の付け根の痛みなどにも悩むようになった。
「体力も食欲も以前のままなのに。明らかに体の状態が変わった気がする」
実際、75歳、あるいは70代での変化は、多くのデータからも見てとれる。
まず本誌が注目したのは患者調査(2017年)。国が3年ごとに行っている調査で、さまざまな病気の推計患者数が年齢別などに載っている。これを見ると、高血圧や糖尿病、COPD(慢性閉塞性肺疾患)などの慢性疾患や、これらの病気が原因で起こる心筋梗塞や脳梗塞などで、若い人よりも患者数が多い。
75歳以上の生活習慣病については、加齢に伴う生理的な変化もあり、症状の表れ方も治療に対する反応も若い人とは異なる。このため、日本老年医学会は高血圧や糖尿病などの病気で75歳以上が目標とする値を打ち出した。
例えば、高血圧では、目標値を74歳以下よりも高く150/90mmHg未満としている。厚生労働省の日本人の食事摂取基準(2015年版)でも、70歳以上が目標とするBMI(体格指数)を21.5~24.9としている(ちなみに、50~69歳は20.0~24.9)。
高齢者に生活習慣病が増える背景を、慈恵医大晴海トリトンクリニック(東京都中央区)で高齢者の寝たきりを防ぐ取り組み「ライフデザインドック」を行っている東京慈恵会医科大学教授の横山啓太郎さんは、「糖尿病や高血圧といった生活習慣病の多くは、病気というよりも、老化と捉えたほうがいい。増えるのは自然なこと」と話す。
「そもそも老化とは、体を一定の状態に保つ力、専門的には“恒常性(ホメオスタシス)”が保たれなくなる状態と考えられています。わかりやすくいうと、若いときは徹夜をしても、少しぐらいお酒を飲みすぎても、翌日には何とかなったもの。ですが、年齢を重ねるうちに無理が利かなくなり、体がきつくなってきます。それは元に戻る力が働きにくくなったためで、それこそが老化現象なのです」
横山さんによると、徹夜や飲酒に限らず、塩分や糖分、脂肪の過剰摂取でも同じことがいえるという。
「若いころはこうしたさまざまなリスクに対して体が対応できていましたが、あるときを境にそれができなくなる。その結果が高血圧であり、糖尿病なのです。当然ながら、老化は腎臓や膵臓、肝臓など、体の一部だけでなく、全身で起こりますから、複数の生活習慣病にかかりやすくなる。つまり、高血圧の人は糖尿病にもかかりやすいといえるのです」(横山さん)
個人差はあれ、恒常性が保たれにくくなり、生活習慣病が進行していく。その結果、免疫力が落ち、要介護になるリスクが高まる。そうした時期が一般的には70代なのだという。

fcb***** | 7時間前
年取れば健康でいるのは難しいというのはあたりまえじゃないのかな。
だから生活習慣や運動やら食事に気を付ければ年とっても病気知らず、元気で若々しいままでいられる筈、そうでない人は自業自得だ、というのは少しおかしいと思う。
いくつになっても元気というのはその人が遺伝子レベルからほかの人とは少し違う、という部分があるという事実を無視してはいけないのではないか。
65 5
返信0
ong***** | 7時間前
高齢者は病院に行ってはいけません。
歳のせいは病ではないので、何をしても治りません。
薬は体のする事に逆らうので、
複数の薬で認知症や、寝たきりになります。
血圧が上がるのは、体がその方が良いからです。
体の管理は体に任せるのが一番良いのです。
体の司令塔が狂っているのなら既に死んでいる。
53 27
返信0
ame***** | 1時間前
今年70歳になった、体力が落ちたので仕事を始めた、血圧125-70、視力1.0-0.8だが、肥満、コレステロール、頭痛がある、検査しても異常はない、老化から来る身体全体の不調は病気ではない、最低限の薬は飲むが医者は薬売っていくらの世界、車と同じで上手くメンテナンスするしか方法はない。チューブ通して長生きする必要はない、健康長寿で無くなればじたばたしても仕方ない。
1 0
返信0
・ | 8時間前
80歳の母は自分が年寄りだと思っていない。
老人ホームに話し相手に行くボランティアから帰ると も〜年寄りの話しは長くて長くて。と言う。
そういう母も話しは長い。
自分が年寄りだと思わないのが若さの秘訣?
90 6
返信0
もも | 9時間前
そうでしょうね。
これからも老化に医療費をつぎ込んでたら
現役世代はたまったものじゃない。
82 10
返信0
j******* | 7時間前
1999年より定期的にきちんと通っている市のトレーニング施設に、81歳の爺ちゃんがいる。僕が通い始めた時にはすでに来ていた方で、ぱっと見で80代には見えない。日ごろ運動する習慣(2回/週)、酒もタバコもやらず、食事はきちんと摂るといったことが若さの秘訣?らしい。筋肉質な体ではないけど、ベンチプレス70Kgを軽々と挙げる。
15 7
返信1
u.w.∞ | 7時間前
スーパーセンチナリアンの免疫細胞がDNAにある方は、「75歳壁」が無いですね。
キラー細胞増やせるなら、増やしたいしたい所ですね。
6 0
返信1
ber***** | 9時間前
そらそーでしょ、としか
34 5
返信0
yut***** | 9時間前
老化ってあれでしょ、廊下
2 14
返信0
NY | 9時間前
なのに、70歳まで働けって(TT)