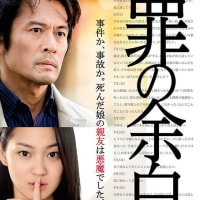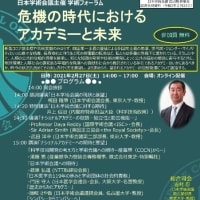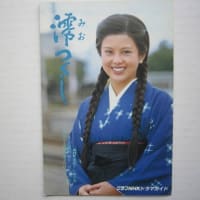昨日記したように古本屋で見つけた1冊、中谷宇吉郎ー「科学の方法」。(アマゾンでも出てこない、もう絶版かな?)
1958年初版、1976年22刷。280円。古本屋で150円。
この値段でこの中身。なんとももったいないというかありがたいというか。中谷57歳の時の著作である。本当に一睡もせずに読んでしまった。感慨がひとしおである。私はこの本を30年も前に一度読んでいる。その時はただただふんふんと読んだとしか記憶にはない。しかし、今30年の時を経て読み、年齢も似たようなものとなると、その心の奥底までも見えてくる気がする。
中谷宇吉郎はすでに亡くなってはいたが科学ファンを魅了して止まないスーパースターであった。北海道大学には中谷に憧れて入学してくる学生が実に多かった。「お前はどうして北大理学部?」「中谷宇吉郎だよ!」てな会話があちこちにあった。既に死後随分経っていたのにである。目の前で彼のいた、時計台の美しい低温研究所の優雅な建物が壊されていく時には、何とも言えない悲しい思いが広がり黒山の人だかりであった。
さて、そんな思い出を胸に読み始めて、その明瞭さに改めて感服した。20世紀半ば、物理帝国主義と言われた自然科学の中で、その方法と限界、人間との関係までをも含めて、こうも平易にかつ明快に展開していたのだと改めて思う。特に物理学の勝利を高々と詠い上げるのではなく、その不得意とする対象と自然、不安定現象と複雑性、歴史性などに関わる記述は、1970年代以降大きく浮上する「複雑性の科学」そのものである。ただ、彼の年齢がそう言わせるのか、彼が人生の中で体験した大病と迫り来る死(彼はこの執筆の4年後、61歳で病死する)のためなのか、そこへ向かって突き進むのだ!という迫力はない。ただただ憧れと、あきらめが入り交じったような心情が伝わってくる。そう勝手に解釈すると読み手の側に感情が高ぶってさえ来る。さすがに寺田寅彦の一番弟子。研究が心からしたくなってくるぞ!
北大博物館に彼の研究室が復元されているという。今月末、また北大へ出張予定があるのでのぞいて見ようと思う。
さ、これから本を片手に、初詣。
1958年初版、1976年22刷。280円。古本屋で150円。
この値段でこの中身。なんとももったいないというかありがたいというか。中谷57歳の時の著作である。本当に一睡もせずに読んでしまった。感慨がひとしおである。私はこの本を30年も前に一度読んでいる。その時はただただふんふんと読んだとしか記憶にはない。しかし、今30年の時を経て読み、年齢も似たようなものとなると、その心の奥底までも見えてくる気がする。
中谷宇吉郎はすでに亡くなってはいたが科学ファンを魅了して止まないスーパースターであった。北海道大学には中谷に憧れて入学してくる学生が実に多かった。「お前はどうして北大理学部?」「中谷宇吉郎だよ!」てな会話があちこちにあった。既に死後随分経っていたのにである。目の前で彼のいた、時計台の美しい低温研究所の優雅な建物が壊されていく時には、何とも言えない悲しい思いが広がり黒山の人だかりであった。
さて、そんな思い出を胸に読み始めて、その明瞭さに改めて感服した。20世紀半ば、物理帝国主義と言われた自然科学の中で、その方法と限界、人間との関係までをも含めて、こうも平易にかつ明快に展開していたのだと改めて思う。特に物理学の勝利を高々と詠い上げるのではなく、その不得意とする対象と自然、不安定現象と複雑性、歴史性などに関わる記述は、1970年代以降大きく浮上する「複雑性の科学」そのものである。ただ、彼の年齢がそう言わせるのか、彼が人生の中で体験した大病と迫り来る死(彼はこの執筆の4年後、61歳で病死する)のためなのか、そこへ向かって突き進むのだ!という迫力はない。ただただ憧れと、あきらめが入り交じったような心情が伝わってくる。そう勝手に解釈すると読み手の側に感情が高ぶってさえ来る。さすがに寺田寅彦の一番弟子。研究が心からしたくなってくるぞ!
北大博物館に彼の研究室が復元されているという。今月末、また北大へ出張予定があるのでのぞいて見ようと思う。
さ、これから本を片手に、初詣。