東日本大震災発生から15日後の2011年3月26日。
映画監督・作家の森達也、映像ジャーナリスト・綿井健陽、映画監督・松林要樹、映画プロデューサー・安岡卓治の4人が、放射線検知器を搭載した車で被災地へと向かう。
福島第一原発から150km地点で線量計のスイッチを入れると、あっという間に東京の数十倍の値を記録。
50km圏の三春町に宿を取った4人は、旅館で会った双葉郡出身の25歳男性に話を聞く。
彼は、津波と地震だけなら既に復興は始まっていると言い、原発事故の影響を語る一方で、東京電力のお陰で町は発展したと語った。
翌日、一行は浪江町方面へと向かい、屋内退避勧告の出ている20~30km圏内の町で見つけた集会所の様子を窺うが、人の気配はない。
集会所から車に引き返す際、放射能防護用衣類の着脱でパニック状態を起こし、また衣類を脱ぐ際にはドアを開け放したために車内の線量も急激に上昇して、車内は不安に包まれる。
曖昧な取材姿勢と不十分な装備を自覚した4人は、福島の取材を断念して津波の被災地へと向かう。
陸前高田市で消防隊員に行方不明者捜索について話を聞き、大船渡市、仙台市市街地と、余震の続く中を取材して回る4人。
石巻市の大川小学校では、自力で我が子の遺体を捜す母親たちの口から、被災者の現実が語られる。
更に取材を続けるうちに遺体発見の現場に立ち会うことになり、その模様を撮影していると、遺族の一人から角材を投げつけられた…
震災発生直後、現地へと向かう4人は妙にハイテンションで、物見遊山に出かけるような雰囲気さえ漂わせている。
車内の線量計の数値がみるみる上昇しても、はしゃいでいるようにしか見えない。
不謹慎とさえ言える4人の言動だが、福島における放射能汚染の厳しい現実を目の当たりにし、津波被害地の凄惨な状況を目撃するにつれ、表情は険しく硬くなっていく。
そして大川小学校の遺体捜索現場で、発見された遺体にカメラを向けた際に遺族と衝突するに至って、ようやく彼らは自分たちの行動に目的を見出し、伝えるべきことを得て、ドキュメンタリストとしての本分を取り戻したのではないだろうか。
被災者へのインタビューや、遺族との話し合いの際に見せる森達也のこわばった表情が、彼らの自省の念を物語っているように思えた。
4人の姿に、阪神淡路大震災の際に、会社の営業拠点に支援に行ったときの自分を思い出した。
確かに自宅も大きく揺れ、神戸方面のすさまじい映像を報道映像で目にしていたとはいえ、どこか他人ごと、
別世界のことのような感覚だったことは否めない。
そして震災翌日、鉄道は寸断されて使えないため、大阪港から船に乗り込んで現地に向かい、神戸ハーバーランドに降り立ったときに受けた衝撃は忘れられない。
本作における4人は、悲しいかな、これが人間の真の姿というもの。
我が身に降りかからなければ、本当の思いは分からない。
しかしそのことを冷静に認識することで、不必要な過剰な哀れみを排除して、被災した人々の心に寄り添うことができるのではないだろうか。
4人の姿を指差して不快に思うのではなく、冷静に自分に置き換えて観るべきである。
大川小学校で、我が子が津波に飲み込まれてしまった母親たちの言葉が胸に突き刺さる。
マスメディアは「悲しい」「辛い」などの言葉を求めてくるが、悲しいとか辛いなどというレベルはとっくに超えている、現実問題として重機が欲しいということを伝えてくれと頼んでも、「それはうまくお伝えできません」と言って取り上げてくれない。
マスコミの在り方に一石を投じる言葉であるが、そのマスコミに民衆は何を求めているのかを表しているのではないだろうか。
またこの言葉は、被災地と被災しなかった地域との温度差を、端的かつ先鋭的に言い表している。
数ある東日本大震災に関するドキュメンタリーの中でも異彩を放つ一品。
「311」
2011年/日本 共同監督:森達也、綿井健陽、松林要樹、安岡卓治
映画監督・作家の森達也、映像ジャーナリスト・綿井健陽、映画監督・松林要樹、映画プロデューサー・安岡卓治の4人が、放射線検知器を搭載した車で被災地へと向かう。
福島第一原発から150km地点で線量計のスイッチを入れると、あっという間に東京の数十倍の値を記録。
50km圏の三春町に宿を取った4人は、旅館で会った双葉郡出身の25歳男性に話を聞く。
彼は、津波と地震だけなら既に復興は始まっていると言い、原発事故の影響を語る一方で、東京電力のお陰で町は発展したと語った。
翌日、一行は浪江町方面へと向かい、屋内退避勧告の出ている20~30km圏内の町で見つけた集会所の様子を窺うが、人の気配はない。
集会所から車に引き返す際、放射能防護用衣類の着脱でパニック状態を起こし、また衣類を脱ぐ際にはドアを開け放したために車内の線量も急激に上昇して、車内は不安に包まれる。
曖昧な取材姿勢と不十分な装備を自覚した4人は、福島の取材を断念して津波の被災地へと向かう。
陸前高田市で消防隊員に行方不明者捜索について話を聞き、大船渡市、仙台市市街地と、余震の続く中を取材して回る4人。
石巻市の大川小学校では、自力で我が子の遺体を捜す母親たちの口から、被災者の現実が語られる。
更に取材を続けるうちに遺体発見の現場に立ち会うことになり、その模様を撮影していると、遺族の一人から角材を投げつけられた…
震災発生直後、現地へと向かう4人は妙にハイテンションで、物見遊山に出かけるような雰囲気さえ漂わせている。
車内の線量計の数値がみるみる上昇しても、はしゃいでいるようにしか見えない。
不謹慎とさえ言える4人の言動だが、福島における放射能汚染の厳しい現実を目の当たりにし、津波被害地の凄惨な状況を目撃するにつれ、表情は険しく硬くなっていく。
そして大川小学校の遺体捜索現場で、発見された遺体にカメラを向けた際に遺族と衝突するに至って、ようやく彼らは自分たちの行動に目的を見出し、伝えるべきことを得て、ドキュメンタリストとしての本分を取り戻したのではないだろうか。
被災者へのインタビューや、遺族との話し合いの際に見せる森達也のこわばった表情が、彼らの自省の念を物語っているように思えた。
4人の姿に、阪神淡路大震災の際に、会社の営業拠点に支援に行ったときの自分を思い出した。
確かに自宅も大きく揺れ、神戸方面のすさまじい映像を報道映像で目にしていたとはいえ、どこか他人ごと、
別世界のことのような感覚だったことは否めない。
そして震災翌日、鉄道は寸断されて使えないため、大阪港から船に乗り込んで現地に向かい、神戸ハーバーランドに降り立ったときに受けた衝撃は忘れられない。
本作における4人は、悲しいかな、これが人間の真の姿というもの。
我が身に降りかからなければ、本当の思いは分からない。
しかしそのことを冷静に認識することで、不必要な過剰な哀れみを排除して、被災した人々の心に寄り添うことができるのではないだろうか。
4人の姿を指差して不快に思うのではなく、冷静に自分に置き換えて観るべきである。
大川小学校で、我が子が津波に飲み込まれてしまった母親たちの言葉が胸に突き刺さる。
マスメディアは「悲しい」「辛い」などの言葉を求めてくるが、悲しいとか辛いなどというレベルはとっくに超えている、現実問題として重機が欲しいということを伝えてくれと頼んでも、「それはうまくお伝えできません」と言って取り上げてくれない。
マスコミの在り方に一石を投じる言葉であるが、そのマスコミに民衆は何を求めているのかを表しているのではないだろうか。
またこの言葉は、被災地と被災しなかった地域との温度差を、端的かつ先鋭的に言い表している。
数ある東日本大震災に関するドキュメンタリーの中でも異彩を放つ一品。
「311」
2011年/日本 共同監督:森達也、綿井健陽、松林要樹、安岡卓治











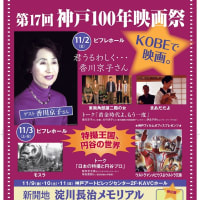








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます