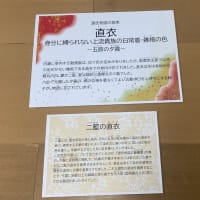梅はバラ科サクラ属の落葉樹。
2~3月の葉が出る前に白または紅色の薫り高い五弁花を開く。
中国原産で、奈良時代に日本に移入されたという。
ただし、紅梅はやや遅れて平安時代にやってきたと考えられている。
2~3月の葉が出る前に白または紅色の薫り高い五弁花を開く。
中国原産で、奈良時代に日本に移入されたという。
ただし、紅梅はやや遅れて平安時代にやってきたと考えられている。
おそらく最初は梅は観賞用としてではなく、
漢方の食用・薬用として中国から入ってきたものとされる。
烏梅(うばい)といわれる実を干したものが薬用に使用されている。
漢方の食用・薬用として中国から入ってきたものとされる。
烏梅(うばい)といわれる実を干したものが薬用に使用されている。
平安時代には<梅干し>の語もあり、
調味料として不可欠の<塩梅(あんばい)>があった。
調味料として不可欠の<塩梅(あんばい)>があった。
万葉集では<うめ>の表記だが、平安時代では<むめ>の表記が多い。
中国語で「梅」はメーと発音するのを、
うめ→むめと日本式音に表記した事にもとづく。
中国語で「梅」はメーと発音するのを、
うめ→むめと日本式音に表記した事にもとづく。
梅は古事記、日本書紀には見えない。
ところが万葉集では梅を詠んだ歌が第1位で120余首もある。2位は桜の40余例。
わが宿のに盛りに咲ける梅の花
散るべくなりぬ見む人もがも (万葉集 大伴旅人)
御苑生(みそのふ)の百木の梅の散る花の
雨に飛び上がり雪と降りけむ (万葉集 大伴家持)
ところが万葉集では梅を詠んだ歌が第1位で120余首もある。2位は桜の40余例。
わが宿のに盛りに咲ける梅の花
散るべくなりぬ見む人もがも (万葉集 大伴旅人)
御苑生(みそのふ)の百木の梅の散る花の
雨に飛び上がり雪と降りけむ (万葉集 大伴家持)
「花」といえば万葉集では梅をさす事が多かったが、
平安時代には次第に桜にとって変わっていった。
平安時代には次第に桜にとって変わっていった。
平安時代には梅の歌は、
万葉集の花の視覚的な色・感覚よりも次第に香り・嗅覚としての歌が多くなる。
万葉集の花の視覚的な色・感覚よりも次第に香り・嗅覚としての歌が多くなる。
また紅梅は香りがやや少ないとされるが、色が桜に似ている事から珍重されたようだ。
梅は鶯の巣くう木とされ、鶯と取り合わされる事も多い。
松・竹・梅は中国では厳寒の3友とされたが日本では池坊専応口伝によると
祝儀生け花にいけた事もあり、後世には祝儀物とされる。
もともとは平安貴族が前庭に植えて心を慰めた事による。「古典文学植物誌知っ得」より
祝儀生け花にいけた事もあり、後世には祝儀物とされる。
もともとは平安貴族が前庭に植えて心を慰めた事による。「古典文学植物誌知っ得」より
『春の夜の 闇はあやなし梅の花
色こそ見えね 香やは隠るる (古今集・凡河内躬恒)』
色こそ見えね 香やは隠るる (古今集・凡河内躬恒)』
また、菅原道真が愛した事でも有名である。
『東風(こち)吹かば にほひおこせよ 梅の花
あるじなしとて 春な忘れそ ( 拾遺和歌集 ・菅原道真 )』
源氏物語では、
若菜下の女楽は梅の盛りの頃の春に行われている。
あるじなしとて 春な忘れそ ( 拾遺和歌集 ・菅原道真 )』
源氏物語では、
若菜下の女楽は梅の盛りの頃の春に行われている。
<紅梅>という巻名や、かさね色の名にも見え、
紫の上が桜とともに愛し、匂宮に紅梅の世話を託す場面(御法)などが有名。
紫の上が桜とともに愛し、匂宮に紅梅の世話を託す場面(御法)などが有名。
余談ながら、私は2月の終わりに京都北野天満宮で雪の梅を見た。
白い雪で花は見えなくても、香りが大変素晴らしくて感激した。
白い雪で花は見えなくても、香りが大変素晴らしくて感激した。
最近では、蝋梅(ろうばい)という黄色の花が香り高く咲く梅も知り、
以来、その香りも気に入っている。
以来、その香りも気に入っている。