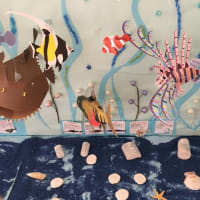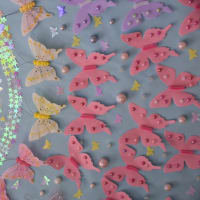口を開けるとのどの両側に見える丸いものを、俗に扁桃腺と言いますが、分泌腺ではありませんせん。正式には口蓋扁桃と言います。扁桃は口蓋扁桃だけでなく、鼻の奥の咽頭扁桃(アデノイド)、舌の付け根の舌扁桃などもあります。体を守る免疫の働きに関わっています。扁桃の炎症を一般に扁桃炎と呼びますが、いろいろな原因によって起こります。
溶連菌感染:細菌性の扁桃炎の中でも、きちんと治療しないと腎炎などの重い合併症を起こすことがあるため、特に注意が必要です。扁桃を中心に、咽頭粘膜に真紅の独特の発赤が見られるので、見ただけでだいたい診断がつきますが、典型的でないものもあるため、簡易キットで検査しますが、数分で結果が出ます。有効な抗菌薬を飲めば、1日から2日で熱も痛みもおさまって、人にもうつらなくなりますが、それまでは一種の伝染病ですから、幼稚園や学校は強制的に休んでもらうことになります。その後も、完全に除菌するために、10日間抗生物質を飲んでいただき、その後治ったかどうかの確認のために、もう一度受診していただきます。この炎症を繰り返すようなら、除菌できずに、この菌が扁桃に住み着いている証拠ですから、扁桃を摘出する手術の適応になります。
細菌性扁桃炎:溶連菌以外の細菌でも扁桃炎は起きます。この点で、小児科と耳鼻咽喉科の考え方に少し差があります。教科書的には小児科では、溶連菌以外の扁桃炎はまず抗菌薬は必要ないとされているようです。しかし、実際には他の細菌でも重症化、遷延化することはあり、小児科でも抗菌薬を処方される先生も多いようです。抗菌薬は、溶連菌でも同じですが、ペニシリンが第一選択です。セフェム系も有効です。マクロライド系は現在あまり有効でなく、薬のアレルギーがあって他の薬が使えない場合以外には、選びません。ニューキノロンは有効ですが、ペニシリンやセフェムが無効のときに選ぶ薬でしょう。急性扁桃炎を年に4回もくりかえすようなら、もう体を守る働きは無くなって、細菌の巣になっている可能性が高いので、扁桃摘出術の適応があります。
扁桃病巣感染症:扁桃が細菌の巣になってしまうと、全身にいろいろな病気を起こすこがあります。代表は、(腎炎)IgA腎症です。掌蹠膿泡症も、少なくありません。
プール熱(アデノウィルス):ウィルスによる扁桃炎の代表です。夏に多く、高熱を発しますが、そのわりには元気なことが多いです。典型的な場合は眼球結膜も炎症を起こすため、咽頭結膜熱とも言われます。この病気は、とくに治療を必要としません。脱水にならないように、十分水分をとって、休むだけです。この病気も、迅速キットで検査することができます。なお、小児の扁桃炎では他の原因の場合も同じですが、鼻の奥のアデノイドも同時に腫れますので、鼻づまりも起きます。
伝染性単核症(EBウィルス):このウィルスの初感染では、ときに強い症状が起きます。通常の細菌感染などで見られるような腺窩性扁桃炎(扁桃のくぼみに白い膿が付く)とは違って、扁桃全体が汚い苔のようなものに覆われているように見えることが多いです。頸部のリンパ節が著明に腫れるのと、肝機能に障害が出るのが特徴です。EBウィルスの感染そのものを血液検査で証明するのは時間がかかりますが、異型リンパ球が血液に見られるのも特徴です。小児に多いですが、しばしば思春期にも発症し、このため欧米ではkissing diseaseと呼ばれることがあるそうです。診断を誤ってペニシリンを投与すると、全身に発疹が出てしまうことが多く、注意が必要です。
この病気の肝機能障害は軽いことが多いですが、稀に重症化します。私も勤務医時代にひとりだけですが、そういった患者さんを経験しています。扁桃炎で受診された思春期の男性でしたが、頸部のリンパ節腫脹が強かったため、血液検査をしたところ肝機能障害があったため、入院させて念のため内科の先生にも依頼しました。ところが、急速に悪化して多臓器に障害が起こり、意識もなくなってしまって、どんな治療行っても日に日に悪化していきました。しかし、脾臓が破裂してしまったため、その摘出手術を行ったことをきっかけに、奇跡的に改善がはじまって、数週間の入院で退院することができました。
白血病、再生不良性貧血など:これらの血液の病気のはじめの症状が扁桃炎であることがあります。のどが痛くて内科を受診され、抗生物質などを投与されても治らないため耳鼻咽喉科を受診され、初診時血液検査をして、これらの病気が見つかったという患者さんは、私の経験では白血病が二人、再生不良性貧血がひとりいらっしゃいます。頻度は多くありませんが、扁桃炎、とくに典型的でない(全体に汚い苔がついたような)扁桃炎を見たときには、血液の病気の事も忘れてはなりません。
扁桃周囲膿瘍、喉頭浮腫:これらは扁桃炎がこじれると起こる、こわい病気です。
扁桃肥大:小児の扁桃肥大は、ただ大きいだけで、とくに体に悪影響が無ければ、経過観察とします。たいていは、4~5歳がピークで、成長とともに小さくなってくれます。絶対的に問題となるのは、睡眠時無呼吸がある場合です。小児の無呼吸は、成長にも問題が起こり、しかも口蓋扁桃とアデノイドを取れば、改善しますので、手術の適応になります。アデノイドの肥大は、滲出性中耳炎や副鼻腔炎に悪影響があると考えられますが、それだけで手術するべきかどうかは、意見が分かれます。アデノイドによる長期の鼻閉は、顎に成長に悪影響がありますが、この点からの手術適応も、まだ決まったものがありません。