
曇り空で暑さが凌げるのはいいのですが、突然の激しい雨に驚きますね。
今日は午前午後とも自宅授業で、その後出張指導があり、移動時に雨に降られることなく車の乗り降りができ、ありがたいことに濡れなくてすみました。
今日は、家の中の照明と暖房です。
裸電球、電球の傘、二股ソケット、懐中電灯、ろうそく(停電用)、ランプ、あんどん
火鉢、ひばし、ごとく、きせる、たどん、練炭、炭、こたつ、いろり、あんか、電熱器、ニクロム線、マッチ、薪、湯たんぽ、ストーブなど
「超自分ガイド」より
今のようにエアコンやファンヒータなどない時代です。
子どもの頃は、練炭や火鉢がまだありましたね。
お湯が沸いていたり、練炭の方は鍋がのせてあり煮物が出来上がっていて、お正月にはお餅を焼いたりして結構活躍していましたよ。
ストーブになったのは、いつごろからだろうか?
居間にストーブが入るようになってから、火鉢を自分の部屋に持ち込んで使っていたのは高校生の頃だったと思います。
夜は親子そろって居間のこたつに入り、テレビの時間でしたね。
寒がりの私は、冬は湯たんぽではなく電気あんかを使っていました。
部屋は蛍光灯になっていたような気がしますが、小屋や通路は裸電球で、ソケットの横のスイッチを回して電気をつけていました。
当時は、台風で停電ということもよくありましたから、雨戸を閉めて台風の通り過ぎるをろうそくの火中で過ごしたこともあります。
お風呂もまだ薪の頃だったので、子どもでもマッチを使って火をつけていました。
最近は、台風でも停電になることがないので、ろうそくもマッチも使うことがありませんね。
些細なことでも、あっそんなこともあったよねと思いだすことができたら幸いです。












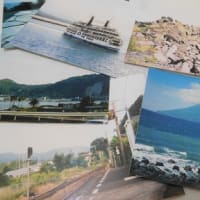





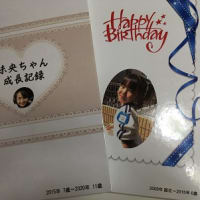

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます