普段、爆速スキャンが心地よいUNIDEN製のスキャナをメインで使っているため、ICOM製の広帯域受信機のIC-R1500の使用頻度がすっかり下がってしまっていた。もったいないので、こいつを再び表舞台に引っ張り出そうと思い、ちょっとした改造をしてみることにした。
その改造は、「10.7MHzIF出力」端子の追加である。
運良く、ネット上を検索すると、サービスマニュアルの英語版があったので、掲載されているブロックダイヤグラムと回路図から、難なく対象の箇所を見つけ出すことが出来た。
対象となるIF10.7MHzの信号を取り出す対象箇所は、IF段でアンプの動作をしているトランジスタでQ60と記載がある2SC4617のEエミッタ端子である。筐体を開けてシールドカバーを外したら真ん中あたりにある。(全体写真の○印)



私の写真の撮り方が上手いため(笑)、対象箇所が大きくハッキリ見えるが、拡大しているから見えるのであって、実際には非常に細かい作業となる。パッと見て、対象となる部品そのものが"見たいのに距離を取らないととてもぼやけて見えない!"と思った人は、挑戦しないほうが無難だろう。何せ、ここをやっつけてしまうと、受信が出来なくなってしまう重要な場所だからだ。(拡大写真の矢印部分がE極)

なお、対象の端子の部分は強度的にもかなり弱いので、ラッピングワイヤや網線を数本抜いてよじったものなんかを使って電極の引き出し線を取付けてから、必要な配線を施すのが良いだろう。また、基板が入っているシールドケースには、IF出力ケーブルを引き出すために使える切り欠き部分があらかじめ存在している。(全体写真を参照)
ちなみに、R1500もR2500も、制御する部分がシングルかデュアルかの差だけで、入っている基板そのものは同じだ。
回路的にはIC-PCR100やIC-PCR1000でも、やる気になれば同じような改造が可能だろう。
信号を取り出したエミッタ端子の電圧は回路図上だと0.25Vぐらい掛かっているので、0.25V程度の電圧が確認出来たら接続は成功である。
自分は何とか肉眼で目を凝らして半田付けが出来たが、年齢相応の"凸レンズ"のお世話になる日はそう遠くない話。
で、今さらIF10.7MHz端子なんて取り出して何すんの?という疑問を抱く方がいるだろうが、最近、ザーザー言うヤツをどうにかしてくれる便利な箱が出てきたもんで、イタズラしてみたくなった訳でした。使えると良いのだけど。
KeyWords
ICOM IC-PCR1500 IC-R1500 IC-PCR2500 IC-R2500 IF TAP OUT 10.7MHz 45.05MHz ARD300
-----
2014/9/22 追記
某所よりお借りした AOR ARD300のテスト機を接続しての受信テストは良好!
デジ簡のグループコードなんかも表示してくれると便利なんだけどな。
その改造は、「10.7MHzIF出力」端子の追加である。
運良く、ネット上を検索すると、サービスマニュアルの英語版があったので、掲載されているブロックダイヤグラムと回路図から、難なく対象の箇所を見つけ出すことが出来た。
対象となるIF10.7MHzの信号を取り出す対象箇所は、IF段でアンプの動作をしているトランジスタでQ60と記載がある2SC4617のEエミッタ端子である。筐体を開けてシールドカバーを外したら真ん中あたりにある。(全体写真の○印)



私の写真の撮り方が上手いため(笑)、対象箇所が大きくハッキリ見えるが、拡大しているから見えるのであって、実際には非常に細かい作業となる。パッと見て、対象となる部品そのものが"見たいのに距離を取らないととてもぼやけて見えない!"と思った人は、挑戦しないほうが無難だろう。何せ、ここをやっつけてしまうと、受信が出来なくなってしまう重要な場所だからだ。(拡大写真の矢印部分がE極)

なお、対象の端子の部分は強度的にもかなり弱いので、ラッピングワイヤや網線を数本抜いてよじったものなんかを使って電極の引き出し線を取付けてから、必要な配線を施すのが良いだろう。また、基板が入っているシールドケースには、IF出力ケーブルを引き出すために使える切り欠き部分があらかじめ存在している。(全体写真を参照)
ちなみに、R1500もR2500も、制御する部分がシングルかデュアルかの差だけで、入っている基板そのものは同じだ。
回路的にはIC-PCR100やIC-PCR1000でも、やる気になれば同じような改造が可能だろう。
信号を取り出したエミッタ端子の電圧は回路図上だと0.25Vぐらい掛かっているので、0.25V程度の電圧が確認出来たら接続は成功である。
自分は何とか肉眼で目を凝らして半田付けが出来たが、年齢相応の"凸レンズ"のお世話になる日はそう遠くない話。
で、今さらIF10.7MHz端子なんて取り出して何すんの?という疑問を抱く方がいるだろうが、最近、ザーザー言うヤツをどうにかしてくれる便利な箱が出てきたもんで、イタズラしてみたくなった訳でした。使えると良いのだけど。
KeyWords
ICOM IC-PCR1500 IC-R1500 IC-PCR2500 IC-R2500 IF TAP OUT 10.7MHz 45.05MHz ARD300
-----
2014/9/22 追記
某所よりお借りした AOR ARD300のテスト機を接続しての受信テストは良好!
デジ簡のグループコードなんかも表示してくれると便利なんだけどな。










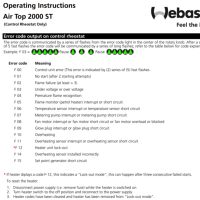





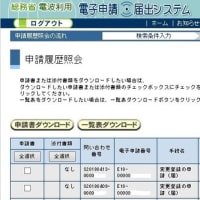
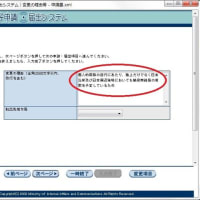
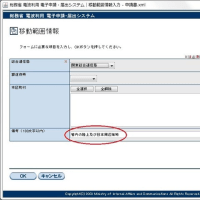
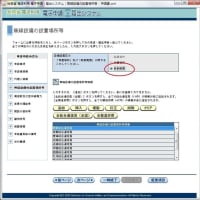
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます