
今日は、前々回で予告した 珍品「BLUE FIRE」 のご紹介。

ゴメンナサイ! どうしても写真を縦にできませんでした。 クヤシイ!
このストーブ、1962年発刊の「暮しの手帖 67号」に掲載された
特集 “石油ストーブをテストする” で取り上げられた全35台のうちの1台。
暮しの手帖の伝説の編集者、花森安治さんを怒らせた、いわくつきの1台でもあります。
暮しの手帖 67号から、その一文を引用しますと・・・・
『よそでながいことかかって苦労してつみ上げたものを、そっくりいただくのではなく、
その性能のよさが、日本人の独自の技術が花ひらいたものであってほしい、
心からそう祈りたいのである』
あぁ、怒ってる怒ってる。
まず、名前が胡散臭い。
明らかに 『BLUE FLAME』 を意識。
次に、デザインがパクリだらけ。
細かなところは違うけれど、ほとんどそっくり。
実はもっと筋金入りの “100%パクリストーブ” があるらしいけれど、
私はまだ出会ったことが無い。
燃焼系の部品たちは、ほぼアラジンと同じ。

でも芯の装着方法は、パーフェクション方式。

使用する芯は、アラジン#15用の芯とまったく同じ仕様で、
ボッチを穴にはめて安定させる方法。

全くパクっていたり、ちょっと変えてあったり、
開発者の心の迷いが、伝わってきます。
同じく、ちょっとした “ためらい” が感じられるのが、この灯油残量計。

アラジン#15のそれと一瞬同じに見えますが、
あの楕円形ではなく、これは数字の “ゼロ” 。
灯油が入っていくと、1、2、3・・・と数字が増えていきます。
まったく同じは、気が引けたんだろうなぁ。
『BLUE FIRE』 というからには、炎は本当に青いんだろうな? と火をつけてみた。

本当に青かった。
“におい” もほとんどせず、使い勝手は悪くなさそう。
また1台、コレクションが増えました。
冬の骨董市で、暖を取るために持って行きたいなぁ。














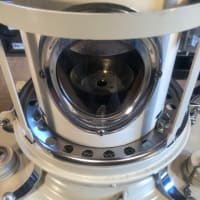





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます