報道関係者各位
山谷えり子国家公安委員長辞任要求抗議実施のお知らせ
差別反対東京アクション
男組
「差別反対東京アクション」は、東京都で行われているヘイトスピーチデモを行政の責任でやめさせるよう、2013年10月14日より毎週月曜日19:00から約1時間、東京都庁前で「差別反対都庁前アピール」を実施しています。「男組」は、「在日特権を許さない市民の会(在特会)」を中心とした差別主義者が行う街頭デモに対して抗議行動を行っています。
本年8月7日に舛添東京都知事が安倍首相と面会し「ヘイトスピーチ(差別的憎悪表現)に対し、「人権に対する挑戦。2020年五輪を控えた東京でまかり通るのは恥ずかしい」として法規制をするよう求め」ました(朝日新聞 8月7日付け)。
これを受けて、8月28日には自民党内においてヘイトスピーチ対策等に関する検討プロジェクトチームが開催され、国レベルでのヘイトスピーチ対策の検討が始まりました。
8月29日には国際人種差別撤廃委員会から日本国に対する勧告が出されました。その中でヘイトスピーチへの対策として、以下5点について適切な方策を取るよう、日本国政府に勧告しています。(勧告全文の翻訳:http://ta4ad.net/wp/?page_id=453)
(a) 集会の場における人種差別的暴力や憎悪の煽動、また憎悪や人種差別の表明について毅然とした対処を実施する
(b) インターネットを含むメディアにおけるヘイトスピーチの根絶のため適切な対策を講じる
(c) 調査を行い、適切な場合には、そのような言動の責任の所在する組織及び個人を起訴する
(d) ヘイトスピーチの発信及び憎悪への煽動を行う公人及び政治家について、適切な制裁措置を実行する
(e) 人種差別的ヘイトスピーチの根本的原因についての取り組みを行い、人種差別に繋がる偏見を根絶し、国家・人種・民族グループ間の相互理解や寛容、友愛の情を育むための指導・教育・文化・情報発信における方策の強化を行う。
このように、ヘイトスピーチへの行政としての対応が求められ、また検討が始まっている中で行われた安倍内閣改造人事において、国家公安委員長に山谷えり子氏が就任しました。しかし就任直後からTwitterを中心に、全国でヘイトスピーチデモを行っている在特会メンバーと山谷氏が一緒に映った記念写真の存在が知れ渡り、山谷氏と在特会の関係についての非難が巻き起こっています。
9月25日に外国人特派員協会で行われた山谷氏の記者会見では、質問時間の大部分が山谷氏と在特会との関係、あるいは差別煽動団体である在特会に対する見解を問う質問で占められましたが、山谷氏は「一般論として、色々な組織についてコメントすることは適切ではないと考えております」などと回答し、一貫として質問者への回答を拒否しました。とりわけ在特会がその名称にも使用している「在日特権」なる虚妄について問われた際には、「あの在特会が言っている、「在日特権」というのが、詳しくは何を示すのか。在日特権という定義というものはそれは、いろいろなグループがいろいろなことをカギカッコで言っているんだと思いますが、法律やいろいろなルールに基づいて特別な権利があるというのは、それはそれで、私が答えるべきことではないと思います。」と答え、「在日特権」の存在を認めているかのような回答をしています。
私たち「差別反対東京アクション」「男組」は、日本社会からヘイトスピーチを無くしたい、差別を許さない社会を作りたいと願う市民の集まりです。そして私たちの行動は、日本のすべての市民が安心して安全に暮らす事ができる社会を作る事でもあります。
国家公安委員会のWebページには国家公安委員会の任務として、警察の仕事のうち「国全体の安全に関係するものや、国が自らの判断と責任において行うべきもの」と明記されています。
ヘイトスピーチデモが全く規制されず野放しにされ、被差別当事者への暴力が行われ、またそれに反対する市民が警察による規制によって反対行動そのものを阻止されている今は、日本が戦争に向かってしまった過去の歴史を振り返れば明白なように、まさしく「国全体の安全」が脅かされている事態であると言えます。
私たちは、在特会との関係について説明を拒否し、また在特会の主義主張を否定する事ができない山谷えり子氏が、市民の安全を守るべき警察組織のトップである国家公安委員長を勤める事に対して断固反対します。
私たちはTwitterで呼びかけられた以下の抗議行動を支持し、全力で支援し、参加します。
@fancy_karate
[拡散]9/29(月)19:30~ 山谷えり子国家公安委員長辞任要求抗議@総務省(合同庁舎第2号館)前 在特会と繋がりがあるにも拘らず在特会も在日特権も否定もしない国家公安委員長、まずいと思う方はご参加ください。大規模に抗議しましょう。
各社様にはぜひこの抗議行動をご取材いただき、日本からヘイトスピーチを無くす為に広くお伝えいただくよう、お願い申し上げます










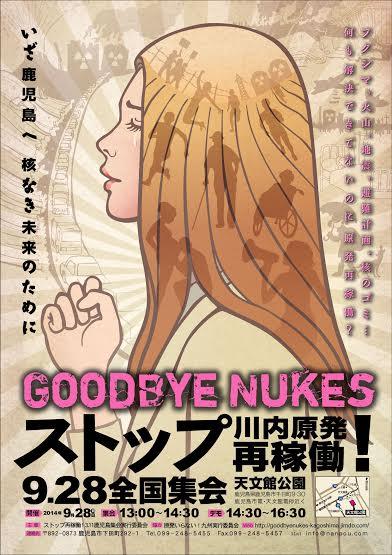


 保科郷雄・丸森町長
保科郷雄・丸森町長 May_Roma
May_Roma

 K10048801311_1409252136_1409252205.mp4
K10048801311_1409252136_1409252205.mp4