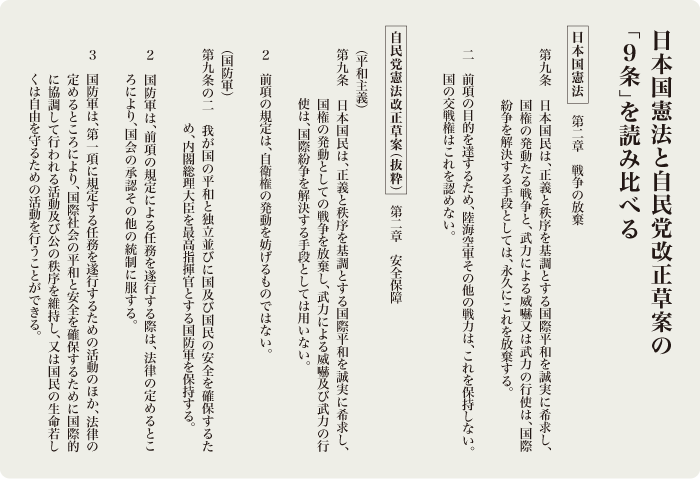シリーズ「憲法特集」では、憲法と出会い直し、考え直すためのきっかけを示していきたい。
第1回は、若き憲法学者との対話を通して、憲法と民主主義の関わり、私たちが市民として成熟していくためのヒントを学ぶ。
構成:佐田尾宏樹/撮影:高橋定敬
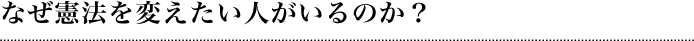
後藤「特に震災以降なんですが、誰かと政治について語り合ったり、デモや集会っていうのに参加するたびに、〝民主主義ってうまく機能してるんだろうか?〟〝自分たちは市民として民主主義や政治に参加できているんだろうか?〟っていう疑問を持つことが増えて。僕たちは長い間、放棄っていうわけではないけど、民主主義に対して無責任というか、当事者意識が薄かったんじゃないかという想いがあるんです。そんななか、この数年、憲法改正の機運みたいなものが高まってきて、すごく嫌な予感がして」
木村「改憲の論議はどうご覧になっていたんですか?」
後藤「僕は、自民党の改憲草案(※1)を読んだときにゾッとしたんです。基本的人権というものに対する考え方ひとつをとっても、このままの流れで改憲が進んだら、日本はとんでもない国になるんじゃないかって。でも、それに抗う準備ができていない歯がゆさがありました。そこで今、憲法をもう一度読み直すこと、勉強し直すことが必要なんじゃないかと思ったんです」
木村「なるほど」
後藤「それで、木村さんが著書のなかで、憲法っていうのは単に日本の最高法規たる条文としての性格だけじゃなくて、〝外交宣言〟としての意味を持つということを書かれているじゃないですか」
木村「そうですね。たとえば憲法9条っていうのは、諸外国に、日本が戦争を放棄し平和を希求する国だということをアピールする効果があるし、逆に海外も、そういう目で日本を眺める意味があると思います」
後藤「それって本当に大事なことだと思って。憲法を改正するっていうことは、日本の問題だけじゃなくて、外交問題に発展しかねないレベルの話だということですよね。なんというか、そういう憲法に書かれている言葉以外の影響力について僕らはもっと意識的でなければいけないし、理解を深めるためのリテラシーを身に付ける必要があるなと。そういった作業を通して、僕らはもっと市民として成熟していかなきゃいけないんじゃないかって、そういうふうに思って今日はお話をうかがいにきました」
木村「わかりました。ではまず始めに、後藤さんのように〝自分は民主主義に参加できているんだろうか?〟っていう疑問、ある種の無力感を抱いてしまうのはなぜなのかっていうところから話を始められたらと。それが改憲の論議っていうものとも繋がってくるはずなので」
後藤「はい」

木村「まず、民主主義への参加という意味では、まさに選挙というのがわかりやすい参加の形ですが、果たして現在、市民の側が自分の投票権をうまく使えるような選挙制度になっているかどうかというのを考えるのが大事だと思うんですね。おそらく、多くの日本人はそう感じていないはずです。それはなぜかといったら、現在の制度が、自分の好みを素直に投票行動に反映できない仕組みになっているからでしょう」
後藤「そうですね。確かに、マイノリティの意見って今の選挙制度では反映されにくいですからね」
木村「現行の制度だと、大政党の公認が取れるかどうかで勝負が8割方決まる仕組みになってますからね。市民が大政党の幹部とは違うことを考えているとき、政治家がそれに耳を傾けるという選挙上のインセンティブはないと思います」
後藤「そうなんですよね。それに対してはもう、不満というよりも〝なぜこんなやり方が制度的に許容されているのか?〟っていう疑問がありますね。国民の3分の1ぐらいしか支持していない政党が、国会の議席の過半数を取ってしまうっていう状況は、果たしてフェアなんだろうかっていう」
木村「すごくいびつですよね」
後藤「もっというと、民主主義=多数決っていうルールがありますけど、それって本当に正しいのかなって。僕はやっぱり、まあ当然ですけど、みんなでちゃんと話し合って合意形成するのが民主主義なんじゃないかと思うんです。最後の決選投票に限っては多数決で、みたいな局面はあっていいのかもしれないけど、そこまでのプロセスがむしろ大事なんじゃないかなぁと」
木村「その通りだと思いますね」
後藤「でも、現在の空気的には、とにかく早く決めたいし早く変えたいし早く動きたいから、そのためには多数決がベストなんだっていう論理が重要視されてきてるというか、〝何か変えたいんならとりあえず多数派になりなよ〟みたいな、そういうマインドセットが蔓延しているように感じるんですよね」
木村「私は、それがやっぱり改憲の機運の高まりっていうものにも端的に現われてるんじゃないかと思うんですよね。つまり、現状への閉塞感みたいなものから、とにかく何かを変えるっていう行為自体が人気を獲得しているような部分があるんじゃないかと」

後藤「そうか……」
木村「本来は、現状のどこに問題があって、何のために変えるのか、どう変えていくのかを明確にしなくてはいけないのに、〝内容はどうでもいいから、とにかく憲法を変えよう〟とでも言わんばかりの〝改革派〟が、中身を問われずに支持されているような状況がある」
後藤「確かに〝変える〟という言葉の持つ強さはありますからね」
木村「こと憲法については、これまで長い間一度も手を加えられてこなかったものなので、〝そこに日本の停滞の原因があるんじゃないか?〟という感覚を持ちやすいという部分もあるでしょう」
後藤「僕がすごく危険だなって思ったのは、まさにそこで。改憲ということになるとどうしても情緒が先に立ち上がるじゃないですか。〝アメリカに押し付けられた憲法なんだから、日本人が自ら編んだものに書き換えて当然だ!〟っていう考え方だったり、それとは逆に、盲目的な〝断固護憲!〟っていう考え方だったり。それがすごく感情的であるがゆえに、力を持ってしまうのは怖いなぁと」
木村「これは私の師匠の石川健治先生が語られていたことなんですが、日本というのは、生まれが正しいかどうか、国の成り立ちというものが正統に受け継がれてきたかということに、非常にこだわる社会だというんですね」
後藤「そうなんですか」
木村「たとえばドイツにしてもフランスにしても、歴史的に、しょっちゅう王朝が変わったり皇帝が入れ替わったりしましたから、正統に受け継がれてきたかどうかということはあまり気にしない。一方で、『万世一系』という言葉がある日本には、それこそ『三種の神器』をちゃんと継承してきたのかというような感情が根強くあると。だからこそ、戦後の混乱の中でアメリカに押し付けられたものだという、生まれが怪しいものに対して強いアレルギーを持ってしまう社会だというのはあるんじゃないでしょうか」
後藤「なるほど。でも、そんな理由で本当に変えられてしまっていいんでしょうか? 改憲もそうだし、重要な法案や政策が動くときって、パッションとか情緒とか、いわゆるマグマのようなもののエネルギーが強いときのほうが、間違いが起きやすい気がするんです。しかもそういった場合の過ちって……」
木村「取り返しがつかない」
後藤「そうなんですよ」
木村「実際、ひとつの失敗だけで本当にひどい状況になってる国家ってたくさんありますからね」
後藤「日本も例外ではなくて、やっぱり第二次世界大戦の敗戦というのは半端ではなかったわけで。もしかしたらこの国の体制がほとんど今の自分たちの暮らしに繋がらないほどにまで変えられてしまっていた可能性もあったぐらいの」
木村「完膚なきまでの敗戦でしたね」
後藤「だからこそ、改憲派に対して不思議に思うのは、たとえば尖閣諸島など で紛争が起きて―これは過去の紛争の歴史からも明らかでしょうけど―〝どっちが先に手を出したのか〟っていうことが必ず問われますよね。そのときに、憲法9条それ自体が〝私たちには憲法9条があるので、先制攻撃は絶対にできません〟ってロジカルに反論する根拠になるものだと思うんです。それを改憲して手放すことによって外交上のリスクが高まるのは、冷静に考えたらすぐわかるのに、なぜ推し進めようとするのか……」
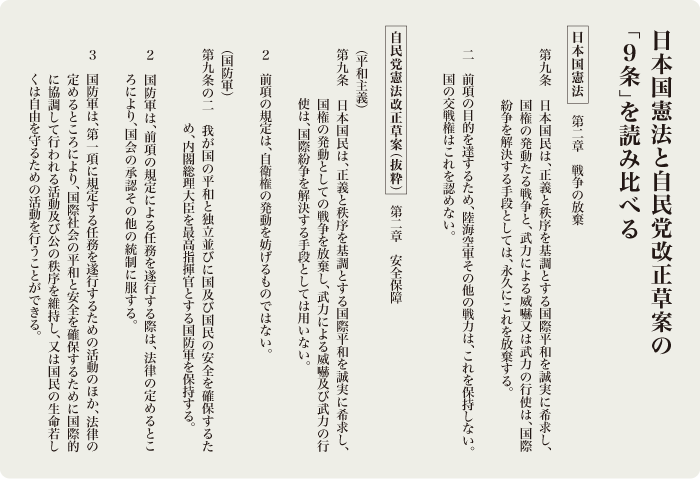
木村「そこはやっぱり〝変える〟ということ、改革派であるということのメンツがかかっているからだと思いますね」
後藤「メンツですか……。でもそれも結局は情緒ですよね。しかもこう、変えさえすればいいというか、変えたその先が想定されているように思えないんです」
木村「改憲そのものが目的化しちゃってるということですよね」
後藤「それによって最高法規の憲法が書き換えられてしまうことに、僕は得体の知れない怖さを感じます」
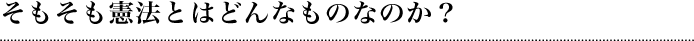
後藤「ここでちょっと聞きたいんですが、木村さんは改憲っていうものの必要性についてどう考えてらっしゃいますか?」
木村「私は、今の段階ですぐに何かをいじる必要があるとはまったく思いません。国連と9条の関係を整理する条文をつくったほうがいいかなと思ってはいますが、それもじっくり議論しながら進めていくべきだと考えているので」
後藤「そうですか」
木村「ただ、改憲が具体的にどういう作業なのかっていう点について知っておくのは、とても意味があることだと思います。……と、その話に移る前に、〝そもそも憲法とはどういうものなのか〟っていう、根っこの部分について確認しておきたいんですね」
後藤「ぜひお願いします」
木村「たとえば後藤さんが創作をするときも、発表する以上は何かが新しくないといけないと思うのですが、ただ新しいだけでは意味がないと思うんです」
後藤「そうですね」
木村「前提として、クラシカルなものというか、大事に受け継いでいかなきゃいけないものがあったうえでの創造だと思うんですね。後藤さんは、どんなことを前提にしていらっしゃいますか?」
後藤「音楽をつくるときですか」
木村「ええ」

後藤「それを言語化するのはとても難しいんですけど、僕はこう、川が一本流れていて、その川下にいればいいと思っているんです。さかのぼっていくと源流があって、そこに接続できているかどうかが大事な気がしますね」
木村「その源流というのは、ロックミュージックの先人たちということ?」
後藤「そうですね。でも、同時にその〝接続すべきものは何か?〟という問いも毎度あります。たとえばですが、土偶を目にして美しさを感じたとき、〝これはいったい何に捧げられた美しさなんだろう?〟ということを思いますよね。たぶん時代や意匠が変わっても、宗教的なものか内省的なものなのかわからないけど、芸術や表現って、ある種の美しさに捧げられていて、僕はそういうとこに惹かれるし、そこに手を触れていたい。そういうブラックボックスのようなものに手を突っ込んで、なんらかのイメージを取り出して、それを次の世代にパスし続けている、そんな作業をやってるんだって信じています」
木村「その感覚、よくわかりますね。僕もまさに憲法をつくるってそういうことなんではないかと思っているんです」
後藤「そうなんですか?」
木村「ええ。憲法は最高法規であると同時に、国の長期的な理想や理念を掲げるものです。日本をどういう国にしたいのか、あるいは、世界に対してどんな貢献ができるのかを考えて、まず日本人にとっての美しさや良心のようなものを探し、それをきちんと落とし込んだものである必要があるわけです。これがまさにクラシカルなものに手を突っ込んで持ってくるという感覚ですね。なので、起草にあたっては、その理想を目指すにはどうしたらいいか、うまく条文に落とし込むためにはどうしたらいいかを考えなくてはいけないし、そういった手順で作業を進めていかなくてはいけないんです」
後藤「なるほど」
木村「実際、現行の日本国憲法も、原案はGHQによるものですが、それを翻訳して条文にするプロセスにおいて、日本が民主主義を実現するためにどのような要素を盛り込み、どんな言葉で表現したらいいのか、繰り返し折衝や議論が行われています(※2)。私が自民党の改憲草案にどうしても共感できないのは、そういう崇高なプロセスを決定的に欠いているからだと思うんです。その結果、非常にグロテスクなものができあがってしまう。もっというと、憲法を変えるというのは、具体的には〝条文を書き換える〟という作業になります。それは非常に技術的な問題なので、トレーニングを積んでいない人が条文を作ると、楽譜の書き方を知らない人が楽譜を書いているような、〝あなたが歌ってる曲とは音符がズレてますよ〟っていう状況になりがちなんです」
後藤「僕が自民党の改憲案を読んだときに感じた怖さって、今の話と繋がってくると思うんです。あの草案には、それを誰がどう読むかによって、どのようにも解釈できる言葉が多く含まれているように感じたんですね。例えば、現行憲法の〝公共の福祉〟という言葉が、わかりにくいからっていう理由で〝公益及び公の秩序〟という言葉に書き換えられていますけど、〝公益〟とか〝秩序〟ってすごく定義することが難しいし、その時々によって形が変わる可能性があるものだと思うんです。決して一義的なものじゃないというか」
木村「その通りだと思いますね」
後藤「僕は、条文の中にそういう曖昧な表現や言葉があるのはどうなんだろうと思うんです。条文の中の言葉の曖昧さを後退させると、ある政権はこう読んだけど、別の政権が立ち上がった時にまったく違う読み方をされてしまう、まったく違うふうに読めてしまう可能性が増してしまうわけですよね?」
木村「句読点がひとつ入るかどうかで、意味がまったく変わってくる可能性だってありますからね」
後藤「僕は、悪い方向に〝読めてしまう〟可能性があるというのは本当に危険だと思うんです。草案に出てきた〝緊急事態〟っていう言葉にしても、何を想定しているのか全然わからないんですが、〝緊急事態=コレとコレ〟っていうふうに具体的に示されないと、解釈次第でなんだって緊急事態にされて、最悪の場合、恣意的な武力行使や人権の抑圧がなされてしまう可能性があるわけですよね。だから条文は〝これ以外の読み方はあり得ない!〟と言えるような、権力が濫用されないものであることが大事だし、そうでないものを受け入れてはいけないと思うんです」

木村「本当にそうですね。言葉で国家の統治をコントロールをするという仕組みを選んだ以上、条文に盛り込む言葉に対する意識っていうのは徹底されなければならないと思います。そして、その言葉に必然性を持たせるのが、先ほども言った、国としての長期的な理想や理念だと思うんです」
後藤「なるほど」
木村「それで、今の話は集団的自衛権の議論とも関係があるように思うんですね。あの議論が、たとえば〝国際平和にもっと貢献するために、侵略を受けている外国の人を助けたい〟というような大きな理想があって、そのために集団的自衛権というオプションが必要なんだという論調になっていればまだマシだったんですが、そうはなっていなかった。むしろ〝中国が脅威だから武力を保持したい〟とか〝中東情勢が不安だから、武力を行使できる機会の幅を広げたい〟というような非常にエゴイスティックな論調になっていたと思います」
後藤「自衛隊はセコムじゃないんだぞっていう話ですよね」
木村「ですから、議論の盛り上がりとは裏腹に〝なんの話をしているのかわからない〟っていう意見をよく聞いたんですが、それもある意味当然なんです。結局、集団的自衛権っていうのは、〝世界を平和にするにはどうしたらいいのか?〟という課題に対するひとつの答え方なんですよね。なので〝攻められた国があったときに周辺国と一緒に対応できたほうがいいでしょう〟とか〝常に国連が正しいとは限らないんだから、国連の判断ではなく自主的に行動できる可能性を検討したい〟とか、集団的自衛権を行使するにあたってのコンセプトがセットになっていなければならないのに、そういう話がなかった。そりゃあ、モヤッとした気持ちを抱いた人がいて当然です」
後藤「結局、平行線のまま時間切れになったという印象ですね」
木村「そうなんです。だから、改憲にあたっても、まず〝なぜ変えなければならないのか?〟っていうコンセプトを一番に示さなければならないんです」
後藤「いきなり〝変えるか変えないか〟〝是か非か〟っていう地点から議論を始めようとするから、おかしな議論になってしまうってことですよね」
木村「そういうことです」

木村「それでは、コンセプトを示すことの重要性を踏まえたうえで、ここからは憲法や民主主義をいかにうまく機能させていけばいいのかっていう、アイデアについての話をしたいと思います」
後藤「はい」
木村「法学には昔から、選挙権っていうのは〝権利〟か〝公務〟かという議論があるんです。後藤さん、〝選挙権公務説〟という言葉はご存じですか?」
後藤「初めて聞く言葉です」
木村「じゃあ、説明しますね。選挙権は憲法で保証されている国民の権利のひとつなんですが、選挙権だけ、他の権利とはちょっと性格が違うんです。たとえば表現の自由、営業の自由、裁判を受ける権利っていうのは、基本的に個人のための権利ですよね。個人がやりたいことを自由にやる権利として与えられている。でも、選挙権に限ってそうではないんです。つまり、個人の一票によって政治家を選ぶっていう強い権力作用があるので、そこには個人的な範疇を超えた、仕事、公務としての意味合いが含まれてくるはずだと、そういう理論です」
後藤「よくわかりました」
木村「この理論を展開させていくと、今度は、なんらかの理由で選挙権が制限されたときに損害賠償を請求できるのかという論点が浮上するんです。表現の自由や営業の自由が侵害された場合であれば、損害をこうむった個人に対して、そのぶんだけ賠償しろというのは理屈として通りますよね。しかし、なんらかの理由で選挙権を行使できなかった場合、〝そこで損するのは誰か?〟という問題が出てくる。もっと言うと、首相である人が権限を行使できなかった場合、不利益を被るのは首相個人ではなく国民全体になるはずですよね。だから、首相個人が賠償金を受け取ることはできないんです」
後藤「なるほど」
木村「それと同じ理屈で、選挙権を行使できなかった国民が果たして賠償金を取れるのかというような話にもなってくるんですが……私は選挙権に公務性を強く読むので、そういう考え方には与しないとうか、ちょっとおかしいんじゃないかと思っていて。今、選挙権っていうとすごく権利性が強いもの、自分が損をしないために投票する資格が認められているものなんだという、非常にニヒリスティックな感覚が強いなと思うんです」
後藤「そうかもしれないですね」
木村「一票の格差の是正論というのがありますが、あれも人口の少ない地域が不相応に多くの議員を出していて、都市部の人間が損をしてるんじゃないかっていう論調で話が進んでいる気がするんですね。〝俺の一票に重みがない!〟と」
後藤「それが投票率の低さにもつながってきているんでしょうね。〝どうせ何も変わらない〟っていう、端から諦めてる感じというか」
木村「それはあると思いますね」
後藤「でも、それって言い換えると、選挙を消費者マインドで捉えてるっていうことなんじゃないですか。つまり、自分はちゃんと一票投じるんだから、そのぶん何かしらの見返りがあって当然だろうっていう」
木村「まさにそうなんですよ。でも、憲法とか民主主義をうまく駆動させるためには、消費者マインドで行動してはいけない領域があるんです。むしろ公務性をこそ強く持つべき領域があるんだって、市民が思ってなきゃいけないんですよ」
後藤「なるほど」
木村「消費者マインドは、どうあっても個人的な利得の域を出ませんから」
後藤「今の話でいうと、僕、昔から田舎の国政選挙に関してずっと不思議に思ってることがあって。言い方は悪いですけど、田舎の土建屋の親玉みたいなオッサンが当選して、地元代表として国政に行くっていう状況が各地で起こってるわけですけど、要するに彼らが選ばれているのは、どれだけいっぱい地元にカネを運んでこれるか、利権で繋がってる企業にどれだけ公共事業を引っ張ってこれるかみたいな、そんな理由だけで選ばれてるんじゃないかと思って。その結果、田舎には不相応に巨大な土木事務所が建つようなことが起こるっていう」
木村「なるほど」
後藤「そういうのって、もう消費者マインドの成れの果てというか……誰かを選んだはいいけど、本当に地元全体の利益になってるのかなって思うんです」
木村「本来、選挙ってそういうものじゃない気がすると」
後藤「そうなんです」
木村「結局、国や地域をつくるのは連帯なので、選挙っていうのはその連帯を生むための手続きだという感覚がないとダメですよね。じゃないと、いつまでたっても消費者マインドから抜け出せない」
後藤「どうやって乗り越えたらいいんでしょうか」
木村「やっぱりね、最近の日本の政治や言論状況なんかを見ていても、いろんなものに期待しすぎている感じがします。〝このチームでやっていくしかないんだ〟っていう前提で物事を考えなきゃダメだと思うんです。日本には人口が1億3千万人いるけど、無限にいるわけではない。あるポストを決めるにも、限られたなかから選ぶしかないんだと。だからこそ厳しく見る目と、自分が支えて盛り立てなきゃいけないんだという感覚を持てるわけで。消費者マインドっていうのはまさに、供給者の側に無限を要求している感じがするんですよね」

後藤「その点、選挙が公務の性格を持つことを認識するだけでも違いますか?」
木村「と、思いますね。そのうえで選挙についての知識を改めて身に付けていくしかないと考えます。先日、この方も僕の師匠なのですが、長谷部恭男先生と日本の選挙制度について話す機会があったんです。で、先生が言うには、やはり今の選挙制度はちょっと極端だろうと」
後藤「はい」
木村「それで、彼がよく参照するアイデアが、フランスで採用されている『小選挙区2回投票制』という制度なんです。小選挙区なので各選挙区でひとりしか当選できません。ただし、1回目の投票だけで当選するには過半数の得票が必要です。1回目の投票で過半数を獲得した候補がいない場合は、一定の得票率を得た候補だけが立候補できる、2回目の投票を行うっていうシステムなんですね」
後藤「おもしろいですね」
木村「この制度下で、ある選挙区に自民党、民主党、共産党の3候補がいるとします。そして仮に共産党の熱烈な支持者がいたと。当然その人は、1回目の投票では共産党の候補に入れるわけですよね。でも、結果的に共産党の候補が規定の投票率を獲得できなかった。すると2回目の投票は、しょうがないから自民か民主、どっちかに入れなきゃいけない」
後藤「ベターなほうへ」
木村「そう、ベターなほうに。この方法がユニークなのは、1回目と2回目で、投票者が全然違うことを求められるという意味合いがあるんです。1回目はとにかくまず〝あなたの気持ちを述べなさい〟っていうものなので、これは負けるとわかっている候補に投票することにもすごく意味があるんです。〝予想以上に共産党が支持を集めたぞ!〟っていうことになったら、仮にその人が2回目の投票に行かなくても影響力を持つので」
後藤「少なくとも〝世論としてはこんな意識が高まってるぞ〟っていう表明になるわけですもんね」
木村「そういうことです。しかもこの状況で、自民と民主がどう反応するかといえば、2回目で勝つためには結局そうしたマイノリティの取りこぼしを拾うための活動をしなきゃいけないので、単なる二大政党制ではなくて、できるだけ多くの意見を反映できるような形でグループを作るということが起きるんです」
後藤「それこそ、合意形成の過程に市民がコミットできる可能性が出てくるっていうことですよね?」
木村「そういうことです。そして、各政党の動きを踏まえて2回目の投票行動を考えられると。私は、この制度にはふたつの利点があると思います。ひとつはやはり今おっしゃったように、多くの人が政治に関われるようになるという点。ふたつめは、政治というのはベターを選ぶ作業なんだっていうことが実感できるという点です」
後藤「なるほど。身をもってそれを学ぶ機会になると」
木村「この制度を通して、選挙のダイナミズムをより感じることができると言ってもいいかもしれません」
後藤「確かに、現在の選挙制度の手応えのなさ、投票前から結果がわかってる感っていうのは改善されますよね。結果がすべてという現状の選挙より、合意形成の過程で少数派の意見が聞き入れられる達成感みたいなものもあるだろうし」

木村「そうなんです。日本も新たな選挙制度として検討する価値は十分にあると思います。でも、この制度の存在を知らないと、こういう提案もできないわけで。やはり、民主主義を駆動させていくためには、政治決定を創造していく過程に自分が関わっていることを意識できるかどうかが大事だと思うんですね」
後藤「当事者意識ですね」
木村「そのためには、選挙制度なんかも含めて、まだまだいろんなアイデアがあるんだよという感覚を持つことにすごく意味がある。やっぱり、現行の制度しかないって思っちゃうとすごく閉塞感があるし、その先にあるのは、その制度のなかでどれだけ自分が得をできるかっていう消費者マインドの横行ですから」
後藤「だからこそ、みんな、自分の投票行為が権利なのか公務なのかっていうことを意識しながら、ちゃんと引き裂かれるっていうか、ちゃんと逡巡することを避けちゃいけないわけですよね。そうした経験を通して、選挙や民主主義に関わるための最善のあり方を、自分なりに模索していくっていうか」
木村「消費者マインドに抵抗できるのは、個々人のクリエイティブですよね」
後藤「本当にそうですね」
木村「ですから、民主主義が今よりちょっとでも成熟した将来、再び改憲の議論が出てきたときに備えて、市民も政治家も〝まずは世界平和が大事だよね〟とか〝みんなが介護に困らない社会をつくりたい〟とか、なんでもいいので〝自分はこういうことがやりたい〟っていう発言をしていくべきだと思います。その理想があったうえで、実現するためにはどうしたらいいかという技術の話に向かう。今はまだその手順がうまくいってないけど、まずは理想を掲げるっていうことを、ニヒリズムにとどめることなく、投げ出さないことが大切だと思いますね」
憲法を理解するためのブックガイド
木村草太『テレビが伝えない憲法の話』
(PHP新書)
普段、メディアが教えてくれない「憲法について考えることの楽しさ」を感じながらリテラシーを高めることができる、入門書に最適な1冊。日本国憲法が持っている〝3つの顔〟や制定時の物語から、9条改正論議のポイント、憲法と人権の関係性についての分析まで、最新の社会情勢を踏まえながら、硬軟織り交ぜたテーマで綴られる。
長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』
(ちくま新書)
木村草太さん、推薦の1冊。日本国憲法の根っこにある〝立憲主義〟にスポットを当てながら、情緒論に傾きがちな憲法9条改正について冷静に考えるためのヒントを示してくれる。なぜ民主主義が大事なのか、なぜ個人は尊重されるべきなのか、といった憲法と関わりの深い〝そもそも論〟をじっくりと見つめ直したい人にすすめたい。
(2014.12.2)