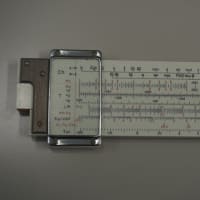鄭州大学TP夏期研修の高分子化学実験を担当しました。
「プラスチックを区別する実験」
2限×2回で実施
担当職員 2名
TA: 2名
7月19日(木)1限8:50~10:20 2限10:30~12:00
1.DVD教材視聴1 身のまわりのプラスチック(①3分)
2.DVD教材視聴2 いろいろなプラスチックの性質(④5分) ワークシート1(空欄埋める)
3.実験①身の回りのプラスチックをリサイクルマーク毎に分類する。(4人1グループで)
リサイクルマークのシートを貼付 ワークシートの読み合わせ
4.DVD教材視聴3 プラスチックを区別する実験「No.3浮き沈み」(実験①の映像2分)
「実験の目的」記入、実験方法の説明
・試験片:PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PS(ポリスチレン)、
PET(ポリエチレンテレフタラート)、PVC(ポリ塩化ビニル)
5種類を約1 cm角に細片する
5.DVD教材視聴4 暮らしを変えたプラスチック(②5分) プラスチックとリサイクル(⑦4分)
6.実験②プラスチックの密度を比べる実験(2人1実験) ワークシート2「浮き沈み」の実験
使用器具の名称確認【メスシリンダー、ビーカー、ピンセット、洗浄瓶、ハサミ】
・50 wt%エタノール水溶液【密度0.91 g/cm3】:50 g(63 ml)エタノール+50 g(50 ml)水
・水:100 g(ml)【密度1.0 g/cm3】 ・飽和食塩水【密度1.2 g/cm3】:26.4 g NaCl/100 g(ml)水
※プラスチック片を静かに沈めてから、ゆっくりピンセットから離し浮くか沈むかを調べる。
7.ワークシートの完成、感想の発表、DVD教材視聴5 プラスチックの進歩(⑥7分)
7月26日(木)1限8:50~10:20 2限10:30~12:00
1.DVD教材視聴5 プラスチックを区別する実験(⑤4.5分)
「No.1燃やす」「No.2熱して伸ばす」(実験②の映像2.5分、1.5分)
2.実験③燃焼実験でペットボトルを分別する!
ペットボトルは、本体、フタ、ラベルと材質が違う。
約1×4 cmに切り、燃焼実験によりどのようなプラスチックが使われているかを調べる。
ブンゼンバーナーの使用方法について説明する。
実験結果からワークシート3に記入
3.実験④フーリエ変換赤外分光光度計でプラスチックを調べる
ペットボトルの本体(PET)、フードパック(PS)、ポリ袋(PE)をATR測定する。
4.核磁気共鳴分光計(NMR)室 装置見学
5.DVD教材視聴6 プラスチックができるまで(2分) エンディング(1.5分)
6.スーパーボールをつくる特別実験
7.変更フィルムを使った特別実験
8.まとめの会(ワークシート1~3の完成、FT-IRチャートの帰属、質問)
今回のプログラムの特徴
1.中学校レベルの実験からスタートし、大学レベルの分析装置
を使った実験まで段階的に進めます。
2.ワークシートを準備し、レポート作成の事前準備としました。
3.危ない試薬は用いない安全実験です。
4.実験の説明は、動画教材を利用します。
5.毎回、時間調整を兼ねて特別実験を実施します。
小中学生向けに実施している「科学啓発活動」から選んだ
科学実験・科学工作を行いました。