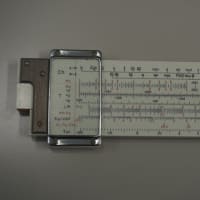北海道大学の高等教育推進機構高等教育研究部に設置されている科学技術コミュニケーション教育研究部門(CoSTEP)主催の、科学技術コミュニケーター養成講座に申込みした。
本科、選科があり、選科の演習Bに出願した。出願に必要な物は、履歴と下記小論文2つであり、定員30~50人、合格発表は4月26日。
(志望理由)
大学技術職員として16年程前から科学教育啓発活動を実施しています。内容は、子ども向けの化学実験、科学工作が中心で、活動範囲は国内のみならず海外まで広がっています。この活動が評価され、平成18年度工学教育賞(工学教育協会)を受賞。今後も継続的な活動を展開したいと考えているところです。
本講座の受講により科学技術コミュニケーション能力を高め、今後の活動を単なる工作で終わらせない「科学を伝える教室」を目指したいとの想いで受講を希望しました。これまで職務活動に加え個人的活動が中心でしたが、今後は同士を募り科学教育ボランティアグループを組織し市民活動的なまちづくりに繋げたいと考えています。この活動では科学の不思議を体験して貰うことを目的に科学教育啓発活動を実施しますが、スタッフ同士も科学を楽しむことを忘れずに行っていけたら良いと思っています。学びたいスキルは、プレゼンテーションおよびサイエンスライティングなどです。今後は大人を対象にした科学リテラシーを意識した教室開催を、本講座で習得したスキルを活かし「正しく科学を伝える活動」としたいと思っています。
(課題文)
科学技術の進歩により物質的豊かさは増大しました。同時に、環境破壊、地球温暖化、ゴミ問題など数多くの社会問題を引き起こしましたが、その一つに原子力発電の問題があります。昨年の福島第一原子力発電所事故により、原子力発電所の持つ課題が問題視されています。原発は埋蔵量に限りがある化石燃料に替わる枯渇のない魅力的なシステムとして開発・推進され日本の基幹エネルギーの一翼を担ってきましたが、重大事故が周辺環境に多大な被害を与え、その影響が長期化するなどの問題がありました。
科学技術のもたらす利益と危険性の両面から科学的に考えていく必要があります。放射線利用の正当化と最適化を十分に検討すべきなのです。今回の福島原発事故により、科学を根拠にした安全宣言が間違っていたことが露呈され、科学者に対する信頼が崩れました。失われた科学技術への信頼を取り戻すためには科学リテラシーの啓発活動が重要と思います。原発関連のニュース報道で当初気に懸かっていた点は、放射線量の数値表示で単位標記が無い、基準値の説明不足のため危機感をあおってはいないか?などがありました。原発関連の基礎知識①放射能、放射線、放射性物質の区別、②放射線にまつわる諸単位(ベクレル(Bq)、グレイ(Gy)、シーベルト(Sv))の意味、③線量限度についての考え方(被曝量と発ガンリスク)、④確定的影響と確率的影響の区別、などを理解した上で、正しい事実の認識が必要です。これらの科学リテラシーの向上には、科学技術コミュニケーションが必要不可欠で重要となってきます。科学技術コミュニケーションが取り組むべきことは、科学技術の正しい理解を手助けし各自が自分の意志で冷静に対処できるようになることだと思います。
戸田山氏は、次のように指摘しています。『放射能汚染とともに生きることを強いられるようになった3.11以降、未来に予想される安全性や危険性を「説得」するための科学コミュニケーションから、現実の放射線防護における市民の主体的意志決定を手助けするための科学コミュニケーションへの転換が必要である』(戸田山和久,福島第一原子力発電所事故以降の科学技術コミュニケーション,社会と倫理,2011,第25号,p.121-138)。このように科学コミュニケーションの力で正しい知識を得、不要な危機感を増大させずに対処出来るようになったら良いなと思います。