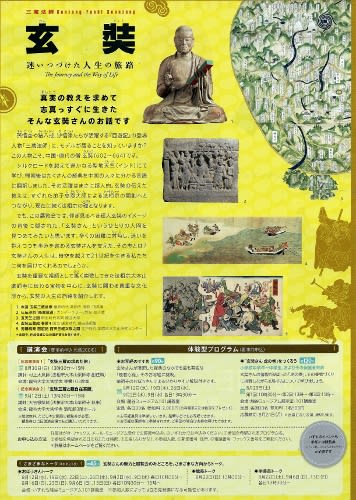今国立博物館の平成知新館で開催されている特別展観は「第100回大蔵会記念 仏法東漸―仏教の典籍と美術─」です。





大蔵会(だいぞうえ)は、仏教にかんする典籍の展観を中心とした伝統ある展観事業で、その主体となる京都仏教学校連合会には、現在、十六の大学が加盟しています。大正4年(1915)、大正天皇の即位式を記念して始まって以来、毎年開催され、今年は100回目という大きな節目を迎えることになりました。これを記念して、平成知新館の特別展示室・書跡展示室のほか、染織展示室・金工展示室・漆工展示室の各展示室を会場に大規模な展観を開催いたします。
構成は大きく二つに分けられ、
第一部は「大蔵会」という名称の由来にもなる、仏教経典の総集である「大蔵経(一切経)」についての展示です。
大蔵経の書写は、莫大な材料、時間と人員を必要する一大事業です。
にもかかわらず、日本では奈良時代以降、相当な数が作られ、あるいは海外からもたらされました。
まさしく、仏の教えがインドから中国、朝鮮半島を経て日本に伝わり、重んじられたこと、すなわち「仏法東漸」の証といえるでしょう。
ここでは、わが国屈指の古写経コレクションとして有名な「守屋コレクション」を中心に、その流れを紹介します。
第二部は、日本に伝えられた仏の教えがどのような広がりをもったのか、なかでも仏教各宗派の宗祖についての展示です。
さきの十六大学の性格にかんがみ、真言宗、天台宗、浄土宗、浄土真宗、臨済宗を中心に、
各宗派の宗祖に関連する書跡のみならず、絵画や工芸品もあわせて紹介し、その足跡をたどります。
日本仏教の歴史を通史的、かつ立体的にみることのできるまたとない機会となりますので、
是非とも多くの方にご覧いただきたく思います。
(ちらしより)
こんな説明書もありました。
分かりやすいですね。




弘法大師や伝教大師の書跡も見ることができました。
龍谷ミュージアムに行っておいたので、余計によく分かります。
龍谷ミュージアム、京都国立博物館で、同じものが出展されています。
愛知・七寺の黒漆塗唐櫃、釈迦十六善神像漆絵蒔絵中蓋。
一目でわかりました。
京都国立博物館の明治古都館。
特別展覧会は、ここで行われます。
今特別展覧会はやっていないので、入り口は閉鎖中です。
全部みるのに、たっぷり2時間はかかります。

明治古都館をバックに考える人。
そして正門と京都タワーをバックに考える人の背中。


正門と噴水。


こちらがいつも開いている平成知新館。
その前にも小さな噴水。

平成知新館の入り口から、正門と京都タワー。

正門。
ここから出ることは出来ますが、入館はできません。

正門からでると、そこには百日紅並木。


百日紅と正門。

ぶらぶらと七条通りを西に歩いてゆきます。
そこに、うなぎ雑炊=うぞふすいで有名な創業400年を越す、「わらじや」。
コース料理しかないので要注意です。
今日は休みだったので確認できませんでしたが、確か6000円以上しますよ。

暫く行くとなんと銭湯!「大黒湯」さん。
行くときは開いていなかったので、てっきり廃業していると思っていたのに、
帰るときには開いていました。
午後3時半に開くようです。
ちょっと覗いて見ると、そこにはお地蔵さん。
いちど入りに期待ですね。


七条大橋から鴨川の鳥。



部屋に戻ったのは午後5時過ぎ。
まだ日は落ちておらず、黒い雲の向こうです。