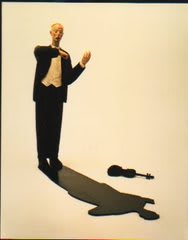アートにとって価値とは何か
三潴末雄 / 著
アートの価値とは何で決まるのか? 日本人のアートは西洋人にとって土人の土産物なのか? 日本の現代美術界において常に台風の目となってきたミヅマギャラリーの闘いのすべて。
海外では草間彌生、村上隆、奈良美智などを筆頭にした日本人アーティストが脚光を浴び、目の飛び出るような価格で作品が売り買いされている。そんな中でつねに日本の現代美術の中心にいて気を吐いていたのが三潴末雄率いるミヅマアートギャラリーだ。彼は、毒と批評精神に溢れた作家を世界に紹介するとともに、ジパング展等の展覧会を積極的にキュレーションし、会田誠、山口晃、OJUN、鴻池朋子、天明屋尚、宮永愛子など注目すべきの作家を輩出させた。彼の四半世紀の過程は、まさに日本人が日本のアートをどうやったら世界に認めさせることができるのかという歴史でもあった。アーティストを評価し、売り出すこと、アート作品を売買することの中で、いったいアートの価値とは何なのか。本書はその闘いの集大成である。
コメント三瀦さんとの訴訟記録をいつか公開し幻冬社にいろんな意味で挑戦してみたいです。
三潴末雄 / 著
アートの価値とは何で決まるのか? 日本人のアートは西洋人にとって土人の土産物なのか? 日本の現代美術界において常に台風の目となってきたミヅマギャラリーの闘いのすべて。
海外では草間彌生、村上隆、奈良美智などを筆頭にした日本人アーティストが脚光を浴び、目の飛び出るような価格で作品が売り買いされている。そんな中でつねに日本の現代美術の中心にいて気を吐いていたのが三潴末雄率いるミヅマアートギャラリーだ。彼は、毒と批評精神に溢れた作家を世界に紹介するとともに、ジパング展等の展覧会を積極的にキュレーションし、会田誠、山口晃、OJUN、鴻池朋子、天明屋尚、宮永愛子など注目すべきの作家を輩出させた。彼の四半世紀の過程は、まさに日本人が日本のアートをどうやったら世界に認めさせることができるのかという歴史でもあった。アーティストを評価し、売り出すこと、アート作品を売買することの中で、いったいアートの価値とは何なのか。本書はその闘いの集大成である。
コメント三瀦さんとの訴訟記録をいつか公開し幻冬社にいろんな意味で挑戦してみたいです。