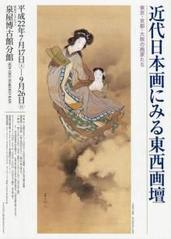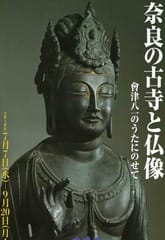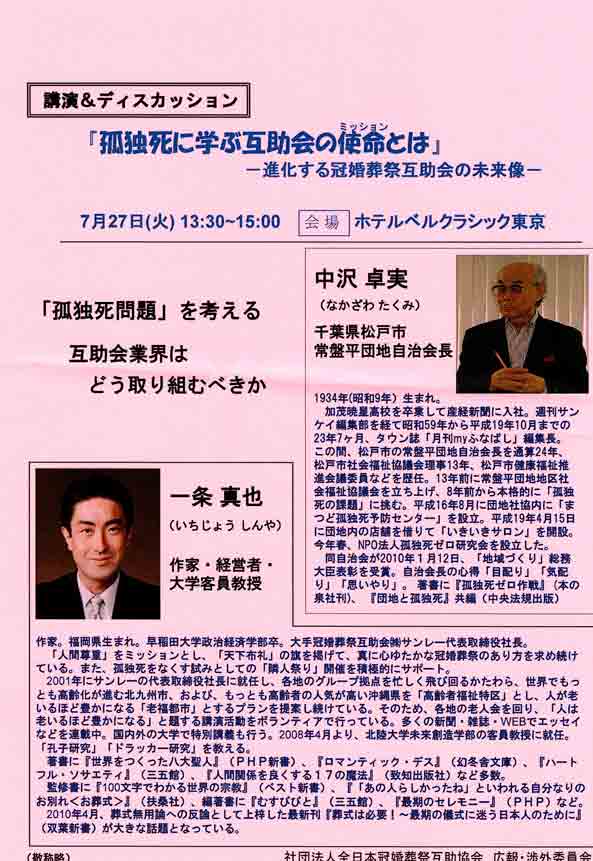先日、銀座のギャラリーに向う途中、ポーラミュージアムアネックスに立ち寄り、作家の桐島洋子さんが収集した骨董品の展覧会「桐島洋子 骨董物語」展を観てきました。子育てを終えた50代から骨董収集を始めたという桐島洋子さんのコレクションは、洋の東西を問わずジャンルも広範囲に渡っていて興味深く拝見することができました。かわいい鼻煙皿ははじめて目にしたのですが、使用目的を知りちょっとビックリ!ビーダーマイヤー様式の家具は知っていましたが、ガラス製品も存在しているという事実に驚きました。造形的にもデザイン的にもとてもセンス溢れていて素敵ですね。ロマノフ家が使ったお皿とブローチには悲しい王家の物語と重なって胸に迫るものがありました。桐島さんは隙間産業ならぬ隙間コレクターを自認しておられますが、単なる収集の目的ではなくて身の回りに置き、生活の中で実際に役立てている所謂生活骨董のコレクターであるところが、好感を持てると思います。時間の結晶を大切にしながら「骨董品」に込められている物語への思いも大切にしている気骨ある方のように思います。個人的には、ガラスのコレクションが、割と高い水準のレベルに達していて見応えがあると思います。僕とは趣味趣向が全然違いますが、隙間コレクターの心意気にとても魅力を感じます。幼少期に泰西名画のコレクションに囲まれていたそうですが、家運が傾き、散逸してしまったことがトラウマとなり悔しさのバネになっているのかな、とちょっと深読みしてしまいました。生活骨董コレクターの鑑として尊敬しちゃいます。通勤時の通り道ですので、時々覗いてみようと思います。この展覧会は、☆☆(2に近い1.5☆)でした。
地を這うようにして落ち穂拾いを楽しんで来た。どんなにささやかな骨董も、人生と同じように飽きることのない物語の結晶なのだ。 桐島洋子

ポーラミュージアムアネックス「桐島洋子 骨董物語」
地を這うようにして落ち穂拾いを楽しんで来た。どんなにささやかな骨董も、人生と同じように飽きることのない物語の結晶なのだ。 桐島洋子

ポーラミュージアムアネックス「桐島洋子 骨董物語」