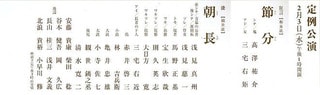たいこどんどん
『天保十二年のシェイクスピア』(05年)以来、『藪原検校』『道元の冒険』『表裏源内蛙合戦』と、井上初期作品に新たな命を吹き込み、エネルギッシュな舞台を世に送り出してきた蜷川幸雄が挑む第五弾!
本作品は井上ひさしが直木賞受賞後の第一作として書いた小説「江戸の夕立ち」をみずから劇化、75年に放った快作です。
江戸日本橋の薬種問屋の若旦那・清之助と、忠実なたいこもち桃八が、ひょんなことから漂流して、拾われた船に連れて行かれたのが東北・釜石。各地を転々とする九年の珍道中がここから始まる。二人には思いもかけないような災難が次から次へと降りかかる。流れ流されたあげくようやく「江戸」に戻ってくると・・・。
若旦那にどんなに裏切られても無償の奉仕を続ける幇間・桃八。社会は激変していっても根本的なところで「なにも変わっちゃいない」日本への静かな怒りや、時代に不意打ちにされつづける大衆への提言。歌や、踊り、お座敷芸など笑いがあふれるエンタテインメントの底には、庶民に向けられる作者の視線が2011 年にもまた同じ強さで光り続けます。

古田新太
確固たるポリシーがあって、携帯電話は持っておらずアナログ人間の側面も持つ。