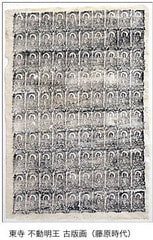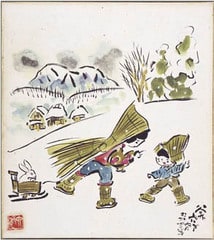三浦俊良著『東寺の謎』(詳伝社)より、 木曜日の続きになります。
餓鬼とはなんでも欲しがる、むさぼりつづける心の状態をいう。
京都の石庭で有名な龍安寺(りゅうあんじ)には、水戸光圀が寄進した銭形のつくばいがある。そのつくばいには「吾唯足知(われただたることをしる)」という文字が刻まれており、「足ることを知るものは、貧しいといえども富めり。足ることを知らざるものは、富めりといえども貧し」という意味が秘められている。
このような、足ることを知らない心の状態を餓鬼という。
畜生とは人のことばが届かない、なにも聞きいれない心の状態、阿修羅とは人を罵倒し、戦うことを生きていることと正当化して争いつづける心の状態をいう。
天上とはどういうものかというと、たとえば画家に「五百万円で絵を描いて下さい」とお願いする。画家は「五百万円は安いな」とか「儲けたな」とおもう。
これは欲の世界だが、一度、絵筆をとってしまえば、一切を忘れて絵に集中する。命を静寂という世界にもっていって書きつづける。この心の状態が天上である。
天上に至った画家は絵を描き終えると、やがて地獄あるいは餓鬼、畜生、修羅、人間のいずれかの道にもどってくる。
そして、苦しくなったら涙を流し、哀しみ、嘆き、怒り、楽しくなったら喜ぶのが人間である。
この人間は、地獄、餓鬼、畜生、修羅、天上という、どの道にも自由に行くことができる。どの道も自由に選べるというのが人間である。
だが、六道の世界にいるかぎり、人は苦しむと仏教は現実を示唆する。人生は四苦八苦であるという。
生、老、病、死という四つの苦しみに加え、愛別離苦(あいべつりく)、愛する人と別れる苦しみ、怨憎会苦(おんぞうえく)、憎い人と一緒にいる苦しみ、求不得苦(ぐふとっく)、欲しいものが得られない苦しみ、それに五陰盛苦(ごうんじょうく)がプラスされる。五陰盛苦とは身体が盛んすぎて、心と分裂してしまう苦しみをいう。
では、救われないのかというと、そうでもない。
この世は十の世界からできているという。それは六道の世界である、地獄界、餓鬼界、修羅界、人間界、天上界、それに声聞界、縁覚界、菩薩界、仏界を加えた十界である。
声聞とは、真実の声を聞こうとする心の状態をいい、縁覚とは、自然現象もふくめ、あらゆるものを縁として悟ろうとする心の状態をいう。菩薩とは仏の教えを実践する人をいい、仏とは真理を悟った人をさす。
講堂の二十一尊からなる立体曼荼羅は、六道をさまよう人間を前提に、声聞界、縁覚界、菩薩界、仏界に至る人間の可能性をあらわしている。人間本来の姿とは、六道を迷い歩く姿ではなく、仏を内に秘めた存在である。だから目覚めなくてはならないと語っている。