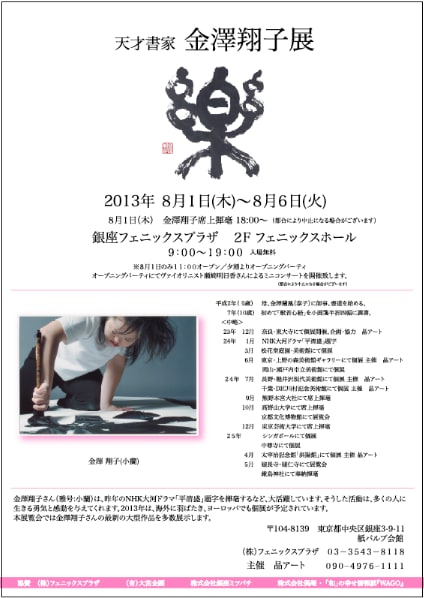河北新報
2013年07月31日水曜日
福島第1原発事故に伴い避難区域に指定された福島県12市町村の小中学校で授業を再開したのは42校中32校で、小中学生は原発事故前の8388人から5分の1以下の1592人に減ったことが、12市町村への取材で分かった。
学校再開状況と在籍生の推移は表の通り。小学校は27校中20校、中学校は15校中12校が再スタートした。再開時期は大熊町の2011年4月が最も早く、現時点では葛尾村のことし4月が最も遅い。
再開校のうち、広野町と川内村の計4校は避難指示が解けて元の校舎に戻り、他校は避難区域外の市町などに移って仮校舎を構えた。小規模校などは合同授業を余儀なくされている。
小中学校の在籍生はことし5月時点でそれぞれ976人、616人で、原発事故前(10年5月)の5395人、2943人から80%前後ずつ減った。原発事故の避難で子どもが大量に転校したことを裏付けている。
最も高い減少率は浪江町で小学生は98.5%減、中学生は93.0%減。町内9小中学校の中で再開校は二本松市に移った2校にすぎない。
町教委は「町民の避難先が広域にわたり、二本松市周辺にあまり子どもがいなかった。転校先になじみ、戻るのをやめた子がいたことも原因でないか」とみる。
田村市と川俣町は減少率が低い。避難区域が一部にとどまり、「学校を町内の別の所に移すだけで済み、転校を最小限に抑えられた」(川俣町教委)という。
学校の変則的な授業再開に伴い、教員も流動化した。双葉町は3小中学校が全て休校で、各校長を除く教職員計31人は籍を元の学校に置いたまま、町の避難児童、生徒の多い福島市やいわき市、埼玉県加須市の計24校に移っている。
県教委は「町の学校がいつ再開しても元の勤務先に戻れる雇用形態にした」と話している。
2013年07月31日水曜日
福島第1原発事故に伴い避難区域に指定された福島県12市町村の小中学校で授業を再開したのは42校中32校で、小中学生は原発事故前の8388人から5分の1以下の1592人に減ったことが、12市町村への取材で分かった。
学校再開状況と在籍生の推移は表の通り。小学校は27校中20校、中学校は15校中12校が再スタートした。再開時期は大熊町の2011年4月が最も早く、現時点では葛尾村のことし4月が最も遅い。
再開校のうち、広野町と川内村の計4校は避難指示が解けて元の校舎に戻り、他校は避難区域外の市町などに移って仮校舎を構えた。小規模校などは合同授業を余儀なくされている。
小中学校の在籍生はことし5月時点でそれぞれ976人、616人で、原発事故前(10年5月)の5395人、2943人から80%前後ずつ減った。原発事故の避難で子どもが大量に転校したことを裏付けている。
最も高い減少率は浪江町で小学生は98.5%減、中学生は93.0%減。町内9小中学校の中で再開校は二本松市に移った2校にすぎない。
町教委は「町民の避難先が広域にわたり、二本松市周辺にあまり子どもがいなかった。転校先になじみ、戻るのをやめた子がいたことも原因でないか」とみる。
田村市と川俣町は減少率が低い。避難区域が一部にとどまり、「学校を町内の別の所に移すだけで済み、転校を最小限に抑えられた」(川俣町教委)という。
学校の変則的な授業再開に伴い、教員も流動化した。双葉町は3小中学校が全て休校で、各校長を除く教職員計31人は籍を元の学校に置いたまま、町の避難児童、生徒の多い福島市やいわき市、埼玉県加須市の計24校に移っている。
県教委は「町の学校がいつ再開しても元の勤務先に戻れる雇用形態にした」と話している。