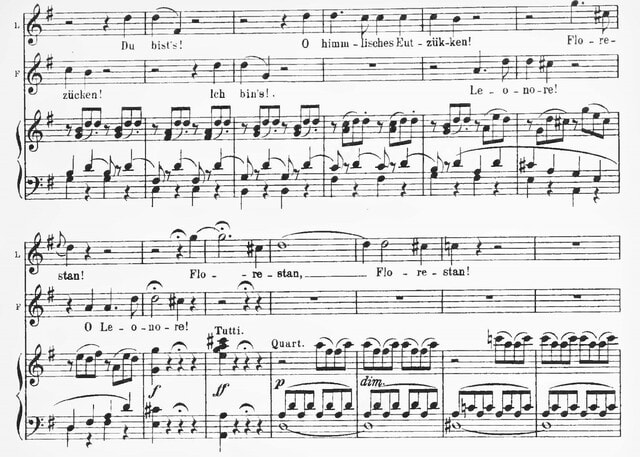オーケストラの楽譜では、トロンボーンはだいたいアルト、テナー、バスの三本がセットになっている。そのせいだろうか、トロンボーン奏者は日頃から三人組で行動し、例えば、合わせなしで一発勝負で大曲を演奏しましょう!って会を私が主催したことがあるのだが、そのときもトロンボーンの三人が事前に集まって練習をし、しっかり和音を作ってくるのが常であった。
と思っていたのだが、そう言えば、モツレク(モーツァルトのレクイエム)の「妙なるラッパ」(最後の審判の際に鳴り響くラッパ)はトロンボーン一本で吹く。

あら、珍しい、一人ではさぞ寂しかろう、と思ったが、モツレクでトロンボーンが一本なのはこの章だけで、トロンボーンの出番のある他の章ではいつものように3本セットである。
何回か前の記事にも書いたとおり、トロンボーンは元々は教会の楽器で、だからレクイエムでは大えばりで使われるわけだが、その後、「娑婆」にも進出を始め、モーツァルトの「魔笛」で登場し、ベートーヴェンが交響曲第5番で使ってからは交響曲の常連となった。
だが、ブラームスなどは、さすがにバッハの研究をするような人だけあって、例えば交響曲第1番の終楽章のトロンボーンは美しい和音を奏でていて、

元教会楽器の面目躍如である。だが、トロンボーンは、その気になれば、「3本で他のすべての楽器を吹っ飛ばす」(高校時代の吹奏楽の指導者の弁)。例えばチャイコフスキーの「悲愴」の第3楽章のエンディングなどはその最たる例である。

この下降音階をバリバリ鳴らして他のすべての楽器を吹っ飛ばすのである。こうなると和声もへったくれもない。世俗の極みである。古楽だけを聴く人がこの箇所を聴いたら失神するかもしれない。そうならないためには観念してここだけは世俗にまみれることである。私はそうしている。すると、だんだんどや顔でバリバリ吹くトロンボーン奏者を眺めるのが楽しくなる。なのに、あるときテレビカメラがこの箇所でヴァイオリンを撮っていた。ヴァイオリンの画面とバリバリの音声の不似合いなことったらなかった。
かように、トロンボーンはオケでは三人組が当たり前なのだが、そんな中でショパンのピアノ協奏曲は、第1番も第2番もモツレクのようにソロを吹くわけでもないのにバス・トロンボーンが一本だけで、まるで谷啓である。これをとらまいて人は「ショパンはオーケストレーションが下手」と言う。私などは、ショパンは偉い人だと思っていて、「偉い人」=「下手」の方程式にどうもなじめない。一本にした意味が何かしらあるのではないか、とも思うのだが、なにせ「死人に口なし」である。
え?谷啓って誰だって?ガチョーンの谷啓だよ。え?ガチョーンって何だって?クレージーキャッツのギャグだよ。え?クレージーキャッツって何だって?えっと、お笑いグループのようだけど、元々ジャズバンドなんだよな。てな具合にジャズではトロンボーンは一本でよいのです。