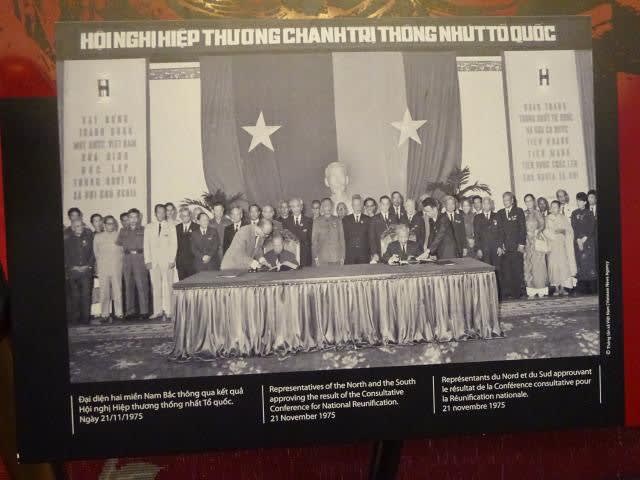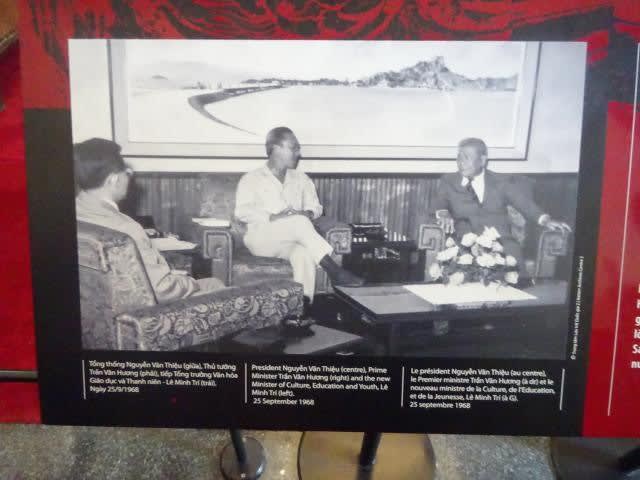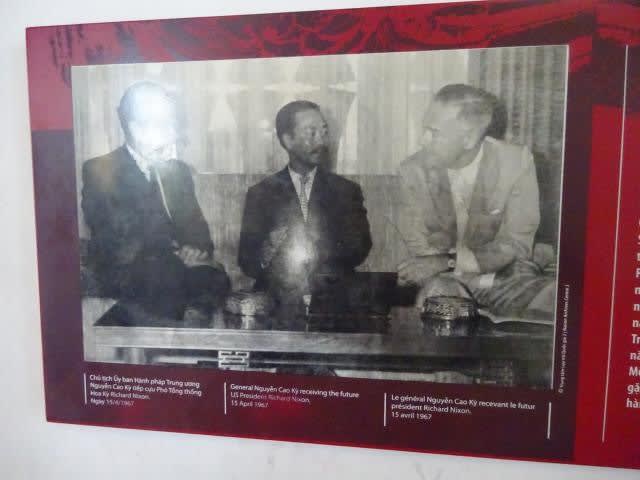ホーチミン市と日本とは時差が2時間ある。現地時間夜9:00頃タンソンニャット
国際空港に到着。ここはホーチミン市街中心部より
北西約8㎞の位置にある。当空港の沿革は1930年代初期、
フランス植民地政府によってタンソンニャット村に飛行場が
創設されたことから始まる。国際線の新ターミナルは
日本政府のODAにより2007年に建設された。
現在年間800万から1000万人の旅客に対応している。

夜のサイゴン・オペラハウス。ホーチミン市民劇場とも言う。
ベトナムのフレンチ・コロニアル様式の建築物の1つで
フランス人建築家ウジェーヌ・フェレにより
1897年に建設された。1956年以降は南ベトナム共和国
下院議会の議場として使用されたが1975年以後は再び劇場となった。



ホテルの部屋から見た、そして早朝と夜のグエンフェ通り。
この大通りは人民委員会庁舎からサイゴン川まで約1㎞あり
ホーチミン髄一のショッピングストリート、ドンコイ通りと
並走している。又この通りのエリアは金融商業地区の中心で
銀行、デパート、土産物店などが建ち並び、2015年から
通りの中央は歩行者天国となった。その結果、ご覧の通り
夜は若者のたまり場になり、ストリートミュージシャン、
大道芸、屋台、行商が出て大変な賑わいと成っている。




レタントン通りから中に入ったエリアが日本人街(リトルトーキョー)と
言われている日系レストランショップが多いエリアだ。
ご覧の様に迷路の様な路地が続き、
タクシーは通れない様な細い道が続く。
夜になると一大歓楽街になり、ネオンが瞬きまるでミニ新宿の様だ。



ホテルの部屋から見たホーチミンの中心街。最近経済発展が
目覚ましく、高層ビルがドンドン建っていく。
1枚目、3枚目写真の超高層ビルがホーチミンのランドマーク81(Landmark81)
高さ350Mでハノイのランドマーク72を抜いてベトナム
最高層のビルとなった。2017年末に完成。


サイゴン川はカンボジアに端を発してホーチミン市内を大きく蛇行し
同市内7区付近でドンナイ川と合流してニャーベー川となり
南シナ海に流れ込む。ホーチミン市にとって水道の拠点として
又、水の供給源としても重要な川となっている。


サイゴン川沿いのメリン広場の中央に建っているチャン・フン・ダオ像(陸興道像)。
氏はモンゴル軍がベトナムに攻めて来た時に迎え撃った英雄だ。
交通量(バイク)が半端ではないロータリーの真ん中に立っている。



ベトナムに来て(特にホーチミン市)最初にそして一番ビックリするのが
バイクの数の多さだ。初めて来た13年前に比べると
かなり減ったとはいえ、道路を横断するのが怖い程
(実際は恐ろしくてできなかった。)途切れなく走っている。
横断をするコツはゆっくり歩くことだと言っていたが
この相手次第の考えにはついていけない。
ガイドさんの話では、夜間バイク量が多いのは目的もなく
ドライブをする習慣があるからとか(ホーチミンは暑い為)。
そして空気が悪い為、多くのドライバーがマスクをしている。
ショップにはこの様な絵の描かれたマスクが売っていた。
昔のバイクには3人~4人乗っているバイクが当たり前だったが
今回は3人乗りは少なくなっていた。(4人乗りはいなかった)。



2010年に完成したビテクスコ・フィナンシャルタワー。
高さは265.5M、地上68階地下3階。施工者は韓国の現代建設。
このビルにはオフィスや会議室、商業施設、展望台
ヘリポートなどが置かれている。ご覧の様に意匠的に
とても目立つビルだが、このビルは危ないという噂が立っている。
鹿島の人も、ここにはなるべく行かない方が良いと冗談半分で言っていた。

入口の所に大勢の女性が集まって何かパフォーマンスをしているところを
メディア(?)が取材していたので、珍しい光景に
思わずパチリしてしまった。

タワー最上階展望台。柱もアールになっていて凝っている。



世界のICONIE(象徴的)ビル ベスト20の第5位に
当ビルはランキングされている。因みに第1位はエンパイアステイトビルディング
(ニューヨーク)、第2位は中国中央電視台(北京)
第3位はCOMMERZBANK本店ビル(フランクフルト)
そして第10位に東京モード学園コクーンタワー(東京新宿)が入っている。
このタワーはハスのつぼみ(ハスの開花)をイメージデザインしているとか。

グエンフェ通りの向かい側、グリーンのガラスの高層ビルが
宿泊したザ・レヴェリー・サイゴン(後日詳細をアップします。)

建築ラッシュのホーチミン市内にはご覧の様な建設ストップした
現場がいくつかあった。こんな大きなビルで一体何があったのだろう?
この仕事に携わっている人間としてはとても気に成る。
金銭のトラブルか、法的、技術的な問題なのか。


1941年に設立された歴史的市場のベンタイ市場。
第2次世界大戦時に大きな被害を受けた。
売場には生鮮品、食品、衣類、服飾品など人々の生活が
ぎっしり詰まっている。ここは日本人と分かるとボッタクリを試みる人達が多いと言う。


ベトナムにはまだ地下鉄がない。バイクが多いのも、公共交通機関が
貧弱だからと言われている。バイクや自動車による
大気汚染と交通渋滞が社会問題化している中
1号線、2号線は2020年に完成予定だそうだ。
当工事はJICA(ジャイカ)の協力の下
ODAでベトナム国営ゼネコンと住友商事などの日本企業が
共同事業体を組み発注している。この工区は清水建設・前田建設工業JVの
現場で、日の丸が掲示されているのが誇らしい。

小さなビル住宅の屋上には高架水槽が目に入り、気に成ったのでパチリ。


昼間の人民委員会庁舎。通称ホーチミン市庁舎。サイゴン市庁舎とも
言われている。1902年から1908年にかけて
当時のサイゴン市庁舎としてフレンチコロニアル様式で建設された。
1975年から今の名称だ。内部は一般公開されていないが
特にライトアップされた建物はとても美しい。


ホーチミン市1区にあるカトリック大司教座大聖堂のサイゴン大教会。
聖マリア大聖堂とも呼ばれる。サイゴンがフランス植民地だった
1863年から1880年にかけて建設されたネオ・ゴシック様式の教会。
ベトナムはカトリック教徒も多い。


この建物はサイゴン中央郵便局。1886年に建設が開始され
1891年に当時のフランス領インドシナの郵便、電信施設として完成した。
鉄骨設計はギュスターブ・エッフェルが手掛けた。
パリのオルセー美術館(当時駅舎)をモデルにしたと言われている。
現在でも通常の郵便・通信業務を行っている。


ベトナムの紙幣50万ドン。現在1円が205ドンだから
このお札は2500円程でベトナムの貨幣単位に馴染むのに
多少時間がかかった。紙幣は1000ドン(5円)~50万ドンまで
9種類あり、ポリマー紙幣になっている。ドンとは漢字の銅の意で
ベトナムでは古くから銅銭が流通し通貨名はこれからとられた。
尚硬貨は存在しているが流通はまれだ。