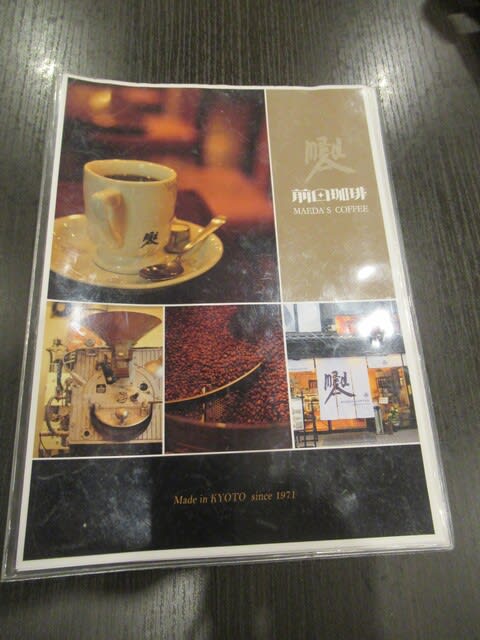どうしても嵐山に来るとアクセスの良い歴史の寺、史跡・特別名勝の
臨済宗天龍寺派大本山の天龍寺に寄りたくなる。
今回は天龍寺の奥にある竹林の道にも行きたくて久し振りに訪問した。
こちらは緑多き山々の中で最初に顔を合わせる「庫裏」。
庫裏とはお寺の食事を準備するところ、すなわち寺院の厨房(台所)のことをいう。

天龍寺の見学コースは丁寧に3つ設けられている。
①本堂と庭園コース ②法堂(はっとう)雲龍図コース ③庭園のみコース
そして目的の竹林へ行くのも北門(有料)と外側参拝コース(無料)の2つある。

今回は世界文化遺産の庭園のみを味わうコースで、
本堂には上がらないシンプルな選択をした。
天龍寺は1339年(暦応2年)吉野で亡くなった後醍醐天皇の菩提を弔うために
足利尊氏が夢窓国師を開山として創建した。
夢窓国師の門流は隆盛し、天龍寺は京都五山第一位の寺格を誇った。








開山夢窓国師が作庭した「曹源池庭園」は
王朝文化の優美さと武家文化の荒々しさを巧みに融合した庭です。
正面の枯山水の三段の石組は龍門の龍といい、これは中国の故事に由来する。
手前の石橋は日本最古の橋石組で右の石組は釈迦三尊石と称し釈迦如来(中央)、
文殊菩薩(左側)普賢菩薩(手前下側)を表現している。
曹源池の名称は国師が池の泥をあげた時、
池中から「曹源一滴」と記した石碑が現れたところから名付けられた。


曹源池庭園より大方丈をのぞむ。
この大方丈は明治32年(1899年)の建築で天龍寺最大の建物。
正面と背面に幅広い広縁をもち、さらにその外に落縁をめぐらせている。
因みに天龍寺は都合8度の火災に罹災している。

天龍寺といえば達磨図を連想する人も多く、天龍寺のシンボルのようになっているとか。
この絵は住職であった平田精耕老師によって書かれたもので、
京都大学を卒業し、インド哲学や仏教を学んだ住職の方だそうだ。






庭園コースを進んでいくと多宝塔から北門開設と同時に
昭和58年に整備された庭園「百花苑」に出る。
この多宝塔の枝垂桜の枝振りがまた見事なこと。
ここでも暫し桃源境の世界に思わずウットリして足が止まってしまった。






自然の傾斜に沿って苑路が造られており、満開の枝垂桜の中、
負けじと木瓜(ぼけ)、山茱萸(さんしゅゆ)、隼人三葉つつじ、沈丁花などが咲き誇り、
まさに春爛漫そのものだ。