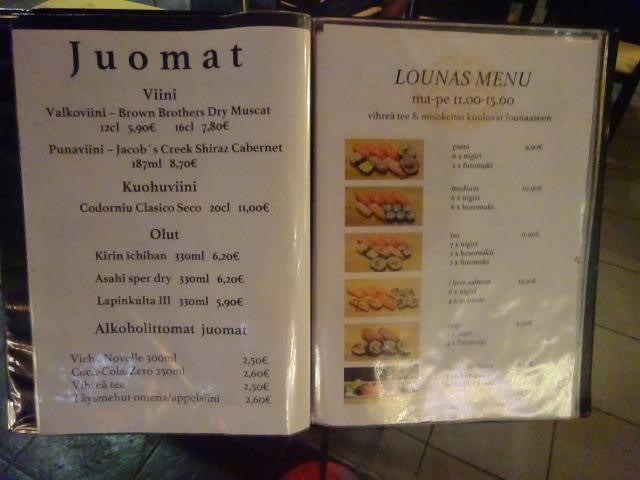これが今年のガイドマップの表紙の写真、本当にこのおまつりの
写真は絵になる。越中八尾(やつお)町は2005年の平成大合併に
よって富山市を中核とした富山地域6市町村と合併した。
毎年9月1日から3日にかけて行われる「おわら風の盆」に
だいぶ以前から行きたいと思っていたが、とうとう今年行くことができた。



このおまつりはとにかく歩く。坂を登る。流しを捜す。こちらが
待っていては何も見られない。そんなおまつりだそうだ。
越中八尾の街には11支部おわら保存会がある。
おわら風の盆はその支部毎に日程を定め行なっている。
各町にはそれぞれの個性があり、踊り、囃子、着物などに微妙に違いを出している。

ここ「福島」は旧町から移り住んだ人達を中心として結成された
最も新しい支部だ。歴史は浅いものの、11支部の中で
最大のおわら人口を誇る支部だ。風の盆期間中は駅横の
特設舞台でステージ踊りが実施される。又、大人数で広い通りを
流す福島独特の町流しは見応えがあり、大変好評だそうだ。

おらわ風の盆は雨に弱い。おわらに使用する楽器(胡弓など)は
雨が降ると使用不能になる。又高価な衣装の保護の為、
雨が降るとこのおまつりは中止になってしまう。今年はこの時期の
天気予報が微妙で半ば中止を覚悟していたが、当日の夕方は
ご覧の様なビックリする程の美しい夕焼けに成って観光客を迎えてくれた。


JR越中八尾駅の近くの地鉄バス駐車場から「坂のまち大橋」を渡り
天満町あたりからダラダラ坂になり、おわら演舞場まで約40分歩く。
八尾が全国に誇る民謡「越中おわら」は300年の歴史をもち
叙情豊かで気品高く、綿々としてつきぬ哀調の中に
優雅さを失わぬ詩的な唄と踊りだ。


今町の青年男女がスタンバイに入った。旧町の古刹聞名寺の正面に
位置する今町支部はかつては中町と呼ばれていた。
青年男女が絡む男女混合踊りはこの支部が他支部に
先駆けて取り入れたものと伝えられており、創作当時のスタイルを大切に守っている。

東町に入った所に男女の踊り手と一緒に記念写真が撮れる店を発見。
ところで「おらわ」の起源については、口伝によると
八尾町の開祖米屋少兵衛の子孫が保管していた町建に
関する重要秘文書の返済を得た喜びの祝として、
三日間、歌舞、音曲は言うに及ばず、その他いかなる賑わい事でも
とがめないから面白く町内を練り廻れというおふれを
町役所より出し、俗謡・浄瑠璃・その他思い思いの催しをなし、
三味線、太鼓、尺八、鼓などの鳴り物に和して昼夜の別なく
町内を練り廻ったのが始まりとか。この祭日三日が孟蘭盆3日に変わり
やがて210日の厄日に豊穣を祈る「風の盆」に変わったと言われている。


風の盆を見るには大きく2つの見方がある。ステージでの鑑賞と
各町内踊りでの町流しだ。初めての人にはおわら演舞場
(八尾小学校グランド)がおすすめ。但し有料だ。





丁度到着PM7:00。この日の当番支部は7:00から
25分間福島支部だ。席は地方席のサイド、前から4列目の最高の席であった。
越中八尾1







越中八尾2
往時を偲ばせる佇まいの家々が建ち並び、坂のまち風情を
色濃く残している諏訪町支部。東新町へと続く緩やかな坂道に
ボンボリが並び、狭い家並みにおわらの音曲が反響し、
道の両脇を流れる「エンナカ」と呼ばれる用水の水音と
相俟っておわらにとって最高の舞台を演出する。
越中八尾3





越中八尾4
東町は旧町でも古い町にある支部で、かつては旦那町と呼ばれた程
大店が連なっていたと伝えられており、他支部と違う
色合いの女性の衣装に当時の旦那衆の遊び心が伺い知れる。
この町からはおわらの名手が輩出され、おわらの芸術性を育んだ町でもある。

演舞場ではこの日最後の下新町支部出演が8時30分からであったが、
時間の予定もあって町流しを捜しにおわら演舞場を後にした。





越中八尾5
町流しで最初に出会ったのが、西町支部。ここは東町とともに
旧町の中心にあって旦那町として栄えた支部。
今でも土蔵造りの家や風情ある酒蔵、格子戸の旅籠など情緒あふれる
建物が残っている。又禅寺橋の石垣をバックにした
輪踊りには独特の風情が感じられる。

富山県出身のタレント柴田理恵のお母さんの実家が経営している
老舗旅館「宮田旅館」は江戸時代から続く古い建物だ。
柴田理恵はおわら風の盆の時期は必ず八尾に帰って来ているらしい。

正面に見える白い建物が曳山展示館ホール。風の盆のやっている3日間、
午後2時から午後4時までおわら踊り方教室を開催している。
又1日4回踊り説明と舞台踊りの鑑賞もここでは出来る。

八屋にはたくさの川があり、大雨が降る度、川が氾濫し、
人々は高台へと移り住むようになった。石垣の上に家が建ち
並んでいるのは今では八尾を代表する景色の1つになっている。





動画6
11支部の中で最も南に位置する西新町支部。新しく区画割されたことを
あらわす「新屋敷」という通称でも呼ばれる。腰を深く落としてから
大きく伸びあがる所作の男踊り、また繊細かつ優美な女踊りと
相俟っての町流しは見応えがある。

諏訪町の先に合って、おわら保存会11支部の中で最も
高台に位置する東新町支部。夜10時も過ぎて、夜食休憩か、
道路に座り込んで飲んだり食べたりしていた。この支部には
カイコを奉った若宮八幡社があり、その境内で披露される
おわらには独特の風情があるという。

東新町から諏訪町へ向けての一本道。ここが八尾のメインの通りで
坂道になっているのが、ボンボリの光で分かる。
この道は日本の道百選通りに選ばれている。それにしても
今回つくづく感じたのは夜あまり照度が無い中で
踊り、舞う姿を上手にカメラで撮るには技術と知識と良い道具がいることを
痛感させられた。難しいものだ。

諏訪町で、2階から町流しを見る為、又疲れを取る休憩所として
旅行屋さんが借り上げてあった町屋「山笑庵」。
しばらく流しが来ることを期待して待っていたが、
とうとうこの前には町流しは来なかった。



越中八尾6
夜も更けてきて、午後11時、最後の町流しを見ようと
鏡町に来たがご覧の様にもう立錐の余地も無い程の混み様。
しかも疲れてきた。かつては花街として賑わった町の鏡町支部。
女踊りには芸妓踊りの名残もあって、艶と華やかさには定評がある。
鏡町支部への入口でもある、おたや階段下が支部のメイン会場と
なっており、その会場で行われる舞台踊りや輪踊りをおたや階段に
座って鑑賞するスタイルが有名だ。


おわら風の盆の踊手の特徴は顔が見えないくらいに深く編笠を被る事。
風の盆が始まった当初は、照れや恥ずかしさから人目を忍び
手拭いで顔を隠して踊ったのが始まりだったと
伝えられている。編笠に変わった今もその名残で顔が見えないくらいに
深く被る。この2枚は踊りが終わって休憩を取っている男女の踊り子。
編笠を被って踊っている時はとても色気があり、又颯爽としていて
大人のにおいがプンプンするが、終わって素顔を見ると
ほとんどの人がまだあどけない。一体この落差は何なんだろう。
とにかく暗闇の中での幽玄の世界へどんどん引き込まれていく。




このおわら風の盆は俗にいうインスタ映えがするまつりだ。
と同時に写真のセンスとテクニックもいる。今まで数多くの写真を見て
女子踊り子さんの帯が黒いのに気が付いたでしょうか?
その昔、おわらの衣装を揃えた際、高価な帯まで手が届かなかったので
どこの家庭にもあった黒帯を用いて踊った名残と言われている。



この日はテクテク歩いて結局8支所の踊りを見ることが出来た。
残りは上新町支部、下新町支部、天満町支部だけだった。
アーくたびれた。ホテルに着いたのは夜中の午前1時過ぎに成っていた。