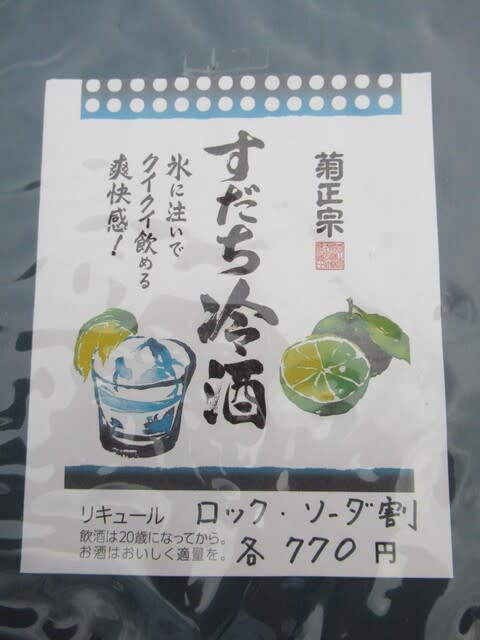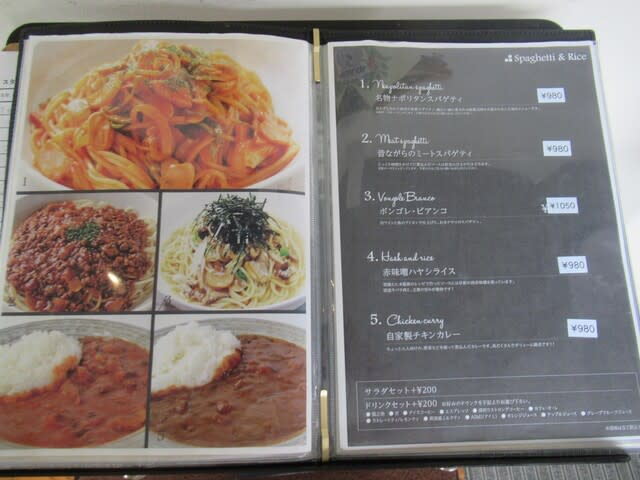1ヶ月にわたり、さまざまな行事が行われる祇園祭のハイライトといえばやはり山鉾巡行だ。
17日の前祭(さきまつり)では、生稚児が乗る長刀鉾を先頭に23基の山鉾が都大路を巡行。
多くの人々の願いと期待を背負った3年振りとなる山鉾巡行が始まる。

巡行の朝を迎えた新町通りと出発準備に追われる放下鉾。
何か祭りが始まる前の心の高まりを感じ、
秘かなワクワク・ドキドキ感を勝手に楽しんでしまう。

大規模改修が終わった京都市役所前の広場に設置された警備本部のテント。
このお祭りを陰日向で支える人々がかなり大勢いるのだろうとこのテントを見て推察してしまった。


午前9:30河原町御池の交差点も車両交通止の規制が入った。
警察も機動隊が投入されている。
この交差点では2回目の辻回しが行われる見せ場のところで、すでに大勢の人が陣取りをしていた。

御池通の寺町通から新町通の間に設置された有料観覧席は先祭で10,000席。
その半分は一般販売で発売日の受付開始からわずか1~2分で売り切れてしまった。

購入できた観覧席の斜め前は京都和風旅館で有名な柊屋(ひいらぎや)さん。
この前の道は規制線ができると案外穴場になるナと思った。

今回心配した天気は当日ご覧のように夏の空、
入道雲がモクモクして祇園祭ならではの天候になった。
但し京都の夏の暑さは格別だ。

観覧席の前のビルはレジテンス系のビルのようで
硝子窓越しに各家から多くの人が山鉾巡行を見下ろしていた。
ここは冷房完備の特等席だ。


祇園祭山鉾巡行①





毎年「くじ取らず」として必ず巡行の先頭を行く「長刀鉾(なぎなたほこ)」。
現在、生稚児(いきちご)が乗る唯一の鉾であり「しめ縄切り」で山鉾が神域に入る。
鉾頭にかざした伝・三条宗近作の長刀(現在は複製)は疫病邪悪を払いながら進む。
長刀は刃が八坂神社と御所の方には向かないように取り付けている。



2番目の巡行は「孟宗山(もうそうやま)」。
中国の史話「二十四孝」に登場する孟宗が病気の母の好物である筍を、
雪の中探し回り、ついに掘り当てて母を喜ばせたことを題材とした山。
見送の白綴地に墨一色で描かれた竹内栖鳳筆の「孟宗竹林図」は
極彩色豊かな山鉾の中では異色。



明治初年まで「花盗人山(はなぬすびとやま)」と呼ばれ、
平井保昌が和泉式部のために紫宸殿の前の紅梅を手折ってくる姿を
あらわしている「保昌山(ほうしょうやま)」。
山の故事に因み宵山には縁結びのお守りが授与される。
前懸と同懸は円山応拳下絵の逸品として有名だ。



貧困のあまり母と子を養うことができず、思い余って我が子を山へ埋め捨てようとしたところ、
黄金の釜を掘り当て母親孝行をしたという中国の史話「二十四孝」の一人である
郭巨の故事を題材にした「郭巨山(かっきょやま)」。
乳隠しという胴懸を吊るす飾り板と日覆い障子の屋根が特徴。





「函谷鉾」の名前は中国戦国時代、斉の孟嘗君(もうしょうくん)が秦の国を逃れ、
函谷関(かんこくかん)に着いたが、この関は早朝の鶏の鳴き声で開く規定なので
家来に鳴き声をまねさせたところ、本物の鶏が和して鳴いたため、
門が開き見事通り抜けたという故事による。
前懸は重要文化財。


山上は唐の詩人白楽天(白の狩衣姿)が道林禅師(紫衣に鴨子姿の僧)に
仏法の大意を問う場面の「白楽天山」。
前懸はトロイ戦争の場面を表した16世紀ベルギー製毛綴。
見送は18世紀フランス製のゴブラン織と山鹿清華作「北京万寿山図」の毛織綿。

昭和60年、117年ぶりに再興され巡行に復帰した「四条傘鉾」。
傘の上に御幣と若松を飾るのが特徴で、応仁の乱以来の傘鉾の原形を伝える。
昭和63年、滋賀県甲賀市の瀧樹神社で室町時代から伝わる「ケンケト踊り」を参考に
踊りと囃子が再現され完全復興した。


古くから町内の風早家に祀られていた天神を勧請してつくられた山。
油小路通にあることから「油天神山」と呼ばれている。
天神さんと深い関係のある紅梅の枝を立て、鈴をつける立派な朱塗りの鳥居が特徴。
見送は梅原龍三郎原画の「朝陽図」綴織。

スミダマンの観覧席の近くのところでは鉾山が通ると
なにやら各山鉾の人達が差し入れ物を取りに来る。
何を差し入れているのか?
暑いので飲み水かしら(?)

祇園祭山鉾巡行②
この「月鉾」は鉾頭に新月型(みかづき)をつけ、
真木の「天王座」には月読尊(つくよみのみこと)を祀る。
屋根裏の草花図は円山応拳筆、天井の「源氏五十四帖扇面散図」は岩城九右衛門筆、
前懸のメダリオン絨毯は17世紀インド製、
蟇股(かえるまた)の彫刻は左甚五郎作といわれている。
破風・軒桁・四本柱の錺金具なども華麗。

祇園祭山鉾巡行③
「蟷螂山(とうろうやま)」は「かまきり山」とも呼ばれている。
かまきりの羽や鎌が動くなど祇園祭では唯一のからくり山。
中国の故事を題材にした山。
前懸、胴懸、見送の色彩豊かな友禅染は友禅作家・羽田登喜男の作品。

「山伏山(やまぶしやま)」の御神体の山伏人形は八坂の塔が傾いた時、
法力によってなおしたという浄蔵貴所(じょうぞうきしょ)の大峯入りの姿を表している。
前懸、胴懸の中央に飾り房がついているのが特徴。

永正年間、京都に大火があった時、季節外れの霰が降り、猛火がおさまった。
その時、霰とともに小さな天神像が降りてきて祀ったのが霰天神山の起こり。
欄縁上に朱塗りの極色彩の透塀をめぐらし、春日造の社殿を安置。
前懸は16世紀ベルギー製の毛綴で「イーリアス物語」が描かれている。

祇園祭山鉾巡行④


「史記」に記された古代中国の聖人堯の治世で天下がよく治まって太平が続き、
訴訟用の太鼓に用がなくなり、鶏が巣を作ったという故事を題材にした「鶏鉾(にわとりほこ)」。
松村景文ら四条派による水引とトロイの王子と妻子の別れを描いた
16世紀ベルギー製の見送(重要文化財)は必見。


世阿弥作の謡曲「木賊」を題材にした「木賊山(とくさやま)」。
わが子を人にさらわれた翁が信濃国の園原で木賊を刈る様をあらわす。
祇園祭山鉾巡行⑤



鉾の古い形態である傘鉾の1つである「綾傘鉾(あやがさほこ)」。
大きな傘と棒振り囃子の行列で構成される。
棒振り囃子とは赤熊をかぶった棒振りが鉦、太鼓、笛に合わせて踊るもの。
6人の公家風装東をまとった稚児も巡行。
垂がりは人間国宝・森口華弘氏寄贈の友禅染。


神功皇后(じんぐうこうごう)が外征に際し、肥前国松浦郡玉島川で鮎を釣って戦勝の兆としたという。
日本書紀の話を題材にした「占出山(うらでやま)」。
神功皇后は安産の神として祀られ、占出山の巡行のくじ順が早いとその年はお産が軽いといわれている。
日本三景を描いた前懸・胴懸などが特徴。


巡行が始まってほぼ1時間半が経過し炎天下の中、
日陰もなくなり前の方の観客の方々が帰る人が増えてきたので
一番前に移動して巡行写真を撮った。
そこには5~6列目とは全然違う風景が拡がり、
よりリアルな写真を撮ることができた。











町内にあった菊水井にちなんで名付けられた「菊水鉾」。
鉾頭には金色で透かし彫の菊花をつけている。
稚児人形は謡曲を題材にし、魏の文帝の勅使が薬水を求めて
山に入った時に出会った菊の露を飲んで700年生き続けた少年枕慈童をあらわしている。
唐破風造りの屋根が特徴。
一番前の席に座ると色々おもしろいアングルの写真が撮れたのでアップしました。

この菊水鉾のところにはどこの局メディアだかわからないが
カメラマンクルーが付いてカメラをまわしていた。


貧しさのために夫婦は離別した後、妻は都で宮仕えをし、別れた夫を探したところ、
落ちぶれて芦を売る夫と再会できたという謡曲「芦刈」を
題材にした「芦刈山(あしかりやま)」。
天文6年、康運作の墨書銘がある御神体人形や御神体衣装(重要文化財)は山鉾最古級である。


よくよく見ると山鉾巡行の中に外国人が参加しているのを見る。
以前TVで見たが祇園祭にやたら詳しいカナダ人がいたが、
この人達も祭にどっぷりハマっているのだろう。

この芦刈山の参加者から後ろを見なさいとの指示があったので振り返ったら、
長刀鉾の生稚児が台に乗って行進していた。
今年の生稚児は老舗呉服店のおぼっちゃんでした。


またまた御池通を巡行する山鉾全景写真。
一番前列は良いアングルの写真が撮れる。


中国・周の時代、琴の名人伯牙が自分の琴を理解してくれた鐘子期の死を聞いて、
その琴の絃を切ったという故事を題材にした「伯牙山(はくがやま)」。






今度は人の表情、姿などに焦点を合わせた写真をアップ。


聖徳太子を祀る山で、四天王寺を建立する際、自ら良材を求めて山に入り、
老人に大杉の霊木を教えられた六角堂を建てたという伝説を題材にした「太子山(たいしやま)」。
他の山はいずれも松を立てているが、この山のみが杉を立てている。
祇園祭山鉾巡行⑥


今朝準備段階の「放火鉾(ほうかほこ)」がラスト3番前で目の前に来た。
また、望遠レンズで河原町御池交差点での辻回し風景も撮ってみた。
放火鉾は真木の「天王座」に放下僧の像を祀り、
鉾頭は日・月・星の3つの光が下界を照らす形をしている。
操り稚児人形は「三光丸」と命名。
この鉾とホテルが近かったこともあり、一番見る機会が多く、
一番親しみを感じてしまった鉾だ。


「古事記」「日本書紀」に記される「国生み」と「天の岩戸」の神話を題材にした「岩戸山(いわとやま)」。





前祭23基のしんがりを務める「船鉾(ふねほこ)」。
日本書紀の神功皇后の出陣を題材としている。
舳先に想像上の瑞鳥「鷁」を飾っている。






山鉾巡行の翌早朝の放火鉾の解体光景。
なぜこんなにも早く解体するのは訳があるらしい。
そもそも山鉾巡行は神輿が通る道を清めるために、言わず霧払いで行う。
そのため山鉾には多くの邪鬼が付いているため一日でも早く払わなければならず、
すぐ解体が必要になると聞いた。


街の中をよく見て歩くと先祭の次の後祭(あとまつり)7月21日~7月23日の
ガイドポスターが貼ってあった。
また、後祭の八幡山(はちまんやま)の準備組み立てが始まっていた。
こうして1150年間、山鉾巡行の歴史は受難と復興の歴史を繰り返してきた。
まさにここ数年のコロナ禍という疫病の中で3年ぶりに復活した今年は
その苦難の歴史にまた深く刻み込まれることでしょう。