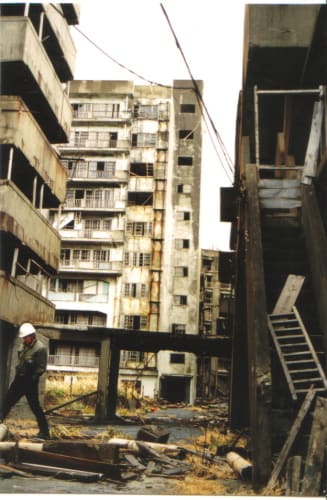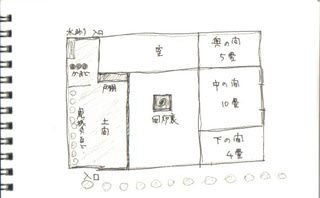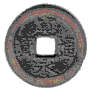“江戸天下祭”を見てきました。
祭りの後は酒がつきものですが、
ちょっと二日酔い気味で、今週は結果、1週間酔いでした。
さて、
“江戸天下祭”は、江戸開府400年を記念して2003年に復活した祭りで、
2年ごとに開催され、今年が3回目に当たります。
このお祭りを、東京丸の内仲通りで見てきました。
時折、小雨が降り前日とはうってかわった寒い日でした。
祭りのステージは、日比谷公園をスタート地点に、丸の内仲通りを通過し、
皇居前広場がゴールとなるが
このコースを、山車(だし)、神輿(みこし)などが練り歩いた。
江戸火消しの木遣りの唄 手古舞(てこまい)


先頭は、江戸木遣り(きやり)の唄が、
火消しの装束で鳶の人たちによって唄われました。
重い木材などを運ぶ時の労働歌が、今では、祭礼の祝賀として唄われます。
続いて、山車(だし)や神輿(みこし)を先導する舞としての
手古舞が踊られました。
男性風の扮装で、花笠を背中に背負い、ズボン風の袴(はかま)を着用し、
派手な刺繍の襦袢を方肌脱ぎにし、反対側は広袖のブルーの着物を着ている。
ファッションのおきて破りの得意な若者が、
この粋でいなせなセンスにそろそろ気づいてもいいのだが・・・
“江戸天下祭”は、江戸文化を復興する新しいイベントだが、
“天下祭”は、江戸城内に祭りの行列が入っても良いという幕府公認の祭りだけを言うそうだ。
数ある祭りのなかで、日枝神社の山王祭・神田明神の神田祭だけが“天下祭”であり、
それぞれ2年おきに開催されて今日に至っている。
朝鮮使節使



今回のハイライトは、山車・神輿だと思うが、“朝鮮通信使”の行列が新鮮だった。
“江戸天下祭”参加の理由は、
豊臣秀吉の朝鮮侵略により国交断絶していた関係を修復するために、
民族衣装をまとい楽団つきで使節使が江戸幕府に派遣されるようになった。
いまから400年前の1607年というから
“江戸天下祭”の重要なイベントとなる。
衣装の色彩感覚・音楽が、日本人にはないセンスであり、
400年前の彼らと我らの生活を彩る文化の違いが浮き彫りとなっていた。
しかし、この使節使の衣装・デザインなどは、古くなく今でも通用すると感じた。
山車(だし)


むしろ違和感を覚えたのは、
山車・神輿を作った我々の文化のほうであり、朝鮮使節使以上に遠い存在と感じた。
江戸と明治は連続していなかったと今でも思うが
あらゆる価値観を破壊して来たがゆえに、
ルーツすら否定しかねなくなり、
新興国民となりかねない。
江戸文化を復興させることが、
これ以前の我々の歴史とのブリッジを架けることに結びつき、
我々の文化が美しく感じられるようになるのではなかろうか?
と”江戸天下祭”を見ていて感じた
祭りの後は酒がつきものですが、
ちょっと二日酔い気味で、今週は結果、1週間酔いでした。
さて、
“江戸天下祭”は、江戸開府400年を記念して2003年に復活した祭りで、
2年ごとに開催され、今年が3回目に当たります。
このお祭りを、東京丸の内仲通りで見てきました。
時折、小雨が降り前日とはうってかわった寒い日でした。
祭りのステージは、日比谷公園をスタート地点に、丸の内仲通りを通過し、
皇居前広場がゴールとなるが
このコースを、山車(だし)、神輿(みこし)などが練り歩いた。
江戸火消しの木遣りの唄 手古舞(てこまい)


先頭は、江戸木遣り(きやり)の唄が、
火消しの装束で鳶の人たちによって唄われました。
重い木材などを運ぶ時の労働歌が、今では、祭礼の祝賀として唄われます。
続いて、山車(だし)や神輿(みこし)を先導する舞としての
手古舞が踊られました。
男性風の扮装で、花笠を背中に背負い、ズボン風の袴(はかま)を着用し、
派手な刺繍の襦袢を方肌脱ぎにし、反対側は広袖のブルーの着物を着ている。
ファッションのおきて破りの得意な若者が、
この粋でいなせなセンスにそろそろ気づいてもいいのだが・・・
“江戸天下祭”は、江戸文化を復興する新しいイベントだが、
“天下祭”は、江戸城内に祭りの行列が入っても良いという幕府公認の祭りだけを言うそうだ。
数ある祭りのなかで、日枝神社の山王祭・神田明神の神田祭だけが“天下祭”であり、
それぞれ2年おきに開催されて今日に至っている。
朝鮮使節使



今回のハイライトは、山車・神輿だと思うが、“朝鮮通信使”の行列が新鮮だった。
“江戸天下祭”参加の理由は、
豊臣秀吉の朝鮮侵略により国交断絶していた関係を修復するために、
民族衣装をまとい楽団つきで使節使が江戸幕府に派遣されるようになった。
いまから400年前の1607年というから
“江戸天下祭”の重要なイベントとなる。
衣装の色彩感覚・音楽が、日本人にはないセンスであり、
400年前の彼らと我らの生活を彩る文化の違いが浮き彫りとなっていた。
しかし、この使節使の衣装・デザインなどは、古くなく今でも通用すると感じた。
山車(だし)


むしろ違和感を覚えたのは、
山車・神輿を作った我々の文化のほうであり、朝鮮使節使以上に遠い存在と感じた。
江戸と明治は連続していなかったと今でも思うが
あらゆる価値観を破壊して来たがゆえに、
ルーツすら否定しかねなくなり、
新興国民となりかねない。
江戸文化を復興させることが、
これ以前の我々の歴史とのブリッジを架けることに結びつき、
我々の文化が美しく感じられるようになるのではなかろうか?
と”江戸天下祭”を見ていて感じた