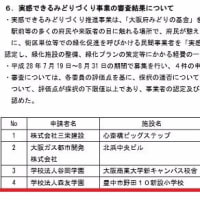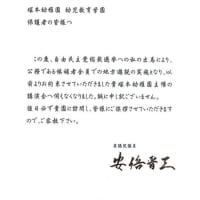前々回で1890年の”ベアリング恐慌”までを投稿させて頂きました。経済史的にはその後の世界的規模の恐慌は1900年前後に起きています。世界史的には”ドイツ3B”政策、中国に対するアメリカの”門戸開放宣言”又”義和団事件”、等々所謂、”帝国主義”の時代であり、世界各地で武力による領土、利権の確保等々が露骨な形で噴出した時代でもありました。又、日本が”欧州列強に対抗”し朝鮮、中国等々に連関し始める時期でもありました。
他方、”経済的”に見るなら、やはり恐慌、不況は克服されずこの1900年前後の恐慌という事態になります。通信網の発達、金融機関の世界各地での統一性等々により恐慌が世界的になるのは”当たり前”の状態でもありました。今回の恐慌はロシアからその口火が切られました。当時のロシアと言えば未だ”後進資本主義国”と言うべきであった訳ですが、その
”農民の没落、労働者の貧困な購買力、農奴制の遺制”(メンデリソン、恐慌の理論と歴史 4)の元でも国内市場の消化力を制限した租税が大きな役割をし、発生したとしています。
まず1898年末にロシアの金融市場の全般的な逼迫によって起きたとされます。(更に世界的にはギリシャとトルコの戦争、フアショッダに於ける英仏の紛争によっても圧迫されたとします。)それは1899年初頭からもロシアの金融市場は不安がみなぎり、外国資本の流入がにぶり始め、又他方でイギリス・ブーア戦争にも影響を受け欧州全体の諸金融市場に影響が出始め1899年6月からは独、米、英での株式相場の下落が始まり、英でのブーア戦争による金の流出を防ぐため
独 ライヒスバンクでも割引歩合を1899年8月7日4%から5%へ引き上げた。しかしイングランド銀行が11月30日、割引歩合を6%に上げると、ロンドン宛為替が再び悪化しライヒスバンクは、金流出を防ぐため、同年12月19日、7%にして応じるしかなかった又、ドイツの大銀行は国内の金融困難を回避するため”自発的に”イギリスへの金輸送を停止した。(ドイツ恐慌史論 石見徹)
その間仏銀行は1898年の2.5%から1899年には3→3.5→4%と割引歩合を引き上げた。(Palgrave Bankrate and The Money Market )
一般に欧州に於いて19世紀後半に英、仏、独の中央銀行の割引歩合を見ると(上記Palgrave等)概して仏中央銀行の割引歩合が一番低く、又レートの変更回数も少ない。これらの事が何処に原因しているのかは、些か問題になる所でありますが、これにつき、ドイツブンデスバング編 ドイツの通貨と経済1876-1957 では”フランスでは一人あたりの銀行券流通額は、1914年以前は通常ドイツの3倍から3.5倍に達していた。その上フランス銀行は、自行の銀行券を金に兌換する事を自行の随意に任されていたので、ライヒスバンク(ブンデスバンクの前身)やイングランド銀行のように、準備を守るために割引歩合という武器を用いる事はあまりなかった。”としています。
・・・以下次回28日予定
最新の画像[もっと見る]
「景気政策史」カテゴリの最新記事
 景気政策史―60 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その16 “大不況”と商工業...
景気政策史―60 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その16 “大不況”と商工業... 景気政策史―59 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その15 “自由貿易”と砲艦...
景気政策史―59 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その15 “自由貿易”と砲艦... 景気政策史―58 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その15 英仏通商条約と...
景気政策史―58 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その15 英仏通商条約と... 景気政策史―57 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その14 後発国の自由と...
景気政策史―57 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その14 後発国の自由と... 景気政策史―56 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その13 後発国の自由と...
景気政策史―56 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その13 後発国の自由と... 景気政策史―55 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その12 関税改革及び穀...
景気政策史―55 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その12 関税改革及び穀... 景気政策史ー54 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その11反穀物法同盟...
景気政策史ー54 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その11反穀物法同盟... 景気政策史ー53 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その10穀物法、通貨、...
景気政策史ー53 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その10穀物法、通貨、... 景気政策史ー52 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その9穀物法、通貨、不況
景気政策史ー52 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その9穀物法、通貨、不況 景気政策史ー51 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その8自由貿易と機械輸出
景気政策史ー51 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その8自由貿易と機械輸出