仮名指導について質問が来ているのでお答えします。
ひらがな指導プログラム
通級指導教室・特別支援学級で使える河村式ひらがなプリント (特別支援教育サポートBOOKS) | 河村 優詞 |本 | 通販 | Amazon
カタカナ指導プログラム
通級指導教室・特別支援学級で使える河村式カタカナプリント (特別支援教育サポートBOOKS) | 河村 優詞 |本 | 通販 | Amazon
質問:仮名などの文字指導に関連したアセスメントツール、教えて!
回答:大抵が低年齢児なので、担任の立場の場合は関係を悪化させないように、そもそも検査物の負荷を避けた方が良いケースもあります。その点に留意しつつ、客観的に指導する上でアセスメントツールが必要な場合、私が使うことがあるものとしては以下のようなものがありますね。
・WAVES:書字に関連する視知覚認知能力のアセスメントができる。教育現場にとって嬉しいことに、コピーして使用可能!また、同じく現場として嬉しいポイントが集団実施が可能!ただし、中度~重度の知的障害児へのアセスに使う、床効果で「全指標低い」という結果で、個体内差がつかみにくいことも。また、全編一気に行うとかなり長いので負担に注意。
・DTVP(フロスティッグ視知覚発達検査):個別検査になるが、WAVESよりももう少し重めの子、低年齢児の個体内差を見やすい。また、絶版本だが訓練法もセットで開発されている。ただし訓練法は大昔の洋書なので、一部絵柄が子どもにギャグとして受け取られることがある。
・ROCFT(レイの複雑図形テスト):色々アレな指導法の効果検証に使われて炎上しているのを見たことがあるが、結構由緒正しきテスト。図形の模写、記憶を扱い、図形の要素ごとに位置と形状に点数をつける。いきなり複雑な図形を見せることになるので、できない見込みがある課題に曝露できるケース(あるいはそれができる関係性が検査者との間にある時)のみに実施することになる。
・DEM:眼球運動の検査。個別実施で数字が読めることが前提。
※他にもSTRAWとかURAWSSとかを使う先生もいますが、私はあまり使う機会が無いですね。
バックナンバー
















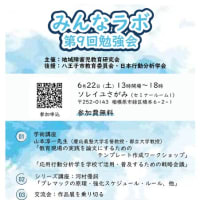
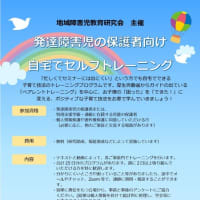


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます