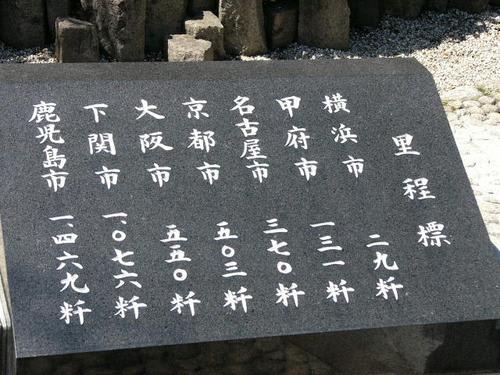日本橋を後にして中山道を歩き始める。
入り口にライオン像のある老舗のデパートを横目に見て、

(老舗デパートのライオン)
入り口にライオン像のある老舗のデパートを横目に見て、

(老舗デパートのライオン)
次の路地を左折するとすぐ右側に日本銀行がある。
左側には日本銀行経営というのも可笑しいが、
貨幣博物館がある。
入り口まで階段を三段上がり、
すこし年季の入った細かい鉄格子の扉は重厚で、
入るにはすこし勇気が必要である。
しかも、両脇に警察官に似た警備員がいる。
でも、大きく入場無料という文字が目に入ったので、
思い切って入ることにした。
(経営者は日本銀行で、お金には執着しない。
しかも、両脇に警察官に似た警備員がいる。
でも、大きく入場無料という文字が目に入ったので、
思い切って入ることにした。
(経営者は日本銀行で、お金には執着しない。
無料で当然と勝手に決め込んだ。)
警備員に頭を下げ、胸を張って入ろうとすると、
扉の両側に「扉に手を触れないで下さい」と看板がある。
(いくら日本銀行だからといって、
警備員に頭を下げ、胸を張って入ろうとすると、
扉の両側に「扉に手を触れないで下さい」と看板がある。
(いくら日本銀行だからといって、
鉄の扉を破って強盗に入る訳じゃあるまいし、
この看板は行き過ぎ)と思ったが、
手を触れないで
どうやってドアーを開けるのだろうと考えながら
恐る恐る扉の前に立つと、
どうやってドアーを開けるのだろうと考えながら
恐る恐る扉の前に立つと、
ドアーがゆっくりゆっくり開いた。
何のことはない自動ドアーだった。
一歩、中に進むと同じようなドアーがもう一つある。
御丁寧に「扉には手を触れないでください」の看板が
また立っている。ドアーは同じように自動で開く。
「扉には手を触れないでください」でなく、
「自動ドアー」と何処かに小さく書けばことは足りる。
中に入って驚いた。
鮮やかな真紅のカーペットが目に入ったからだ。
一歩足を踏み出すのをためらった。
ボクは知っている、
何のことはない自動ドアーだった。
一歩、中に進むと同じようなドアーがもう一つある。
御丁寧に「扉には手を触れないでください」の看板が
また立っている。ドアーは同じように自動で開く。
「扉には手を触れないでください」でなく、
「自動ドアー」と何処かに小さく書けばことは足りる。
中に入って驚いた。
鮮やかな真紅のカーペットが目に入ったからだ。
一歩足を踏み出すのをためらった。
ボクは知っている、
外国の要人が来日して、
首相が案内し、閲兵式をするとき、
あるいは外国の元首が国賓として招かれ、
飛行機のタラップを降りて歩き始める時、
そこには必ずレッドカーペットが敷かれていることを。
辞書にある、
Red carpet=
首相が案内し、閲兵式をするとき、
あるいは外国の元首が国賓として招かれ、
飛行機のタラップを降りて歩き始める時、
そこには必ずレッドカーペットが敷かれていることを。
辞書にある、
Red carpet=
(貴賓などを迎えるための)赤じゅうたん
丁重なもてなし、手厚くもてなす意味とある。
ままよ、と足を一歩踏み出した。
こんなこともあろうかと、
丁重なもてなし、手厚くもてなす意味とある。
ままよ、と足を一歩踏み出した。
こんなこともあろうかと、
今日は出掛けに靴もピカピカに磨いたし、
下町の粋な小父さん達に失礼があってはならないと、
イギリス王室御用達のトレンチコートを着てきたし、
同じメーカーのカラーシャツに、
胸と袖口に四つの金ボタンが付いた
下町の粋な小父さん達に失礼があってはならないと、
イギリス王室御用達のトレンチコートを着てきたし、
同じメーカーのカラーシャツに、
胸と袖口に四つの金ボタンが付いた
ヨーロッピアン・タキシードと言われるジャケットも着てきた。
ここにも警備員がいる。
いかにも物々しく厳重であるが、日本銀行でもあるし、
これくらい厳重にしておけば
(中の展示物の重要さを判って頂ける)
と思っているのだろう。
警備員が「こちらに記帳を」と言って手招きをする。
これまた重々しい年代物と思しき机の前で紙を手渡される。
(展示してある貨幣の一部でも盗られた時の用心?)
で止むを得ないかと思ったら、
記入するのは性別、住所の都道府県名と個人か団体かの区別だけ。
「展示は二階です」の案内で階段を上る。
この間もレッドカーペットが敷かれており、
最上級のおもてなしを意味している。
博物館のお客様はボクと先客の40歳がらみの紳士だけで
静まり返っている。
展示物は、貨幣の歴史で人間が貨幣を必要とした
起源から始まり、世界の貨幣の移り変わりから、
日本の貨幣の変遷が実物で展示されている。
現存する硬貨で、世界一大きいといわれる大判は
小判と比べると本当に大きい。

(江戸時代一両で買えたもの)
ここにも警備員がいる。
いかにも物々しく厳重であるが、日本銀行でもあるし、
これくらい厳重にしておけば
(中の展示物の重要さを判って頂ける)
と思っているのだろう。
警備員が「こちらに記帳を」と言って手招きをする。
これまた重々しい年代物と思しき机の前で紙を手渡される。
(展示してある貨幣の一部でも盗られた時の用心?)
で止むを得ないかと思ったら、
記入するのは性別、住所の都道府県名と個人か団体かの区別だけ。
「展示は二階です」の案内で階段を上る。
この間もレッドカーペットが敷かれており、
最上級のおもてなしを意味している。
博物館のお客様はボクと先客の40歳がらみの紳士だけで
静まり返っている。
展示物は、貨幣の歴史で人間が貨幣を必要とした
起源から始まり、世界の貨幣の移り変わりから、
日本の貨幣の変遷が実物で展示されている。
現存する硬貨で、世界一大きいといわれる大判は
小判と比べると本当に大きい。

(江戸時代一両で買えたもの)
お金はその昔は不要で、物々交換で取引されていた。
それが物と物の間で均衡が取れなくなり、
物に代わるための物として、お金が出来た。
お代としての品物であるから、希少で誰もが欲しがる
貴重品と言うことになる。
最初にお金に変わるものとして、貝殻が中国で発見された。
なぜ貝殻かと思ったが、考えてみると中国は広く、
昔の都は大陸の内深いところにあったので、
海にある貝殻が珍重されたと容易にうなずける。
小さな貝から大きな貝に、
価値としては上がって行ったであろう。
だから、お金に関わる漢字には、貝の文字が入っている。
売、買、寶、財、費、貯、etc.

(お金にかかわる文字と貝殻)
だから、お金に関わる漢字には、貝の文字が入っている。
売、買、寶、財、費、貯、etc.

(お金にかかわる文字と貝殻)
ついで、新札についての展示。
一万円、五千円、千円の登場人物について。
最後、出口の直前に、一億円が束になってケースの中にあり、
両サイドに手が入り、10センチほど持ち上げる体験が
出来るようになっている。
一億円を持っていかれると困るからだろうか?
ここにも警備員がいる。
両側に手を入れて一億円を持ち上げてみる。
説明によれば、十キロあるそうだ。
ずしりと重い。一億円を一度は手にしたいと、
庶民ならばそんな夢を誰もが持っているのであろう。
そんな気持ちをくすぐらせる展示であった。
警備員とレッドカーペットで重々しくお迎えするのは、
一億円のお客様の気持ちを満喫させる演出であった。
コートを抱えて、出口に向かった。
貨幣博物館に一度は訪ねてみたいものだ。