「子連れ狼 子を貸し腕貸しつかまつる」 1972年 日本

監督 三隅研次
出演 若山富三郎 富川晶宏 露口茂 真山知子
藤田佳子 内田朝雄 渡辺文雄 伊藤雄之助
内藤武敏 加藤嘉
ストーリー
子を乗せた箱車に、“子を貸し腕貸しつかまつる”墨痕鮮やかな旗差物たなびかせて進む狼人の姿が、街道の人々の眼を惹いていた。
人呼んで“子連れ狼”。
いかに困難な依頼も必ず果たす凄腕の刺客と恐れられている拝一刀親子流浪の姿だった。
その拝一刀(若山富三郎)の胸には、柳生一族への怒りと恨みが激しく燃えていた。
拝一族が勤める公儀介錯人の役職を狙った烈堂(伊藤雄之助)率いる柳生一族は、一刀に“徳川への反逆”の汚名を着せ、職を追い、妻(藤田佳子)をも殺害したのだった。
この窮地を脱した一刀は一子大五郎(富川晶宏)と共に、血と屍の魔道に生きることによって、怨念を柳生一族に叩きつけようとした。
ある日、殺しの依頼がきた。
依頼者小山田藩江戸家老市毛(内藤武敏)の狙いは、国家老杉戸監物(内田朝雄)一味の、世嗣暗殺計画を壊滅させることだった。
一味が、世間のはみ出し者たちばかりが寄りつく峡谷の湯治場にひそんでいることを知った一刀は、早速目的地に向った。
子供連れと侮りいたぶる無法者たちの暴言暴挙にも耐えた一刀は、枕探しお仙(真山知子)の命を救うため衆人のなかで、彼女と肌を合わせる恥辱に動ぜず、ただひたすら時を待った。
暗殺計画決行を伝えるため監物が湯治場に姿を現わし、その機会がやってきた。
計画遂行のためには手段を選ばぬ一味は、秘密維持のため湯治客の皆殺しを図った。
騒然となった湯治場の中を大五郎を乗せた箱車を押した一刀が、一味に向って進んでいった。
手裏剣の名手紋之助(松山照夫)、道場破りのしがらみの丹波(波田久夫)など曲者ぞろいを相手に一刀の業物同太貫の豪剣が唸っれた。
そして箱車が武器に一変し、小山田三人衆も、監物も倒れた。
累累と横たわる屍を残して一刀は立ち去り、涙で見送るお仙の瞳に大五郎の可愛い笑顔がにじんで消えた。
寸評
かつて人気を博した時代劇漫画があった。
漫画アクションに連載された小池一夫原作・小島剛夕画の「子連れ狼」である。
ドラマ化されて、主人公の拝一刀をテレビは萬屋錦之助、映画は若山富三郎が演じた。
「しとしとぴっちゃん、しとぴっちゃん・・・」という橋幸夫の歌う主題歌も大ヒットして、人気歌手だった橋幸夫を復活させた。
拝一刀は冥府魔道に生きる鬼となって殺戮と非道の刺客道をたどるのだが、一子大五郎にその事を告げて生死のどちらを選ぶかを決めさせる。
胴太貫を選べば父と共に刺客道を行き、手まりを選べば母の待つ黄泉の国へ送ってやるつもりだったが、大五郎は本能的に胴太貫を選んだ。
こうして子連れ狼のありかたは決められた。
親子はどちらが先に死のうが、それが宿命ならば仕方がないと言う覚悟が出来ており、それだけに立ち廻りは壮絶なものである。
父なれば子の心を、子なれば父の心をという結びつきが命を懸けた瞬間に発揮される。
親子の断絶を真っ向否定する結びつきである。
大五郎は拝一刀が繰り広げる修羅場を、瞬きもせず見つめている。
大五郎が見ている世界は、今で言えば紛争地の子供たちが見ている世界と同じなのだ。
大人たちの殺し合う姿を子供の目を通すことで、当時の紛争を批判していたのかもしれない。
僕は現役時代に物流センターへ出張に行った折、地元の名士でもある刀剣収集が趣味と言うセンター長のお宅を訪問して胴太貫を持たせてもらった。
錆びてはいたがズシリと重かった。
こんな重い物を振り回していたのかと、武士の腕力の凄さを体感したのだった。
大五郎が乗っているのが箱車である。
いわゆる乳母車なのだが武装されていて、その仕掛けも見どころである。
底に分厚い鉄板が張られており、手すりや取っ手に刃物が仕込んであり衝撃を与えると刃が飛び出す。
つなぎ合わせば長槍にもなるもので、ジェームス・ボンドも顔負けの装備品であった。










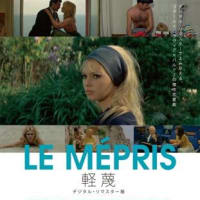
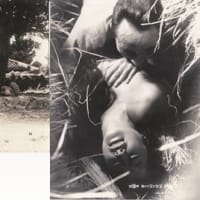

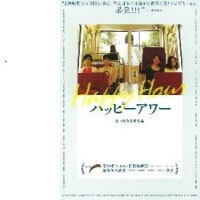
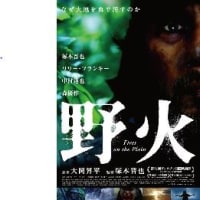
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます