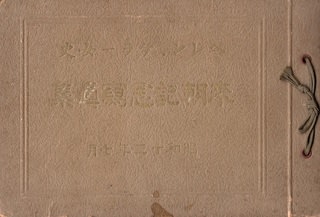(以下明石にて)
梅にほふ夕陽丘の花かげにたふれて立たず梅は又咲く
道ばたに道を教へて立つ石も見て過ぎにけりよばざりし故
日のくれて既にくらきや曙の浮ばんとしていまだ暗きや
よるも來ずさりとて日照る晝しらず繋がれてありたそがれの獄
病どもわが骨かぢる齒の音と時計をきゝぬ夢の柱に
花瓶の櫻ほろほろ涙しぬ我も泣く夜のわづらひの床
やめど我櫻を見れば櫻見る心となりぬ何かなげかん
(以上明治四十二年)
(以下明治四十三年九月より但馬にて)
悲しさに堪へたる人と西行はのき並べむといはざりしかな
われ生れし第一日のあかつきに門にあたりて石つぶてふる
花かげにとかげはねむるねむるまは眠れりとして見てはあれども
思ふことなくて蟲きゝ思ふことなくて風きく思ひつくして
〔写真〕 著者の遺児美津子(六歳の春)
わが心秋の夕べのくもり日の雲のやうなる衣 きぬ につゝまる
晴れわたる秋空高く白雲の浮ぶも見えて靜けき日かな
樂しきはわが西行が集の中に心のかよふ歌得たるとき
何すともいふことなしに同じみちゆきかへりするこの頃のくせ
人を友を擲ち世をも擲つと思ふはあらずわれ擲たる
日を見たる月見草かも病みほけてわれ一目見てうつむける人
博士等が手にする醫書の萬卷も何せん我の一人救はず
病もて苦しみをもて鞭うつに涙はいでず歌ぞあふるゝ
あまりにもさびしき秋の夕よりことばはなくて指を折るくせ
血に飢ゑし虎狼の牙の前にして兎もあらず小羊もなし
「吾は人の生死の外に超越す」とかゝる面する醫學博士よ
猶われに食ふべきほどの肉ありやそこに眠れる痩犬も來よ
あしきこと惡しといはんは言ひよかり善き事をしも善しとして後
軒つたふ雨だれをもて玉琴の響を聽きし人羨まし
鉛筆を忘れてや來し有るがまゝに花に染めたる定家集かな
唯一本立ちてあるより並木することのよろしさ君と我とも
何事も人いつくしむこそよけれ我れうつ手にはつるぎ與へて
我死なば親も泣くらん子泣くらん妻も泣くらん泣かざるは我
汝何ぞ生をもとむるかく問はれうつむくは豈われのみならめや
過去といふ闇がりのなか赤々と眼を射る光眠り誰かり
(以下明治四十三年十月二十三日以降)
早く暮れ早く明けよと願ふより外にねがひもなき床の上
悲しみが來て骨かぢるその響うつす即ちわが歌はなる
いき死は一つのものゝ別の名といひしことはあり思ひしはいまだ
悲しみは悲しみを呼び悲しみは悲しみを訪ひ吾れに集まる
弓町の友の蝸牛よいまも猶昔のゆめを殻に負へるか
護國寺の壁の樂書見るごときすき心もて成る歌にあらず
白蟻に心をはまれし大木の倒るゝごとく吾横たはる
何事も見るにつかれて目を閉ぢてあれども暗に招くまぼろし
〔上の左の写真〕 著者病やゝよき頃の肖像と自讃
流れゆく雲の一つに跨りて炎の中の我が家を見る
磁石の針ふり亂さんは無益なり磁石はつひに北をさす針
ふるさとにかへりし君の安からんこの言葉きゝ涙流るゝ
いくとせの前の落葉の上にまた落葉かさなり落葉かさなる
南極の探撿船よ新しき世界を見いで我を救へよ
骨は父に肉は母にと返すときそこにのこれる何物やりや
釋迦にゆきクリストにゆき追はれたる汝は野らの土にはらばへ
徒らにクリストをよび釋迦をよぶ三千年は遂にかへらず
時として高きに登り見るとせよ汝の外に物もこそあれ
月も見ず花も見ずまた靑筋の額に立てる人の顔も見ず
武庫河のかはらの石はましろなる炎をたてゝ燃ゆる夏の日
木枯や大海も泣き山も泣く君がむくろを土に蔽ふ日
病人は顔をしかめて藥のむ元三の日もきのふの如く
忘れては病かなしむ歌もかく硯の水の若水をもて
家隆の朝臣が骨を埋めたる夕陽丘に吾病えし
いつとなく悲しきことにならされて人に語れば人ぞまづ泣く
干からびし我が血を吸ひていきてある虱は更にあはれなるもの
盗人猫魚をぬすみてとびこゆる垣根にゆらぐ小てまりの花
(以下明治四十四年臨終まで)
いにしへのかしこき人も我がごとく病みて我かごと歎かずかあらん
今の世に文珠殊利なし憶良なし病むべき時にあはざりしかな
人のため流るゝ涕のこるかや我もたふとし尚生きてあらむ
何故に猶生くべきかゝることを思ひつゝあり蠅の飛ぶ見て
風ふけば松の枝鳴る枝なれば明石を思ふ妹と子を思ふ
思ひ出の二つ三つ 平木白星 〔下は、その最初の部分〕
前田翠渓君は音楽に多大の嗜好を有つてをった。天才もあった。殊にヴァイオリンが得意で、彼の作曲も決して凡庸ではあらなんだ。doが高いのかmiが低いのかさへ知らぬ私が、自分の作詩にデタラメの節調をつけて歌ふとすると、内発的だとか印象的だとか勸勵して、彼は即座にそれを音譜に構成して呉れるのが常例で、私の拙い詩も曲を附けた為呼吸づくやうになったのが少なく無い。『歌劇富士』『機おり唄』『国歌』『羽衣』『星となりて』『嵯峨野』なぞがそれだ。その中の二三は既に青年会館や中央会堂に於ける朗読会の公開場で、作曲者自身なり私なりが吟唱を試みた。明治三十九年頃私は『復活』(發市せし時の題名は『耶蘇の恋』)『釋迦』と共に三部曲の一として『マホメットの死』と題するオペラの『リブレット』めくものを書いた。彼は其に作譜しようとして手許に置いてあったうち、『衷心から溢発した生力の律呂でなければならぬ。』とて、作興の燃焼を待ちつゝ、その序曲の二分の一をも了へず、夕陽丘高等女学校の教授として大阪へ赴任する事となった。
翠渓歌集の後に 矢澤邦彦 〔下は、その一部〕
君が彼の新派和歌の流れに第一に飛びこんだ事は君が永久の名の爲めに全然利益であつたかどうかは知らぬ。併し當時の高踏的な唯美主義の態とらしい作風に對して君は少なくとも二つの利器を有つてゐた。一は音樂的天賦で一は爛熟した京阪都會趣味の理幹である。君を理解するに京大阪を忘れてはならぬ。二千年の歴史の蓄積を背景として君の初期の詩歌は初めて充分の意味を發現して來る。鐵幹晶子のそれが其通りである樣に。
君の音樂的才能が音樂家として何處まで發展したかは私には明言することが出來ぬ。韻文朗讀會に天野初子と合唱したなどが社會の表に現れた最も晴れの事であつたらう。又樂曲又は唱歌作者としての才能とても後年不治の病に呻吟して是非なく生活の奴僕として之を軀使するに至るまでは殆んど目に立つほどの結果を生み出さなかつた。
けれども朝起きるから夜寢るまで物を言はぬときは終始何をか歌つてゐた君は、詩でも文でも何を作る上にも知らず知らず音樂の助を受けてゐた。私は君と一處に過した三年間、君の詩歌のどの一つでも何等か其折々の譜曲口調に乗せられて音樂的彫琢を受ける事なく出來上つたのを見た事がない。さればこそどんなに間違つても蕪雜生硬などといふ批難をば取ることが出來なかつたのだ。遊戯道樂と今の人は云ふかも知れぬが流暢な明快な透明な純正な作風は慥かに君の音樂的天賦によつて作り出されたものであつた。
「葛原滋」「佐佐木信綱」この二人の名は晩年の君に最も深い印象を殘したに違ひない。君の短歌は「心の花」に、君の歌詞は色々の雑誌や出版物に絶間なく載る樣になつた。小供の爲めの気輕な気の利いた小曲は幾個となく成つた。君は此等によりて辛じてパンを得られた。
東京時代はむしろ長詩に重きを置いてゐた藝術の爲めの藝術時代。大阪時代は最も特徴のない時代でまづ低徊時代とも言ふべき時。郷里時代が最も徹底した人生の爲の詩歌時代。かう明瞭に作物の上で區別せられる。出來るならば此三時代を區別して世に公けにしたい。
唐錦赤い地は皆戀の花、最後にポタリ本當の血が。
君の一生を私は此一首の中に見る。君の詩歌の變遷も亦其歌で蓋ふことが出來る樣に思ふ。此歌集を讀む人もどうか君の本當の血の赤さを見逃さぬ樣にして欲しい。
哀しき一束の書簡 葛原滋 〔下は、その一部〕
はからずも、その人に接近する時が來た。大塚音樂會の聲樂練習の折であった。今の高師教授文學博士神保君が、オルガンを弾いて、「鶯のうた」(ハラー作曲。のち『中等教育唱歌集』に出づ)の練習があつた。ソプラノとバスとには唄ひ手が多かった。テノルは、六しいといふのでか人は少かつた。神保君は弾くのをやめて、「テノルが弱いね」とオルガン越に謂つた。するとソプラノから、進んでテノルに入って、大きなつ聲で、「ケキヨ、ケキヨ」と、うたつた人ーそれが美男の、わが翠渓兄であつたのである。左手に譜本をもち、右手を自然に垂れて、細い指で、ヅボンをうちゝタイムをとつて、大きな聲で、ケキヨゝとうたふのであつた。それが、わが純孝兄、その唱歌作者であつた。その頃の私は、驚いた、畏敬の念を強うした。君の直ぐ後に立つて、バスを歌う筈の私は、まだ歌へぬ私の、タイムにあはぬ節を、君に聞かれたくなくて、たゞ、後から君の、気持よくタイムをとる手の指を見て、只立った。
それと前後して、正午の大食堂で、オルガンで六段を弾くものがある。巧に弾く。明暮琴の音の中に大きくなつた私は、オルガンで六段をきくのを、珍しく欣び、夕々の食後には、只耳に知るそのメロデーを辿つて、苦心して、遂に完全に弾ける様になつた程の親しみの六段である。多くの校友も六段の、はじめ一段位は、まごつきゝ弾くものも多かつたが、その時の六段は、すらゝときれいに弾かれた気持よさ。立ち上って見ると、それは翠渓兄であった。食パンに砂糖をつけて牛乳を飲むのが流行してゐた頃の、食堂に、私は立上つて、欣んだ。甘い、柔かな、色も平和なミルクの中食時に、君の六段をきいて、心はおどらざるを得なかつた。同級の一友は、翠渓兄と師範時代の同窓だといふので、紹介して呉れようといだつた。しかし、紹介されたのは、よほど後であった。其までには、幾度か君と相見た。幾度か同じ室で相うたった。
著者の年譜
明治十三年四月三日 但馬國美方郡諸寄村六十一番地にて生まる。父は純正氏、母はうた子。
四十五才のとき、うた子、故を以て前田家を去り高村氏に嫁ぐ。純孝氏は祖母に養はる。
明治二十年四月 鳥取市に赴き叔母の家に寓し、鳥取県師範學校附属小學校に入る。
明治三十年七月 兵庫縣より小學校の准教員の免許状を受く。
同 九月六日 美方郡諸寄尋常小學校准訓導となる。
明治三十一年四月 兵庫縣師範学校(御影師範學校と改稱)に入る。
明治三十四年 痔を病んで約一月病院生活を送る。
明治三十五年 師範學校卒業と同時に東京高等師範學校に入學在學中同級生を集めて鼎會を作りて短歌を競作し、又明星の社友として毎月作物を掲載す。
明治三十七年 前田林外氏等の白百合の社友として大に盡力す。
明治三十九年四月 高等師範卒業と同時に大阪府島之内(後に夕陽丘)高等女學校に教頭として赴任。
同 八月 歸省途次発病、肋膜炎にて十月まで欠勤。
明治四十年 三月 秋庭信子と結婚。
明治四十一年 美津子生る、夫人信子産後の肥立よろしからず。
明治四十二年二月 又々肋膜炎。 五月 味原池のほとりより住吉に轉地療養。
素人目には快方の如く見えたれど、佐多博士は、肺尖カタルに罹りゐたりといふ。一日に一里も散策出来、肉もつきしに、梅雨に入りてより元気食慾共に減退、七月喀血、少量なれど衰弱す。
同年 十月 佐多博士の診察ー左右とも肋膜炎を患ひをり、肛門にも痔核あり、膓結核の疑もあり、十中八九難治。
校長などは歸國を勧められたれど、人の壽命は解らぬものゆゑ、充分療養させたしとの夫人の希望にて、明石なる夫人の里家に轉居。
明治四十三年五月まで よくもならず悪くもならず。夫人の病のため、五月十四日、但馬へ帰る。
同年 六月二日 膓出血、のち稍佳良。時々喀血す。
病間筆をとり歌を賣って、藥餌を買ふ。
日々の生活を、短歌に作りて日記に代ふ。
明治四十四年一月 乳母の家に移居。半歳あまり、大に心和ぐ。
明治四十四年九月二十五日 遂に起たず。但馬に葬る。年三十二。
大正二年八月十五日發行 (非賣品)
著者 前田純孝


翠渓歌集
序
指折り數へれば、もう一昔にもなる、東京高等師範學校の教室に、予は日々前田君を見たのであつた。其時の印象は今もなほ鮮やかに殘つてゐる。あまり濃くはない眉が長く曳いてゐて、眼の涼しい、唇のいかにもいゝ色をした細面に才気の溢れた人であつた。教課とした英吉利の詩文を予が購讀する時、君が會心の章と覺ぼしい條に來ると、その濕ひのある眼中に夢見るやうな影の浮ぶのを度々見受けた。藝術の愛を持ちうべき人かと、其折に予は推察したが、既に君が短歌を詠じ、音樂に親んでゐられた事は、まだ少しも知らなかつたのである。其後數年にして君の抒情詩を讀み、また樂會の爲に曲譜を供する事などを聞いて、噫、君も亦終にあの光榮ある而も危險の多い藝術の道を行くのかと心密かに頷いた。
明治新藝術の途上には幾多の薄命な才人等の手に半築き上げられたのみで、その儘に棄て置かれた多くの事業がある。地覆の一部、平臺の斷片がかなたに横はり、迫持の片割、圓柱の破片、半仕上げられた蛇腹、搏風などのこなたに散らばつてゐるが、是等は皆藝術の愛ある人々が、自から生得の傾向に驅られて着手した業でもあるが、ひとつにはまた當來の偉觀を豫想して、自身等は唯夢にのみ見て果つ可き藝術殿の建立に努力した結果である。哀いかな、神々の愛する者は夭折する。かゝる藝術の先軀者には不幸短命の人が多い。前田君もまた其一人であつた。
福祿の報無く、名聞の光も薄く、やゝもすれば窮迫し、輕視せられて、無用有害の人物と評せられる藝術の士は、現代日本の如き社會に居て、永く其信じる處を保つのは難い。而もあらゆる不利を顧みずに、この道の愛に專らなる人々の、絶えず、相次いで、其唱へる所の思想、其感じる所の情調が、やうやく一世の基音となりかけて來たのが、現今の形勢である。藝術の中殊に文藝は學術よりも道徳論よりも、又、固定宗教よりも、更に痛切にしみじみと人心を動して、新しい文化の基礎を置かうとしてゐる。而して其傾向は表面上、或は矛盾する如き觀を呈する場合もあらうが、根本の情調は、自から窺ひ知られる。それは抒情詩に表はれた恐ない誠實の気と微妙な多感性とである。姑息偸安を厭ふ事また形式に拘泥する遅鈍な思想に安じない點が、今の人々の特色であるが、前田君の遺作は這般の消息をよく傳へてゐるので明治末期の新情調を後世に示す一文書としても、此集は頗る價値多いものである。その上にまた集中の佳作は、薄倖の短生涯に作られたにも拘らず、例へば、莊麗なる繪樣大間の浮彫、端正なる大斗の装飾に似た秀逸であつて、天もし君に壽をかしたらば、いかに美しい藝術の宮殿が大成されたらうと思はしむるにつけ、この哀悼の情は、ますます此集の美を加へる。曙と夕暮との美を兼ねてゐる此集よ。
大正二年七月 上田敏
明治の終末に余と曾て詩社を同じくした二人の友が共に肺を病んで亡くなつた。前田翠渓君と石川啄木君。
二君はその資性も職業もちがつて居たが、その短い生涯の思想の經過は太略似て居た。理想主義の憧憬から現代主義の苦悶へ。そのうへ、病を得てからの境遇が同じやうに悲惨を極めて居たのは、之を言ふに忍びない。
生活意志の熾烈な現代の青年が、生の藝術、動の哲學の創作せられる時に會ひながら、
「幾とせの前の落葉の上にまた落葉かさなり落葉かさなる。」
如此き悲痛とは、どんなであつたらう。
啄木君は、負けぬ気の勝つた貴族的な気質から、口を少し歪めて、冷い苦笑に之を撥無しやうとあせつたが、翠渓君は、醞籍な田園風の性情から、宇宙自然の律のまにまに我を任せて、静かに之を諦めようと努めた。
「磁石の針振り亂さんは無益 むやく なり、磁石は終に北を指す針」
さうだ、二君は終にその焦燥と努力との無益なるあなたに消えてしまつた。予は之を他人事 ひとごと と思はない。さきに啄木遺稿に接し、今この翠渓歌集を讀んで、二君が留めた哀歌の眞實の教に粛然として心の凍るを覺える。
ああこの一卷、まことに故人が蒼白い手と黑ずんだ血とを以て、自己の癒しがたい痛恨をしるした堕涙の碑であるのみならず、心に幽暗の痼疾ある予の如き者のために、更に行手の大濛を示す哀しい路標ではないか。
大正二年七月
よさのひろし
序
生あるものは必ず死あるは、世の掟とはいひながら、年若き才人の早世ばかり、悲しむべきはなし。殊に文學の士に於て然り。そは彼等の場合に於ては、或は激切なる感情、或は生活の苦など、彼等が地上に於てそのすぐれたる才をうけ得つる負擔として、殆ど有せざるを得ざる苦しびの伴ふをならひとすればなり。我が前田純孝君の如き、實にその一人なりとす。
君は志すところ教育者たるにありて、はやくより小學教育に従事し、高等師範學校を卒業せし後、大阪島之内高等女學校に教頭たり。三十餘年の短生涯の事業は、主としてその方面にありき。しかも君が天賦の才と、君が境遇と、君が病とは、君をしてむしろ詩人たらしめき。教育者たる君は、他に説く人あらむ。予は詩人としての君に就いて一言せむ。
君夙く和歌を嗜み、高等師範學校在學中、已に雑誌明星に投稿し、新詩社の社友として、當時文壇の一新運動に關係せり。のち、雑誌白百合のおこりし時も、大に力を盡し、その間詩作をたゝざりき。高等女學校赴任後は、専心教育事業に携はりて、しばらく和歌に遠ざかりし觀ありしが、明治四十一年、病をえ職を辭してより、再び詩人たる本來の面目にかへりぬ。それより世を終ふるに至る三年間は、專ら詩作につとめし時代にして、衣食の計は、君をして病軀をかりて筆を執らざるを得ざらしめしとともに、この間の精神上境遇上の苦悶奮鬪は、君をして幾多悲痛の作あらしめたり。而して予が君を識りしは、この晩年のことにして、君の親友葛原𦱳君の紹介により、君の作品論文等を、我が竹柏會の雑誌心の華に載することヽなりしより、たえず書翰の往復をなしたりき。
君が和歌をみるに、夙く新詩風の影響をうけ、殊にその學素をなして辭句純正、優に一家をなしゝが、その歌風のいよゝ輝く異彩を發輝し來りしは、晩年のことに屬す。君が病の爲に職を去りて、衣食の道に苦しみ、世路の險しきに戰ひ、惨憺たる境遇の中に詠み出でつる幾多の作品は、感情の痛切なる、その發表の自然純直なる、千古のもと人をして泣かしむるに足る。而してその間自ら和歌の爲に一新歌風を拓けるものあり。
君が病と、君が悲惨なる境遇と、君の爲に眞に悲しむべしといへども、これありて君をしてその晩年の一進境あらしめたりとせば、また些か慰むべからずや。而して君が早世はた、決して無意義ならざるをおぼゆ。况して生れながらの詩人たりし君自らに於てをや。
このたび君の遺友相はかりて、君の爲にその遺稿出版の擧あるに當り、生前のちなみによりて、その選擇校閲を遺友諸氏より囑せられ、こゝにその事を了へ、この一卷を成しつるにのぞみ、いさゝか思ふところを卷のはじめにしるしつ。
大正二年六月 佐佐木信綱識
天地 あめつち もかなしかりけり若き子の死にたる後の歌におもへは
たくひなき悪夢を見つゝこの君はやかて覺 さ めすもなりにけるかな
この君は何をたのみし妻か子か悲しけれとも一卷の歌
若き人はやく世になしその歌はしら玉のこと後をてらせと
夏の雨純孝の君のありし日の病のころのはなしなと聞く
與謝野晶子
〔上の中の写真〕 明治四十年の著者
翠渓歌集 故前田翠渓著
〔各頁には短歌三首が掲載されている。下はその一部。〕
狗のごと君が門べを追はれては狗の如くも野をさまよへる
たゞひとり寂しき國にのこされて小指かみても染むる名のなき
憎き人を猶にくみ得ぬ心には戀しき人を戀ひずしあるべし
忘れても戀ひする人となるべしや戸に立たざれば打たれじを狗
指すところ皆わが道と行かん身か花ある方を唯行かん身か
名も知らぬ遠き國より唯一人大口たのみて我まよひこし
我をおきてまた賴まるゝ誰ありや人は人のため我ぞ我が爲め
かくて行かば花野あるひは消えうせんふりかへりてか人のさと見る
いつの世か我を見知りさびしみと石にもたれて泣くに似たる日
(以上明治三十六年作)
二千年三千年の御佛が訪ひもくる夜と奈良は雨降る
ひとり立てば我も佛となりぬべし額にしみくる黙示二千年(法隆寺金堂にて)
人麻呂がまなこに染みし星一つ得ばや足らんとまた來にし寧樂
月の中 ち の山の一つが落ちて來て圓きに似たり若草の山
若草にのぼりて今の奈良は見ず聖武がしら咲く花の御代
佛よぶ鐘か人よぶ戀の鐘きみまつほどの黒谷の月
かりそめの京の土産の京扇我ならなくに似たる歌筆
君が手の牡丹の花にうたれなばうたれて消ゆるほどの罪をば
(以上明治三十七年)
蝸牛葡萄の蔓の幾曲り曲り行きなば春の日暮れむ
君と我れ同じ垣根の卯の花を見て育ちたる故里の家
我が戀は古事記の神のことごとを招じてとへどいさめぬごとし
雨だれの音と椿の落つる音と君が怨と居睡りによき
圓光を脊負ふと燃ゆる火の中に思ふといづれ君にうれしき
生れいでゝ死なばつとめの足るごとく悲しといひて泣けば和 な ごみぬ
わが神はふたゝび燭を手に取りてまた一線 すぢ の道てらしけり
君ならぬ人にまじらひもの言ひて笑ひとぼけて世は有るらしき
ことゝはむかゝるおもひも花守が夢におちては花とひらくや
(以上明治三十八年)
地に伏して乳呑兒のごと泣きもせばあるひは母のかへり來まさむ(母を失へる友に)
いらか越えていらかいろする茅渟の海をけふも見て居ぬ蝸牛と我と
忘れては君がまぶたを拭はんと思ひもみたり濡れし袂に
一人してかなしき思二人してうれしき思君しりますや
いつよりかゆゝしき心みづからをなみする心君得てしより
思ひ出のその花園にかくてたゞ一人しあらんわれや花守
何佛か御名はしらねど出現の圓光たるを疑はず虹(大阪へのかへるさに)
過ぎし世はまなかひ去らぬまぼろしの夢のくさりよ我いましめの
幾度か死ねよとおもふ夕まぐれ悲しきにこそよみがへりくれ
ふとさめて聞けば木さけび石もなく今世か亡ぶ大風の夜半
過ぎし日のその悲しみか來む明日のおそれの影か呼びぬ追ひ來ぬ
粉藥 ふんやく の水のあまりを根にすひて咲き出し花の大和なでしこ
君をおもひ涙する夜となみだせぬ夜とある我をうたがひにける
ひたすらにうすき命のともし火をかゝげてたどる思ひす病
永久の黒き鎖につながれし明日の捕虜と見てや日暮るゝ
(以上明治三十九年)
我今はいそがずおめず顧みず與へられたるぬかるみを往く
人の世に何すとて來し瓦斯燈の大路に長くひく我の影
路にちる桐の花ほめ風をほめあらぬこと言ひて別れけるかな
かりそめの別のやうに別れつる二人の中をふく秋の風
諏訪山のみちけはしみか諏訪山の木かげ暗みかわが手とる君
天地に君あることを忘れたるその一瞬に我は死ぬべし
君をおもふ我をはたおもふ君我の二人の中のいとし兒ぞこれ
汝をえて汝が父母は靈魂の不滅を信じ涙流しぬ
いとし子よ汝を抱くとて父母は相爭へりいつれ選ぶや
君とわれ二人ながらの一生の日とてえらびしけふなりしかな
憎き人を猶にくみ得ぬ不可思議を我なるものゝうちに見むとは
しばらくは無言にありき後れ毛のひとり波うつ君が頬を見て

來薰閣書店新書目錄
羅雪堂先生●印書
殷虡書契後編二卷 羅振玉 一 册 二十元
殷虡書契菁華一卷 羅振玉 一 册 二元五角
增訂殷虡書契考釋三卷 羅振玉 二 册 六元五角
殷商貞卜文字考一卷 羅振玉 一 册 六角
鐵雲藏龜之餘一卷 羅振玉 一 册 一元六角
殷虡文字類編十四卷 羅振玉 六 册 十元
集殷虡文字楹帖一卷 羅振玉 一 册 八角
集殷虡文字楹帖彙編 羅振玉 一 册 二元五角
夢郼草堂吉金圖三卷續編一卷 羅振玉 四 册 四十元
高昌壁畫菁華一卷 羅振玉 一 册 九元
鳴沙石室佚書 羅振玉 石印本 四 册 十八元
鳴沙石室佚書續編 羅振玉 一 册 五元
鳴沙石室古籍叢殘三十卷 羅振玉 六 册 六十元
墨林星鳳三種唐太宗溫泉銘 柳公權金剛經 一 册 十元
歐陽詢化度寺碑
古文尚書殘卷 一 册 二元八角
六朝寫本禮記子本疏義殘卷 日本早稲田 一 册 一元五角
大學藏
原本玉篇殘卷 一 册 四元四角
又一種 一 册 四元
古寫本史記殘卷 一 册 二元八角
古寫本世説新書 存第六卷 一 册 三元四角
古寫本文選集注 十六册 十五元
古寫本涅槃經悉曇章 一 册 五角
古寫本悉曇字記一卷 唐智廣 一 册 八角
影宋本景祐天竺字源六卷略抄一卷 四 册 十五元
殷虡書契待問編一卷 羅振玉 一 册 一元八角
秦漢瓦當文字四卷 羅振玉 二 册 六元五角
古明器圖錄四巻 羅振玉 一 册 十四元
續百家姓印譜 呉大澂 一 册 三元五角
隋唐以來官印集存一卷 羅振玉 一 册 四元四角
歴代符牌圖錄二卷 羅振玉 一 册 二元二角
四朝鈔幣圖錄一卷 羅振玉 一 册 六元五角
貞松堂唐宋以来官印集存一卷 一 册 八元
凝淸室古官印存二卷 羅振玉 二 册 五元五角
漢晋石刻墨影一卷 羅振玉 一 册 二元八角
六朝墓誌菁英十八種 羅振玉 一 册 五元五角
六朝墓誌菁英二編 羅振玉 一 册 五元五角
石鼓文考釋七種 羅振玉 一 册 六元六角
天發神讖碑考一卷 呉玉搢 一 册 一元二角
樂毅論考一卷 翁方綱 一 册 五角
宏農冡墓遺文一卷 羅振玉 一 册 三元
西陲石刻錄一卷 羅振玉 一 册 一元七角
楚州金石錄一卷 羅振玉 一 册 一元二角
兩浙佚金佚石集存一卷 羅振玉 一 册 五元
蒿里遺珍一卷附考釋 羅振玉 一 册 三元
金石萃編校字記一卷 羅振玉 一 册 六角
金石萃編未刻稾三卷 三 册 三元五角
蜀石經殘字一卷 一 册 三元四角
芒洛冡墓遺文二卷 羅振玉 六 册 六元五角
鄴下冡墓遺文二卷 羅振玉 一 册 三元
四校昭陵碑錄三卷補一卷 羅振玉 一 册 一元七角
中州冡墓遺文 羅振玉 一 册 二元二角
東都冡墓遺文 羅振玉 一 册 二元二角
唐拓化度寺 敦煌石室本 一 册 二元二角
雪堂磚錄四種四卷 羅振玉 四 册 二元二角
蘭亭十三跋 珂羅版精印 一 册 五元五角
水拓本瘞鶴銘 羅紋紙印 一 册 五元五角
宋拓本王先生碑 孫北海舊藏羅紋紙印 一 册 六元六角
海内孤本宋拓郎官廳壁記 羅紋紙印 一 册 五元五角
宋拓越州石氏帖 羅紋紙印 一 册 五元五角
夜雨楚公鐘 全形影印本 一 幅 三元四角
漢晋書影 六吉棉連印 一 册 二元二角
智永眞草千文眞跡 六吉棉連印 一 册 五元五角
趙文敏公虞文靖公法書 六吉棉連印 一 册 四元四角
元八家法書 六吉棉連印 一 册 四元四角
明呉門四君子法書 六吉棉連印 一 册 五元二角
祝京兆法書 六吉棉連印 一 册 三元四角
文待詔書離騒九歌眞跡 六吉棉連印 一 册 一元
昭代經師手簡 一 册 二元五角
昭代經師手簡二編 一 册 四元四角
二十家仕女畫存一卷 一 册 九元
雲窗叢刻十種 十 册 二十元
雪堂叢刻五十二種 二十册 十二元
吉石盦叢書初集 六 册 九元
吉石盦叢書二集 七 册 十元
吉石盦叢書三集 五 册 八元
吉石盦叢書四集 六 册 九元
宸翰樓叢書八種 八 册 十元
玉簡齋叢書初集十四種 八 册 六元五角
玉簡齋叢書二集八集 十二冊 八元八角
孴古叢刻十種 十 册 四十元
影北宋齊民要術殘本 一 册 十四元
影宋刻唐三藏取經詩話 一 册 二元二角
明費信星槎勝覽二卷 天一閣藏明鈔足本 一 册 二元二角
星槎勝覽 一 册 五角
内府寫本石渠寶笈三編目錄 三 册 三元五角
王石臞先生手稾本羣經字類 一 册 一元
王子安集佚文 羅振玉 輯 一 册 一元二角
臨川集拾遺 羅振玉輯 一 册 一元
手稾本浣花詞 査容手寫本 一 册 五角
河東君傳一卷 顧苓手寫本 一 册 三角
雪堂校刊羣書叙錄 二 册 三元
面城精舎雜文二卷 羅振玉 一 册 六角
番漢合時掌中珠殘本 即西夏字典 一 册 三元四角
西夏譯蓮華經考釋 羅福成 一 册 八角
毛詩草木蟲魚疏 陸機元恪 一 册 一元五角
毛鄭詩斠義 羅振玉 一 册 一元二角
明季三孝廉集 十 册 八元
徐俟齋先生年譜 羅振玉 一 册 一元五角
萬年少先生年譜 羅振玉 一 册 一元二角
朱笥河年譜 一 册 六元
空際格致 高一志 一 册 一元二角
平津舘書畫記 陳宗彝 一 册 一元二角
永豐郷人稾八卷雜著八卷雜著續編九卷附錄一卷
羅振玉 十 册 十四元
續彙刻書目附閏集 羅振玉 八 册 七元
三部經音義四卷 信瑞 一 册 二元
制錢通考三卷 唐與崑 一 册 一元八角
影宋本草窗韵語六卷 周密 一 册 九元
敦煌零拾 一 册 一元
新疆圖志一百十六卷 三十二册 六十元
新疆圖 二 册 十六元
史料叢刊初編二十二種 内閣大庫鈔出 十 册 七元五角
古寫原本貞觀政要卷五殘卷附佚篇一卷 一 册 一元二角
六
帝範二卷臣軌二卷 一 册 一元二角
北宋元豐寫本乾象新書卷三 一 册 一元
四
魏書宗室傳注六卷附表一卷 羅振玉 四 册 三元八角
話雨樓碑帖目 王楠 一 册 一元四角
粤西得碑記 楊翰 稾本鉛印 一 册 一元
食醫心鑑 稾本鉛印 一 册 一元
雪堂藏古器物目 羅振玉 一 册 一元
蒿里遺文目錄 羅振玉 二 册 二元八角
江村書畫目 稾本鉛印 一 册 八角
唐折衝府考補 羅振玉 一 册 六角
四夷館考二卷 明人鈔本鉛印 一 册 一元
高郵王氏遺書 均未刻稾鉛印 八 册 七元
沙州文錄一卷 蔣斧 補一卷 羅福萇 一 册 一元六角
玻璃版精印宋拓汴學石經 一 册 四元四角
内府唐寫本王仁昫刊謬補缼切韵 一 册 二元八角
王静安遺書初二三四集 王國維 宣紙 四十二册 六十元
王静安遺書初集 王國維 影印本 白紙 十六册 七元
漢熹平石經殘字拓本 羅振玉藏 一 册 二十五元
漢熹平石經殘字集錄 羅振玉 三 册 四元五角
漢熹平石經殘字一二三四編 羅振玉 三 册 六元五角
漢熹平石經殘字集錄補遺 羅振玉 一 册 七角
貞松堂集古遺文 羅振玉 八 册 二十元
皇宋十朝綱要 明鈔本鉛印 六 册 三元五角
續宋中興編年資治通鑑 明鈔本鉛印 四 册 二元二角
國史列傳八十卷 二十册 十四元
國朝宮史三十六卷 十 册 五元五角
待時軒傳古別録 一 册 一元八角
紀元以來朔閏考六卷 三 册 三元四角
重校訂紀元編 白紙本 三 册 二元二角
重校訂紀元編 竹紙本 三 册 一元七角
博古頁子 一 册 一元二角
金文編 容庚 五 册 十元
雪堂所藏金石文字薄錄 一 册 二元八角
懐氓精舎金石跋尾 一 册 六角
古器物識小錄 羅振玉 一 册 七角
契文擧例 二 册 二元二角
增訂碑別子五卷 羅津鋆 二 册 四元五角
墨表 一 册 一元二角
振綺堂書目 稿本 二 册 二元八角
西夏官印集存一卷 一 册 二元二角
古璽漢印文字徴 羅福頤 八 册 九元
璽印姓氏徴 一 册 一元六角
敦煌石室碎金 一 册 一元二角
古文四聲韻五卷 夏竦 四 册 三元
洛陽伽藍記 如隠堂本 一 册 二元二角
金文靖公北征錄 明鈔本鉛印 一 册 六角
西遊錄一卷 一 册 四角
黑韃事略 鉛印抄本 一 册 四角
讀易草堂文集 一 册 一元二角
李商隠詩集 一 册 一元六角
方泉詩集 一 册 一元六角
壬癸集 一 册 三元二角
遼居雜著 羅振玉 二 册 四元五角
遼居稾 羅振玉 一 册 一元六角
遼居乙稾 羅振玉 一 册 二元二角
松翁近稿 羅振玉 一 册 一元七角
丙寅稾 羅振玉 一 册 一元六角
丁戌稾 羅振玉 一 册 一元六角
殷禮在斯堂叢書 十二册 十二元
北平瑠璃廠一八〇電話南局四〇九三
(中華民國二十一年七月印)










亦詩世界唱和集 庚申編
滿江紅 奉題亦詩世界 李遂賢
故里倉山幾度訪隨園遺迹空想像詩成世界琳瑯滿壁桂話貞元嗟已往名流壇坫欣重接羨而今百尺又高樓千秋亦 看變幻雲明密懐正始音沉寂且闌花階草商量容膝小醉偏宜風月友豪吟穏臥瀟湘雪算古今大隠在金門幽人宅
目録
古體
贈亦詩世界錬人 謝贈畫象 樊增祥
和樊山吟丈寵贈原韻 鍊人
題亦詩世界呈鍊人吟長 金銘人
和緘三詩友題亦詩世界原韻 鍊人
鍊人招飮亦詩世界集唐句奉謝 易克僕
集杜句答敦之吟友 鍊人
五律
琴三詩友賜亦詩世界序作此以謝 並序 鍊人
七絶
贈亦詩世界袁鍊人 樊增祥
和樊山吟丈寵贈原韻 鍊人
再集隨園句和樊山吟友 鍊人
〔略〕
七律
〔略〕
樊樊山先生肖像
易實甫先生肖像
鐵漢近影
鍊人近影
序一 林傳甲 〔下は、その一部〕
傳甲非詩人周游所至舟車所通得江山自然之助袁子毎錄登交通叢報自憾行李匆匆未能到處留題今亦詩世界唱和集褎然成冊爲第一集發刊
大中華民國十年一月二十日閩侯林傳甲謹序
序二 贈亦詩世界 陶鞠通 〔下は、その最初の部分〕
交通報社長袁君鍊人卜宅於都城東李靖胡同槏通於厊樓高以軒盍簪風雨詠觴昕夕曹君鐵漢顧而樂之謂鍊人之逸才踵隨園而繼起爰擷隨園中詩世界之名以名其樓曰亦詩世界既自爲之記
亦詩世界唱和集 巻一 庚申編
中華民國十年四月一日出版
非賣品
亦詩世界藏版
華明印書局代印

嗚呼紅葉尾崎徳太郎君
特製 K.KUWADA & co. IMAMIYA OSAKA
なお、この絵葉書とは別に、次の絵葉書が発売されたようで、明治三十七年一月一日発行の『文藝倶楽部』第十巻 第一号 博文館 の 時報 に下の記載がある。
◉紅葉祭
舊臘十二月十六日は、故尾崎紅葉氏の第三十七回誕辰に当り、且つは四十九日逮夜に相当するより永く氏を追慕するの趣旨依にり、友人其他文藝同好者の発起に催されし同会は、同日午後一時半より芝公園紅葉館に開催せられたり。来会者無慮三百名、巌谷小波氏開会の辞を始め、角田竹冷氏の追慕演説、岡田朝太郎、高田早苗、芳賀矢一三氏の演説を了り、観世清廉氏と丸岡九華氏の謡曲あり、継いて二階食堂に於て会食あり、食後猫遊軒伯知氏の講談「金色夜叉」、紅葉館美人の「和歌三神」川上一座の演劇「心の闇」等ありて散会したるは午後十時頃なりしが当日会場に於て頒布したる紅葉山人肖像入の絵端書は、非常の好評にて、午後二時頃は既に四百余枚を売尽し、漸次騰貴して一枚五拾錢の価を生じたるは鳥渡愛嬌なりき。因に曰ふ、此肖像は山人が露国の文豪トルストイ伯に贈らんとて、心を籠めて撮影し、山人自筆にて、露国トルストイ伯に贈ると書し、遂に其意を果たさゞりしを、大江印刷所に托して精巧に印刷したるものなりしと云ふ。
ヘレンケラー女史の面影
女史は、一八八〇年六月二十七日、北亜米利加合衆国アラバマ州タスカンビア町に生れ、生後十九ヶ月目に熱病で、一時に耳と目の両感覚を失つた。満七歳少し前に、アンニー・エム・サリヴアン嬢によつて、その言葉の教育が有効に行はれて、知識の戸門が開かれ、思想の発展又極めて顕著なるものがあつた。十歳に及んで口にて語らんとする強烈なる衝動にかられて、苦辛努力の結果、遂に発音発語に成功し、その全教育の進歩又、甚だ顕著であつて、世人をして驚嘆せしめた然るに女史の稀有なる好学心と向上心とは、初等教育に満足する所とならず、更に高等専門の教育に志し、困難なる入学試験を突破して、二十歳にしてラツドクリフ女子大学に入学し、四ヶ年の過程を見殊に修了して卒業の栄冠を與へられた。実に盲聾者にして、大学を卒業するに至つたことは、空前であつたのみならず、その後に於ける修養研鑽の結果、その思想の豊麗深遠なる、その徳性の円満崇高なる、蓋し絶後と称するも決して溢美ではなからう。嘗て米国の文豪マーク・トーウエン氏は、十九世記には世界的二大偉人が出た。それはナポレオンとヘレン・ケラーである。前者は剣を以て世界を征服せんとして遂に破れたか、ケラーは思想の力を以て、永遠に人類の大なる炬光となつたといふ様なことを言つたことがある。誠に然りである。
此の世界的の偉人、人類愛の戦士たるケラー女史は、昭和十二年春爛漫なる四月十五日、万里の波濤を越えて本邦に来朝せられ、邦人は親しく女史に接する機会を得た。時恰も新宿御苑の観桜御会の開かるゝありて、御召の恩命を賜はり、又高松宮御殿にも伺候を差許さるゝの光栄を蒙り全国民又空前の熱誠を以て女史を歓迎した。爾来女史は三ヶ月に亘りて、全国各地に於て講演を行ふこと七十七回、其他の会合に出席し、又四十校以上の聾学校及び官立学校を訪問して、所謂奇跡の声を発し、豊麗なる思想と温雅なる聖容を示し、日本国民に聖女の語を冠らしめるに至つた。女史は本邦における盲及び聾者の教育並に、福祉事業の発展に絶大の熱意と努力を以てし、口を開けば必ずやこの事に及び、その深厚絶大なる人類愛には、真に驚嘆と敬服に堪へないものがある。而も女史の高遠なる思想は、本邦民の崇敬する神社仏閣に詣でては、日本精神を体得すること無比たらしめ、又その鋭敏なる感覚は、美術工芸の優秀なる作品に接して、非凡なる心眼を以て之を鑑賞せしめ、吾人をして転た観賞おく能はざらしめて居る。
本写真帖は、女史の来朝を永遠に記念する為に、本邦に於ける女史の活動の諸相と、女史が本邦人の生活を満喫し、我が芸術を鑑賞する所の光景を、彷彿せしむるに足る、各種の写真十八葉を蒐輯したものである。
写真






・ポリー・タムソン女史 ヘレン・ケラー女史
・四月十五日来朝第一日の聖女【帝国ホテルに於て】
・徳川侯邸に於ける歓迎午餐会
・徳川侯邸に於て日本美術に陶酔する聖女
・徳川侯邸講堂にて‥‥【其の一】
・徳川侯邸講堂にて‥‥【其の二】







・古都奈良にて‥‥【其の一】 (主婦之友社撮影)
・古都奈良にて‥‥【其の二】 (主婦之友社撮影)
・主婦之友社長邸に於て (主婦之友社撮影)
・軍人会館に於て
・羽折を着てカナリヤを相手に悦ぶ二女史
・所・日比谷公会堂 日本音楽の鑑賞 【其の一】 弾奏は宮城道雄氏 (東京朝日新聞社撮影)
・所・日比谷公会堂 日本音楽の鑑賞 【其の二】 弾奏は吉田晴風氏 (東京朝日新聞社撮影)





・東京聾唖学校講堂に於て
・徳川侯邸講堂にて 【其の一】 (署名はケラー並にタムソン女史)
・徳川侯邸講堂にて 【其の二】
・徳川侯邸講堂にて 【三】
・七月五日日米国大使館に於て‥【右より廣田外相・聖女・米国大使・タムソン女史】

盲・聾・唖の聖女 ヘレン・ケラー博士とライト・ハウス
桃谷順天館奉仕部パンフレツト 「女性之光」 第三輯 昭和十二年 〔一九三七年〕 四月廿五日発行 昭和十二年五月三日三版 編輯兼発行者 桃谷勘三郎 発行所 桃谷順天館奉仕部 〔19.2センチ、本文10頁〕
見返し
「ヘレン・ケラー女史に託されたルーズベルト大統領のメツセージ」・写真「ルーズベルト大統領」
「三重苦」の聖女ヘレン・ケラー女史は三月二十五日午後五時半ニューヨークを出発、日本訪問の旅程についたが、出発にあたりルーズヴェルト大統領は特に次のメッセージを託した。
X X
女史今回の日本訪問より肉体的困苦に悩む日本人は不断のインスピレーションを受けることを確信する、さらに女史が今回の訪問で人道的事業に携はる日本人ならびに日本の各団体と親しく交際する結果、日米両国民の親善友好関係に寄与するところ甚大であらう、国家間の親善関係はつねに国民相互間の親善に依存するが女史は申し分ない親善使節としてアメリカ国民衷心からの挨拶を日本国民へ伝へられることを切望する
・「詩聖タゴール翁と語るヘレン・ケラー女史」

本文は、桃谷順天館編輯の「ヘレン。・ケラー博士小伝」他である。
〇盲・聾・唖の聖女 ヘレン・ケラー博士小伝
はしがき
父母のねがひ
サリヴアン女史
当時、電話の発明家として世界に名声を轟かしてゐたグラハム・ベル博士は、その老母が晩年に聾になつたために聾唖教育に多大の関心をもつてゐましたが、不幸な少女ヘレン・ケラーの話をきゝ、何とかして一人前にしてやりたいと思つて、かつてサミエル・ハウ博士が盲唖教育で尽粋されたので有名なパーキンス盲学校にその事を相談されました。そのしてその結果、同学校を卒業したばかりのアン・マンスフスキールド・サリヴアン女史がヘレン・ケラーの家庭教師として選ばれる事になりました。時にサリヴアン女史は芳紀まさに二十一歳、ヘレン・ケラーが七歳になつた春の事です。
かくて、サリヴアン女史は、七十歳にいたるまで、即ち昨年十月に長逝されるまでの約五十年間といふ長い歳月を、文字通りヘレン・ケラー博士のために全身を捧げ尽くしたのです。たゞ一人の不具者を教育するために、一生涯を捧げ尽したサリヴアン女史!何といふ尊い一生でせう!それであるだけにまたどんなにそれが難しい仕事であつたでせう!サリヴアン女史の努力は全く筆紙につくせぬものがありました
文字を知るまで
無形の物を知るまで
口で語るまで
栄冠を得るまで
全世界讃嘆の的
女史の信仰
むすび
〇ヘレン・ケラーを語る 〔一部省略〕
ルーズベルト大統領曰く
▲ヘレン・ケラー博士は盲聾唖の三重苦を突破して今日アメリカに於てゆるされたる学術の最高峰を往くのみならず闇に住む同胞のために日夜寝食を忘れ献身しつゝある事は実に驚嘆の限りである。彼女こそは『アメリカの国宝』としして推すべき存在である。
文豪メーテルリンク曰く
▲青い鳥を見出した女性!
ヘレン・ケラーこそは私の著『青い鳥』の中に秘められた幸福を見出した唯一の女性です。ヘレン。ケラーをおいてこの祝福を受ける資格者は他にありません。
文豪マークトウエン曰く
▲十九世紀の奇蹟!
十九世紀の奇蹟は不可能を可能にしたボナパルト・ナポレオンであり、今一人は盲聾唖の女性ヘレン。ケラーである。
山室救世軍中将曰く
▲神の力の活ける證明!
桑木文学博士曰く
▲懦夫を起たしむ!
〇ヘレンケラー博士を招聘せる ライト・ハウスとその愛盲事業 ライト・ハウス館長 岩橋武夫
〇ライト・ハウス館長 岩橋武夫先生
裏の見返しには、写真5枚がある。

① 指話するサリヴアン先生とヘレン・ケラー女史
② 幼き日のヘレンケラー女史とサリヴアン先生
③ 大阪中央公会堂にて講演中のヘレンケラー女史(右端)
④ ライト・ハウスの於けるヘレン・ケラー女史(向つて右よりケラー女史、トムソン女史、岩橋先生(写真③④は桃谷順天館奉仕部撮影)
⑤スピーカーに手を触れてラヂオを聴くヘレン・ケラー女史」がある。
裏表紙には、次の表がある。

ヘレン・ケラー博士日満巡講演日程表 (昭和十二年四月十一日現在調)
横浜 四月十五日 郵船浅間丸
臨時列車東京へ
東京 四月十六日 宮内省外務省米国大使館訪問
四月十七日 内務省文部省訪問
四月十八日 市民歓迎会
歓迎晩餐会
大阪 四月十九日
四月二十五日
東京 四月二十六日
四月三十日
横浜 五月一日 港記念館 二回
横須賀 五月二日 海軍下士官兵集会所
箱根 五月二、三日 静養
静岡 五月四日 公会堂その他
五日
名古屋 五月五日 公会堂 一回
六日 その他 二回
彦根 五月七日 高商
大津 五月七日 教育会館
京都 五月八日 朝日会館其他
五月十日
奈良 五月十一、十二日 女高師及休養
神戸 五月十三、十四日 海員会館他四回
岡山 五月十五、二十日 静養
五月二十一日 岡山公会堂其他
広島 五月二十二、三、四日 教育会館
下関 五月二十五日 梅光女学院
福岡 五月二十六、二十七日 九大其他 三回
長崎 五月二十八、二十九日 勝山小学校
雲仙 五月二十九、三十日 静養
熊本 五月三十一日 公会堂
六月一日
大分 六月二日
大阪 六月四日
六月七日
岐阜 六月八日 市公会堂
金沢 六月九日 市公会堂
六月十日
長岡 六月十一日 公会堂
新潟 六月十二日
秋田 六月十三日 二回
大鰐 六月十四日、十五日 静養
弘前 六月十六日
青森 六月十七日
湯ノ川 六月十八日 静養
函館 六月十九日
湯ノ川 六月二十、二十一日 静養
小樽 六月二十二、二十三日
札幌 六月廿四、廿五、廿六日 四回
盛岡 六月二十八、二十九日 二回
仙台 六月三十日 二回
七月一日
福島 七月二、三日
水戸 七月四日
日光 七月五、七日 静養
東京 七月七日
大阪 七月八、九日
朝鮮 七月十一、十七日 二回
満州 七月十八、二十四日
なお、七月七日、北京郊外の盧溝橋で発生した事件により、日中は全面戦争に突入した。

ヘレン・ケラーアルバム 岩橋武夫編 主婦之友社
ヘレン・ケラー アルバム 序 1948年3月 岩橋武夫
目次
出発にあたりて
タムスン女史と共に
一九三〇年当時のヘレン・ケラー
ケラー女史の両親と妹
北米アラバマ州タスカンビアにおけるヘレンの生家
レンサムにおけるヘレンの家
アニー・サリヴァンとヘレン・ケラー(一八八七年) (アニー二十一歳、ケラー七歳当時)
・十一歳当時のヘレンとサリヴァン先生
ナイヤガラ瀑布にて(一八九三年)
点字の読書をするヘレン(一八九一年)
インドの詩聖タゴールと語る(一九〇一年)
マーク・トウェインとヘレン(一九〇二年)
ヘレンが二十二歳の時であった。あるお茶の会に招かれて行ってみると、そこに文豪のマーク・トウェインに紹介された。このときトウェインは六十七歳であったが、ヘレンはそれ以来トウェインと大そう親しくなった。トウェインはその後ある雑誌に、『十九世紀に二人の大人物がこの世に生れている。その一人はナポレオンで、他の一人は、三重苦を突破してあらゆるものを征服したヘレン・ケラーである。』と書いた。
大学在学中のヘレン・ケラー(一九〇三年)
なつかしい自然(その一)(一九〇四年)
なつかしい自然(その二)
大学卒業を前にして(一九〇三年)
自然の美を(一九〇四年)
樹上で読書のひとゝき(一九〇四年)
グラハム・ベルと指話
『石壁の歌』(一九〇九年)
正装せるヘレン・ケラーのプロフィル(一九〇九年)
先生、そしてもう一度、先生
先生と指話するヘレン(その一)(その二)(その三)
サリヴァン・メイシー、夫君ジョン・メイシーと共に語る
ジョセフ・ジェファーソンと共に
時計を見るヘレン
カルソーの独唱を聴く(一九一五年)
イタリヤの生んだ世界的名歌手カルソーがヘレンのために歌っている。彼女はカルソーの唇に手をおいて、その妙なるテノールの旋律を振動によって聞き、鑑賞するのであった。
楽聖ハイフェッツのヴァイオリンを聴くヘレン・ケラー
遠乗り(一九一八年)
ハリウッドにて(その一)(一九一八年)
ハリウッドにて(そのに)(一九一八年)
弟と共に(一九一八年)
愛犬と共に(一九二二年)
幼き協力者(その一)(その二)
タイプライターを打つケラー
世界盲人大会にて
テンプル大学にて博士号を受く
悲しみを知る人の顔
ウェルズと共に(一九三一年)
評論家、歴史家として、『世界文化史』の著者として有名なエイチ・ジー・ウェルズは、ケラーについて次のように言っている。
『私はアメリカに行って最も驚くべき人物にあった。それはヘレン・ケラーである。彼女は、英、独、佛、伊、ラテン、ギリシヤの数ヵ国語を解して、世界の思潮に通じている。その見えない眼で、世の哀れな人たちの生活を見る。現代の不正と不義をも見る。即ち彼女は世界の涙を見ている。その聞えない耳で、人道の叫びを聞き、飢えに泣く幼児の泣き声を聞くのである。』と
グラスゴー大学にて博士号を受く(一九三二年)
遠き思い出(一九三二年)
芸術の世界(一九三三年)
愛犬と戯れるケラー
日本来朝のヘレン・ケラー(その一)
日本来朝のヘレン・ケラー(その二)
日本来朝のヘレン・ケラー(その三)
日本来朝のヘレン・ケラー(その四)
ヘレン・アダムス・ケラー年譜
昭和二十三年 〔一九四八年〕 七月三十一日発行


安政六年開業したる本邦最初の写真店全楽堂 〔上左の写真〕
Photographic studio first and foremost in Japan established at Yokohama by the late Renjo※ Shimooka by whom photography was first introduced into this country.
今日でこそ如何に不便な片田舎に行つても到るところ写真館の設けがつて、田夫野人の末に至るまでレンズの中の人となり得るのであるが、今から六十年前には我国に唯だの一軒の写真撮影所といふものはなかつたのである。然るに安政六年(大正六年を距る五十九年前)当時我国に於ける写真術研究の第一人者下岡蓮杖氏始めて一の写真店を横浜太田町に設立して人物撮影及び写真販売を開業し是に全樂堂と命名したので る。写真は当時其の全樂堂の外観を撮影したもので、富士山を象どつた看板や、“up stairs” と誌された案内書きに対照して江戸風の紺の暖簾の鬱陶しげに重く懸れる有様など、今日より是を見れば誠に興味ある光景である。
(東京浅草 二世下岡蓮杖氏寄贈)
本邦写真術の鼻祖故下岡蓮杖翁の撮影旅行振 〔上右の写真〕
Lake Renjo Shiomooka by whom the photographic art was first introduced into Japan taken at that time when he used to make a trip for photographic purpose, upper left being the photpgrapher in his last years.
写真術は独逸人シユルツエ氏が西暦一千七百二十七年銀鹽の感光性を利用して書画の複写を試みたのに始まり、次で一千八百二年英吉利人デーヴイ等是を研究し、爾来幾多の苦心を重ね、遂に一千八百七十一年英吉利人マツドツクスがジエラチン製乾板を発明するに及び大成の域に達したのである。而して此の技術が本邦に渡来したのは、徳川幕府の安政年間であつたが、当時邦人の多くは是を以て一種の魔術と見做し其の技を賞讃するといふよりも寧ろ恐怖の念を以て見てゐたから容易に流行しなかつた。然るに当時下岡蓮杖といふ人、長崎に出でゝ米国人の写真師に就き該技を修得し、あらゆる迫害に抗しつゝ是が開拓に従事し、遂に今日の如き斯道隆盛の源を成した。写真は明治維新前蓮杖翁が大なる撮影器械を背負ひつゝ今や採写に出で立つ有様、又左上は同翁晩年の肖像である。 (東京浅草 二世下岡蓮杖氏寄贈)
※ 0 の上に、- あり。
上の2枚の写真と解説文は、大正六年 〔一九一七年〕 十月一日発行の『歴史写真』 大正六年 十月号 第五十五号 に掲載されたものである。