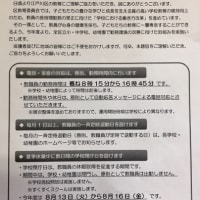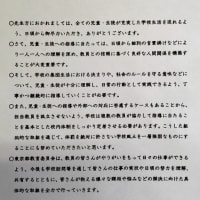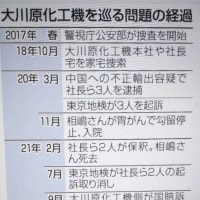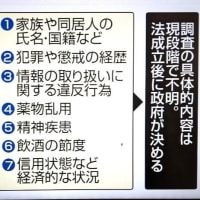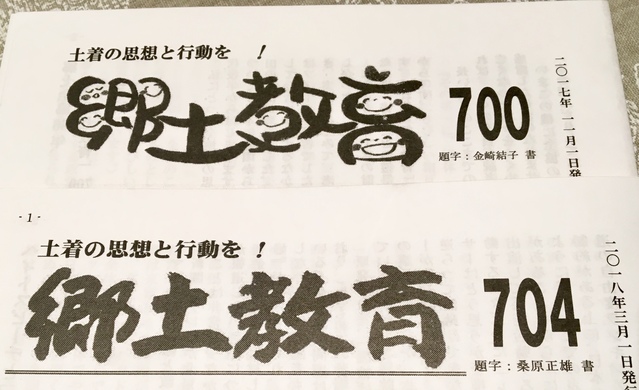7年目の3・11を前にして、3月10日飯舘村の酪農家だった長谷川健一さんの話を聞く会に参加した。
飯舘は、阿武隈山系の高地にある盆地、飯舘牛と花卉栽培の村、2010年「日本で最も美しい村」に選定、までい(手間暇惜しまず)の精神、村民参加、若い「嫁」達を海外視察に派遣など菅野典雄村長は意欲的な村つくりを実践した。
3.11原発事故で、放射能プルームは福島原発から北西40キロ離れた飯舘村に流れ降り、土壌は汚染された、村人は何も知らされず、浪江からの避難民の対応におわれ、高線量の中、宿泊の世話、炊き出しをしていたという。
4月22日計画的避難地区に指定され、6月末までに村民は退去した。
人望の厚かった菅野村長だったが、原発事故では、村人の命・健康より村存続を優先し、放射能汚染の実態を隠し村民避難に消極的だった。
全村民避難後も、役場の隣にある老人施設は継続、職員は避難先から通勤した。
2014年11月、村民の半数3千人が集団でADR(原子力損害賠償紛争解決センター)に申し立てをした。
「謝れ!償え!かえせふるさと飯館村」原発被害糾弾飯舘村民救済申立団の団長でもある長谷川さんは、「3年過ぎてなんにも解決されない、このままでは、ばらばらにされ切り捨てられてしまう、黙って我慢していたらいいようにされる。
裁判はやっぱりハードルが高いので、ADR申立賛同者を仮設住宅を回って呼びかけていった。
千人集まればいいと思ったら、どんどん参加者が増えて、村民の半数、約3千人が申し立てに参加した。村人は、みんな怒っていた」
2017年12月ADRは事故直後から3ヶ月で9~20ミリSV外部被ばくしたと推定される143名の村民に一律15万円の精神的賠償を提示した。
しかし、今年1月東電は拒否、「飯舘村民が逃げなかったのは、村の行政の責任。村人が、親の介護とか牛の処分等ですぐ避難しなかったのは自己責任」「20ミリSV程度の被ばくの危険性は科学的に証明されていない」といい、今まで支払った賠償で十分と拒否。
たった15万円の少額にびっくりしたが、その支払いをも拒否する東電。
家族同様に育ててきた牛の処分をめぐって時間がかかったって、そもそもなにゆえに、人生をかけた生業を停止せねばならないのだ。
ADRの申立を通して「東電と言う得体のしれない真っ黒なもの、その後ろに国家の存在をまざまざと感じた」と長谷川さんは言う。
3月11日NHKスペシャル「めざした『復興』のいま」で、飯舘村が取り上げられていた。
昨年3月31日に避難指示解除された飯舘村、田畑に除染土のフレコンパックが山積された風景が映し出され、菅野村長は、「人つくり、教育にまさる村つくりはない、一歩一歩村の再生をはかっていきたい」と笑顔で語る。
40億円をかけて子ども園、小学校、中学校を建設、75人が通学予定。
(昨年避難指示が解除され、今年4月から学校を再開する5つの町村でダントツ、どこも十数人、または一ケタ)、しかし通学予定の子ども9割以上が飯舘に戻っていない。
村は送迎車を手配し子どもを送り迎えする、その費用年間1億3千万円、給食費、教材費、制服代、遠足代など教育にかかわる経費は全額村の負担で、一人当たり200万円という。
他の町村では、住民の要望で避難先に村の学校を存続させるが、飯舘村は仮校舎は閉鎖し飯舘内の学校に通うように仕向けるようだ。
嫌なら、避難先の学校に転校。教育費用一切無償、本来ならすべての子どもにそうあってほしいが、そこまでして飯舘に戻そうとするのか、親は、子どもの健康リスクを心配しながら、線量の高い飯舘小学校通わせるだろうか?
ちなみに村長のお孫さんは飯舘小学校に通わないそうだ。
避難先から飯舘村内の学校に子どもたちをムリに連れ込んで被ばくのリスクに曝すーー本当に子どもを大事にしているのだろうか。
「人つくり」って村の人材養成なのだろうか、
長谷川さんの母親は、震災前は元気だったが仮設暮しの中認知症を発症、いまは施設に入所しているという。
もし、原発事故がなければ、住み慣れた広い家で土いじりをしたり、孫たちの相手をしたり穏やかに天寿を全うできたのではなかろうか。
息子たちと離れ仮設に残された70~90歳代は、仮設住宅は取り壊される、復興住宅に入れば家賃がかかるから、被ばくがあっても故郷に戻り暮らすことになるだろう。
村には食料品や日用品の商店がない、巡回商店が週に1回、各集落やってくる、でも高齢者にはそこまで行くのも難儀、医者は1週間に1回来る、薬局はない、一人暮らしの高齢者はどうやって生活をしていけるのだろう。
実際に村に帰還する高齢者のために生活環境を整えることが緊急の仕事だろうに。。
「飯館村は7割が山や森、山や森の除染はしない、出来ません。
放射性物質は風が吹けば山から飛んでくる、雨が降れば流れてくる。
だから、田畑を除染したとはいえ、飯舘で野菜を作っても消費者は買わない、当然です。
だからといって、故郷の田畑を荒れ地にしてしまうのは耐えられない。
自分が住んでいる前田地区で、所有者の6割が農地の管理は出来ないという。
仲間で耕作組合をつくって、請け負ってそばを栽培している。
去年収穫した蕎麦の放射能を測定すると17㏃/kgだった。国の100ベクレルの基準値はクリアしているが・・・」と悩ましげな長谷川さん。
3月11日東電本社前で、900人が集まって抗議行動があった。
「本当の復興は、被害者賠償」というコールがあった。
-Ka.M-
飯舘は、阿武隈山系の高地にある盆地、飯舘牛と花卉栽培の村、2010年「日本で最も美しい村」に選定、までい(手間暇惜しまず)の精神、村民参加、若い「嫁」達を海外視察に派遣など菅野典雄村長は意欲的な村つくりを実践した。
3.11原発事故で、放射能プルームは福島原発から北西40キロ離れた飯舘村に流れ降り、土壌は汚染された、村人は何も知らされず、浪江からの避難民の対応におわれ、高線量の中、宿泊の世話、炊き出しをしていたという。
4月22日計画的避難地区に指定され、6月末までに村民は退去した。
人望の厚かった菅野村長だったが、原発事故では、村人の命・健康より村存続を優先し、放射能汚染の実態を隠し村民避難に消極的だった。
全村民避難後も、役場の隣にある老人施設は継続、職員は避難先から通勤した。
2014年11月、村民の半数3千人が集団でADR(原子力損害賠償紛争解決センター)に申し立てをした。
「謝れ!償え!かえせふるさと飯館村」原発被害糾弾飯舘村民救済申立団の団長でもある長谷川さんは、「3年過ぎてなんにも解決されない、このままでは、ばらばらにされ切り捨てられてしまう、黙って我慢していたらいいようにされる。
裁判はやっぱりハードルが高いので、ADR申立賛同者を仮設住宅を回って呼びかけていった。
千人集まればいいと思ったら、どんどん参加者が増えて、村民の半数、約3千人が申し立てに参加した。村人は、みんな怒っていた」
2017年12月ADRは事故直後から3ヶ月で9~20ミリSV外部被ばくしたと推定される143名の村民に一律15万円の精神的賠償を提示した。
しかし、今年1月東電は拒否、「飯舘村民が逃げなかったのは、村の行政の責任。村人が、親の介護とか牛の処分等ですぐ避難しなかったのは自己責任」「20ミリSV程度の被ばくの危険性は科学的に証明されていない」といい、今まで支払った賠償で十分と拒否。
たった15万円の少額にびっくりしたが、その支払いをも拒否する東電。
家族同様に育ててきた牛の処分をめぐって時間がかかったって、そもそもなにゆえに、人生をかけた生業を停止せねばならないのだ。
ADRの申立を通して「東電と言う得体のしれない真っ黒なもの、その後ろに国家の存在をまざまざと感じた」と長谷川さんは言う。
3月11日NHKスペシャル「めざした『復興』のいま」で、飯舘村が取り上げられていた。
昨年3月31日に避難指示解除された飯舘村、田畑に除染土のフレコンパックが山積された風景が映し出され、菅野村長は、「人つくり、教育にまさる村つくりはない、一歩一歩村の再生をはかっていきたい」と笑顔で語る。
40億円をかけて子ども園、小学校、中学校を建設、75人が通学予定。
(昨年避難指示が解除され、今年4月から学校を再開する5つの町村でダントツ、どこも十数人、または一ケタ)、しかし通学予定の子ども9割以上が飯舘に戻っていない。
村は送迎車を手配し子どもを送り迎えする、その費用年間1億3千万円、給食費、教材費、制服代、遠足代など教育にかかわる経費は全額村の負担で、一人当たり200万円という。
他の町村では、住民の要望で避難先に村の学校を存続させるが、飯舘村は仮校舎は閉鎖し飯舘内の学校に通うように仕向けるようだ。
嫌なら、避難先の学校に転校。教育費用一切無償、本来ならすべての子どもにそうあってほしいが、そこまでして飯舘に戻そうとするのか、親は、子どもの健康リスクを心配しながら、線量の高い飯舘小学校通わせるだろうか?
ちなみに村長のお孫さんは飯舘小学校に通わないそうだ。
避難先から飯舘村内の学校に子どもたちをムリに連れ込んで被ばくのリスクに曝すーー本当に子どもを大事にしているのだろうか。
「人つくり」って村の人材養成なのだろうか、
長谷川さんの母親は、震災前は元気だったが仮設暮しの中認知症を発症、いまは施設に入所しているという。
もし、原発事故がなければ、住み慣れた広い家で土いじりをしたり、孫たちの相手をしたり穏やかに天寿を全うできたのではなかろうか。
息子たちと離れ仮設に残された70~90歳代は、仮設住宅は取り壊される、復興住宅に入れば家賃がかかるから、被ばくがあっても故郷に戻り暮らすことになるだろう。
村には食料品や日用品の商店がない、巡回商店が週に1回、各集落やってくる、でも高齢者にはそこまで行くのも難儀、医者は1週間に1回来る、薬局はない、一人暮らしの高齢者はどうやって生活をしていけるのだろう。
実際に村に帰還する高齢者のために生活環境を整えることが緊急の仕事だろうに。。
「飯館村は7割が山や森、山や森の除染はしない、出来ません。
放射性物質は風が吹けば山から飛んでくる、雨が降れば流れてくる。
だから、田畑を除染したとはいえ、飯舘で野菜を作っても消費者は買わない、当然です。
だからといって、故郷の田畑を荒れ地にしてしまうのは耐えられない。
自分が住んでいる前田地区で、所有者の6割が農地の管理は出来ないという。
仲間で耕作組合をつくって、請け負ってそばを栽培している。
去年収穫した蕎麦の放射能を測定すると17㏃/kgだった。国の100ベクレルの基準値はクリアしているが・・・」と悩ましげな長谷川さん。
3月11日東電本社前で、900人が集まって抗議行動があった。
「本当の復興は、被害者賠償」というコールがあった。
-Ka.M-